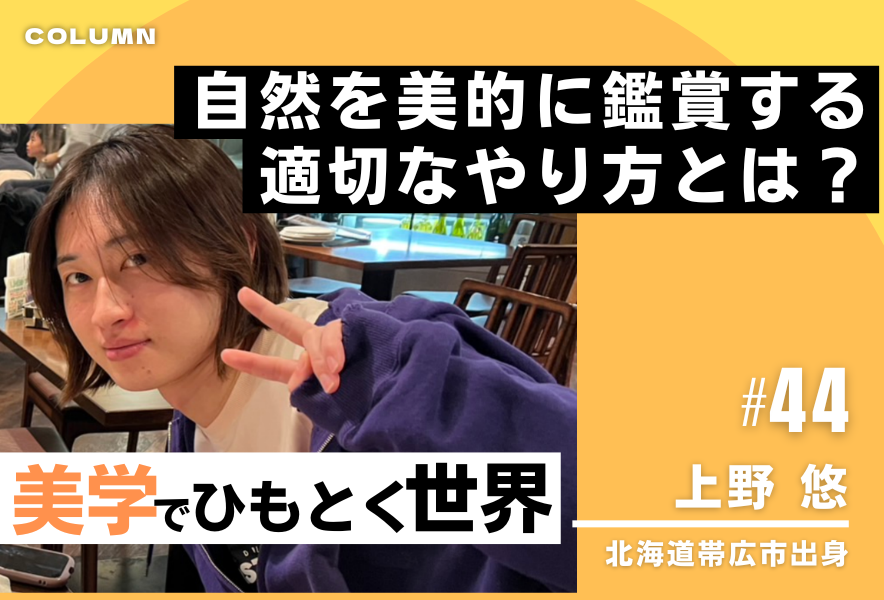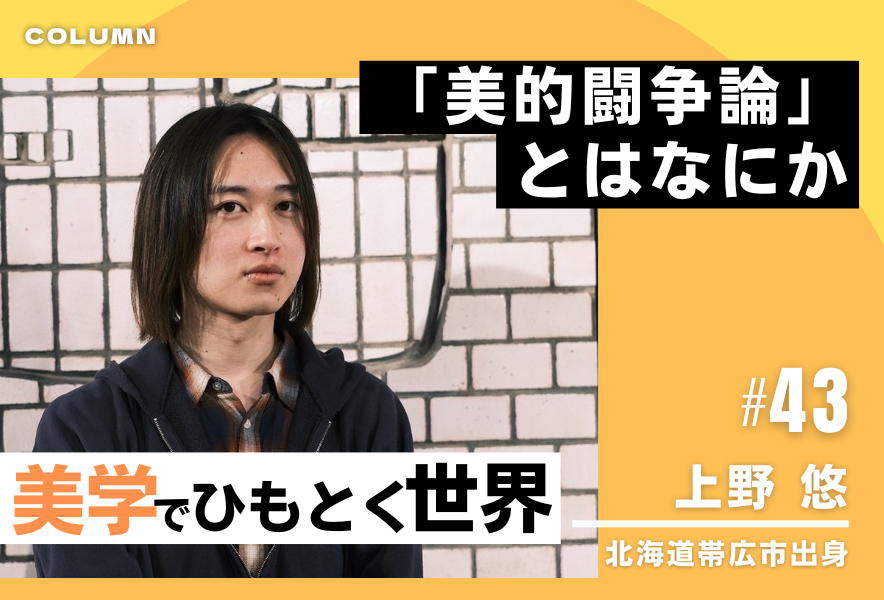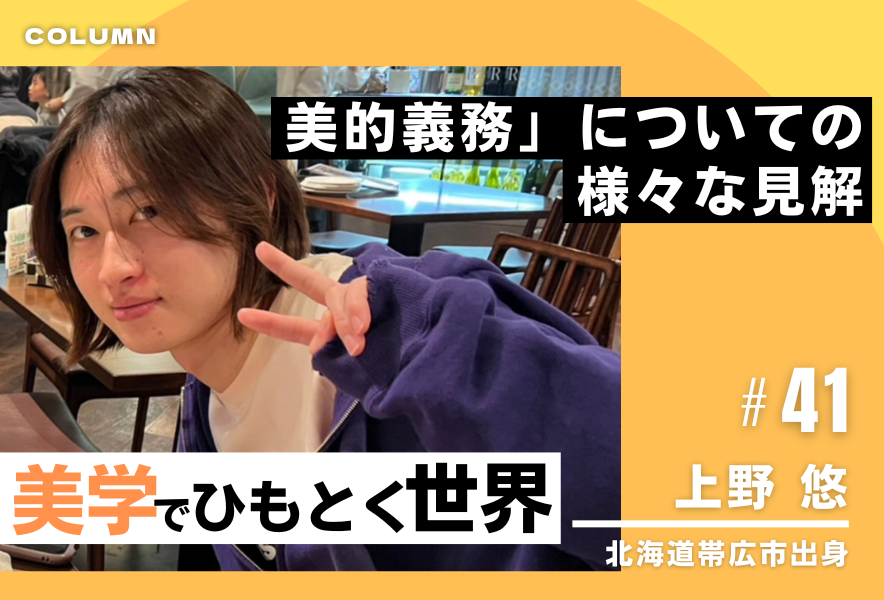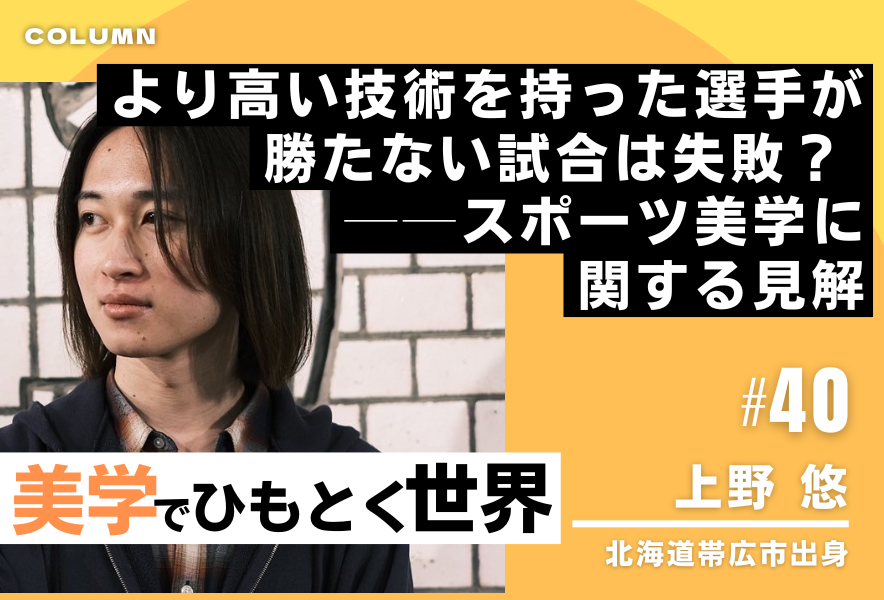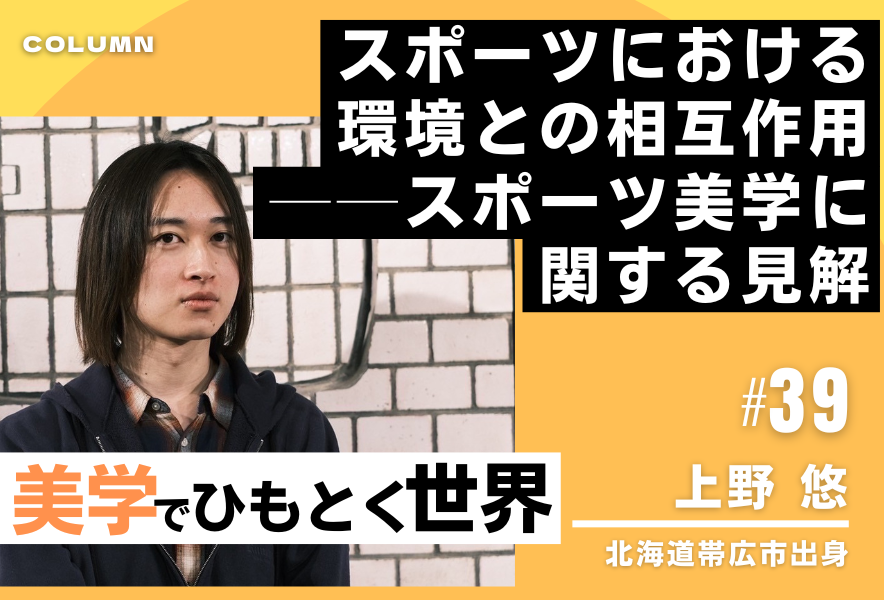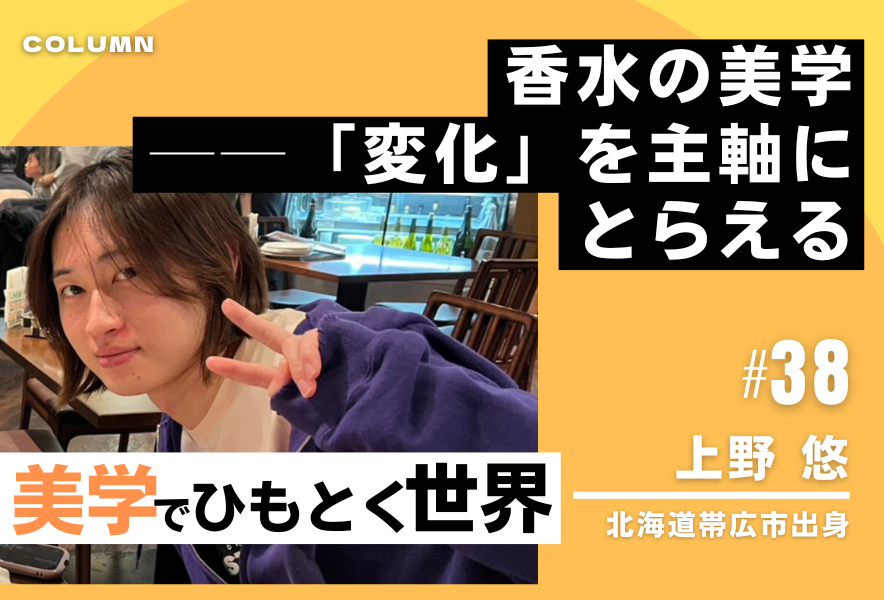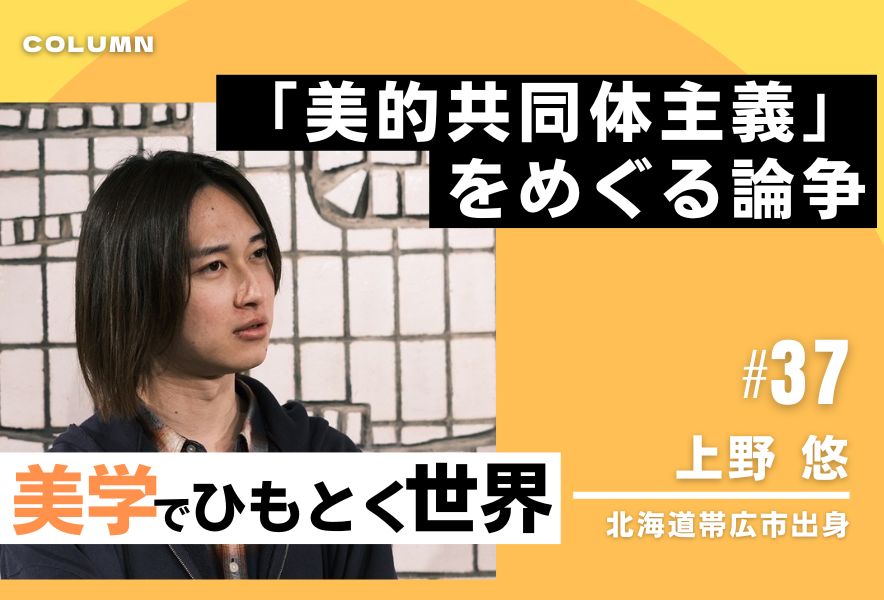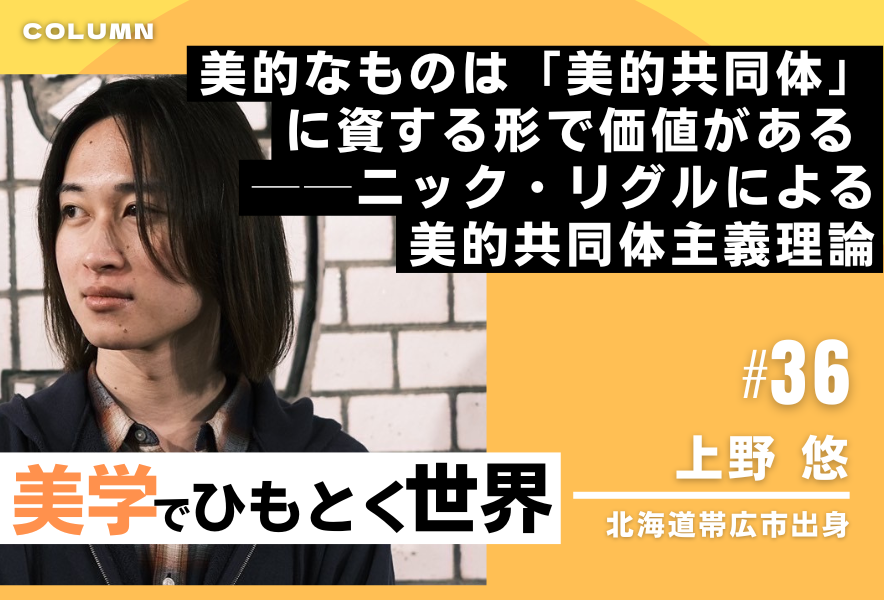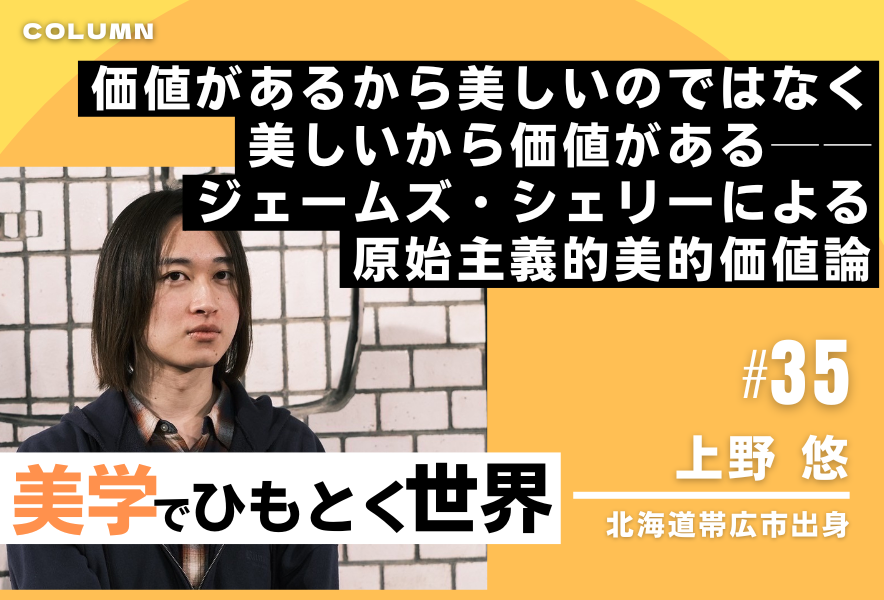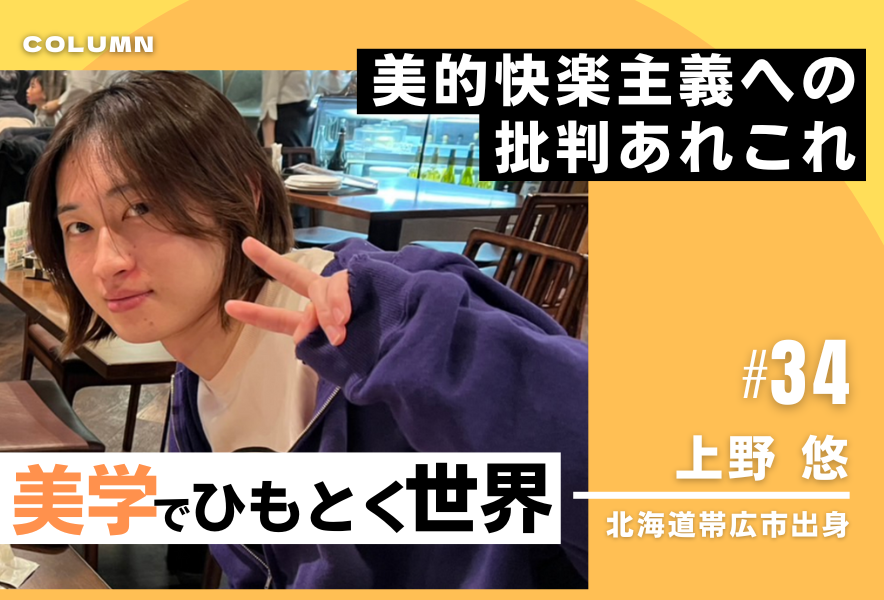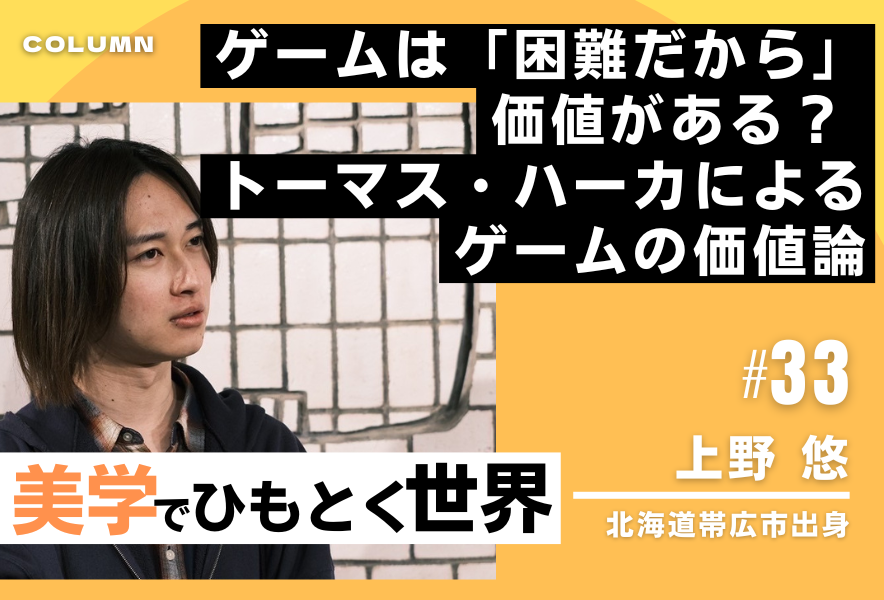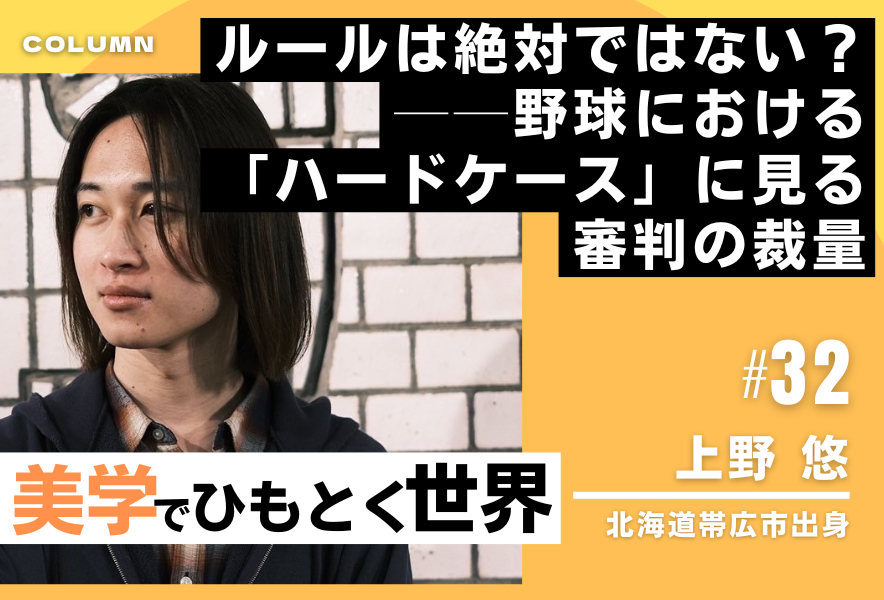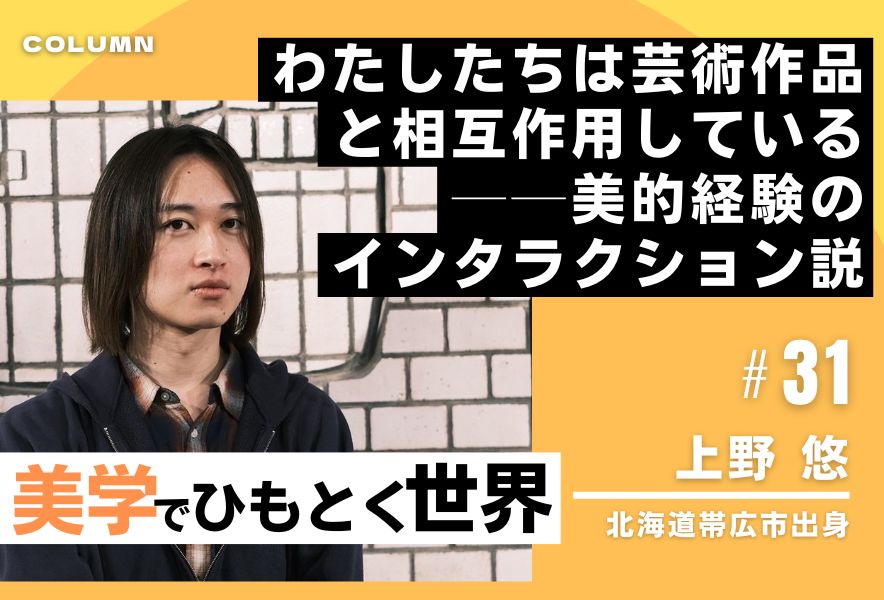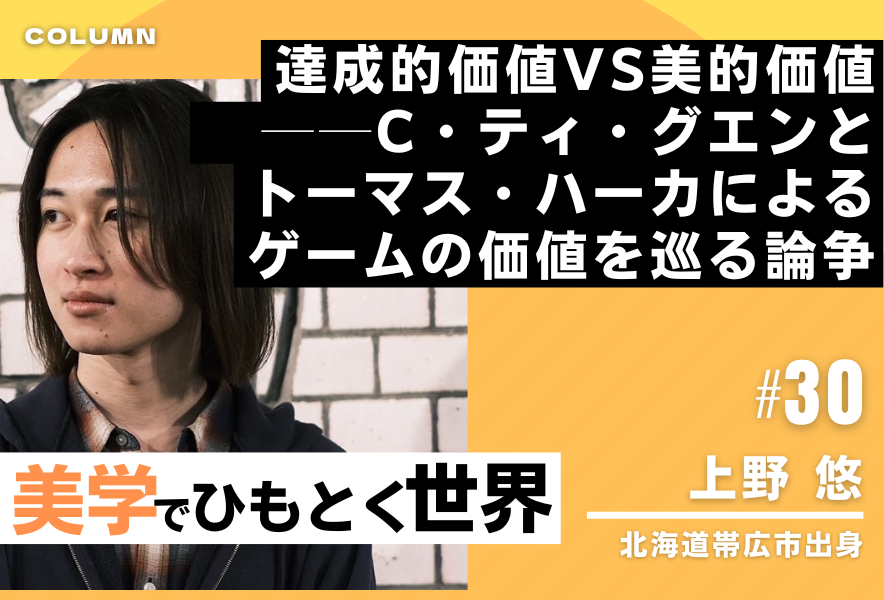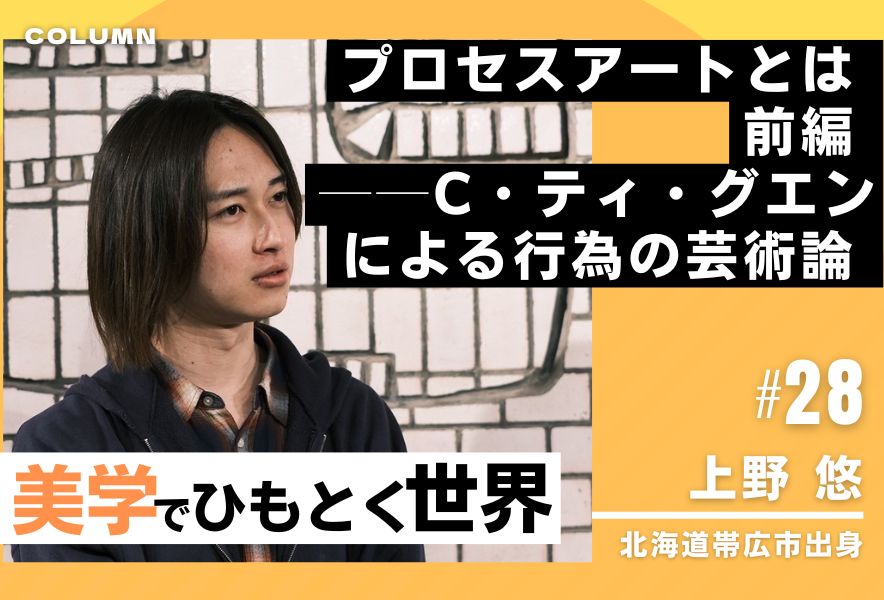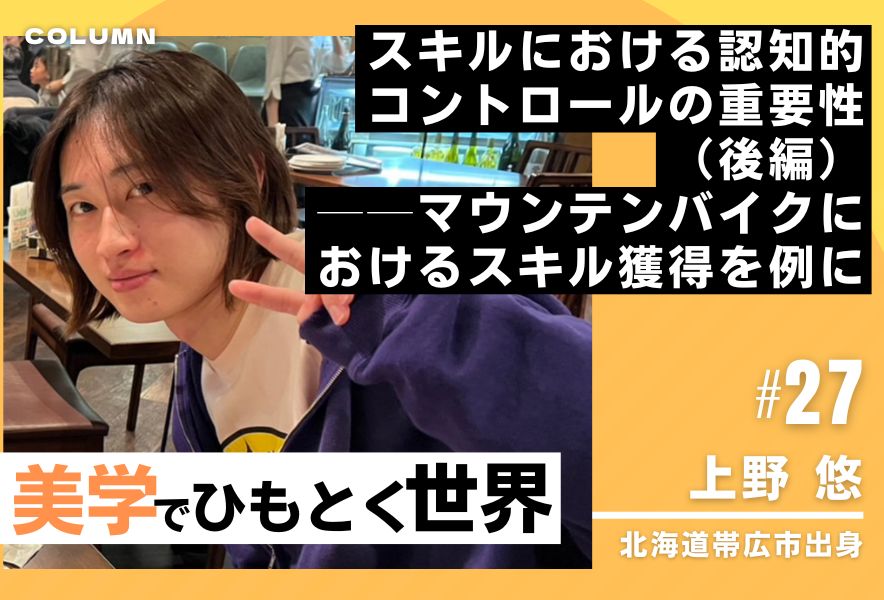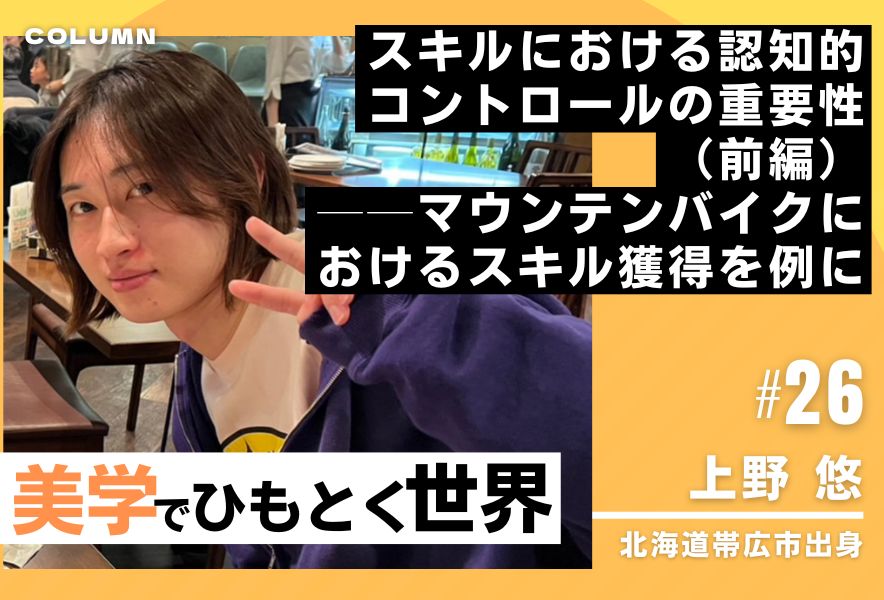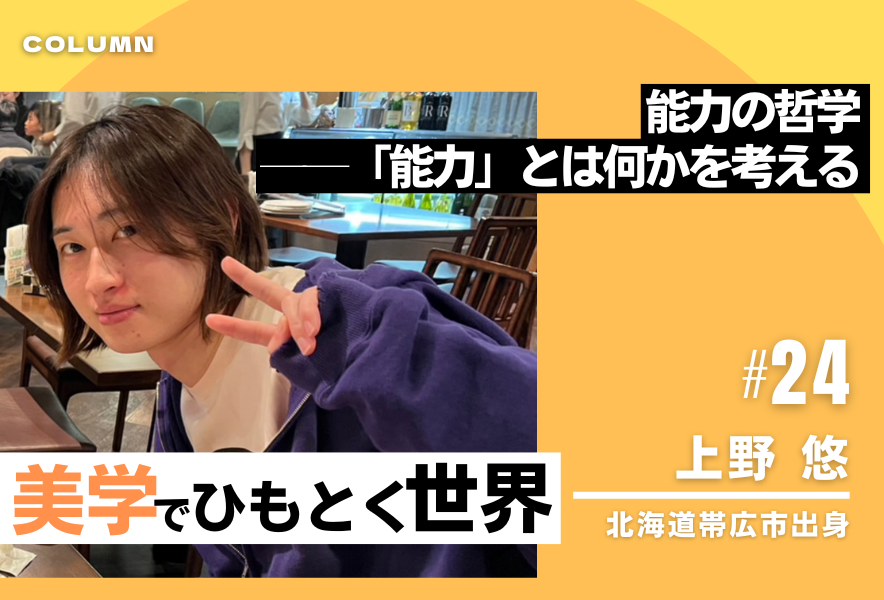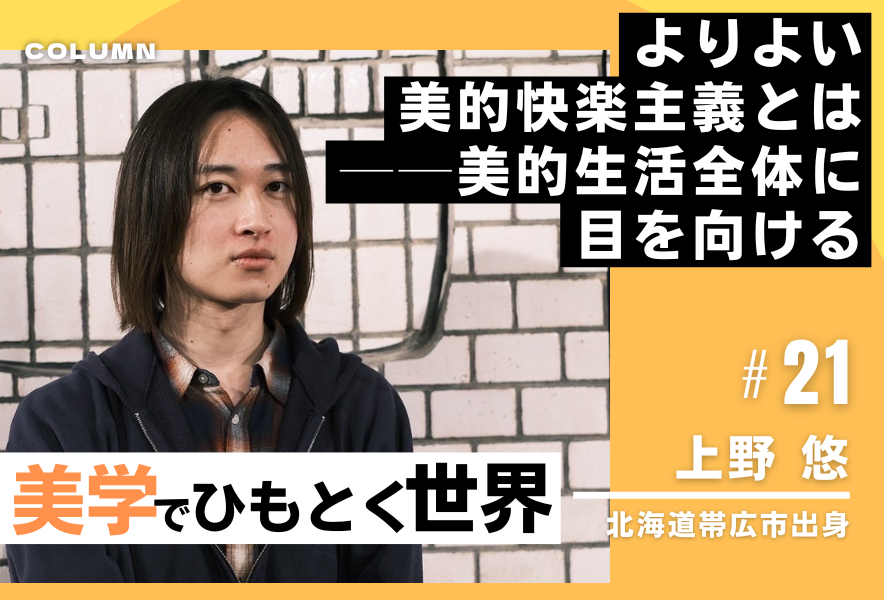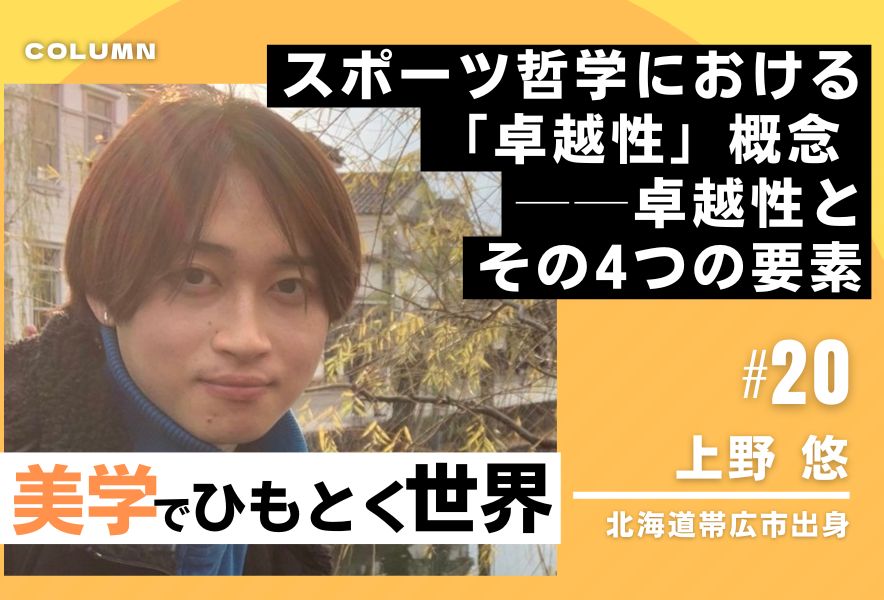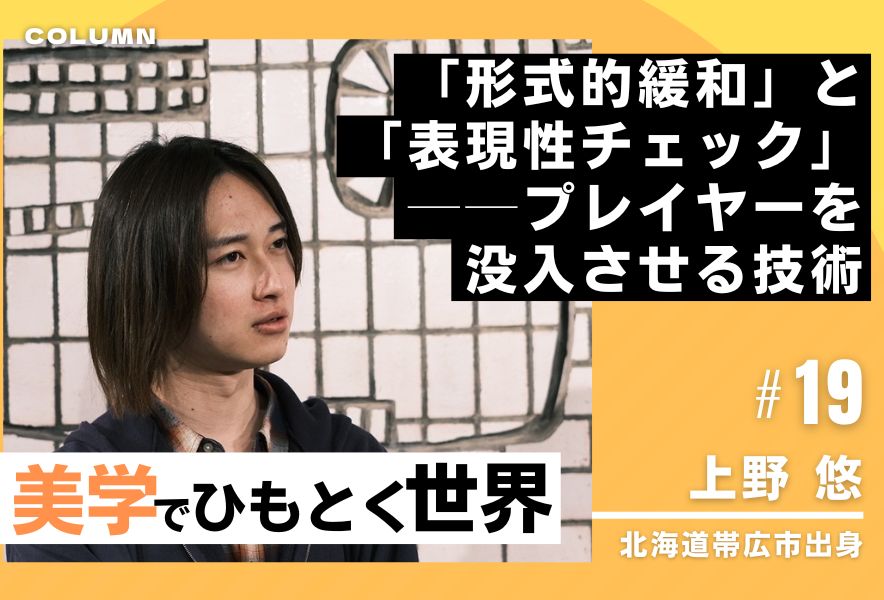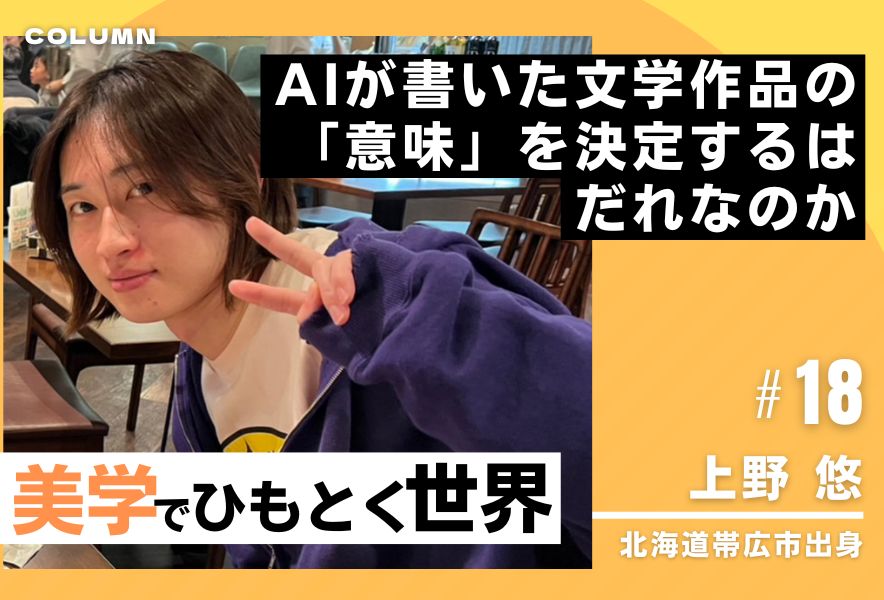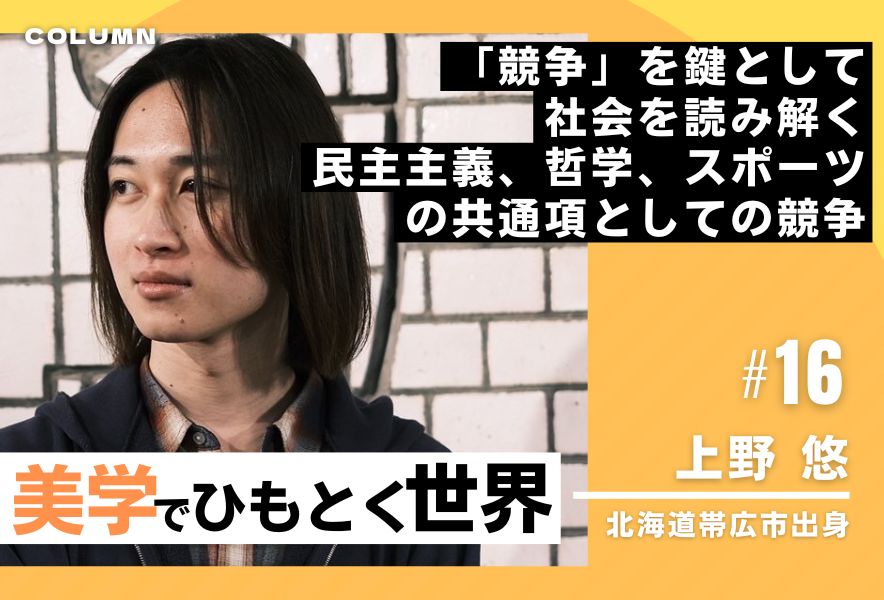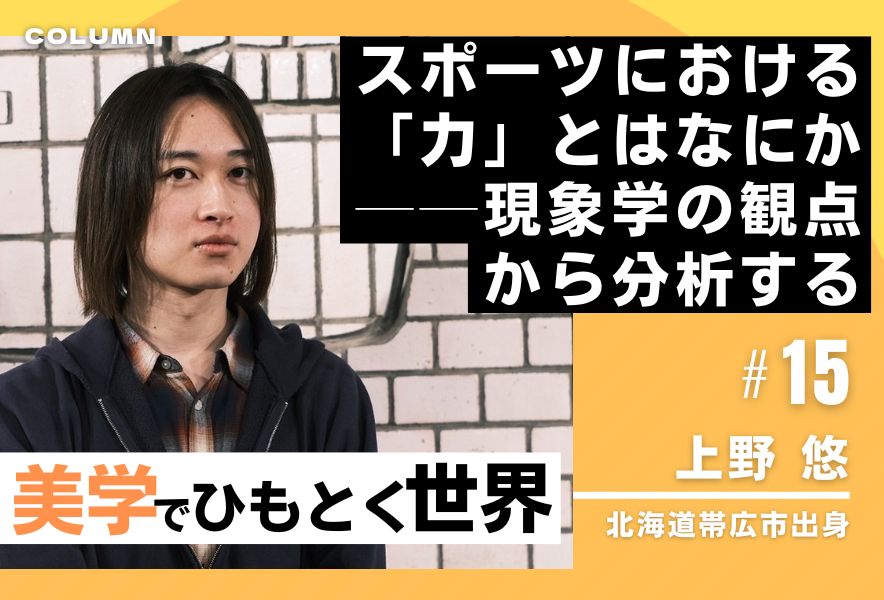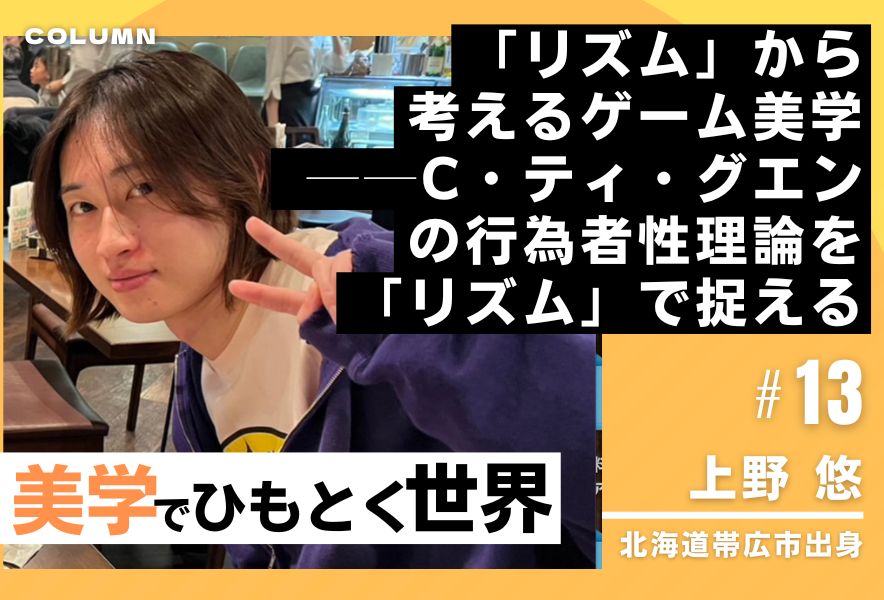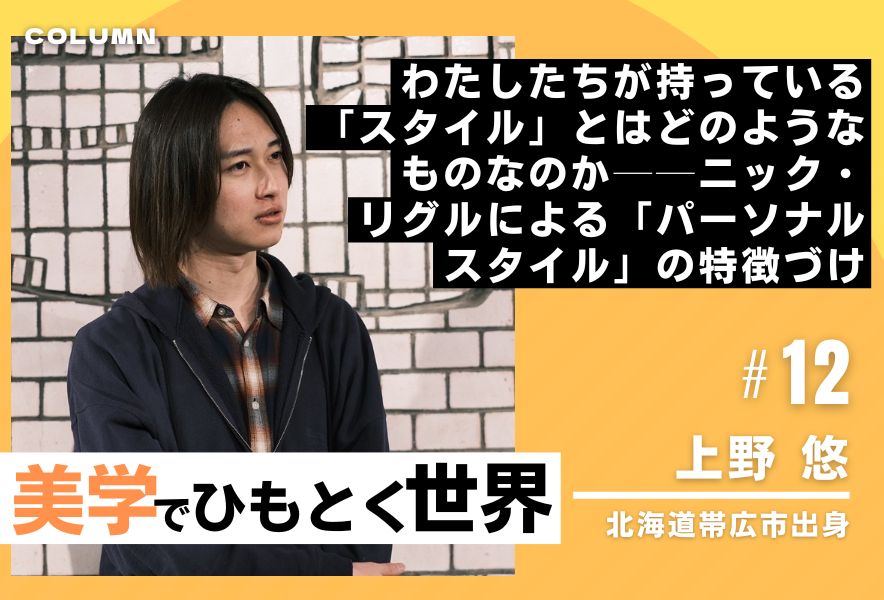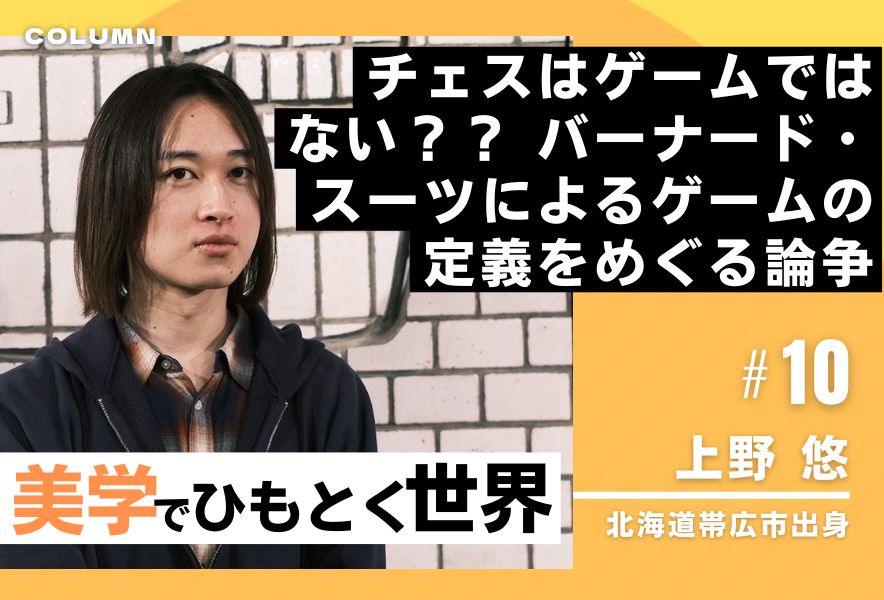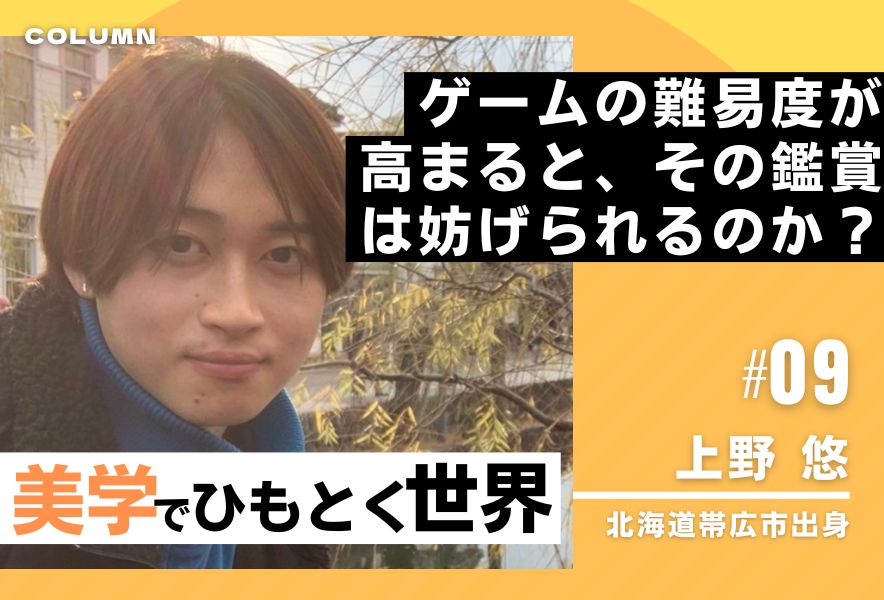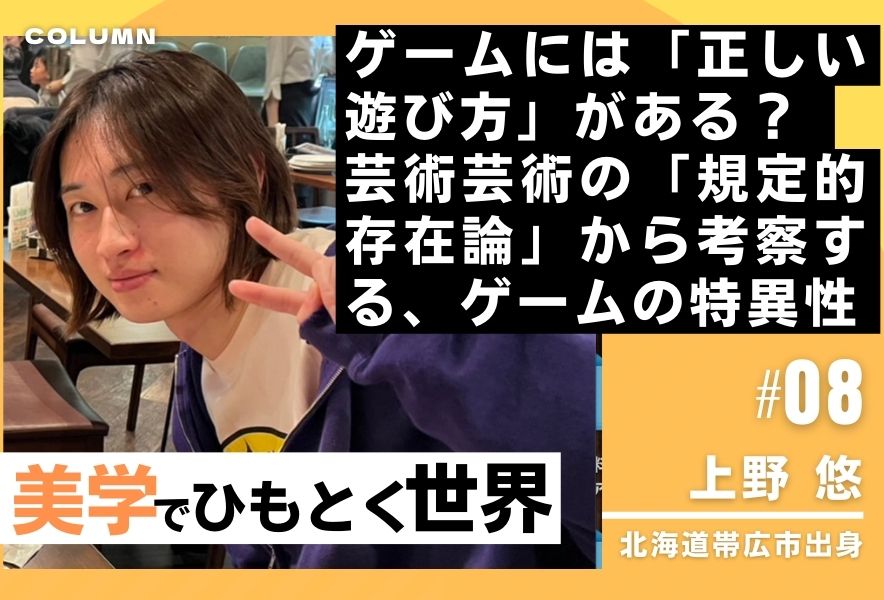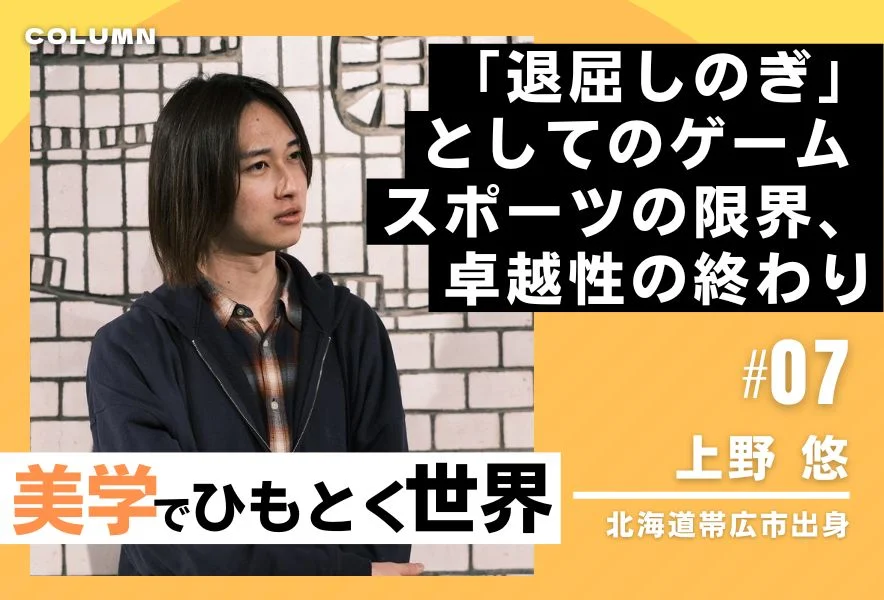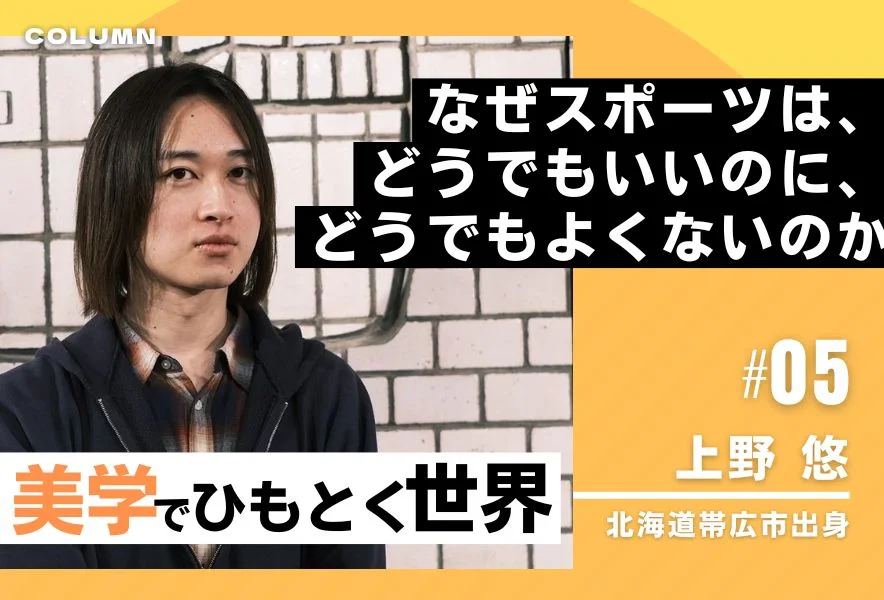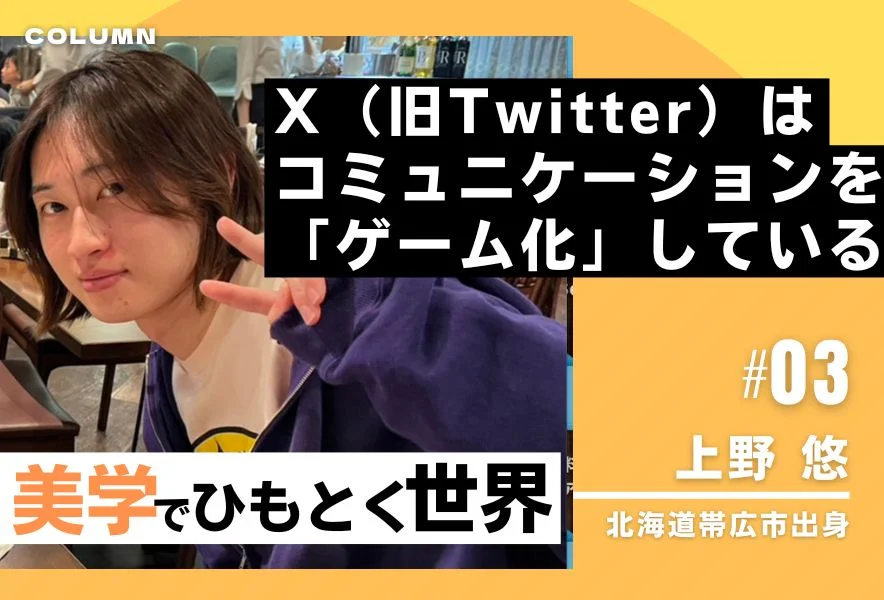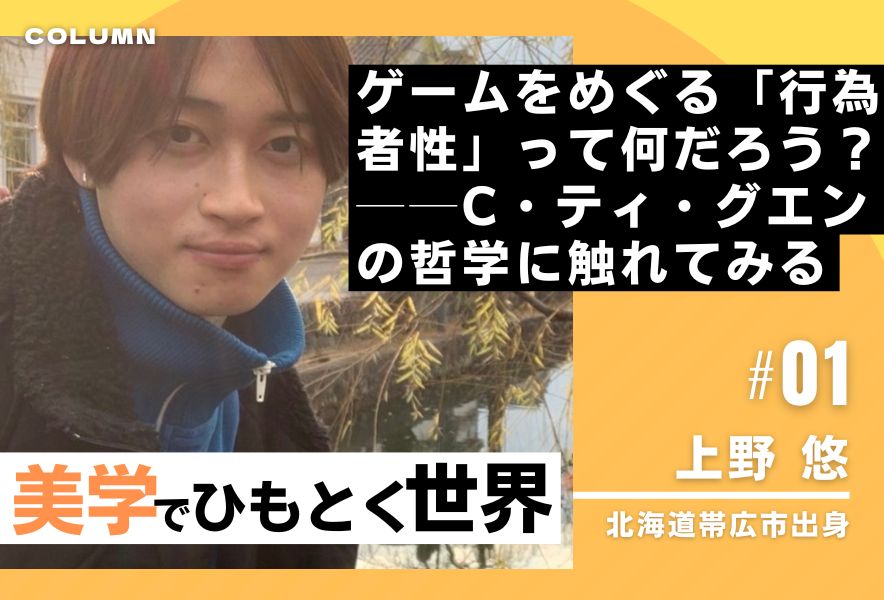【連載】美学者 上野悠の「美学でひもとく世界」
自然の鑑賞
美学分野の研究対象は絵画や文学、映画といった、いわゆる「芸術作品」であることが多いですが、「自然」の鑑賞についての議論もされています。考えてみれば、わたしたちはひょっとしたら芸術作品以上に自然を鑑賞する機会に恵まれているかもしれません。都会に住んでいたらあまり気づかないかもしれませんが、それでもやはり、公園や街路樹、または空や雲など、身の回りを探せば鑑賞の候補となり得るような「自然物」がいくつも見つかります。

しかし、なぜわざわざ自然を美学の対象とするのか、と思うかもしれません。それには、自然の鑑賞は芸術の鑑賞と勝手が違うところがあるのではないか、という直観があります。どういったところでしょうか。例えば、芸術作品はまごうことなき人工物なので、額縁などによって、その「範囲」が決定されているのがふつうですが、人工物ではない自然はわたしたちを取り囲むように存在しており、必ずしも「範囲」が決定されているわけではありません。
このようなことから、自然を美学の対象とし、その鑑賞の独自性を見定めようとする議論がなされています。ベンジャミン・クラッセンによって書かれた2023年の論文は、この分野において影響力の強い、アレン・カールソンが退けたアーノルド・バーリアントによる「没入モデル」を検討し、それに修正を加えて復興しようとしています。
自然鑑賞モデルの要件

前述のとおり、自然は人工物である芸術とは違い、私たちの身の回りにほぼ無限と言えるくらいに広がっています。よって、自然の美学ではまず、自然を適切に美的に鑑賞する理論は、何を、どのように美的に鑑賞すべきかについての何らかの説明を必要としている、というところからはじまります。
クラッセンによると、カールソンは、これについて五つの要件を提示しています。
第一の要件は「あらゆるものの鑑賞説」であり、これは、自然物であれその他のものであれ、知覚可能なあらゆる対象は美的評価の対象となり得るのであり、そのような評価が不可能な対象は存在しない、というものです。
第二の要件、自然としての制約は、自然を自然そのものの条件、すなわち自然が真に持つ本質にふさわしい方法で鑑賞すべきだと主張します。これは、自然を人間の設計による産物であるかのように扱うことは美的誤謬を犯すことを意味しています。
第三に、統一的な美学理論の要件は、美的経験における包括的な理論の必要性を主張します。これは、芸術は芸術として、自然は自然として鑑賞されなければなりませんが、一方で、これらの異なる質を持つ事象の経験には、何か共通点がなくてはならない、というものです。しかし、これに付随して、「より深い美」の直観は、美的鑑賞の事例にはその他のものよりも価値の高いものがあると主張します。痛みが強度によって異なるように、美的快楽もまた様々な強度がある、ということです。ある経験は表面的(うすっぺら)であり、ある経験はより深いものとなりうつのです。
最後に、客観性の要請は、自然に関する美的理論は客観性の担保を目指すべきだと主張します。自然の美は個人の趣味の偏りにのみ基づくべきではないのです。というのも、完全に主観的な理論では、「誰もが、自然環境を鑑賞することを学ぶべきだ、あるいは少なくともそれを保護に値するものとして見るべきだ」というような議論をする余地が一切なくなってしまいます。このような望ましくない帰結を避けるために、客観的な理論が望ましいのです。このようなことが主張される背景には、伝統的に、自然美学の大きなモチベーションの一つに自然保護があるためです。
バーリアントの没入モデル
バーリアントは、没入(engagement)という概念を中心とする美的鑑賞のモデルを提示します。彼にとって没入とは、現代の美的理論化が抱える三つの病——無関心、二元論、距離——に対する治療薬となるものです。
無関心とは、美的鑑賞の対象に対して取り得る態度であり、カントの言う「無関心性」の要件に始まる非常に伝統的なものです。では、無関心とはどのような態度のことを言うのかというと、平たく言うと、「何かのために」それを鑑賞するのではない、ということです。何かを鑑賞するときに、対象がそれ自体として存在するかのように、その性質について考察するとき、無関心性というものが満たされます。逆に言えば、対象を何かの手段として、すなわち目的達成の道具として考察するとき、我々は関心をもってそれに接していることになります。美学では、伝統的に、美的経験や美的判断には無関心性が必要不可欠であると言われているのです。
これとは対照的に、バーリアントの言う第二のモデル——能動的モデル——に属する理論は、関心を伴う美的没入を認めています。 能動的モデルのアプローチは、美的経験の創造と形成における、関心を抱く主体の能動的役割を強調します。美的鑑賞者は、ただ受動的に美的対象を受け取るわけではないのです。

しかし、これら観照的モデルと能動的モデルは、双方とも、美的経験の主体と対象の間の根本的な二元性を前提としています。それらは知覚する主体と知覚される対象を、根本的に異なる実体として扱い、結果として、双モデルは必然的に美的鑑賞を何らかの経験的な距離を伴うものと特徴づけます。
没入の美学はそれらとは全く異なる図を想定しています。没入は、欲望(無関心性がはじこうとしているものです)によって形作られる可能性があります。バーリアントが示すことには、私たちは、食欲を満たそうとするときのように、美の瞬間を興奮をもって待ち望むべきなのです。上記の二つのモデルが前提とする「距離」に対して、没入の美学は親密さを要求します。私たちは、あらゆる感覚に触れながら、自然を感じるべきであり、そうすることによって、主体と対象の間の継ぎ目は消え去り、美的知覚者は環境に対して異質な存在ではなく、環境と連続していることが明らかになるのです。芸術や自然についての美的経験は、有機体と世界との間の身体化された相互関係として生じるのです。
没入の美学への批判

クラッセンは、没入の美学は、自然が提供する美的快楽の一端を的確に描写していることを認めます。一方で、没入モデルは、理論として、重要な問題を残してしまっているのです。特にクラッセンは、「何を」「どのように」鑑賞すべきか、という自然美学における中核的な問題を、バーリアントの理論は解決していないと指摘します。「何を」という点では、没入の美学はあらゆるものを美的に鑑賞すべきだと示唆しているように考えられます。一方、「どのように」という点では、自然に関心を持ち親密に関わることが示されているのみです。
こうした点において、没入の美学は美学の理論的には成立していないと批判されてしまいます。カールソンがこの理論を退けたように、もし私たちがあらゆるものを美的に鑑賞すべきなら、鑑賞対象を真に美的に識別することは不可能になってしまいます。というのも、率直に言って、もしこの世のすべてが強調されるのであれば、むしろ何も強調されなくなるのと同じだからです。したがって、あらゆるものと関わるべきだという考えは、自然の美的鑑賞に対する指針として貧弱に映ってしまいます。
しかしながら、クラッセンは、没入の美学は美的経験の現象そのものにおける重要な要素、すなわち、「自己概念が消滅するほどの完全な没入体験、そして純粋な驚嘆」を的確に捉えていると評価します。そこでクラッセンは、この没入の美学を再考し、修正案を提示しようとします。興味深いのは、クラッセンはこの没入の美学に「無関心性」を取り入れようとしている点です。
没入の美学+無関心性

クラッセンは、没入の経験の「みそ」は実は「無関心」にあるのではないかと主張します。クラッセンは例として、魂のこもった華麗な演奏でステージ上で感情を表現する音楽家を想像するように促します。ソロパートが目前に迫り、演奏家は高音を出したいと願い、同時に出せないかもしれないという恐れを抱きます。つまり、それまでは無関心的だった演奏家の心に、関心の態度が侵入してくるのです。この時点で演奏家の落ち着きは緊張に変わり、思考は改善策へと向かいます。このとき演奏家は没入状態から離脱したのです。つまり、関心を持った態度は真の没入を阻害してしまうのです。
しかしながら、没入は無関心だけでは生まれません。没入をしようとする者はさらに自らの活動に注意を向ける必要があります。注意を向けないと、たとえ無関心であっても完全に没入することはできないとクラッセンは言います。これは、没入するアスリート、ダイバー、俳優、恋人、観客、そして美的鑑賞者たちが、それぞれの活動の本質を成す身体と世界の特異な相互作用に、無関心な状態で注意を向けなければならないことを意味しています。
クラッセンが言うには、この「注意」は関心に影響されてしまいます。これが、関心のある態度が没入を妨げる理由を説明するのです。例えば、欲望と嫌悪に満ちた音楽家は、自身の活動に注意を向ける能力が低下してしまいます。その注意は、代わりに、彼女が望む目的(欲望や嫌悪の向かう先)の達成手段である対象や楽器へと揺らいでしまいます。
クラッセンは、このようにして、関心は注意を制約するのであり、逆に、無関心は注意を解放するのだと言います。結果として、私たちが完全に無関心でない限り、完全に注意を向けること──したがって、美的に没入すること──はできないのです。
こうした関心の唯一の例外として、クラッセンは「好奇心による関心」を挙げています。好奇心は私たちの注意を強めるのだと言うのです。なぜ好奇心だけがそうした特別な点を持つのでしょうか。一般的に、関心とは世界のあり方に関わるものです。クラッセンが言うには、関心を持つとは、世界がどのようであるかを気にかけることです。しかし、好奇心はそれとは構造がやや異なり、むしろ世界が何であるかに関心を持つことである。好奇心とは、それがむけられる対象が「何であるか」を明らかにすることへの関心なのです。真摯な好奇心を持つなら、例えば、雲についての何らかの知識ではなく雲そのものに関心を持つと考えられるのです。

したがって、美的没入には、世界が「どのようであるのか」に対しては無関心な状態で、なおかつ、世界が「何であるか」に好奇心を持って注意を向けることが求められます。このようにして何かに注意を向けている経験が美的快楽を生みだすのです。私たちが自然を美的に干渉するには、自然に対して無関心な態度を保ちつつ、好奇心を持って注意を向けるということが必要なのだ、というわけです。
参考文献
Claessens, Benjamin. 2023. “Wonderful Worlds: Disinterested Engagement and Environmental Aesthetic Appreciation.” British Journal of Aesthetics 12.
美学者とは
美学者の役割
- 【美的判断】なぜある人が「美しい」と感じる対象を、別の人は「そうでもない」と思うのか
- 【芸術作品の価値】作品が私たちの感性に与える影響を、どう評価し、言葉で説明できるか
- 【日常の美】ファッションやインテリアなど身近なところに潜む「美しさ」をどのように考えるか
こうした問いに取り組むのが美学者の役割です。近年では、ゲームの体験やデザイン、スポーツや身体表現、さらにはSNSなど、従来は「美学」とはあまり結びつかなかった分野にまでその探究範囲が広がっています。哲学や芸術学と深く関係しながら、現代社会のあらゆる「感性の問題」に光を当てるのが、美学者と呼ばれる人々なのです。

【PROFILE】
北海道帯広市出身。早稲田大学文学研究科博士後期課程在籍。専門は、ゲーム研究、美学。主な論文に、「個人的なものとしてのゲームのプレイ: 卓越的プレイ、プレイスタイル、自己実現としての遊び」『REPLAYING JAPAN 6』、「ゲームにおける自由について──行為の創造者としてのプレイヤー──」『早稲田大学大学院 文学研究科紀要 第68輯』。ゲームとファッションとタコライスが好き。