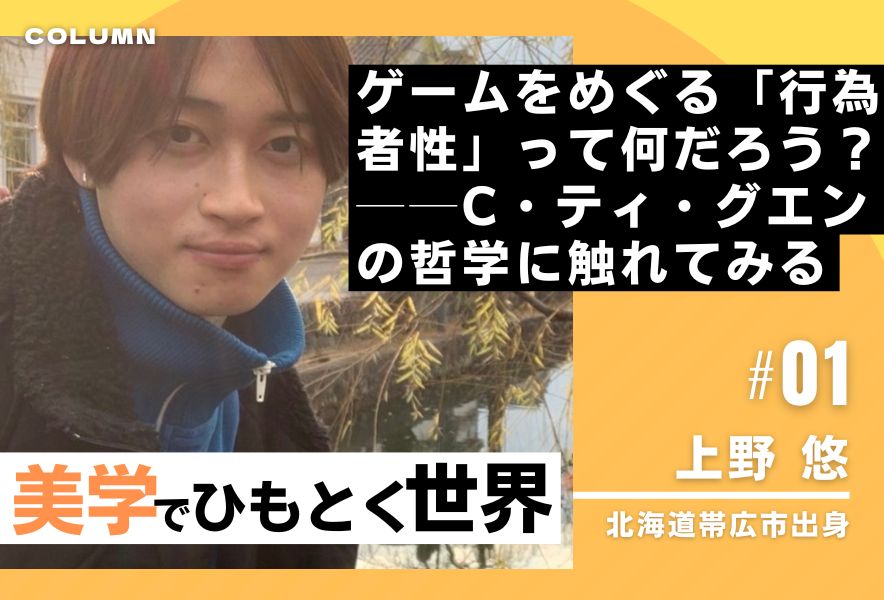【連載】美学者 上野悠の「美学でひもとく世界」
【テーマ】「環境」を美学する ──観光と居住の美的鑑賞

私は北海道の帯広市というところの出身なのですが、会話のはずみで北海道出身であることを明かすと、「いいなぁ~」とうらやましがられるということがよくあります。つづけて、その人が北海道へ旅行に行ったとき(たいていは札幌です)のエピソードについて語られたり、北海道がいかに素晴らしい土地であるかということを熱弁されたりすることもあれば、逆に北海道に行ったことがないのでぜひ行ってみたいと思っているという旨を聞かされることもあります。
どうやら「北海道」という土地は、多くの日本人にとって結構特別な場所だと思われてるみたいです。同じく北海道出身である友人もみんな同様の経験をしょっちゅうするようなので、これは「北海道出身あるある」として多くの北海道出身者が共感してくれるのではないでしょうか。
そのようなときに感じるのが、「観光地」としての北海道と、「居住地」としての北海道の間にあるギャップです。観光客として経験される北海道の雪景色や冷たい空気、澄んだ青空と広大な大地…などはとても新鮮で魅力的に写るということがよくわかりますが、実際に住んでる身からすると雪が降るとその美しさよりも、雪かきのことがすぐ頭によぎってげんなりする…という方も少なくないのではないでしょうか。他の地域のことをよく知っているわけではないので、断言はできないのですが、こうしたギャップで言うと、北海道はかなり大きい方なのではないかと思います。
そんな観光地としての側面も持つ北海道は、当然、観光業も発達しており、海外からの観光客が急増中の昨今では、これをビジネスチャンスと様々に趣向を凝らしたサービスや施設が続々と立ち上げています。もともと日本有数の観光地としての側面を持っていた北海道ですが、いまではその「観光地化」がさらに加速していると言えるのではないでしょうか。

そこで今回は、「環境美学」というものをご紹介することにします。前回が「ゲームの美学」だったので、あまり驚きはないかもしれませんが、「環境」も美学のテーマになるのです。とはいっても、環境の場合はゲームとは少し事情が違います。というのも、「美学」という学問領域において、今でも非常に重要な古典であるイマヌエル・カントの時代には、芸術作品よりも、むしろ自然の方が美学の対象として優遇されていたからです。それが時代を下りにつれ徐々に芸術の方に主眼が移行していき、20世紀には美学はほとんど「芸術哲学」となってしまっていたと言われるほどにまでなります。そんな「自然美無視」をしてしまっている美学への反省から、1970年代に「環境美学」というものが立ち上がってきました。
美学者の青田麻未による『環境を批評する ──英米系環境美学の展開』(春風社、2020年)は、そのような環境美学の経過をなぞりつつ、「環境の批評とはどのような営みであるのか」という問いに対して独自の答えを提示しようとする本です。今回は、この本を参照元として、環境美学についてみなさんにご紹介していきたいと思います。議論の流れすべてを紹介するのはかなり大変なので、特に「観光と居住」をテーマに書かれた第5章を中心にしたいと思います。
本書における「環境」とは

まずは前提となるような概念の整理から始めましょう。まず、本書における「環境美学」が対象としているような「環境」とはどのようなものでしょうか。環境はかなり多義的な意味を持つ言葉ですが、本書で言う環境は「自然」に限定されず人工的なものも含んだ、より広い対象を指す言葉として用いられます。というのも、「人の手が加わっていない」という意味での自然は、我々の目の届く範囲にはほとんど存在していないからです。
また、環境という言葉は「風景」とも区別されます。「風景画」というものが示すように、風景という言葉は、鑑賞者に目の前にあるものの視覚的特徴のみに注意を促すことを表しています。このとき鑑賞者は「主体」として、風景は「客体」として、「主客」が分離した状態となります。環境という言葉は、こうした「視覚偏重」、「主客分離」な状況を脱するために用いられてもいるのです。以上を踏まえて、青田は先行研究を踏まえつつ、次のようにまとめています。
世界を環境として捉えたうえで鑑賞するということは、空間的に言えば我々を取り囲むものとしての、時間的に言えば常に変化していくものとしての特徴にこそ付随する美的な特徴を感じ取っていくことである。(青田麻未『環境を批評する ──英米系環境美学の展開』25頁)
さて、こうして環境美学が対象とする「環境」がどういうものかがなんとなくおわかりいただけたかと思います。しかし、環境を芸術と同じように扱おうとすると問題が発生します。芸術の場合、鑑賞の対象となるものははっきりとわかります。絵画や彫刻などを想像するとわかりやすいですね。それらのように物理的な実体を持っていない、演奏や演劇のようなものでも、それらがどこからどこまでなのかは明確に認識することができます。
一方で、環境の場合は、こうした「区切り」のようなものがあらかじめ存在してはいないのです。このような、我々が何かを鑑賞する際に注意を向けるべきものを限定するような仕組みを、本書では「フレーム」と呼びます。
しかし、むしろフレームがあらかじめ設定されていないことこそが、自然を鑑賞する際の特徴となります。自然がフレームを持たないということによって、我々がフレームなしに自然を鑑賞することが不可能になるのではなく、環境が刻々と変化していくように、我々自身がフレームを何度でも決定しなおすことによって、美的経験の対象となるものを変化させ続けることも経験のうちに含まれているのです。
「観光」におけるフレーミング

それではここから、「観光」と「居住」という二つの活動に焦点を当てていきましょう。観光と居住は一見すると別々の活動ですが、例えば、自分のまちの行ったことない場所に歩みを進めながらしばらくふらつくことは、もはや立派な小観光と言えますが、このように、我々が真っ先に想像するような、典型的な観光と居住の間にはグラデーションが存在するのです。さらには、観光というのは「旅すること」それ自体を楽しむことを目的に行われるものですが、その構造から言って「行って、帰ってくる」ことが必ず伴われます。行って帰ってこなかったら観光とは言いませんよね。その帰る場所というのがまさに「居住」が営まれる場所なのです。こうした関係から、青田はこの二つの活動を対になるものとして題材にとったのです。
青田はまず、「観光」の方から見ていきます。はじめに指摘するのは、環境美学において、観光はこれまで、どちらかというと批判的に見られてきた、ということです。環境美学の先駆者であるヘプバーンは、自然美が理論に敵に語られなくなった原因として、当時の人々の自然美の趣味の劣化を挙げていました。その劣化を示すような最たる例が「観光者」なのです。
こうした批判の的となるような「観光」はさらに、写真というメディアと結びつきます。私たちは観光に行くとその場所の写真を撮ることがよくありますよね。また、観光地を選ぶ際には、インターネットやガイドブックなどに載っている写真を判断材料にすることもあるのではないでしょうか。わたしたちは知らず知らずのうちに観光地を写した写真によって、「観光地」という場所のイメージを、行く前から抱いてしまっているのです。
こうした背景から、青田は、環境美学は、観光を「視覚偏重」であるという早計な判定を下してきたのではないかと指摘します。しかしながら、実際の観光には視覚由来のもの以外の経験もたくさん含まれています。観光という鑑賞態度が不適切なのかどうかを決めるためには、まずは観光というものがどういうものであるのかをじっくりと考えていく必要があるのです。
青田は観光における「フレーミング」を以下の3つに注目して整理しようとします。
2.個別的活動によるフレーム
3.再構成されたフレーム
順に見ていきましょう。
1.事前の計画による(プレ)フレーム
まず、「事前の計画による(プレ)フレーム」は、観光へ行く前の計画段階において行われます。事前計画において私たちは、他者によって共有されたフレームを得ることで、旅行に行ったときに自分自身のフレームを構築するための準備をします。他者のフレームは、写真以外にも旅行記や映像など様々なメディアの形をとりますが、これらを獲得することによって、わたしたちは自分が経験することになる観光と比較考量するための基準点を設定するのです。
2.個別的活動によるフレーム
次に、「個別的活動によるフレーム」です。まず、個別的活動とは「統括的活動」という別の概念との対比される概念で、統括的活動は、個別的活動に「意味」を与えることのできる、より上位に置かれる活動です。例えば、「観光」は統括的活動にあたり、この場合、個別的活動とは「移動」や「食事」があてはまります。移動も食事も視覚が関わりはしますが、視覚のみに特化した経験ではありません。こうした活動を通して私たちは、様々な感覚を作動させながら、観光地をフレーミングすることができるのです。
3.再構成されたフレーム
最後に、「再構成されたフレーム」です。これは観光から帰ってきたあとの、振り返りの段階に当たります。観光から帰ってきたあと、わたしたちは観光先での様々な経験=個別的活動が構成した個々のフレームを事後的に総合し、編成していくことで、その観光=統括的活動における美的鑑賞を振り返り、観光地に対する美的判断を練り上げていきます。このときわたしたちは、観光のフレームを再構成しているのです。
このように、観光においては、事前・最中・事後においてフレームを形成する契機を得ます。私たちは様々な土地に、何度も観光に行き、その都度フレームを作り上げることによって、「よそもの」だからこそ発見できる環境の観賞対象を見出していくことができます。そしてその経験は、「日常」におけるわたしたちのまなざしにも影響を与えていくかもしれません、このように、観光の経験の価値は、日常へと還元されていくことにもあるのです。そういうわけで、今度は「居住」についての青田の論を見ていきましょう。
「居住」におけるフレーミング

わたしたちはしばしば、自分の住んでいる町について「何もない」という否定的な見方をし、時折訪れる、観光の新鮮な経験をありがたがる傾向にあります。そんな中で青田は、「親しみ」という居住を特徴づけるポジティブな性質に着目して論を進めていきます。
日常にありふれた様々な対象は、新鮮さや驚きこそ与えないものの、ある種の心地よい安定性を与えてくれるという意味で、わたしたちに「快」をもたらしてくれます。しかしながら、「親しみ」を美学的な概念として扱うためには、この「快」が「美的な快」であるとしていいのか、という問題に取り組む必要が出てきます。青田は「日常美学」の第一人者であるユリコ・サイトウの論を参照し、問題に答えるためには、「普段は後景に退いているような日常がいかにして前景化するのか」、「前景化したときに、なぜ非凡なものへと転じず、親しみと呼べるような美的鑑賞につながるのか」ということを解明しなければならないと示しています。
青田は「居住する」ということが一定の期間を要することに着目し「居住環境」をその場だけでなく、そこに住んできたという「時間の厚み」も含んで認識される環境であると特徴づけます。同じ土地に一定期間住むことによって、第一に、その土地にある様々な対象の変化を感じ取ることができます。季節の変化による変化のほか、時間の推移によって、建物が取り壊されたり、新しいお店ができたりします。こうした変化はどれも、繰り返しの日常の中で、一回限りのものとなります。
第二に、同じ土地に住み続けることで、人は自身の記憶を形成していきます。こうした記憶は蓄積されていく一方で、現在の光景の中に投影されていくことになります。例えば、近くの公園をながめながら、幼いころにそこで遊んだ記憶が投影されること、などが挙げられるのではないでしょうか。
青田は、居住環境についてのフレームについても考えますが、今度は以下の2つに分けられます。
2.未来志向のフレーミング
1.過去志向のフレーミング
では、「過去志向」の方から見ていきましょう。まず、過去と現在の差は、居住空間内のなんらかの要素の変化によってもたらされます。日々の暮らしのルーティンの中で、居住空間内での個別の活動は、たまに特殊な出来事によって個別な活動としてフレーミングされることはあっても、全体としては渾然としています。そこへ、先に挙げたような建物やお店の消失など、なんらかの欠損が生じ、それを認識することによって、フレーミングが反省的に為されます。一方で、ポジティブな変化の場合は、その変化のみにフレーミングが集中するため、過去志向の「親しみ」のフレームは否定的な何かが起こったときにしか起こらないという、「否定を介しての肯定」という特徴を持っています。
2.未来志向のフレーミング
次に、「未来志向」について見ていきましょう。こちらの方は、現状では変化は起こっていない状態から、未来の居住環境を思い浮かべることで生じるフレーミングです。わたしたちは、居住環境の「鑑賞者」というだけでなく「制作者」になることができます。どういうことかというと、わたしたちは日常生活のうちに、気づかれず埋没していた美的特徴に気づくことによって、美的な側面から世界のあり方を決定していくプロセスに参加することができる可能性が秘められているのです。
そしてそこには、ある種の「責任」が存在します。こうしたことを踏まえて青田は、自分たちの居住環境が今後どうなっていくかを考える際にも親しみのフレームが到来すると述べています。環境に対して制作者的な視点をもって接するとき、その環境の持つ性格を無視してはなりません。ですから、わたしたちはそのとき、自らの記憶の中を参照しながら、その環境の美的なよさを感じ取り、今後の「あるべき姿」を構想する、という一連の流れの中に、親しみのフレームが現れることになるのです。
フレームの概念を用いれば、その土地の新たな側面が見えてくるかもしれない

章の最後に、青田は、「親しみ」からさらに発展していく可能性について示唆しています。すなわち、わたしたちは、居住空間に「親しみ」を覚え、自分にとって美的に好ましい空間であると思うからこそ、新たなフレームのもとで、これまで気づかなかったよさについて気づきたいと思うようになるのです。この点に関しては、私(上野)自身は、かなり共感できるように感じられます。というのも、最近まさにこのようなことを経験したからです。
前述のとおり、私は北海道出身なのですが、現在は首都圏に在住しており、北海道には、毎年の年末年始に帰省で訪れるくらいになっていました。先の年末年始に、家族で札幌に出かけることになったのですが、その帰り道で、自家用車で揺られながら家のある帯広市へ向かっている道中、ふと車窓から木々の枝に雪が積もっている光景を見て、非常に心を打たれたのです。現在は離れて住んでいると言っても、雪景色は見慣れているつもりだったのですが、これまで感じたことのなかった美しさを、その枝から感じ取ることができたのです。
なぜその瞬間、その木の枝から感じられたのかは自分でもわかりませんでしたが、本書の議論を踏まえることによって、なるほど、札幌-帯広間の車での移動は、私自身はあまりしたことがなかったことから、それによって新たなフレーミングの契機が生まれたのがその原因として考えられるのではないか、と推測することができました。
さてここで、本記事の最初の方にした話を振り返りましょう。私は観光地としての北海道と居住地としての北海道の間にはギャップがある、という話をしましたが、これまでの議論を踏まえるならば、それはフレームの違いによってもたらされている、と考えられるでしょう。
もっと深堀するならば、もし北海道が他の地域と比べて、観光地としてのフレーミングと居住地としてのフレーミングの差が大きいと言えるのならば、それがなぜなのかを、フレームという概念を用いることによって考えていくことができるでしょう。また、そのことによって、北海道という土地が持つ新たな側面も見えてくるかもしれません。
今回紹介したように、新たな概念を発明したり、既存の概念を使いやすくしたりして議論を進めていくのは美学という営みの特徴とも言えますが、そうしてできた、ある概念の存在によって、日常における疑問や問題に対する解決の糸口をつかめたりすることもあるのが美学という学問のひとつのよさかもしれません。
美学者とは
美学者の役割
- 【美的判断】なぜある人が「美しい」と感じる対象を、別の人は「そうでもない」と思うのか
- 【芸術作品の価値】作品が私たちの感性に与える影響を、どう評価し、言葉で説明できるか
- 【日常の美】ファッションやインテリアなど身近なところに潜む「美しさ」をどのように考えるか
こうした問いに取り組むのが美学者の役割です。近年では、ゲームの体験やデザイン、スポーツや身体表現、さらにはSNSなど、従来は「美学」とはあまり結びつかなかった分野にまでその探究範囲が広がっています。哲学や芸術学と深く関係しながら、現代社会のあらゆる「感性の問題」に光を当てるのが、美学者と呼ばれる人々なのです。

【PROFILE】
北海道帯広市出身。早稲田大学文学研究科博士後期課程在籍。専門は、ゲーム研究、美学。主な論文に、「個人的なものとしてのゲームのプレイ: 卓越的プレイ、プレイスタイル、自己実現としての遊び」『REPLAYING JAPAN 6』、「ゲームにおける自由について──行為の創造者としてのプレイヤー──」『早稲田大学大学院 文学研究科紀要 第68輯』。ゲームとファッションとタコライスが好き。