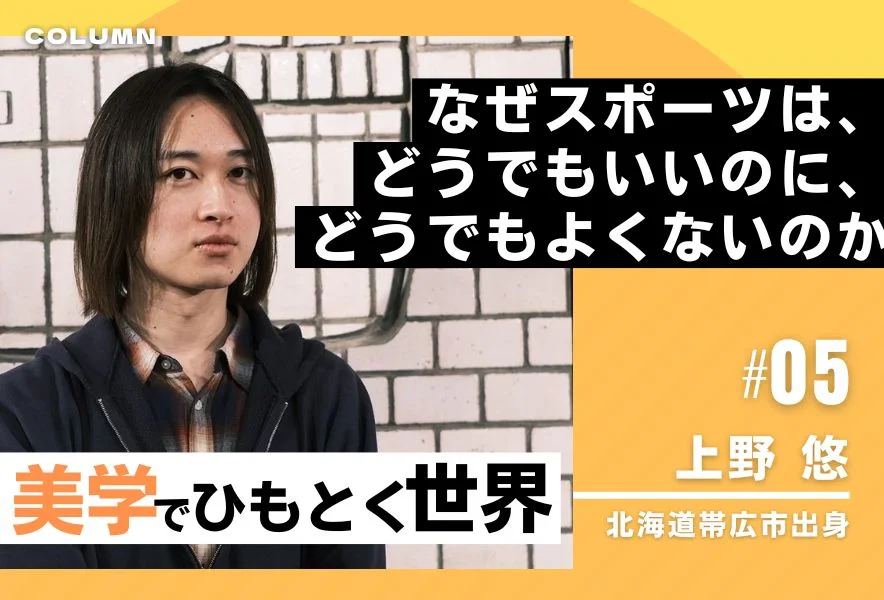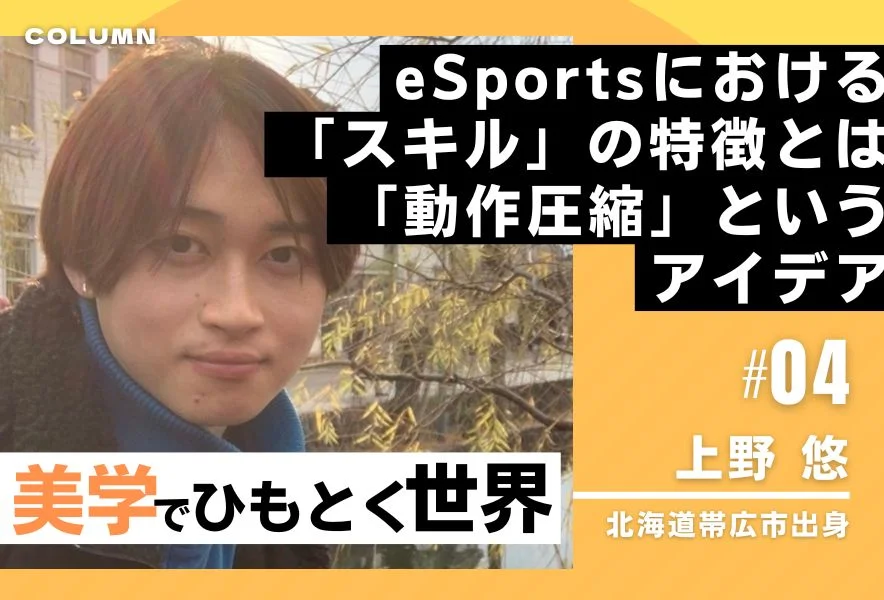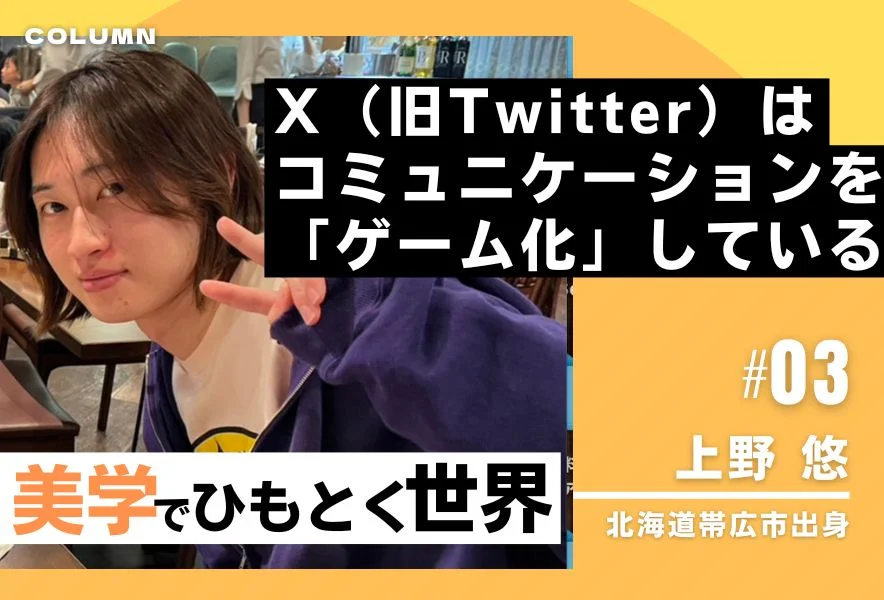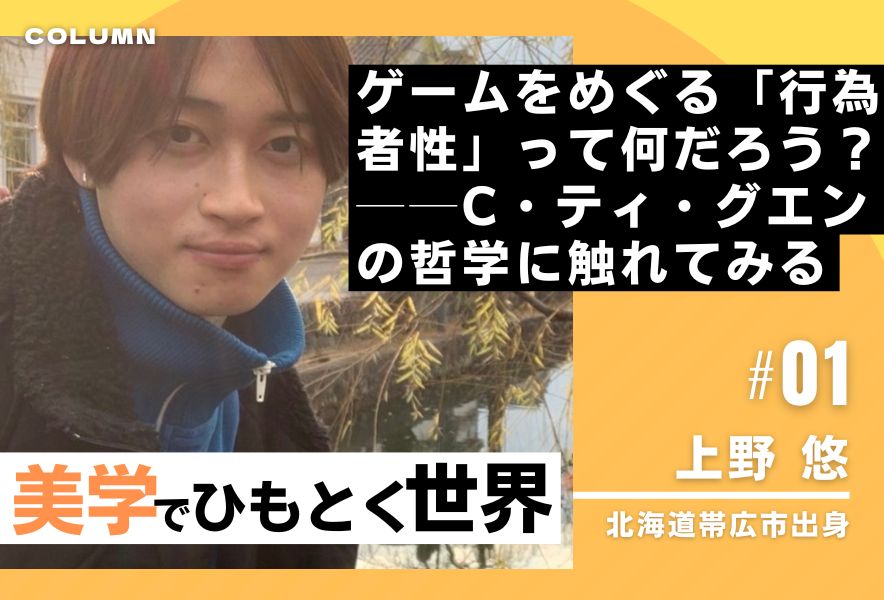【連載】美学者 上野悠の「美学でひもとく世界」
スポーツは、どうでもいいのに、どうでもよくない

みなさん、野球やサッカーなどのスポーツ観戦を(テレビなども含めて)これまでに一度はしたことがあるのではないでしょうか。なかには、特定のチームを応援している人も少なくないでしょうし、さらには、毎週のように現地で応援に参加するような、かなり熱狂的なファンの方もいらっしゃるのではないでしょうか。逆に、スポーツ観戦するときに、どちらにも肩入れせずに応援する、という方は少ないのではないでしょうか。それよりもやはり、特定のチームを熱心に応援して、その勝敗に一喜一憂する、というのがスポーツ観戦の醍醐味とも言えますよね。
そんなスポーツ観戦ですが、ひとによっては、なんでそんなに熱心に応援できるんだろう、と疑問に思うこともあるでしょう。スポーツに全く興味のない人からすると、あるチームやある選手が、勝った負けたなどという事実は、実生活にほとんど影響のない、取るに足らない出来事です。それどころか、熱狂的に応援している人でさえ、一歩引いてみてみると、チームや選手の勝敗が自分の人生にほとんど影響を与えないことがわかるのではないでしょうか。
確かに、応援しているチームや選手が勝った場合は気分がよくなって、その逆もまた然りですし、そのチームや選手を応援しているということが生活に彩りを与えてくれることもあるでしょう。しかし、例えば、自分が働いている会社の売り上げが上がったり下がったりすること(後者は特に重大かもしれません)と比べれば、生活に直接的な影響はあまりない、「取るに足らない出来事」であると考えられるかと思います。
一方でやはり、自分の応援しているチームの勝敗は、かなり気になる事柄のうちに入りますし、ワールドカップやオリンピックなどの国際大会のときには、国中が選手の活躍に注目し、連日のように試合の結果がメディアで取り沙汰されます。スポーツにおける、勝ち負けなどの結果は、「どうでもよくて、どうでもよくない」ことなのです。
スポーツのパズル
ウプサラ大学のニルズ゠へネス・ステアは、このような問題を「スポーツのパズル」と呼び、この謎に答えようとします。ステアはまず、美学における別の大きな謎──「なぜ、われわれが、現実でないと分かっている、虚構(フィクション)上の出来事や登場人物に感情移入してしまうのか」という問い──「フィクションのパラドクス」と似た問題であると捉えることで、この問題を解こうとするアプローチを検討します。

ケンダル・ウォルトンの「メイクビリーブ」理論からのアプローチ
ステアは、ケンダル・ウォルトンによる有名な「メイクビリーブ」理論を参照します。ウォルトンは、なぜ私たちは、ゲームの結果(この場合、ゲーム全体から個々のプレイ、記録の更新など、おおよそゲームの結果すべてを含んでいます)を重要視しているように見えるにもかかわらず、その重要性を否定することもできるのでしょうか。ウォルトンは、その答えとして「ふり(make-believe)」を挙げています。私たちは、子供向けのゲームで遊んだり、フィクション作品を鑑賞したりするとき、ルールに則った想像上の活動に従事していますが、競技ゲームの参加者や観客として参加するときにも、この活動に従事しているのです。
具体的に言うと、スポーツや競争的ゲームに参加する人(観客も含まれます)は、スポーツやゲームの結果が、本当に重要であるとは信じていないかもしれませんが、それが重要であるという「ふり」をしながらゲームに参加しているのです。こうした主張をステアは論文内で「SMB(Sports as Make-Believe)説」と呼ぶことにします。
フィクションのパラドクスとは、分解すると、以下のように構成することができます。
2.私たちは、虚構の出来事や登場人物は存在しないと信じている。
3.私たちは、虚構の出来事や登場人物を、感情を向ける対象とすることができる。
このパラドクスを解決するには、上に挙げた3つのうちの1つを否定しなければなりません。しかし、①も②も③も否定するのが難しいように見えます。
そこで、ウォルトンの解決策は、③を否定することです。ウォルトンの提案では、例えば『ちびまる子ちゃん』において「藤木というキャラは卑劣な奴だ」という読者の発言は、「○○は××である」(例えば「りんごは果物である」)というような“現実世界における”命題を主張するものではなく、その読者が、藤木は卑劣な奴だ、と“虚構的に”主張しているということになります。つまり、その読者は、藤木君を「卑劣な奴だ」と思う「ふり」をしているのです。
ウォルトンは、スポーツにおける観客の態度も、(少し事態はこみいりますが)これと同じようなものだとしています。つまり、わたしたちは、スポーツの結果を重要だと思う「ふり」をしていることになります。

メイクビリーブ説の難点
しかし、ステアは、このSMB説を批判します。ステアはまず、SMBを支持する人たちが採用する理由を挙げ、それらが過度に一般化されていると指摘します。
「気にかけ」の不一致
SMB説が採用される理由の一つは、「重要でないことを気にかける」という、不一致な態度を説明できることです。しかし、ステアはこれについて、いたずらをするときの緊張感や、パズルを解いた時の喜びなどを挙げて、スポーツ特有のものではないと指摘します。
ステアは、オバマ大統領のスピーチを聞きに行ったとき、観衆のうちの一人がジッパーを直そうとしていた時のエピソードを例に挙げています。そのジッパーを直すために、観衆が集まって色々と思案しており、結局ステアはそのジッパーが治るところを見ることはありませんでしたが、もし直っていたら、見ていた人たちは大喜びしていたであろうと想像します。そのように、一般的に言って、注目に値するものでも、歓声や苦悩を呼ぶものでもないと考えられるものが、私たちが、注目したり、歓声を上げたり、苦悩したりする原因となることはよくあると考えられるのです。
立ち直りの早さ
SMB説が採用されるもうひとつの理由は、「スポーツの結果に対する私たちの気にかけの深さと、悪い結果に直面した後の立ち直りの早さとの不調和」を説明できることです。これは、虚構上の悲劇に直面した後の立ち直りの早さに似ています。しかし、このような立ち直りは、フィクションやゲームに限ったものではなく、私たちは現実に起こった、重大な出来事も早く乗り越えることもあります。例えば、ニュースで私たちは、災害などを被る人々を目にし、深く心を揺さぶられるかもしれませんが、生活しているうちに、日常の雑事に気を取られて、そうした心配事を忘れてしまう、ということもよくあります。
こうしたことから、ステアは、スポーツにおける悲劇と、日常における悲劇のような区別を設けて、前者にのみ「メイクビリーブ説」を適用しようとするアプローチに対し疑義を投げかけます。
他にもいくつかの理由から、ステアは結局、他のメイクビリーブ説が当てはまるような活動とスポーツとの間に際立った違いはないのだと主張し、代替案を提示します。

「不安定性」を用いた新たな説明
ステアは、競技の結果に対する私たちの態度は、その他の「ふつうの」行動の結果に対する態度と同じ線上にある、という考え方をカバーした、新たな説明を提示します。ステアは、これらの結果に対する私たちの態度の奇妙に見える部分は、私たちの「気にかけること」全般に関する「不安定性」という観点から説明できると主張します。
ステアによると、スポーツも含めた、私たちの何かをする動機づけとなるような態度は、変動しやすいものなのです。ある人が(スポーツも含めた)何らかの活動に熱中しているとき、その人が直接的に気にかけていることは、ころころと移り変わっていくことがあります。状況の変化によって、特定の意志が際立ったり、まったく新しい懸念が生まれたりもするでしょう。そして、スポーツはそのような「状況」を提供することができるものの一つだと言えるのです。このように、スポーツのパズルは、私たちの動機づけの不安定性と、状況依存性の側面から十分に説明することができるのです。
私たちは、何らかの行動を起こすときに、それが結局何のためであるかをしっかりと把握できていることは、実はほとんどないかもしれないのです。というのは、私たちが、ある行動を起こすときに考慮するような最終目標は、私たちがそれを推測できる範囲において、その行動から、正当化の鎖の数リンク分くらいしか離れていないと考えられるからです。そして、スポーツの結果を気にかけることは、しばしば、この短さがさらに強まった形で現れます。スポーツの結果は、最終目標から1つか2つしか離れていないか、あるいはそれ自体が最終目標であることがあります。
これこそがまさに、スポーツの結果を気にかけることが、「普通の」ケースで気にかけることよりも、より不可解で、より不合理に思えるものにしている理由となるのです。例えば、上司から提示された締め切りを守ることを気にかける場合、なぜ納期を守らなければならないのか⇒商品を期日通りに発送するため、それを気にかける理由は⇒配送を保証するため、それを気にかける理由は⇒顧客を満足させるため、などと言ったように、手段と正当化される最終目標の連鎖はより長くなります。一方で、スポーツの場合は、この連鎖はほとんどの場合即座に途切れます。これが、スポーツの結果を気にかけることがふつうよりも不合理に見える理由となるのです。
ネーゲルの「バックステップ」論による補強
それでは、なぜ、正当化と理由づけの連鎖が短いと、長いものよりも不合理に思えるのでしょうか? ステアは、トーマス・ネーゲルによる「バックステップ」についての説明を参照します。ネーグルは、叙勲式の最中にズボンがずり落ちた場合を例に出し、見せかけと現実が衝突すると、状況は不条理に思えるのだと説明しています。私たちは、個々の取り組みについて考えるとき、「バックステップ」を踏んで、取り組み全体を俯瞰し、その取り組みの要点を検討したり、評価したりします。通常、このステップにより、取り組みを評価するための「基準」が明らかになります。
例えば、自分の仕事を評価する際には、一歩下がって、自分の所属する組織の基準で評価することが考えられます。また、自分の所属する組織の価値を問うこともできます。このようにバックステップをどんどん踏むごとに、より究極的な基準が見えてくるようになります。そうして、ある状況や取り組みが、後ろにある基準に達していないとわかっていながらもなお、その状況や取り組みに依然として関わり続けている場合、その人は不条理に直面していると言えるのです。

ステアが言うには、スポーツはバックステップを一歩や二歩踏むだけで、この「不条理」にたどり着くことになります。なぜなら、スポーツへの関心は、私たちの他の多くの関心事から相対的に独立しており、したがって、スポーツの結果を気にかけるような態度が、より究極的な基準に達していない──つまりは不合理な態度であること──が容易に理解できるからです。
そしてステアは、ここからさらに、この考えが正しいと思えるような事例を挙げます。ステアが言うには、スポーツの結果(試合における点数や勝敗など)が、それに関連するより大きなスポーツの結果の構造に埋め込まれている場合、目的達成の手段として、小さいほうの結果を気にかけることは、それ自体が単独で存在する場合よりも、より理にかなっているように思われるのです。つまりは、例えば、試合に勝つため、リーグで優勝するため、プレーオフに進出するためなどといった、より大きな目的があれば、得点獲得を気にかけることは、それ以上の目的もなくただ一点獲得することに気にかけることよりも、明らかに不合理ではないということです。このことから逆説的に、ただ一点を気にかけることが不合理であると説明されるのです。
ヴェルマンの「メタ願望」論による補強
ステアはもう一人、デイヴィッド・ヴェルマンという人による論によって、自説を擁護しようとします。ヴェルマンは、動機づけの変動性は、自分の行動に「意味を持たせる」ためのメタ願望の形によって説明できる可能性を示しています。メタ願望とは、自分自身の継続的な物語に自分の行動を適合させようとする、通常の願望よりも上の階層にいる願望のことです。自分の行動を理解したいという欲求が、自分自身によるさまざまな行動の意味づけと結びつくことで、行動を導く中心点に意味づけのための物語を当てはめるように、さまざまな動機づけの態度を促進することになるのです。
ヴェルマンの説明は、私たちが、チームを応援する、勝者になるなど、スポーツへの参加に関する意味づけを、意識的であろうとなかろうと採用していることを理解させてくれます。この意味づけと、自分の行動を理解したいというメタ願望が組み合わさり、この意味づけに最も一致する態度(例えば、応援したい、頑張りたい、という気持ちや、負けを悔しく思う傾向など)が前面に出てきて、そうでない態度(例えば、公平でありたい、など)は、脇役に回るようになります。ネーゲルのバックステップ論が「どうでもいいのに」を説明するとすれば、ヴェルマンの論は「どうでもよくない」を説明するような感じですね。
グエンによる「行為者性の層」との比較
以上のステアによる論を、以前僕が書いた記事にある、C・ティ・グエンによる「行為者性の層」論と比べると、かなり似た視点を持っていることがわかります。グエンは、ゲームのプレイヤーが「奮闘を楽しむ」という大きな目的を抱えながらも、プレイ中はそのことを忘れて「勝利すること」を唯一の目標として集中できる、という態度の構造を「行為者性の層」と呼び、プレイヤーが複数の行為者性の層を行き来することを「行為者性の流動性」と位置づけていました。ステアの言う、正当化と理由づけの連鎖、並びにスポーツにおけるその短さへの着目も、これと似たものと言えるでしょう。
一方で、グエンが行為者性の層をゲームに特徴的なものとしていた側面があるのに対し、ステアはむしろその「短さ」をスポーツに特徴的なものとしています。このことをどうとらえるかはまだ考え切れていませんが、ここに着目すると、かなり興味深いことが浮かび上がりそうにも思えます。

美学者とは
美学者の役割
- 【美的判断】なぜある人が「美しい」と感じる対象を、別の人は「そうでもない」と思うのか
- 【芸術作品の価値】作品が私たちの感性に与える影響を、どう評価し、言葉で説明できるか
- 【日常の美】ファッションやインテリアなど身近なところに潜む「美しさ」をどのように考えるか
こうした問いに取り組むのが美学者の役割です。近年では、ゲームの体験やデザイン、スポーツや身体表現、さらにはSNSなど、従来は「美学」とはあまり結びつかなかった分野にまでその探究範囲が広がっています。哲学や芸術学と深く関係しながら、現代社会のあらゆる「感性の問題」に光を当てるのが、美学者と呼ばれる人々なのです。

【PROFILE】
北海道帯広市出身。早稲田大学文学研究科博士後期課程在籍。専門は、ゲーム研究、美学。主な論文に、「個人的なものとしてのゲームのプレイ: 卓越的プレイ、プレイスタイル、自己実現としての遊び」『REPLAYING JAPAN 6』、「ゲームにおける自由について──行為の創造者としてのプレイヤー──」『早稲田大学大学院 文学研究科紀要 第68輯』。ゲームとファッションとタコライスが好き。