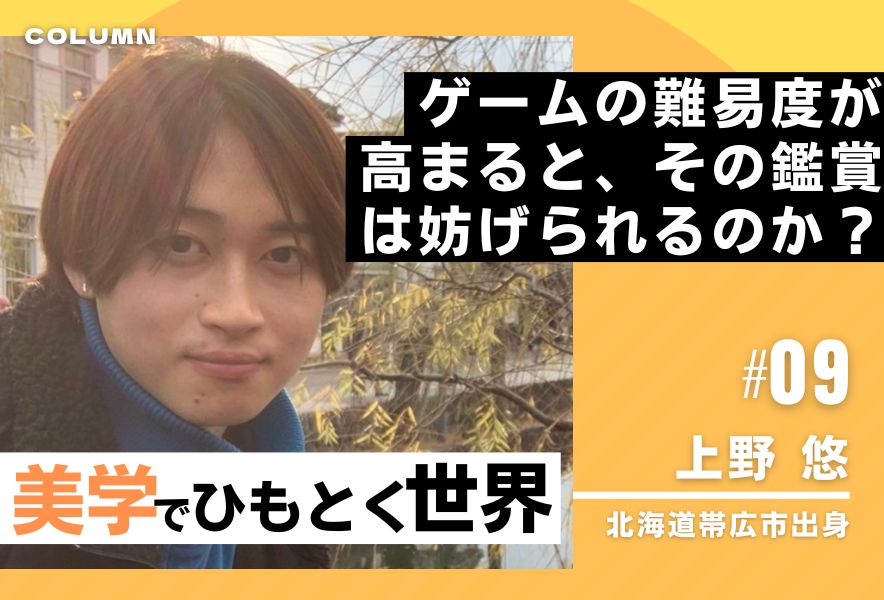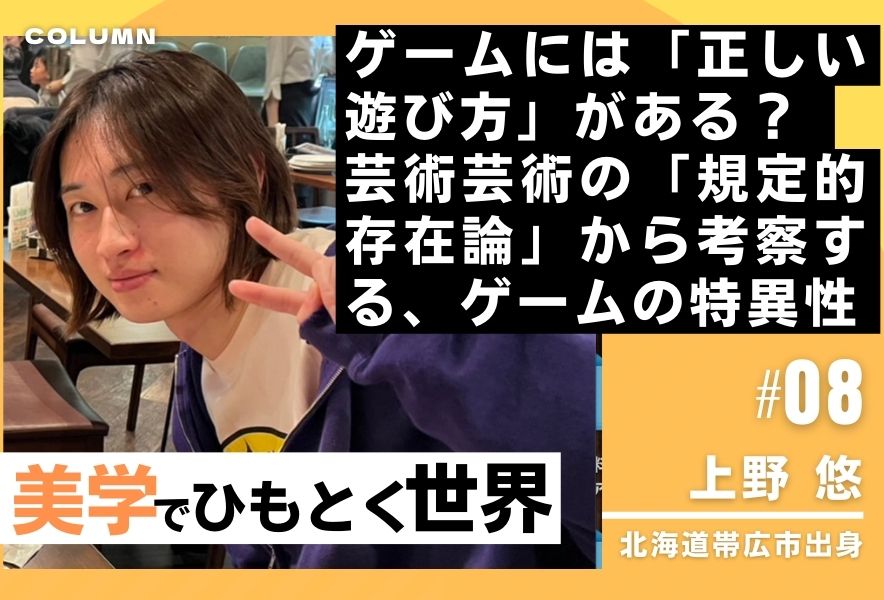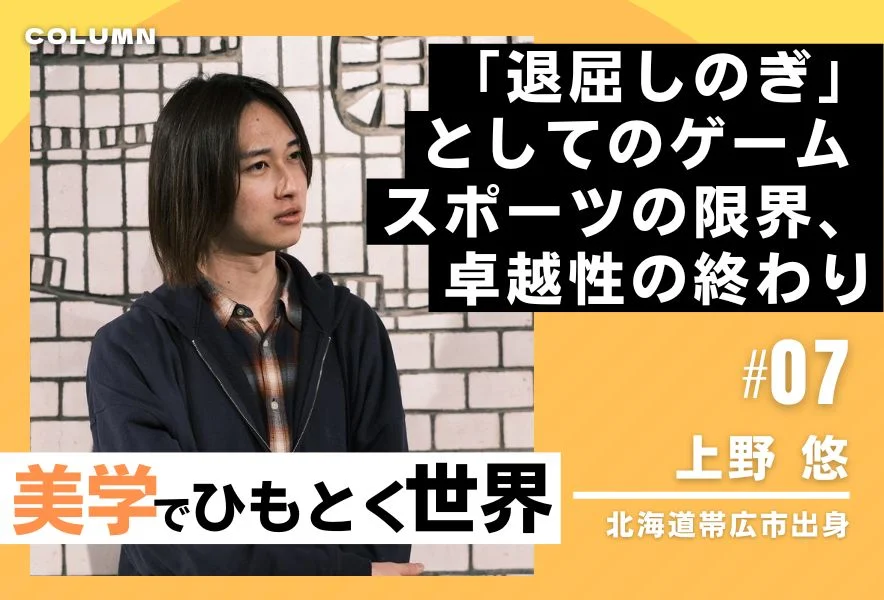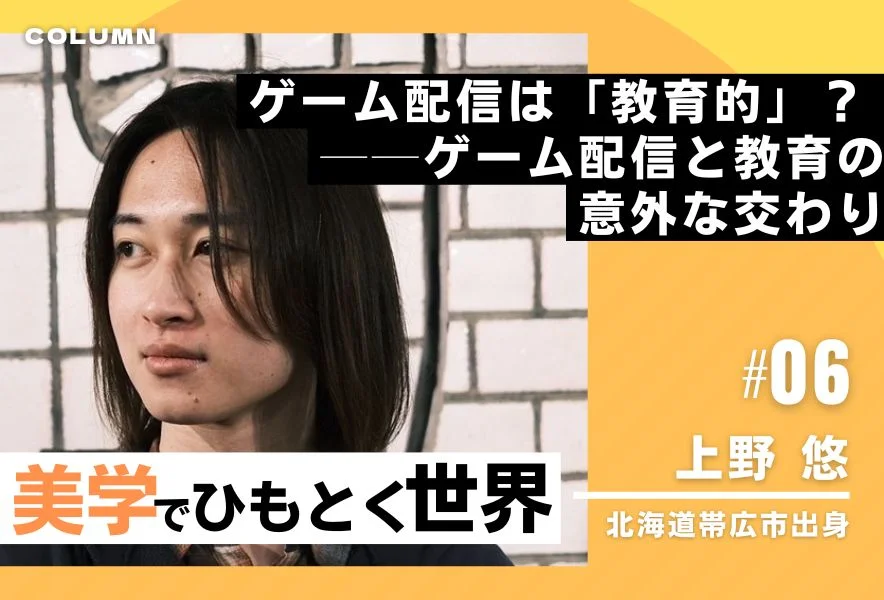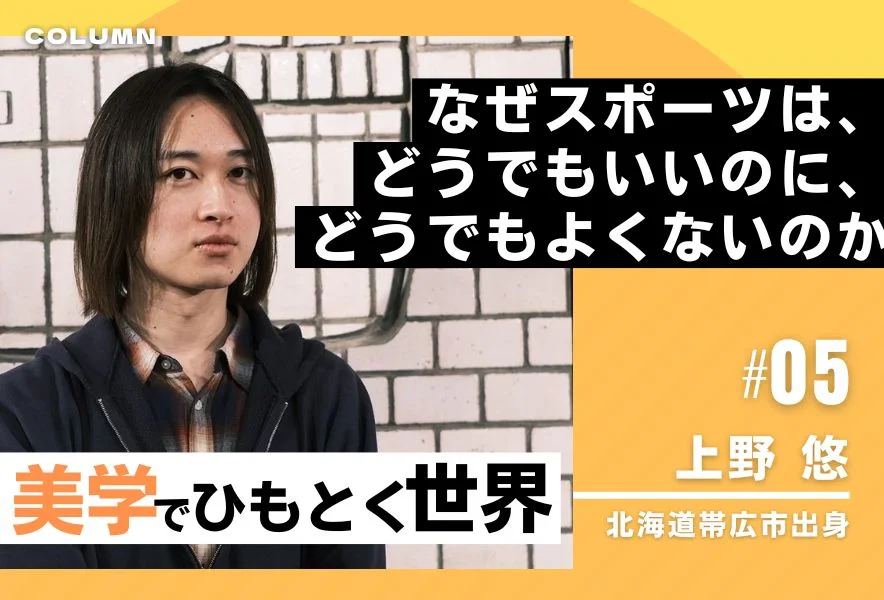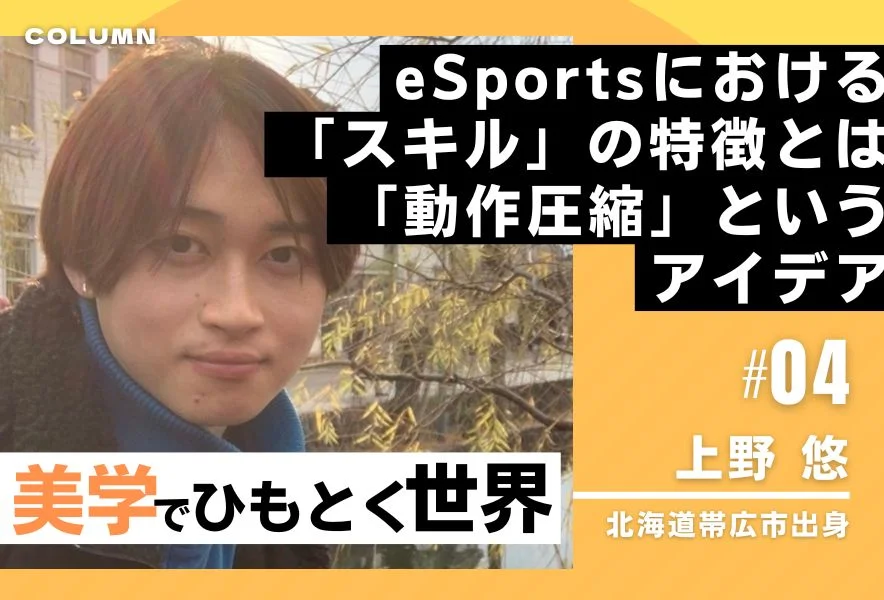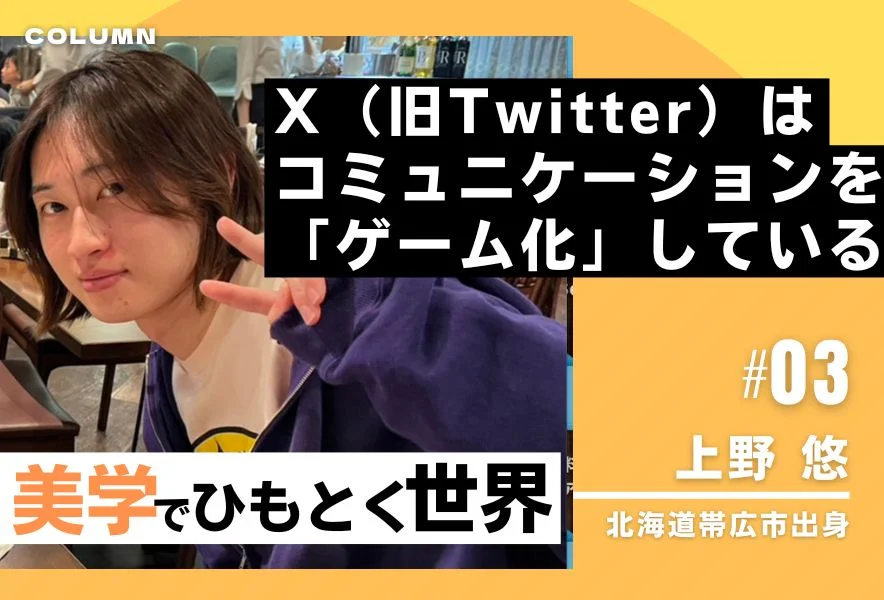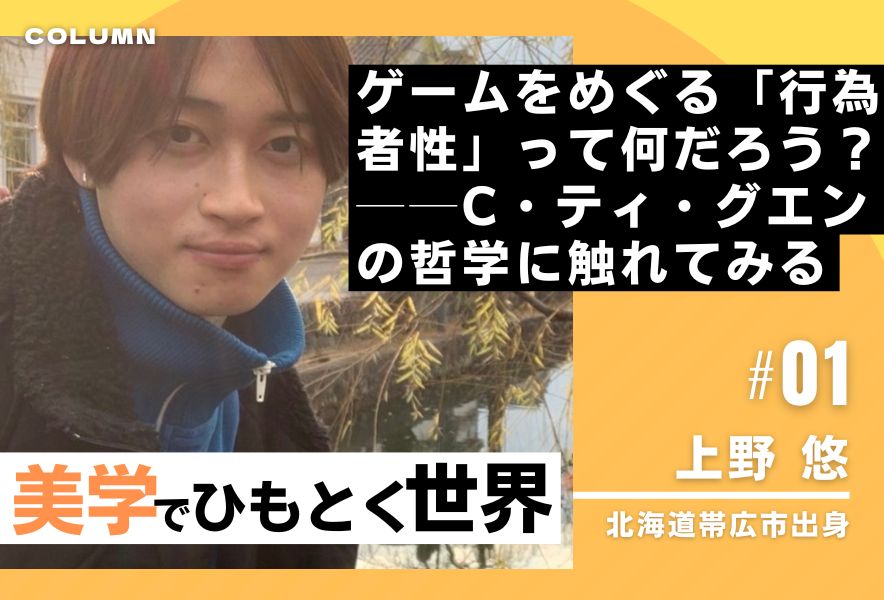【連載】美学者 上野悠の「美学でひもとく世界」
ゲームであることと芸術であることは相いれない?

多くのビデオゲーム作品では、ゲームによって提供される挑戦課題をクリアするために、しばしば、複雑かつ素早く熟練した、身体動作の連なりを求められます。そうした難易度の高い身体動作は、ゲームプレイに「歯ごたえ」を与えてくれるため、一般的に言って、ゲーマーたちからは歓迎される傾向にあります(そうでないこともありますが)。先日発売されて好評を博している『モンスターハンターワイルズ』(カプコン 2025)などはその好例でしょう。
一方で、ゲームを──どんな意味であれ──美的関与(Aesthetic engagement)の対象として考えたい人たちにとっては、こうしたゲームと難易度の高さの関係によって、ある問題が生じてしまう可能性があるのです。
難易度の高いゲーム特有の美学的問題
ミシガン大学の准教授であるアデレミ・アルティス(Aderemi Artis)は、「ゲームをプレイするために必要な注意の性質とその量の多さは、美的関与の余地を排除してしまうのではないか」という問題──彼はこれを「極度の難しさ(extreme difficulty)にまつわる議論」と呼びます──に反論しようと試みています。
アルティスはまず、上記のような主張は、「強いバージョン」と「弱いバージョン」の二通りが考えられると述べています(*ここで使われている「強い/弱い」という言葉は、論としての説得力の強弱を意味するものではなく、取っている立場の強硬さのようなものを表しています)。強いバージョンの主張とは以下のようなものです。
しかし、この強いバージョンの主張は、ビデオゲームの「反省的な鑑賞」(Lopes 2010; Jurgensen 2018)や、「パフォーマンス的観賞」(Robson 2018)を挙げることによって退けられます。プレイヤーは、ビデオゲーム作品をクリアした後に、その作品について深く考えて評価することができるし(反省的鑑賞)、外部の観賞者によって、そのプレイをパフォーマンスとして評価されること(パフォーマンス的鑑賞)も可能なのです。こうした事例によって、「難易度の高いビデオゲームを美的に鑑賞することはできない」という強い主張は退けられます。
しかし、強い主張を退けたことによって、それが修正された「弱いバージョン」の主張が浮上してきます。アルティスは、弱いバージョンの主張を次のようにまとめます。
アルティスは、この弱いバージョンにも反論することを試みます。
「弱いバージョン」の暗黙の前提

アルティスは、この弱いバージョンの主張に、暗黙のうちに前提とされている点がいくつかあることを指摘します。
まず、アルティスによると、ゲームが提供する課題を実行するという活動と、その活動、もしくは、ゲームプレイ中に現れる(活動以外の)ものの美的特徴に注意を払うことは、同一ではない、という主張が暗黙のうちに存在しています。
そうであるならば、それ自体が美的関与のモードであるようなゲームプレイが存する可能性を一見のうちに排除することはできないと反論される余地があります。アルティスはここでもう一歩踏み込み、ゲーム内でジョン・ケージの『4分33秒』が流れ、それに耳を傾けなければならない、という課題があるビデオゲーム作品、というケースを想像するように促します。このようなゲームプレイは、どう考えてもおかしく、少なくとも、「弱いバージョンの主張」が言及したいようなゲームプレイではないのです。
このことから、アルティスは、「弱い主張」のような、ゲームプレイの課題はそれ自体、美的関与のモードと同一にはならないという考え方は、実際のビデオゲームの歴史の厚みと豊かさのもとに確立された、われわれにとってなじみ深いゲームプレイの慣習、状況、活動が暗黙のうちに想定されているのだと結論づけます。つまり、弱い主張の前提には、ジャンプや、火の玉の投擲、魔法の行使といった、ゲームらしい行為が設定されているのです。また、もっと具体的に言えば、ここでは、複雑でテンポが速く、実行するのが難しい、「瞬間的な動き」が重視されたゲームプレイ──アルティスは「トゥイッチ・ゲームプレイ(twitch gameplay)」という俗語を用いています──が想定されていると考えられるでしょう。
素早い動作が要求される、トゥイッチ・ゲームプレイは、ターン制でプレイが進行するビデオゲーム作品などと比べると、美的鑑賞を妨げる可能性が高いと言えます。また、芸術作品や自然物を対象としてとるような、伝統的な美的鑑賞を考える場合、その傾向はより強まります。
最終的にアルティスは、次のような3つの前提をもった主張を、弱いバージョンの主張の最終版として提示します。
- 時に、十分に難易度の高いビデオゲーム作品のゲームプレイで、最も困難な瞬間においては、プレイヤー自身が目の前の課題に最大限の注意を払うことが必要となる。
- これらの課題は、プレイヤーに継続的で、複雑で、激しく、反射的な身体運動を要求するため、プレイヤーのゲームプレイへの関与度は、美的なものを含むビデオゲームの 他の側面への関与能力と反比例する。
- ゲームプレイの成功に必要な身体動作の難易度が極めて高いことは、多くの場合、優れたトゥイッチ・ビデオゲームであることの重要な要因となっている。
固有受容感覚を通した美的鑑賞

アルティスは、ダンスをもとにした「固有受容感覚(proprioception)」にまつわる理論に訴えて反論しようとします。アルティスは、「一部の」ダンスは、踊っている最中に、踊っている本人が美的鑑賞を達成することを目的として、実際にそれに成功することも可能であると考えるのは、決して突飛な考えではないだろう、と主張します。
アルティスは、こうした主張の参照元として、バーバラ・モンテロによる、「固有受容感覚(proprioception)」というものを美的感覚として扱うことができるという主張(Montero 2006)を挙げています。
固有受容感覚について説明しましょう。固有受容感覚とは、大まかに言うと、自らの身体の動き、力の入れ具合、身体の位置などについての、筋肉や関節を通して感じることができる感覚のことです。例えば、目をぶっていても自分の腕の位置が把握できたり、足元を見なくとも階段を上り下りできたりするのは、この固有受容感覚が働いているおかげでもあります。
バーバラは、我々はこの固有受容感覚においても美的なものを感じ取ることができると主張しているのですが、その主張を通すためにはいくつかの壁が存在します。バーバラは、十分納得のいく形でそれらに答えようと試みており、その議論もかなり面白いのですが、バーバラの議論に深く踏み込むのはまた次の機会にしたいと思います。
トゥイッチ・ゲームプレイは「ダンスというよりデッドリフト」

しかし、固有受容感覚が美的感覚として扱うことができたとしても、そっくりそのままゲームプレイに適用してよいのかという問題が生じます。というのも、バーバラは「ダンス」をその範例として考えているからです。
アルティスは、ダンスとビデオゲームのプレイ、それと「デッドリフト」そこでアルティスは、ダンスとビデオゲームのプレイ、それとデッドリフト(パワーリフティングの一種目で、床に置かれたバーベルを立った状態で持ち上げる競技)を対比して、議論を進めていきます。アルティスは、ダンスにおいては、固有受容感覚を通して美的鑑賞を行い、それに基づいた相互主観的に理解可能な判断をすることができる、という主張が妥当なものであることを前提条件とし、デッドリフトをそのような鑑賞ができないものと仮定して、ダンスと対置させます。
すると、問題になるのは、ビデオゲームのプレイヤーの身体の動きは、ダンサーに近いのか、それとも、デッドリフトに近いのかということです。さらには、それらに限らずとも、トゥイッチ・ゲームプレイは、激しい身体運動を伴うようなあらゆる活動と十分に類似しているため、プレイヤーが(ダンスのように)継続的に美的鑑賞を行うことができると信じるに足るものなのか、というような疑問の余地があることを指摘しています。
というのも、トゥイッチ・ゲームプレイはダンスよりむしろデッドリフトに似ていると思われる点が多く見当たるからです。アルティスは、トゥイッチ・ゲームプレイがダンスよりもデッドリフトに近いと考える理由の一つとして、手段と目的の関係を挙げています。ビデオゲームには、ボス敵を倒す、決められたラインに到達する、など、目標が定められているものが多くありますが、一連の身体動作の終点にそうした目標がおかれています。このことはデッドリフトに類似しており、デッドリフトにおける「ロックアウト」と呼ばれる目標は、グリップを握る、腰を据えて引く、などといった一連の動作の終点に位置しています。目的に対して手段があり、それらは切り離されて存在しているのです。
これに対して、ダンスにおける固有受容感覚による美的鑑賞は、一連の動きの各動作と同時に行われます。つまり、ダンスにおいては、少なくともそれらの動作が起こっている最中については、手段と目的を切り離すことができないように思われると、アルティスは指摘しています。こうしたことから、ダンスのような活動における手段と目的の関係は、ビデオゲームのプレイやデッドリフトの場合とは異なる性質のものであると考えられるのです。
さらにアルティスは、トゥイッチ・ゲームプレイをダンスのように扱うことを疑うもう一つの理由として、不正行為(cheating)の在り方の違いを挙げています。例えば、デッドリフトでは、 「靴底に接着剤を塗る」ことで不正を行う可能性が、『パックマン』では、コードを操作して追いかけてくるゴーストを遅くすることで不正を行う可能性があります。こうした例において、プレイヤーは、自分のパフォーマンスの成果を偽るために、ルールを破っています。

一方で、ダンスにおける不正行為とはどのようなものでしょう。アルティスは、ダンスにおいては伝統的慣習がルールの代わりのように機能すると前提し、実際にはそうではないのにもかかわらず、まるでそのような慣習にしっかりと従って表現できているように、自らをだます自己欺瞞がこの場合は不正行為になるとしています。この帰結はゲームプレイやデッドリフトとは大きく異なります。
以上の2点から、アルティスは、トゥイッチ・ゲームプレイがダンスよりむしろデッドリフトに似ていること、そして、デッドリフトは、ふつう、美的な評価の対象となることはない、ということを認めざるを得ないことであると言います。しかしながら、それでもなお、デッドリフトやビデオゲームをクリアしようとするような活動には、固有受容感覚的な美学鑑賞を生み出す可能性があるのだ、と主張することはできると述べているのです。
アルティスは、デイヴィッド・ベスト(Best 1978)による、スポーツの美学に関する議論を参照し、スポーツにおいて、プレイが「上手く決まった」瞬間に着目します。ベストは、例えば、スカッシュで、絶妙なタイミングでの完璧なショットを決めた瞬間のような経験は、美的なものとして特徴づけるのが最も適切であると述べています(Best 1978, 11-12)。また、こうした経験は、ボールを打つ瞬間に「浸る」ための時間があるかどうかに左右されず、自分のパフォーマンスを振り返って熟考することだけに限定されるものでもないような美的経験なのです。
こうしたベストによる説明をゲーム中の身体の動きにも適用できるのであれば、プレイヤーがゲーム上のタスクを完遂することに最も強く、かつ限定的に専念している場合でも、固有受容感覚的な美的鑑賞を達成することができるのだとすることができると思われます。そしてそれは、アルティスが述べたように、ゲームプレイとデッドリフトがかなりの程度類似するものなのであれば、それは十分可能であると考えられるでしょう。
ゲームプレイの「調和」と「エレガンス」

アルティスは、このようにしてトゥイッチ・ゲームプレイが固有受容感覚的な美的鑑賞を達成しうることを示唆したうえで、その美的判断がどのようなものになるかについて、二つの具体例を挙げます。
ひとつは、「調和」です。この調和とは、プレイヤーの精神や身体の能力が最大限に引き出され、挑戦課題に対しギリギリのところで適合するような形のものであり、自己と挑戦、現実の自己とその世界の障害との間に達成されるような調和です(Nguyen 2020, 12-13)。実際、多くのビデオゲーム作品はこのような調和を達成するために、プレイヤーが利用できるリソースを制限したり、プレイヤーの取れる行動を限定したりしているのだとアルティスは指摘しています。
つぎに「エレガンス」です。ここでのエレガンスとは、「最大限の経済性と効率性」をもって課題を完遂すること(Best 1978, 106)というような意味です。アルティスは、スピードラン(日本では「RTA=リアルタイムアタック」と呼ばれることの多い、ビデオゲーム作品をいかに早くクリアできるかを競う競技のことです)の文脈において、より効率的なスピードランを追求する過程で、通常であれば踏破する必要のある面やゲーム内環境の大部分をスキップできるバグが発見され、利用されるという事例を挙げ、スピードランの大きな魅力の一つとして「エレガント」な移動経験が挙げられることを指摘しています。
アルティスは、ビデオゲームを美的関与の対象として考えた場合、「難易度が高ければ高いほど、好まれる傾向にある」というビデオゲームの特徴と相いれなくなってしまうのではないか、という問題に対し、まずその問題自体を分析しクリアな形にして提示したうえで、固有受容感覚を美的感覚として捉えることができるというモンテロの理論を参照しましたが、それをそのままビデオゲームのプレイに適用することはせず、そうすることの問題点を洗い出し、最終的には、ビデオゲームがダンスよりもスポーツに近いことから、スポーツの美学におけるベストの議論を援用することで、難易度の高い身体動作を含むビデオゲームのプレイでも、美的関与の対象として捉えることができるということを示しました。このように、しっかりと段階を踏み、問題を整理しながら議論を進めていくことが、哲学や美学の議論をしていく上ではとても重要なのです。
参考文献
- Artis, Aderemi. 2021. “The Argument from Extreme Difficulty in Video Games.” Journal of Aesthetics and Art Criticism 79 (1): 64-75.
- Best, David. 1978. Philosophy and Human Movement. London: Allen & Unwin.
- Jurgensen, Zach. 2018. “Appreciating Videogames.” In The Aesthetics of Videogames, edited by Jon Robson and Grant Tavinor, 60–77. New York: Routledge.
- Lopes, Dominic McIver. 2010. A Philosophy of Computer Art. New York: Routledge.
- Nguyen, C. Thi. 2020. Games: Agency as Art. Oxford University Press.
- Robson, Jon. 2018. “The Beautiful Gamer? On the Aesthetics of Videogame Performances.” In The Aesthetics of Videogames, edited by Jon Robson and Grant Tavinor, 78–94. New York: Routledge.
美学者とは
美学者の役割
- 【美的判断】なぜある人が「美しい」と感じる対象を、別の人は「そうでもない」と思うのか
- 【芸術作品の価値】作品が私たちの感性に与える影響を、どう評価し、言葉で説明できるか
- 【日常の美】ファッションやインテリアなど身近なところに潜む「美しさ」をどのように考えるか
こうした問いに取り組むのが美学者の役割です。近年では、ゲームの体験やデザイン、スポーツや身体表現、さらにはSNSなど、従来は「美学」とはあまり結びつかなかった分野にまでその探究範囲が広がっています。哲学や芸術学と深く関係しながら、現代社会のあらゆる「感性の問題」に光を当てるのが、美学者と呼ばれる人々なのです。

【PROFILE】
北海道帯広市出身。早稲田大学文学研究科博士後期課程在籍。専門は、ゲーム研究、美学。主な論文に、「個人的なものとしてのゲームのプレイ: 卓越的プレイ、プレイスタイル、自己実現としての遊び」『REPLAYING JAPAN 6』、「ゲームにおける自由について──行為の創造者としてのプレイヤー──」『早稲田大学大学院 文学研究科紀要 第68輯』。ゲームとファッションとタコライスが好き。