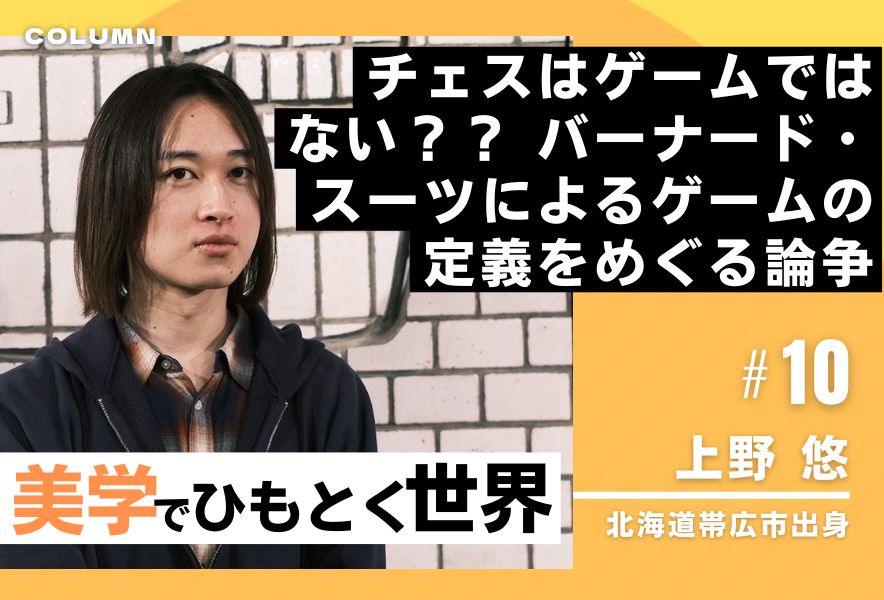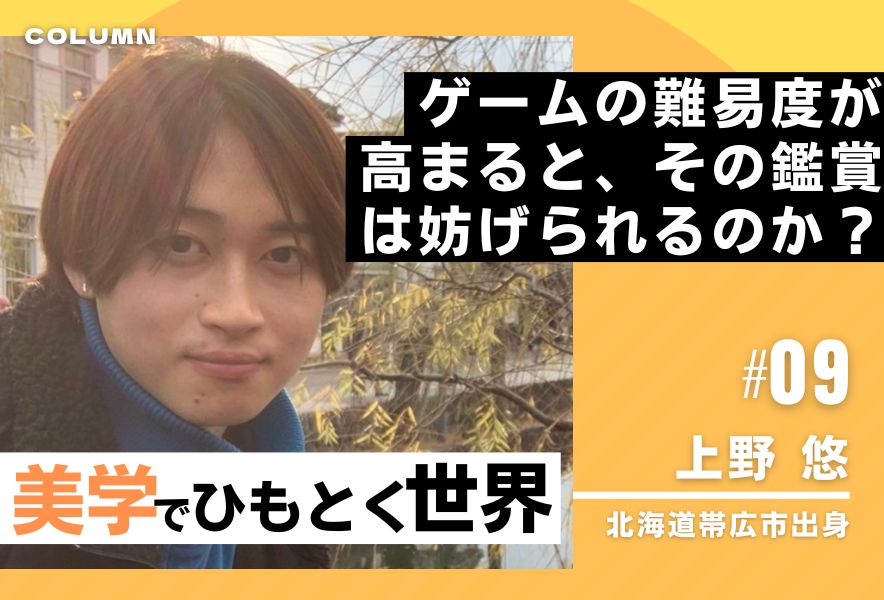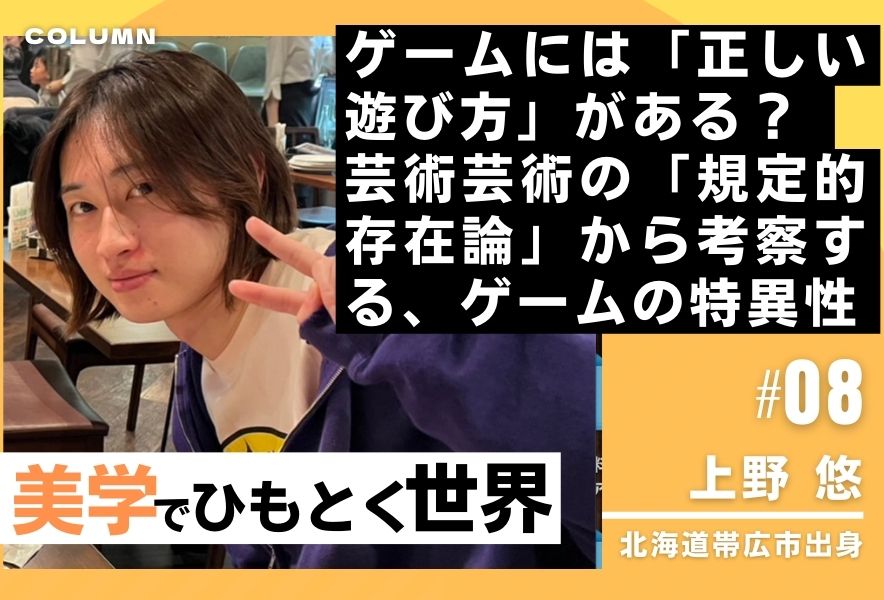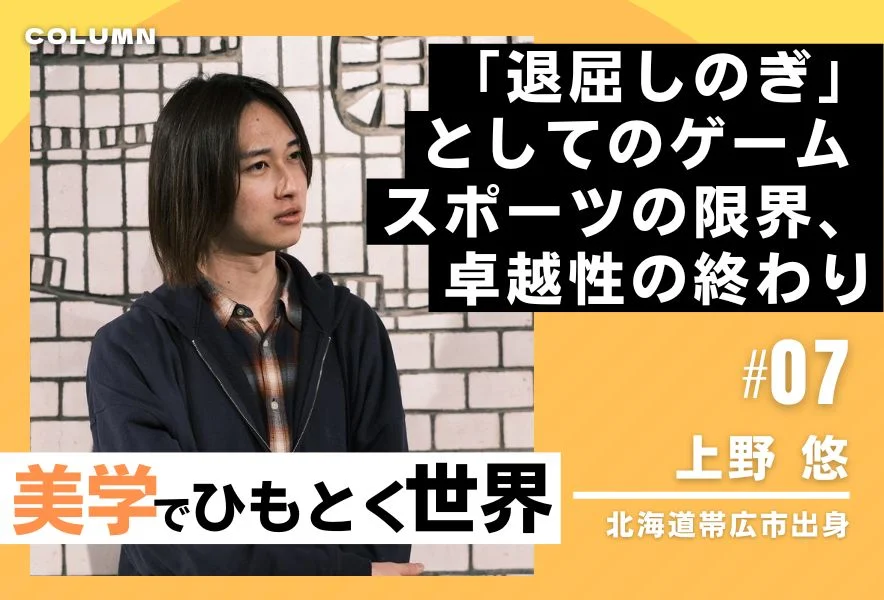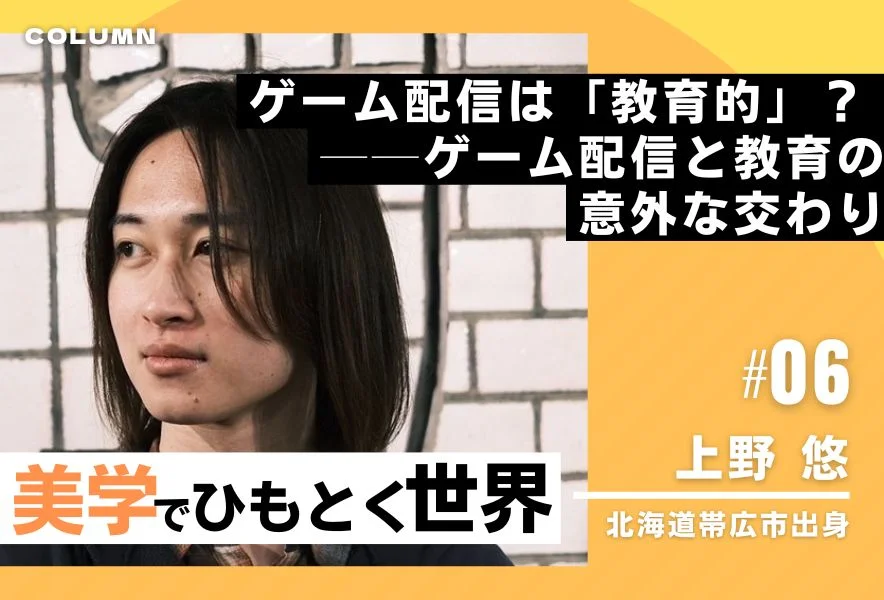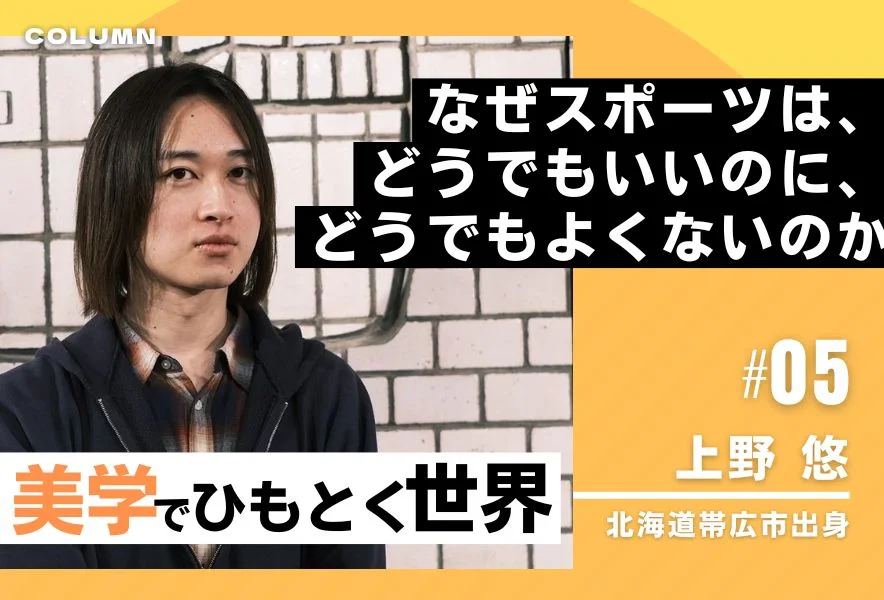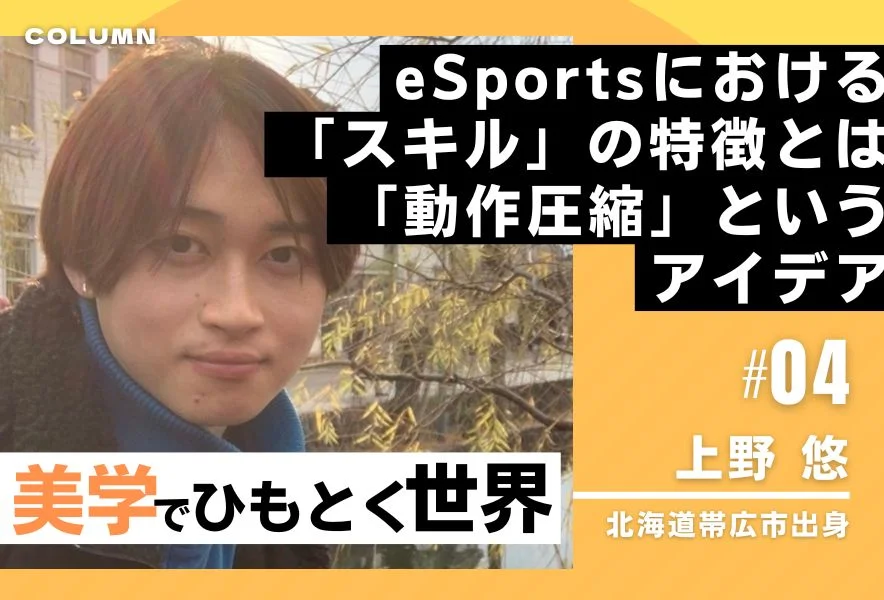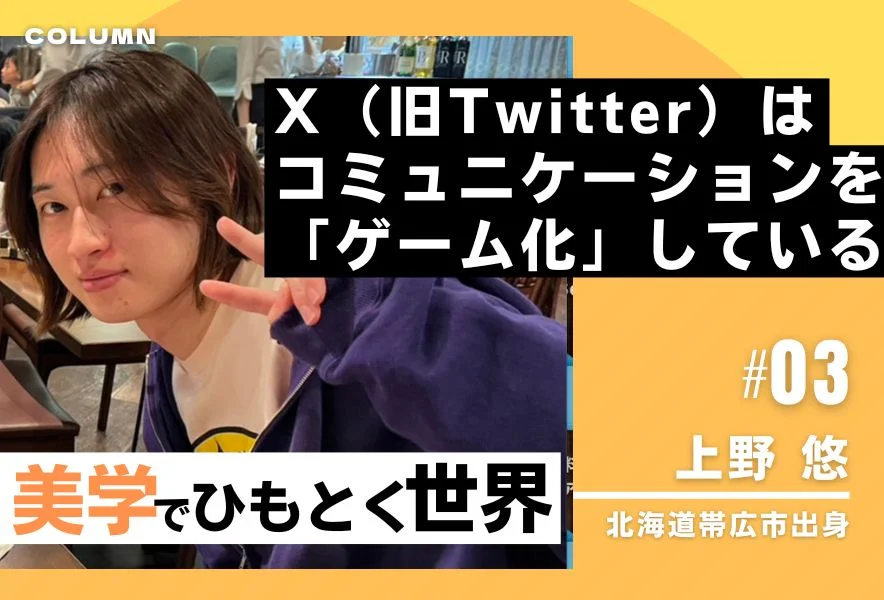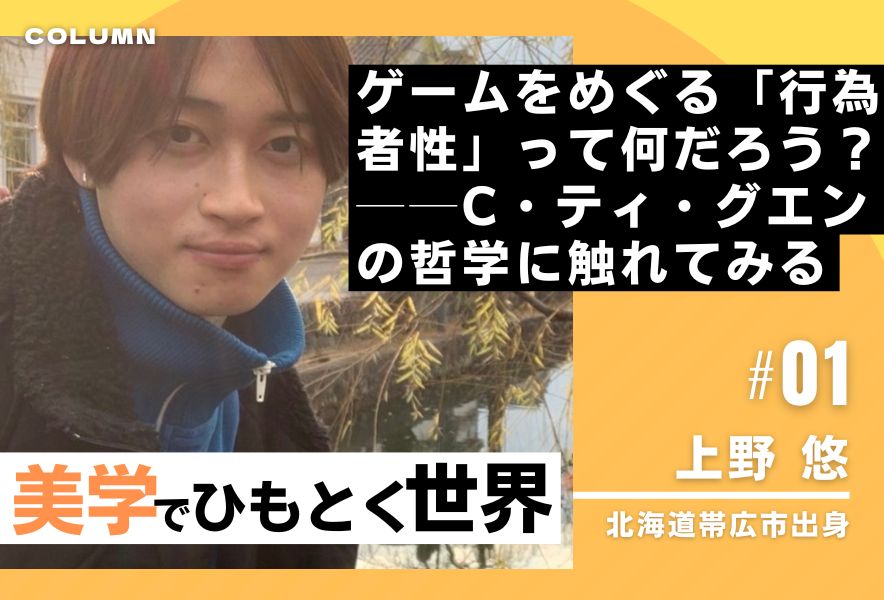【連載】美学者 上野悠の「美学でひもとく世界」
チェスはゲームじゃない? そんなわけある?

もし「チェスはゲームですか?」と聞かれたら、多くの人は「なんでそんな分かり切ったことを聞くんだ」と思うことでしょう。チェスがゲームであることはだれもが知っている常識、つまり「自明」のことのように思われます。それどころかむしろ、チェスはゲームの中でも、もっとも「ゲームらしい」存在、つまりゲームというものの「範例」として扱われているようなケースも珍しくありません。
ところが、そんな自明のことに挑戦しようとする人が存在するのです。トレント大学の准教授であるマイケル・ヒクソンは、その名も「幻のチェックメイト:なぜチェスはゲームではないのか」という論文で、「チェスはゲームではない」という驚きの主張をしています。
ゲームの定義について
しかし、そんな主張がどのようにして成り立つのでしょうか。我々の直観に大きく反することを主張するには、それなりの論理を組み立てなければなりません。ヒクソンはどのような根拠があってそのような主張をするのでしょうか。
まず、「チェスはゲームではない」と主張するためには、「ゲームとはどのようなものであるのか」をある程度明確に提示しなければなりません。というのも、例えば、「ゲームとはこういうものである。チェスはしかじかの点でゲームとは異なる。だから、「チェスはゲームではない。」と述べるとして、「こういうものである」の部分が、我々のおもう「ゲーム」から大きくズレている、ゲームの中心的な特徴を捉えられていない、などといった理由で到底受け入れられないようなものだった場合、その主張は成り立ちません。

このような背景には、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインという哲学者による、ゲームの「完全な」定義は不可能である(かなりざっくり言うと、ですが)という主張があります。我々は、さまざまな存在物をゲームというカテゴリの中に含めますが、そのような存在物のすべてを特徴づけるような共通の定義は存在しないという意味で、こうしたゲームのようなものを「家族的類似」と名付けました。そして、ウィトゲンシュタインによるこの見解はかなり広く受け入れられているものなのです。
それでは、ゲームの定義を示すのは不可能なのでしょうか。それは、必ずしもそうではありません。“すべての”ゲームを含むような定義を作ることは難しくても、ある程度広い範囲のゲーム──誰しもがこれはゲームであると認めることができるようなもの──に共通するような特徴を並べることは十分可能であり、また、そうすることの意義も十分に認められるのです。
バーナード・スーツによる定義
そんなわけで、ゲーム研究においては、ゲームを定義しようとする試み、いわゆるゲームの定義論が結構盛んにおこなわれているのですが、なかでもバーナード・スーツという哲学者による定義が、非常に強い影響力を持っています。
まず、スーツはゲームそのものを定義するのではなく、「ゲームをすること」を定義しようとします。スーツによるゲームをすることの定義は、端的に言うと「不必要な障害を自ら望んで乗り越えようとすること」です。
〇スーツによる定義
ゲームをプレイすることは、ルールの認める手段[ゲーム内部的手段]だけを使ってある特定の事態[前提的目標]を達成する試みであり、そのルールはより効率的な手段を禁じ、非効率的な手段を推す[構成的ルール]。そしてそうしたルールが受け入れられるのは、そのルールによってそうした活動が可能になるという、それだけの理由による[ゲーム内部的態度]。(邦訳、37頁)
スーツは、「ゲーム内部的手段」、「前提的目標」、「構成的ルール」、「ゲーム内部的態度」という4つの独自の概念を用いることで、ゲームをすることを定義しようとしているのですが、今回の議論で重要なのは、「前提的目標」という概念です。

前提的目標
前提的目標とは「達成可能なある特定の事態」というようにも説明されますが、ようするに、チェスで言えば「チェックメイト」、徒競走で言うと「フィニッシュラインを越えること」のような、個々のゲームの目標となるものです。チェックメイトは同時にそれを達成したものの勝利も意味するので分かりづらいですが、目標とは必ずしも「勝利」ではありません。この辺はスーツ定義の勘違いされやすいところです。スーツの考えでは、勝利の前にまず、目標となるような何らかの事態(例えば、「フィニッシュラインを越える」)があって、それを前提として「勝利」(例えば、「“どのプレイヤーよりも先に”フィニッシュラインを越える」ことで達成される)という第二の目的が生まれるのです。
この前提的目標は、論理的に言って、ゲームのルールやその適用よりも前に存在するものでなければなりません。この点が今回の論点になります。なぜならば、スーツにとってゲームのルール(=構成的ルール)とは、「前提的目標を達成するための手段を制限するもの」だからです。手段というものは目的があって初めて存在しうるものです。だから、「ある目標を達成するための手段を制限する」ようなルールが、目標より先に存在するのはおかしいのです。
ゲームの「制度」
実は、スーツ自身もチェックメイトがスーツによる定義に含まれないのではないか、と言う反論を予期してそれに応えています。
なぜチェックメイトがスーツ定義から外れるように思われるのかというと、チェックメイトはそのゲームのルールなしには存在しえないような目標に思われるからです。この点は徒競走と比較するとわかりやすいでしょう。徒競走における「フィニッシュラインを越える」という目標は、別にゲーム中でなくても達成することができます。歩いて(あるいは自転車に乗りながらでも)線を横切ればいいのです。しかし、チェックメイトという事態は、チェスのルールによって設定されているものであり、チェスというゲーム抜きには存在しない事態のように思われます。
これに対してスーツは、「ゲームのルール(rules)」と「ゲームの制度(institution)」の区別によってこれを退けようとします。ゲームのルールは上記の「構成的ルール」と同じものですが、それに対し、ゲームの制度とは、チェスの駒のそれぞれの動き方などを示す、「記述的」なものです。これは現実で言う「物理法則」のようなものと言うとわかりやすいでしょうか。
ちょっとわかりづらいこの概念を、スーツは「ふざけ屋(trifler)」、「いんちき屋(cheat)」、「荒らし屋(spoilsport)」という3タイプのダメな(=ゲームをプレイしていることにならない)プレイヤーの例を出して説明します。今回はふざけ屋の部分だけ取り上げましょう。
ふざけ屋とは、チェスのルールには従ってはいるものの、チェックメイトという目標を目指さずに、別の目標のためにプレイしていたり、ただただふざけて適当に駒を動かしていたりするだけのプレイヤーです。こうしたプレイヤーはチェスをプレイしているとは言えませんが、チェスの「制度」の内側で行動していることにはなります。このように、制度には違反せずに、しかしゲームをプレイしていることにはならない、ということが可能なのは、ゲームの制度とゲームそのものが区別されているからなのです。
この考えに則って、スーツは「チェックメイト」を前提的目標として示すように求められたときは、単にチェックメイトの形を盤上で作って示せばいいのだと答えています。
ヒクソンによる論

さて、スーツによるゲーム定義についてざっくりと解説したところで、ヒクソンがどのように、チェスがそれに当てはまらないことを示しているのかを説明していきたいと思います。
ヒクソンは、チェスがゲームではないことを「チェックメイト」をいくつかの分類に分けることで説明しようとします。まず、ヒクソンによるチェックメイトの定義とは以下のものです。
しかし、先ほどの、前提的目標と勝利の区別を思い出してください。プレイヤーは不正な手を使うことで、前提的目標を達成することができますが、そのことによって勝利したことにはなりません。このことはチェックメイトの更なる区別を示唆します。
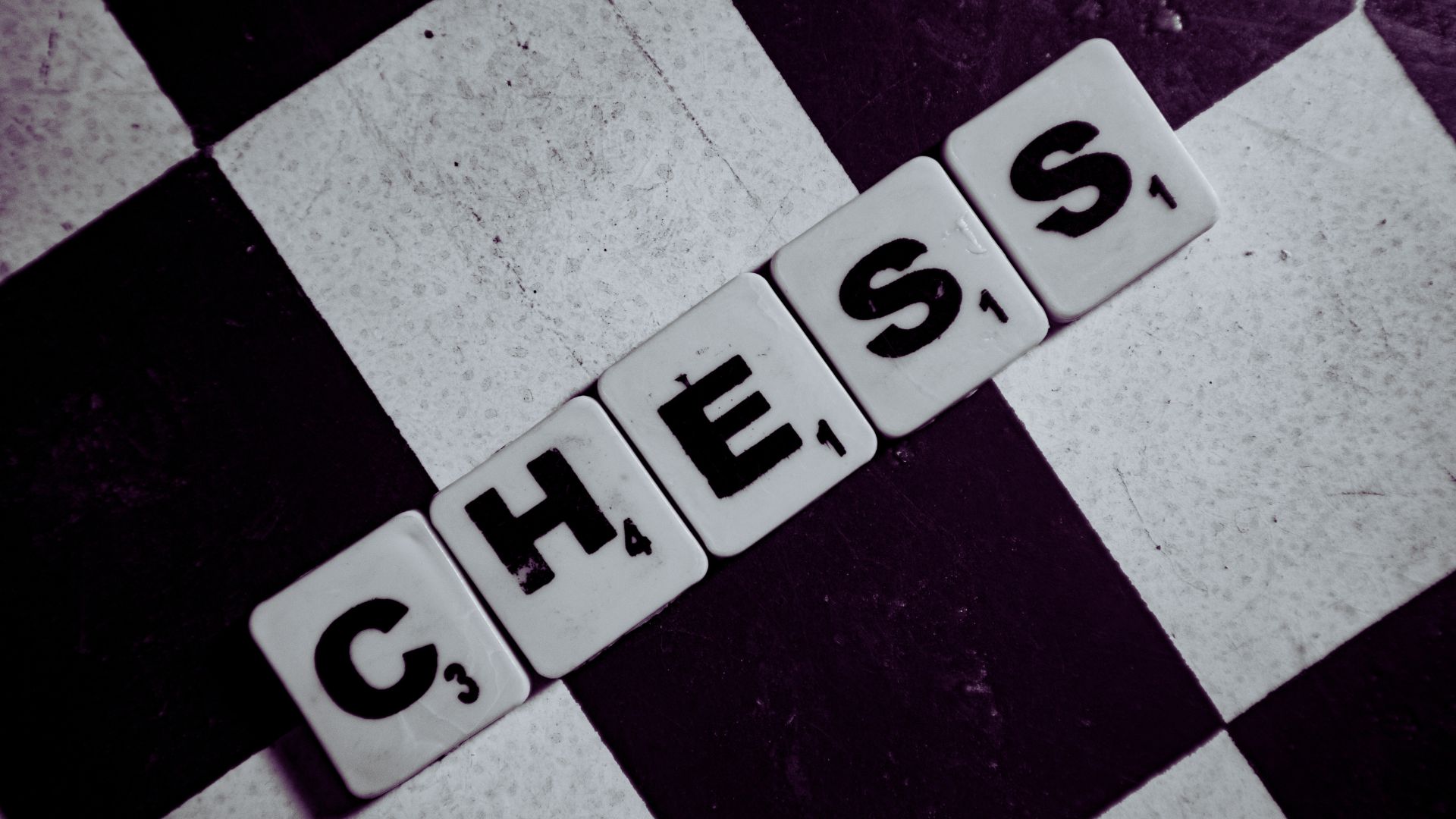
幻のチェックメイト
ヒクソンはさらに、違法な手にも二つのパターンがあることから更なる区別を取り入れます。不正行為を行うプレイヤーは、ふつう、不正であることがばれないように、チェスのルール上、「ありうる」ような盤面を作ろうとするでしょう。しかしながら、もし不正行為をしようとするプレイヤーが不注意だった場合、チェス盤上で「ありえない」ような盤面、合法な手のみで行われたチェスの試合からは決して生まれないような盤面を作り出してしまうかもしれません。そのことから、ヒクソンは次のような区別を導入します。
ヒクソンは、この「幻のチェックメイト」に注目します。幻のチェックメイトが、一目見て、違法な状態だとわかる分には問題ないのですが、議論を呼ぶと思われるのは、それが違法であることが、一目ではわからないような場合です。ヒクソンはハーバード大学の数学者でありながら、チェスのナショナルマスターや、チェス・ソルヴィング(詰将棋のようなもの)の元世界チャンピオンという称号を持った卓越したチェスプレイヤーである、ノーム・デイビッド・エルキーズの作ったチェックメイトの図を持ち出します。
ここではその図を取り上げることはしませんが、ヒクソン曰く、その図が指し示す状況は、一目見て幻だとわかるものではなく、かなりチェスに精通した人でないとわからないようなものだそうです。
ここでヒクソンは、チェックメイトが前提的目標であるための条件を持ち出し、そのうちの一つとして、チェックメイトが前提的目標であるためには、「いかなる特定のチェスの試合に依存せずに達成可能であることが示せるようなものでなければならない」ということを取り上げます。
ヒクソンはさらに複雑な図も示しながら、一部のチェスのチェックメイトが「ゲーム内部的チェックメイト」か「幻のチェックメイト」かを判断するために、そのチェックメイトの盤面から初期位置まで逆行しながら分析し、それが可能かどうかを証明する必要があるということを示唆します。このような場合、そのチェックメイトが幻であるという判断は、特定のチェスの試合に依存してしまっているのです。
リッジの反論

ヒクソンのこの考えに対し、エジンバラ大学の教授、マイケル・リッジはさらに反論しようとしています。
リッジは、ヒクソンは「達成可能性」をスーツが示している以上のものとして解釈してしまっているのだと指摘します。リッジが言うには、「チェスにおける特定のゲームとは無関係にチェックメイトが可能であること」を示すよう求められたときに、スーツは単に、チェスゲームをプレイしなくてもチェスボード上でチェックメイトの状況を作り出すことができる、つまり、特定のチェスゲームとは無関係にチェックメイトを表示できることを指摘しているだけです。それに対しヒクソンは、ゲームのゴールとしてある状態を表示するには、それがルールに従って達成されたことを知らなければできないと考えているようですが、リッジはその点を問題視します。
リッジは、ヒクソンの達成可能性の解釈に対するこの反論には、2 つの問題があると述べています。
一つ目が、上記の通り、「スーツは、到達可能性は目標を目標として表示できることを必要とする、といった命題を一度も記述していないこと、また、そうした命題を必要とするわけでもない」という点です。チェスの目標がチェックメイトであることをまったく知らなくても、盤上にチェックメイトの形を再現することは可能なのです。
二つ目が、「ある種の目標であることを知らずに、ある種のゴールとして何かを表示することはできないという命題は、誤りである」という点です。これをリッジは非常に分かりやすい例を挙げて説明しています。何らかの際に身分証明書の提示を求められた際、求められた人(この場合リッジ本人)は、自分の大学職員カードを身分証明書として提示します。なぜなら、その人はそれが身分証明書として有効だと信じているからです。
しかしながら、その場では、大学職員カードは有効ではなく、運連免許証だけが身分証明書として有効だった、というケースを考えてみてください。彼がこの事実を知らなかったからといって、彼がそのカードを有効な身分証明書として提示しなかったということにはなりません。それはただ、その人の提示が誤りだったというだけのことになります。つまり、それが本当は有効でない場合でも、そのものを有効なものとして提示することは(そして間違えることは)可能なのです。以上のことから、リッジは「達成可能」という語をヒクソンの主張が要求するような極めて強い意味で解釈する必要はないと結論づけます。
ゲームに制度には目標は含まれなくてもよい

ヒクソンの論に反論するなかでリッジが提示するのは、「チェスのようなゲームの制度には必ずそのルールが含まれるが、その目標は含まれなくてもよい」ということです。リッジが言うには、このことは、チェスの試合におけるルールは規定的なものである一方で、制度に関連するルールは、単に記述的なものであると考えるのが自然だということを説明してくれているのです。
リッジはそこまでは述べていませんが、僕のイメージでは、ゲームのルールは、「チェックメイト」のような目標が置かれ、ゲームプレイがはじまるときにはじめて、ルールが実際に「制限」として機能するのであり、そうでないとき(プレイされていないとき)は──絵画における絵具やキャンバスのように──そのゲームの存在を支えるものとして存在しているという感じです。これをスーツやリッジは、規定的ルール/記述的ルール、もしくは、制度という言葉で表現しているのだと思います。
だから、リッジも話に挙げていますが、チェスの制度だけ使って、一般的に言うチェスとは別のゲーム──負けを目標とするチェスや、駒の総取りを目標とするチェス──を行うことが可能になるわけです。
規定的ルールと記述的ルールの区別
今回紹介したヒクソンとリッジは、いずれも「分析哲学」と呼ばれる哲学的伝統に身を置く哲学者です。分析哲学では、今回紹介したように、ある論に対しての批判や反論、それに対してまた反論が・・・というように続いていく中で、議論を発展・洗練させていこうとする流れがあります。今回紹介した「チェスはゲームなのか否か」についての論争は、その雰囲気が感じられるものだったのではないでしょうか。
また、今回出てきたキーワードにゲームにおける「ルール」と「制度」の区別がありましたが、この点に関しては、以前に紹介したC・ティ・グエンによる「ゲームの正しい遊び方」についての論にも似たような話がありましたね。グエンによる論では、ビデオゲームにおける普通のプレイと、「スピードラン」と呼ばれる変わったプレイが例に上がっていましたが、これはまさにゲームにおける制度とルールの区別に起因するようなものと考えられるでしょう。こうした区別はゲーム研究においてはかなり重要なものとなってきているように思えます。
参考文献
- Hickson, Michael. 2022. “Illusory checkmates: why chess is not a game.” Synthese 200 (5):1-21. DOI: https://doi.org/10.1007/s11229-022-03855-z
- Ridge, Michael. 2024. “Chess is Still a Game.” Journal of the Philosophy of Games 5 (1). DOI: https://doi.org/10.5617/jpg.10845
- Suits, Bernard. 2014. The Grasshopper: Games, Life, and Utopia. 3rd ed. Toronto: Broadview Press. (『キリギリスの哲学──ゲームプレイと理想の人生』川谷茂樹・山田貴裕訳、ナカニシヤ出版、2015年)
美学者とは
美学者の役割
- 【美的判断】なぜある人が「美しい」と感じる対象を、別の人は「そうでもない」と思うのか
- 【芸術作品の価値】作品が私たちの感性に与える影響を、どう評価し、言葉で説明できるか
- 【日常の美】ファッションやインテリアなど身近なところに潜む「美しさ」をどのように考えるか
こうした問いに取り組むのが美学者の役割です。近年では、ゲームの体験やデザイン、スポーツや身体表現、さらにはSNSなど、従来は「美学」とはあまり結びつかなかった分野にまでその探究範囲が広がっています。哲学や芸術学と深く関係しながら、現代社会のあらゆる「感性の問題」に光を当てるのが、美学者と呼ばれる人々なのです。

【PROFILE】
北海道帯広市出身。早稲田大学文学研究科博士後期課程在籍。専門は、ゲーム研究、美学。主な論文に、「個人的なものとしてのゲームのプレイ: 卓越的プレイ、プレイスタイル、自己実現としての遊び」『REPLAYING JAPAN 6』、「ゲームにおける自由について──行為の創造者としてのプレイヤー──」『早稲田大学大学院 文学研究科紀要 第68輯』。ゲームとファッションとタコライスが好き。