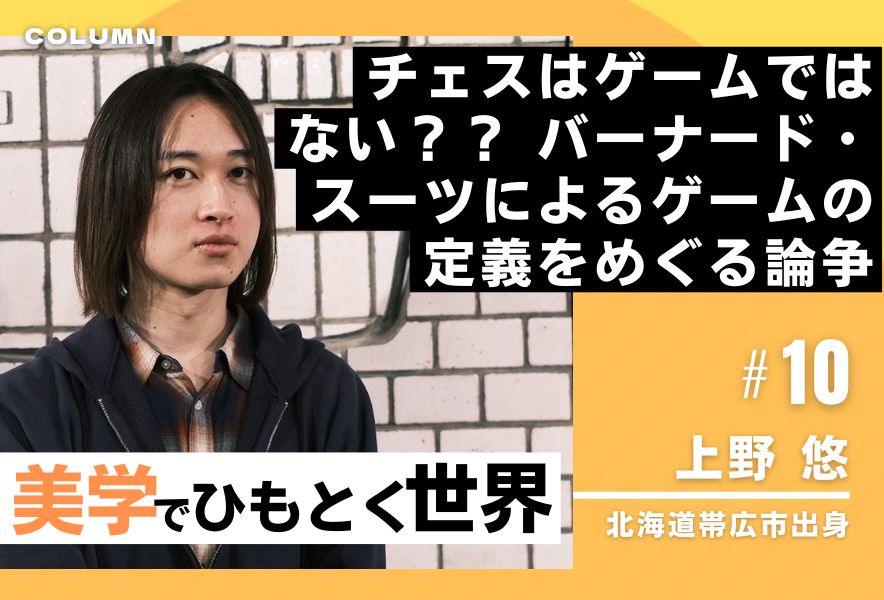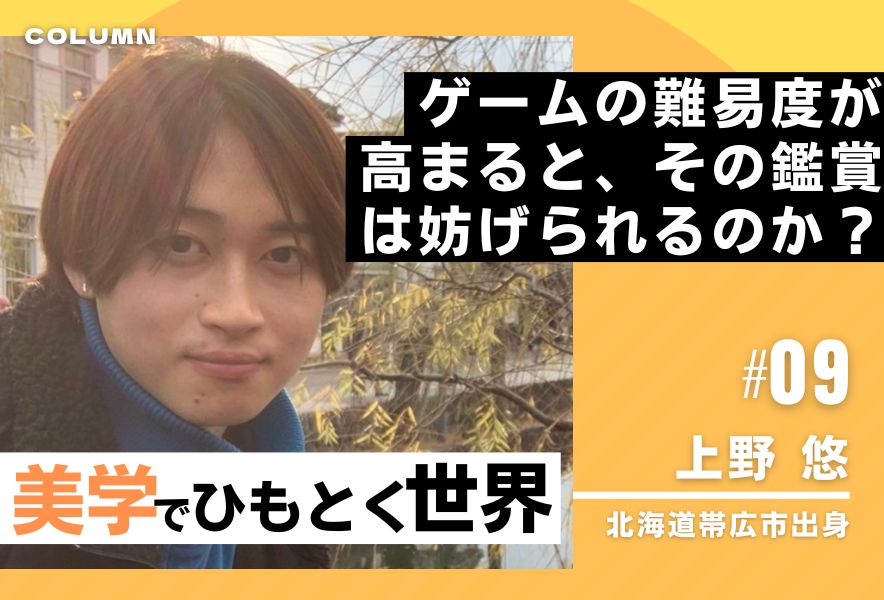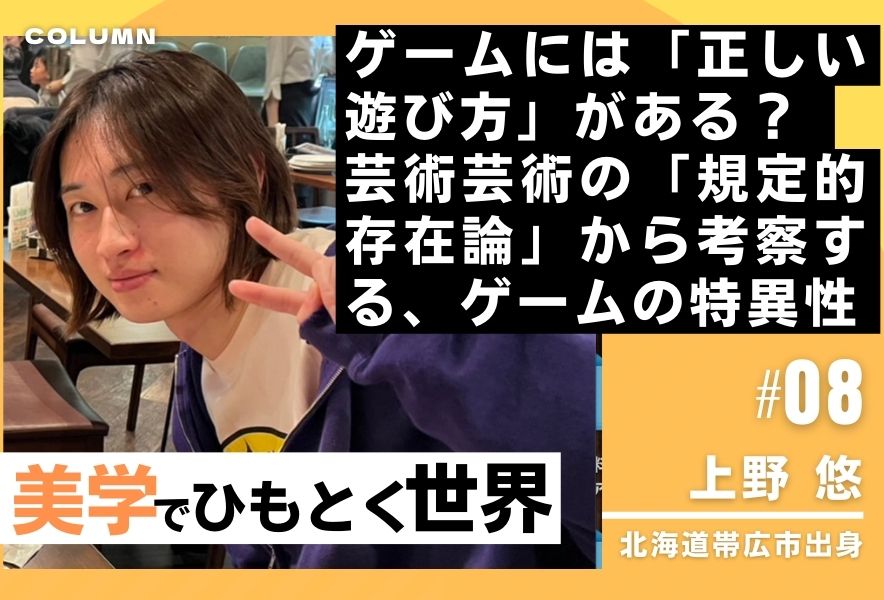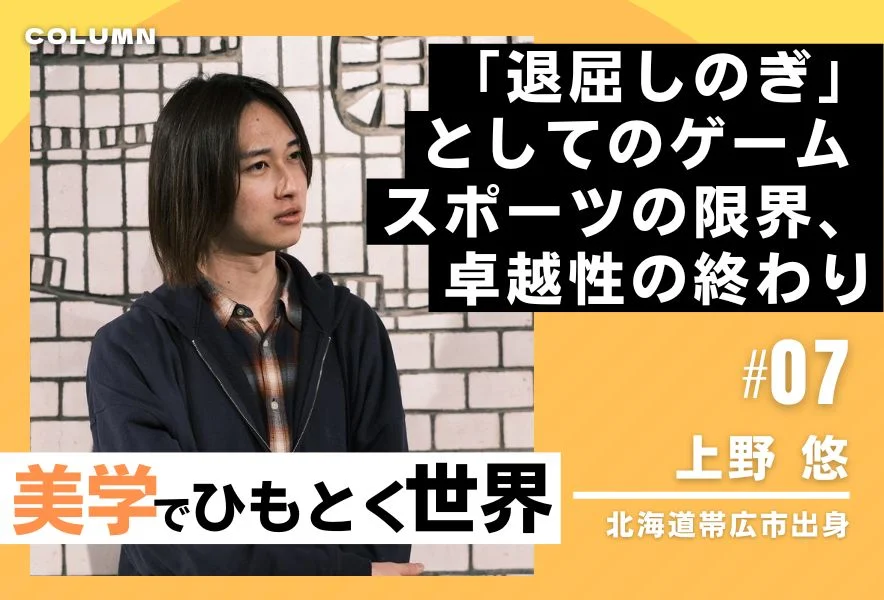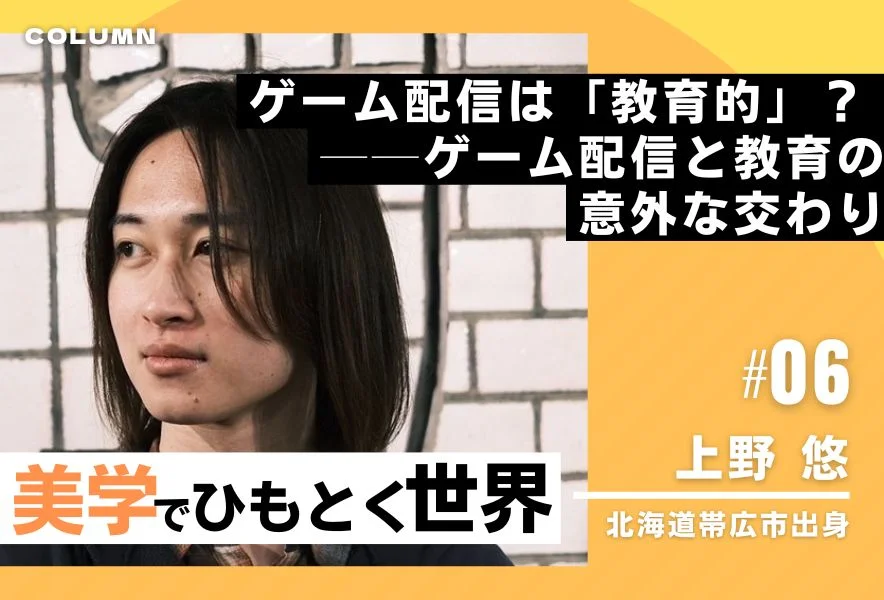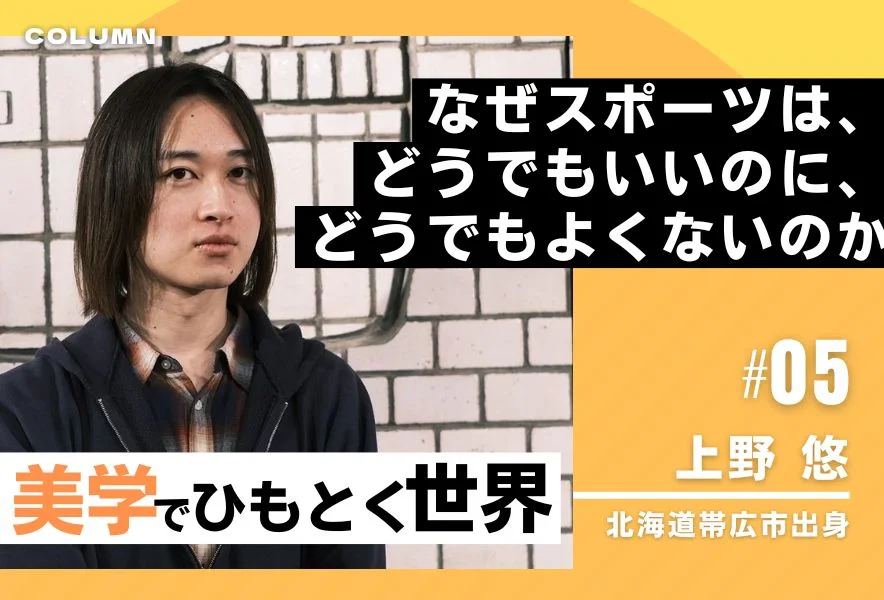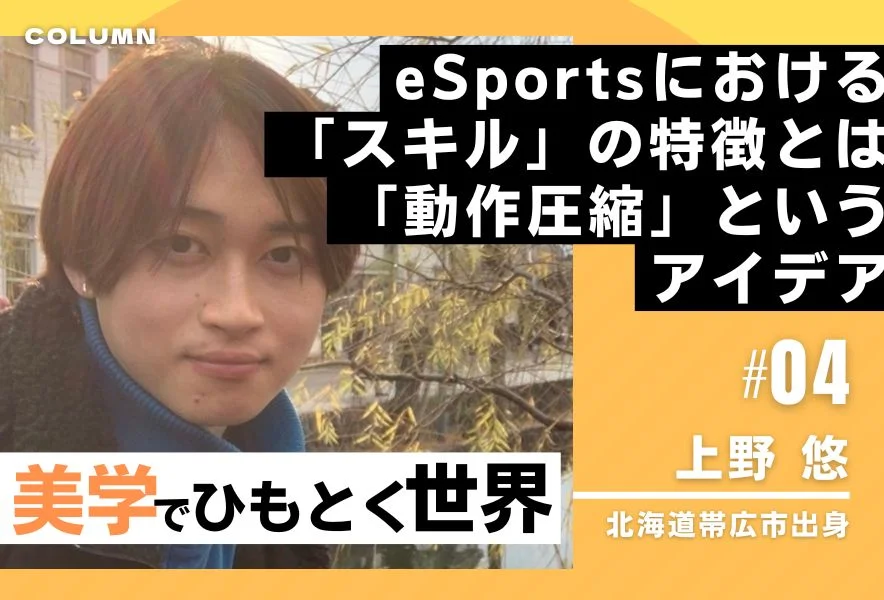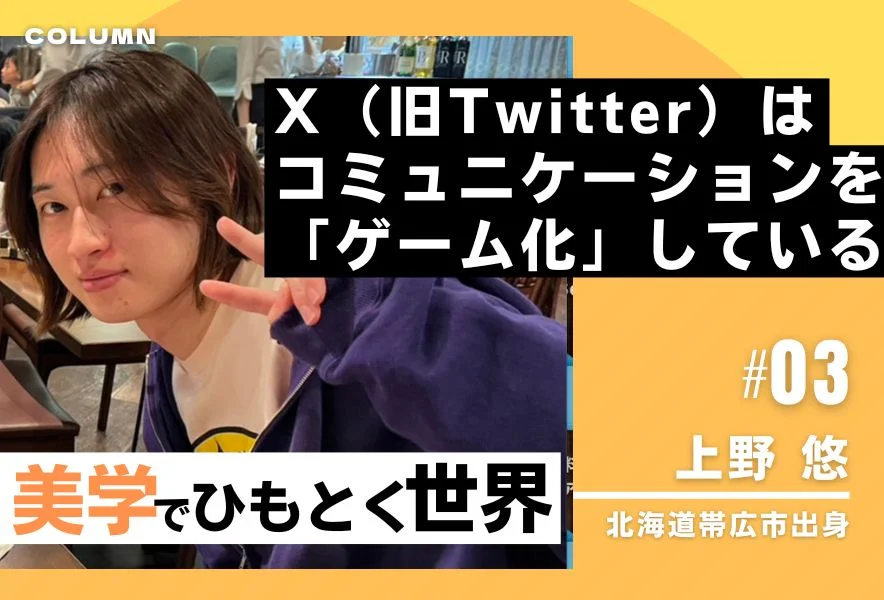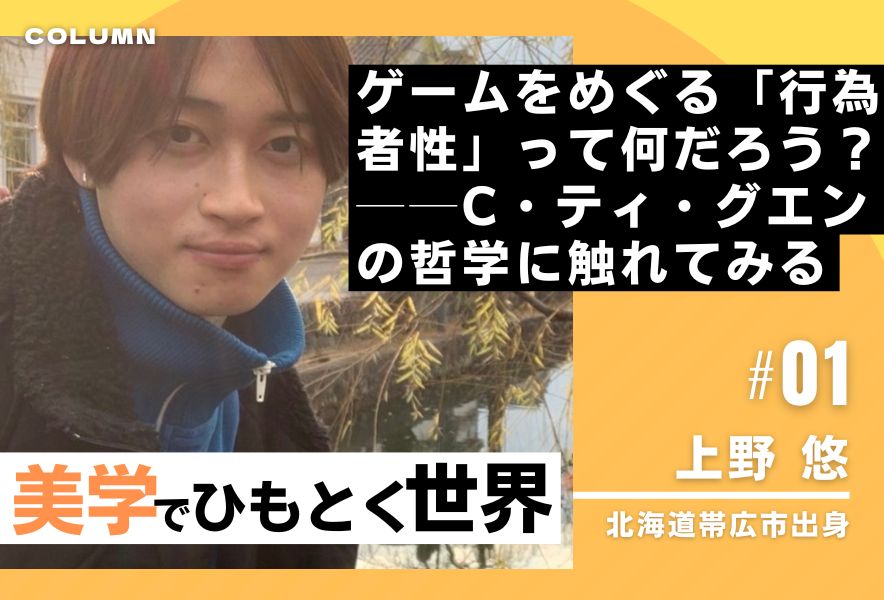【連載】美学者 上野悠の「美学でひもとく世界」
人生の意味

こんなことを突然聞かれたら、少なからず訝しんでしまうかもしれませんが、「人生の意味(meaning of life)」は実は哲学においてかなり伝統的な問題であり、現在においても頻繁に議論されているホットトピックなのです。
人生の意味が提起する問題は、ひとつには文字通りの意味での人生の意味、つまり、「人生そのものにどんな意味があるのか(そもそも意味があるのか)」といったものがありますが、もうひとつ、別のものもあります。それが、「有意義な人生とはどういうものなのか」といったような問いです。
そんなことを言うと、「何がよい人生かなんて人それぞれじゃないか」と言われてしまいそうですが、そんな「人それぞれ」から共通項を探し出して、一般化を試みるのが、この分野において行われていることであり、中にはあまり哲学になじみのない方々からしても、なかなか興味深い帰結を与えてくれるような議論もたくさんあるかと思います(そう思いたいです)。
今回は、そんな中でも、有意義な人生と「スポーツ」との関係という、おもしろそうな論点を取り上げてくれている、ノルウェースポーツ科学大学の教授、グンナル・ブレイヴィクによる研究をご紹介したいと思います。
スポーツと有意義な人生

ブレイヴィクはまず、「意味」という概念と、「有意義な人生を送る」という考え方を明確にすることから始めます。
意味の意味
ブレイヴィクは、「意味」の意味を、リバタリアニズムで著名な哲学者ロバート・ノージックによる著作(Nozick, R. 1981. Philosophical Explanations. Cambridge: Harvard University Press.)を参照することで整理しています。ノジックによると、意味という概念は次の8つの解釈のされ方があります。
| 1. 外的因果関係としての意味(Meaning as external causal relationship) |
| 2. 外的参照または意味論的関係としての意味(Meaning as external referential or semantic relation) |
| 3. 意図または目的としての意味 (Meaning as intention or purpose) |
| 4. 教訓としての意味 (Meaning as lesson) |
| 5. 個人的な重大さ、重要性、価値、気がかりなこととしての意味(Meaning as personal significance, importance, value, mattering) |
| 6. 客観的な有意味性としての意味 (Meaning as objective meaningfulness) |
| 7. 内在的な有意味性としての意味 (Meaning as intrinsic meaningfulness) |
| 8. 意味の総体がもたらす意味(Meaning as total resultant meaning) |
ブレイヴィクはそのうち、3、5、6、7、8をスポーツと結びつくものとしてピックアップしています。
まず、⑶については、言わずもがな、選手たちは「勝利」という目的に向かって行動することからスポーツに当てはまります。⑸については、特定のライバルに勝つことや、新しい技術を成功させること、前回の試合より上達することといった個人的な意味合いが含まれます。⑹については、オリンピックや公債大会などといった大きな大会、あるいはボイコットやデモのような特定のスポーツイベントの歴史的・社会的影響を通じて、客観的な有意味性を持つことが挙げられます。⑺については、よく構成されたスポーツにおける、ルールの構造や美しい試合展開などが内在的な有意味性を持ちうることが挙げられています。最後に、⑻については、(これまで挙げたような)スポーツが人々の生活にもたらしうる様々な意味が、結集・統合されることが述べられています。

意味に関する二つの世界観
次にブレイヴィクは、意味に関する基礎的な問題について触れます。それは、意味は「見出す」ものなのか、それとも、意味は「作り出す」ものなのか、という問題です。西洋の哲学の伝統では、意味に関する、この両方の考え方があります。
「見つけ出す」見解によると、歴史や社会、個人の人生には客観的な意味があり、人は意味の秩序を探し求め、見つけなければなりません。しかし、「作り出す」という見解によれば、そうしたものには客観的な意味など存在せず、人は自ら意味を創造しなければなりません。ブレイヴィクは、これらをそれぞれ、全体論的西洋形而上学と個人主義的実存主義と呼んでいます。
西洋的形而上学の全体論的な見方の背景には、神の存在があります。世界や人間は神によって作られたものであり、人間は、そうした神によって作られた世界の意味を見つけ出すべき、という考え方です。この考え方をスポーツに適用すると、世界の真の姿に従う形で、スポーツにはパターンや意味があるということになります。
対して、実存主義の見解にはそのような存在はなく、私たちはそれぞれ、どのように生きるかを選択しなければなりません。実存主義の哲学者たちは、有限性(=死)が意味の前提条件であるとし、私たちはこの究極の事実と向き合いながら、どのように生きるかを決定しなければならないと言っています。私たちの生には常に、無意味に陥る可能性が存在しているのです。
ひとつつけ足しておくと、人生において「意味」が重要なものとして考えられている背景には、「私たちは単純に快楽だけを追い求めているわけではない」という直観があります。自分や身の回りを見てみると、単純な快楽だけを享受する人生はどこか「空虚」なものであると思われている傾向にあることに気づかされます。快楽は、それはそれで重要なものではあるのですが、生きる価値のある人生とはそれだけではないと思わされるような何かがあるような気もします。それこそが「意味」であると、一部の哲学者たちは考えているわけですね。
意味に関する二つの世界観
ブレイヴィクはさらに、有意義な人生(meaningful life)の特徴を明確にするために、再びノージックを参照します。ノージックが考える有意義な人生の特徴から、ブレイヴィクは、次のような2つの結論を導きだします。
ブレイヴィクは、意義ある人生のこの 2 つの特徴は、基礎的(fundamental)なものであるように思われると述べています。さらに、ノージックは、意義ある人生の特徴として、「透明性」や「倫理的であること」といった特徴も挙げており、ブレイヴィクはこれらの基準を満たすためには、スポーツは「意図的かつ定期的な活動」でなければならないと指摘しています。
さらには、「つながり」という2つ目の基準も満たさなければなりません。そのために、スポーツは、人生の他の部分とのつながりがあること、すなわち、生活の一部でなければならないことになります。こうした条件は、エリートスポーツやライフスタイルスポーツにおいては、明確にクリアしていることになりそうですが、一方で、ブレイヴィクは、それらほど熱心ではない多くのプレイヤーたちにとっても、満たし得る条件であるとしています。つまり、スポーツは、「何らかの目標や意図」があり、「人生のほかの部分とのつながりを持つ」ことで、意義ある活動となるのです。ブレイヴィクはこうした考えを含めて、「人生計画(life project)の一部となること」というふうに表現しています。
意味と「価値」の関係

しかし、ここでまた問題が生まれます。ここまでスポーツをすることの「意味」について議論してきましたが、そもそも、そのような意味や有意味性とは、「それ自体で成り立つ」ものなのでしょうか。
どういうことかというと、例えば、サッカーで言えば、ドリブルやフェイントが「攻撃の一部」として意味を持ち、さらにその攻撃は試合に勝つための戦略の一部として意味を持つ…というように、何らかのものは、大きな意味的構造の一部となることで、意味を持つようになるように思われるのです。
しかしながら、そうした個々の意味を支えるための意味的構造は、突き詰めた先の「究極的な意味」がなければ、崩壊してしまいます。意味の連鎖の終端には、それ自体で意味を持つようなものが存在していなければならないのです。
しかし、ブレイヴィクはここでもノージックを参照し、意味の連鎖はそれ自体で意味を持つものでなくとも、「価値のあるもの」で終わってもよいのだと主張します。
価値のあるものとは
それでは、意味の連鎖を支えうる、本質的な価値を持つものとはどのようなものなのでしょうか。ブレイヴィクはここでもノージックを参照します。
ノージックによると、価値は、そのものの外側に何らかの繋がりを持たなければならない意味とは対照的に、そのものの中で何らかの統合の形態を含むのだとしています。しかし、そうだとしても、意味の終端である価値は、これまたそれ自体で完結するような、本質的なものでなければなりません。そうでなければ、その価値を支えるためにまた別の価値が必要となり、連鎖が始まってしまうからです。
では、本質的な価値を持つものとは一体どのようなものなのでしょうか。ノージックは、本質的価値について、ずばりそれは、「有機的統一性(organic unity)であると主張しています。何かが本質的価値を持つのは、有機的な統一性の度合いに応じて決まるというのです。
ブレイヴィクはこれをスポーツにも当てはまるものだと主張しています。例えば、レベルが高く、よいサッカーの試合は、複雑なやりとりの間にも選手の動きや行為の間に統一性が見られますが、反対に、レベルが低かったり、調子が悪かったりして、よくない試合だとそれぞれの要素の間の関係は複雑であっても、統一性はあまり見られなくなります。そうすると、試合の価値も落ちてしまうのです。
このように、スポーツは「有機的統一性」という形で、本質的な価値を持つことができます。すると、スポーツをプレイする人はスポーツの外(例えば「健康」など)に価値を求めなくてもよくなります。つまり、スポーツに参加すること自体に本質的価値があることで、スポーツのさまざまな意味を担保できるようになるのです。
行為そのものが本質的価値を持つ

ノージックによる意味や価値についての議論を参照した、ブレイヴィクによるスポーツの意味についての論は、「有機的統一性という本質的価値を持つ構造を、スポーツに適用する」というアイデアが基になっているものでした。
これは、有機的統一性というものがあって、それによって個々の要素が意味づけされる、という、いわばトップダウンの理論として捉えられるかと思います。
それに対して、「行為中心」にとらえたい私としては、むしろスポーツにおける個々のプレイ=行為それ自体に価値があるのだと考えたいと思っています。これは、ブレイヴィクの論に対して、いわば、ボトムアップの理論と言えるでしょう。
しかしながら、ブレイヴィクによる理論にも、私にとって魅力的な点があります。それは、「有機的統一性」というものが、すべての意味を裏づける、意味の終端として働くという考えです。
というのも、確かにスポーツやゲームにおける個々の行為(サッカーにおけるドリブルやシュートなど)は何らかの形で「意味を与えられている」からこそ、やっていてたのしいものとなっている側面もあるように思えるからです。
そこで、私は、本質的価値としての有機的統一性を、構造内の各要素に「意味を付与する機能」によって、価値があるものになっている、というようにいえるのではないかと考えています。
しかしながら、この考えは、一見して、意味の循環に陥る危険性があります。というのも、有機的統一性が「意味を付与する」がゆえに価値があるのだとしたら、その価値の裏付けはそのまま各要素に流れていき、そこからまた有機的統一性に戻ってきてしまう、という構造になってしまうからです。これをどう解決するかを今後の課題としたいですね。
参考文献
- Breivik, Gunnar. 2021. Sport as part of a meaningful life. Journal of the Philosophy of Sport 49 (1):19-36.
- Nozick, R. 1981. Philosophical Explanations. Cambridge: Harvard University Press.
- Nozick, R. 1989. The Examined Life. Philosophical Meditations. New York: Simon and Schuster.
美学者とは
美学者の役割
- 【美的判断】なぜある人が「美しい」と感じる対象を、別の人は「そうでもない」と思うのか
- 【芸術作品の価値】作品が私たちの感性に与える影響を、どう評価し、言葉で説明できるか
- 【日常の美】ファッションやインテリアなど身近なところに潜む「美しさ」をどのように考えるか
こうした問いに取り組むのが美学者の役割です。近年では、ゲームの体験やデザイン、スポーツや身体表現、さらにはSNSなど、従来は「美学」とはあまり結びつかなかった分野にまでその探究範囲が広がっています。哲学や芸術学と深く関係しながら、現代社会のあらゆる「感性の問題」に光を当てるのが、美学者と呼ばれる人々なのです。

【PROFILE】
北海道帯広市出身。早稲田大学文学研究科博士後期課程在籍。専門は、ゲーム研究、美学。主な論文に、「個人的なものとしてのゲームのプレイ: 卓越的プレイ、プレイスタイル、自己実現としての遊び」『REPLAYING JAPAN 6』、「ゲームにおける自由について──行為の創造者としてのプレイヤー──」『早稲田大学大学院 文学研究科紀要 第68輯』。ゲームとファッションとタコライスが好き。