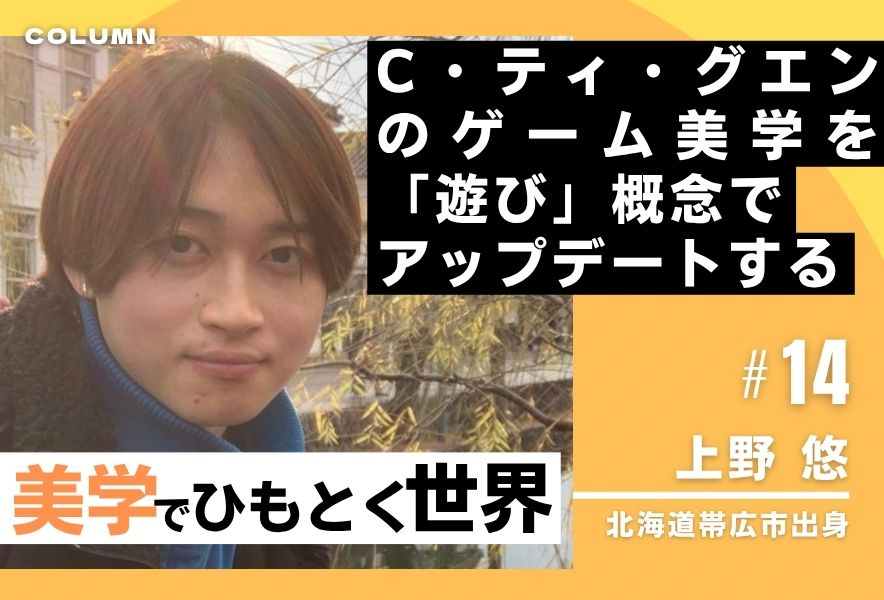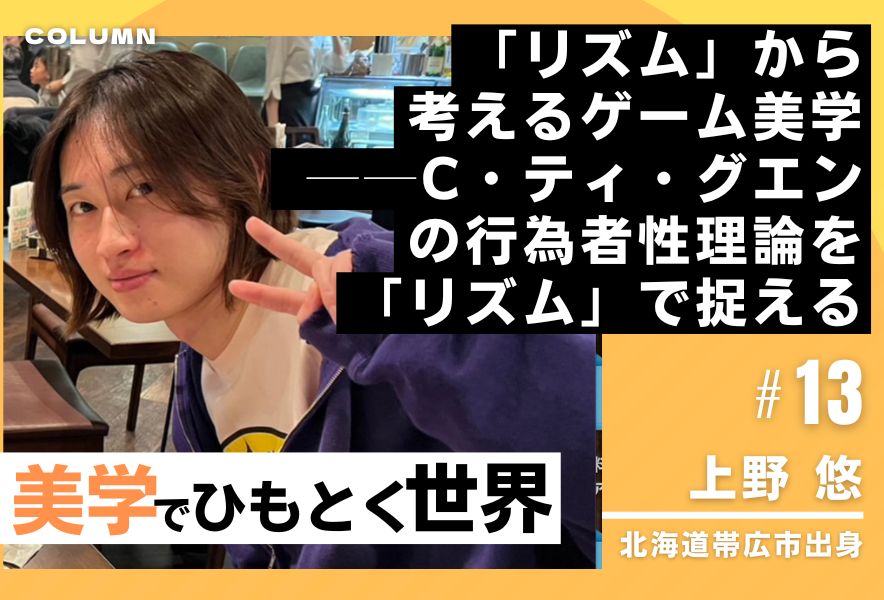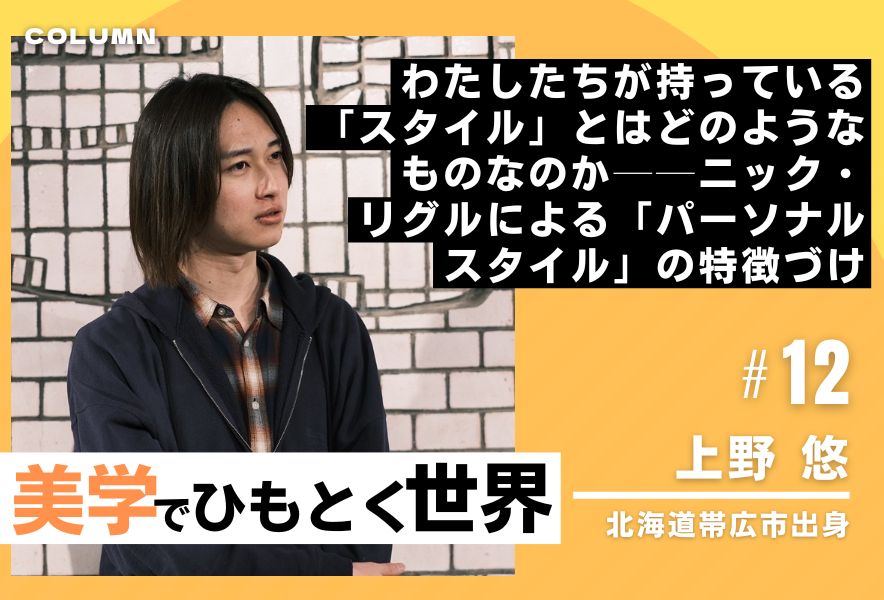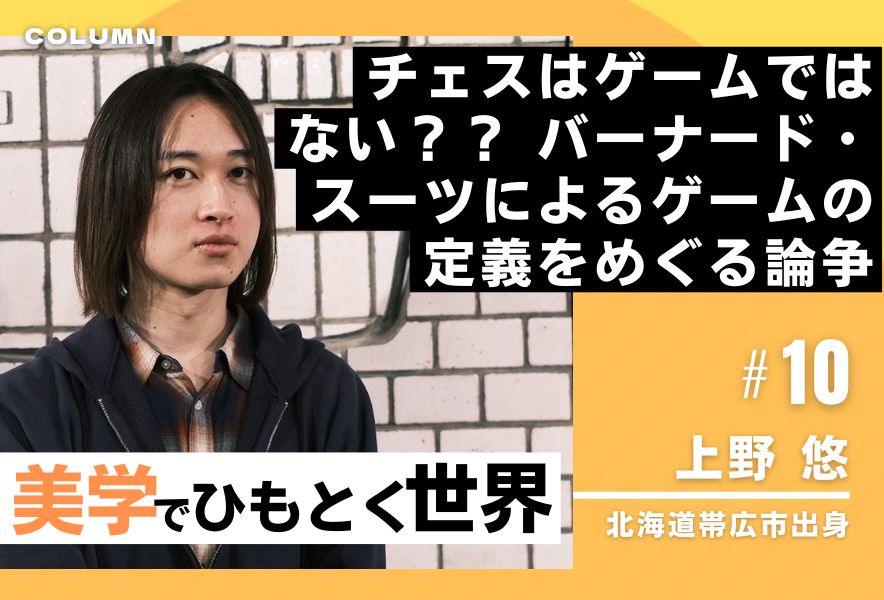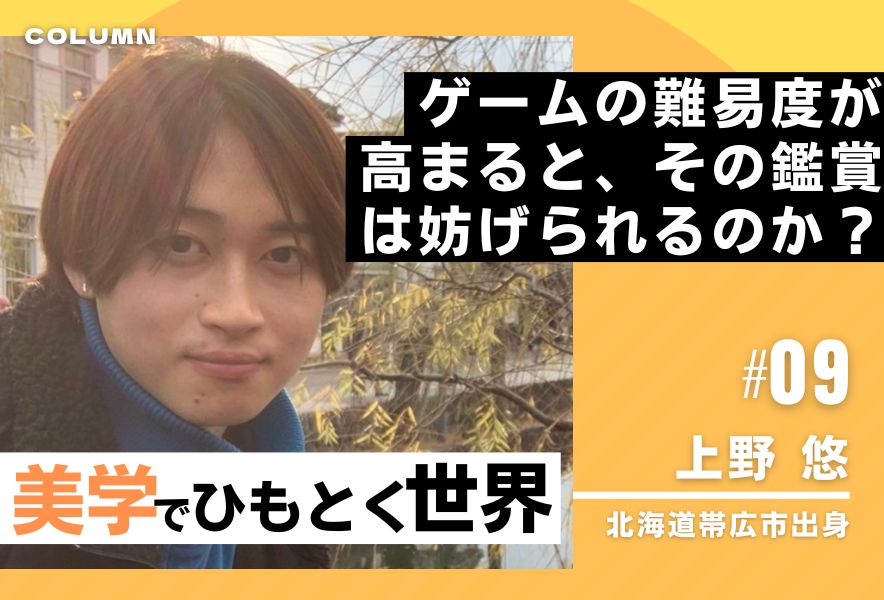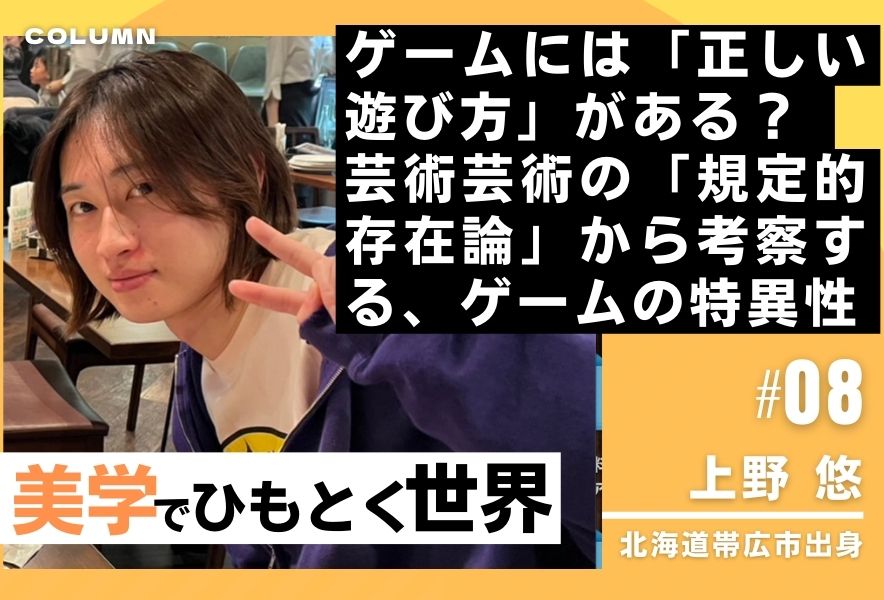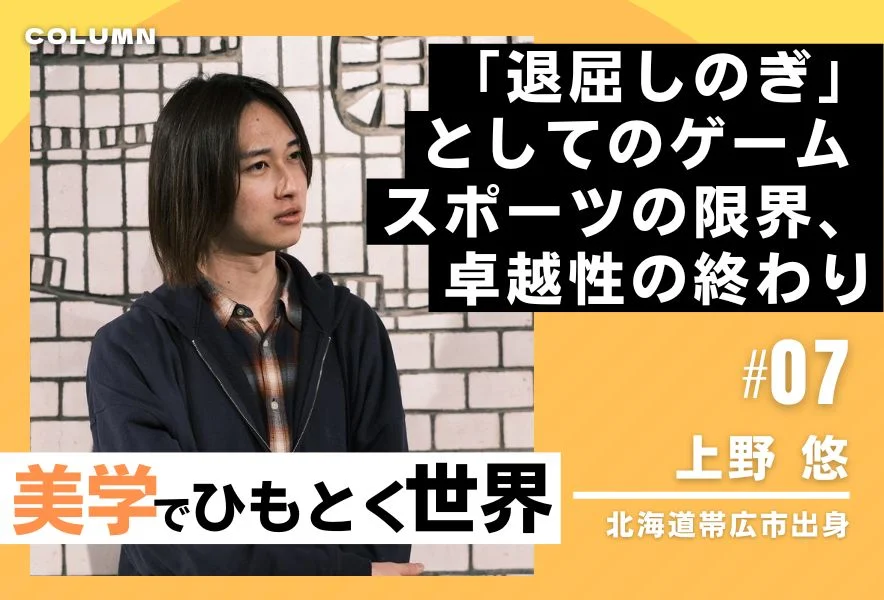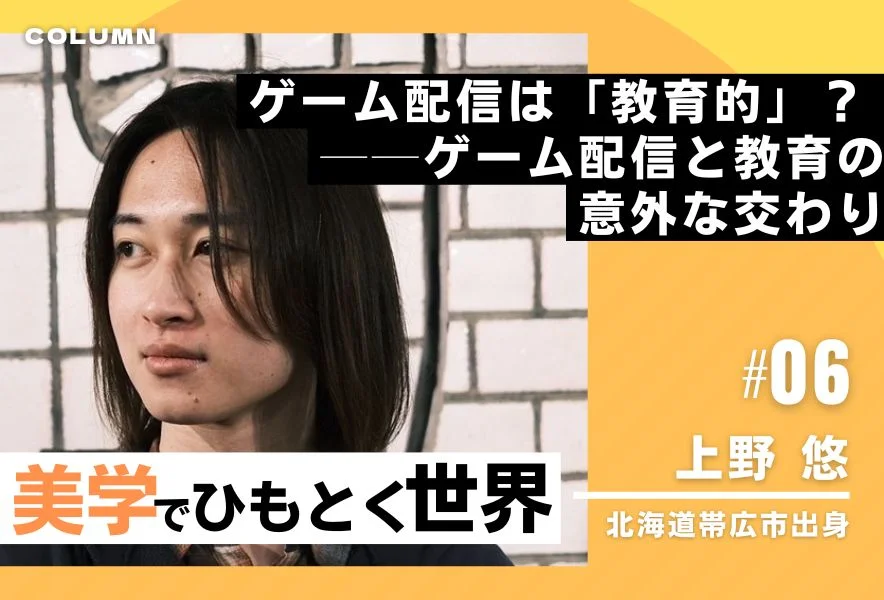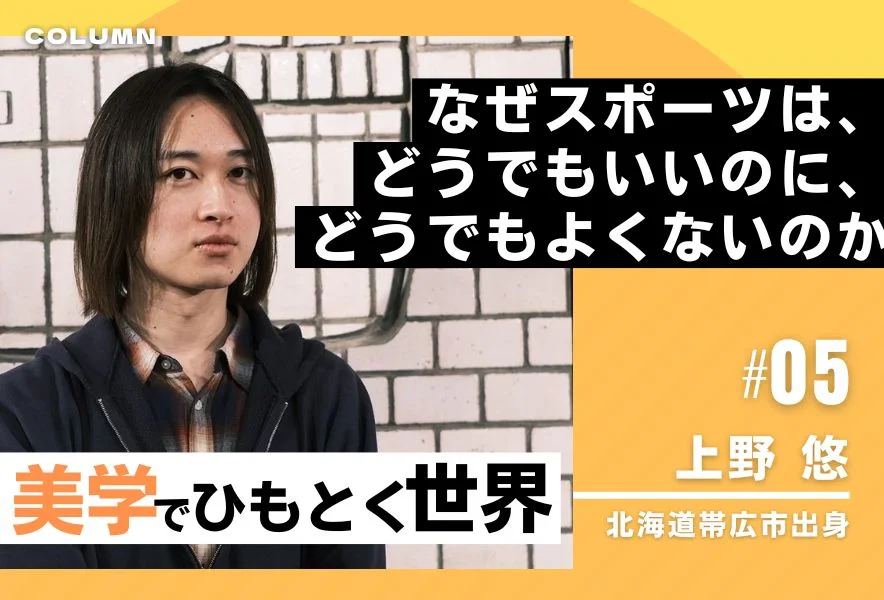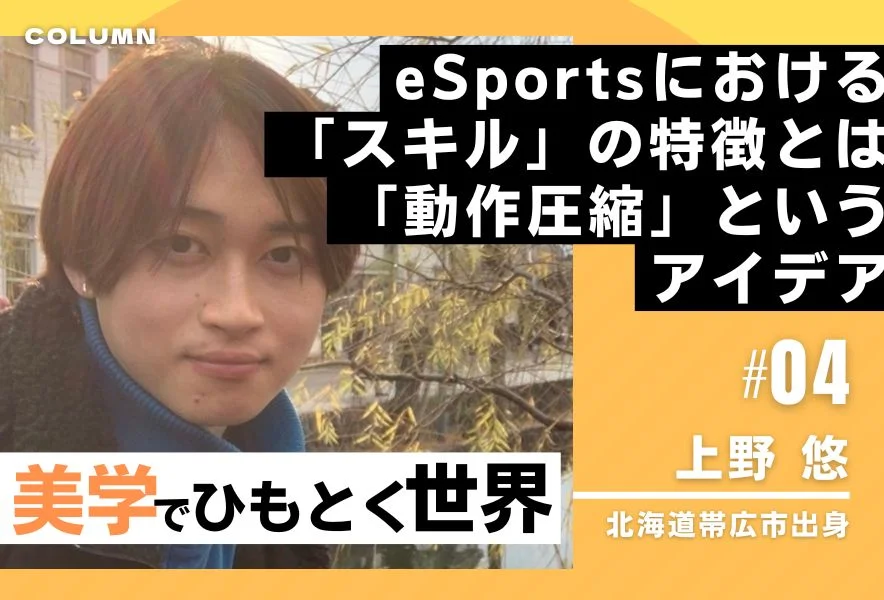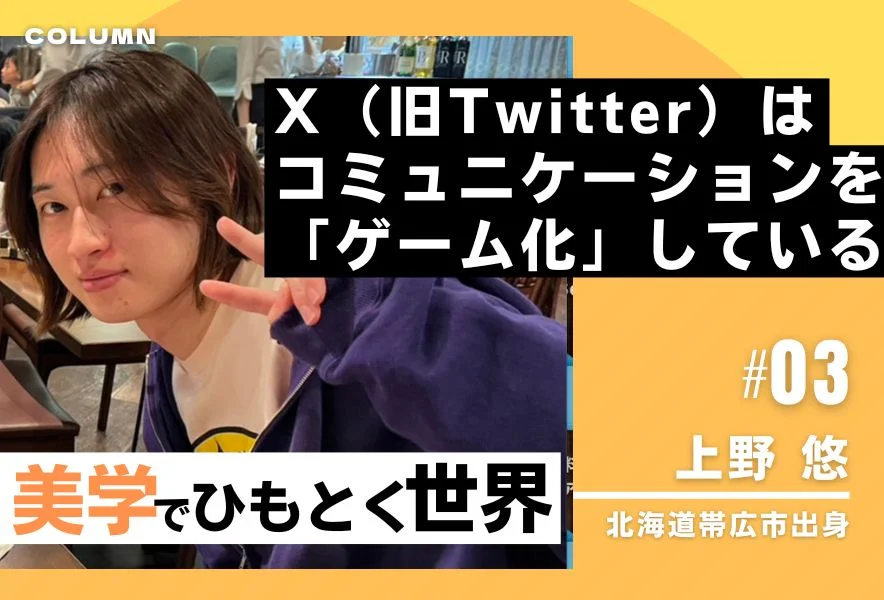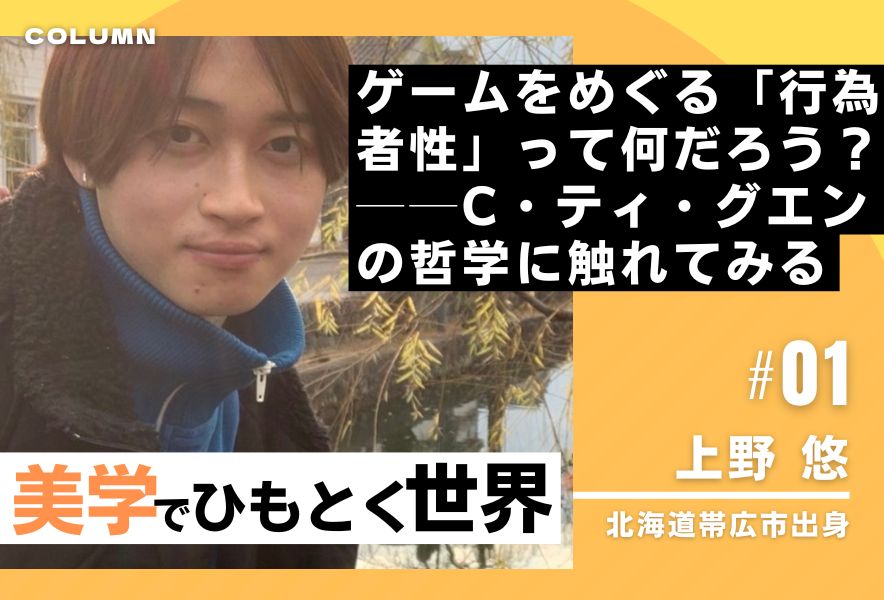【連載】美学者 上野悠の「美学でひもとく世界」
ゲームをすること、遊ぶこと

いきなりですが、「ゲームをする」ことと、「遊ぶ」こととの間にはどんなつながりがあるでしょうか。
英語で言えば、ゲームをすることと遊ぶことは、どちらも“play”です(日本語でも「ゲームをプレイする」といいますよね)。そのことも手伝ってか、ゲームに関する人文学研究では、ゲームをプレイすることと遊ぶことの間にある関係は、長い間研究者の注意を引いてきました。
その流れは現在まであり、例えば、コペンハーゲンIT大学(ビデオゲーム研究でかなり有名なところです)で教授をつとめている、ミゲル・シカールは、ゲーム研究者でありながら、「遊び中心主義」的な立場を提示したことにより、現在は遊び研究者とも言えるような独特な立ち位置を得て注目されています。シカールが言うには、重要なのはゲームではなく遊びであり、ゲームは遊びを導く様々なもののうちのひとつでしかないのです。
C・ティ・グエンのゲーム哲学

本連載でも何度も紹介してきたC・ティ・グエンのゲーム哲学ですが、ゲーム研究やスポーツ哲学、はたまた美学といった様々な分野で注目を集めています。そうはいっても、グエンの哲学は注目を集めながらも、賞賛されるだけでなく、批判や反論もかなりされています。というのも、グエンがバックグラウンドとしている「分析哲学」という分野には、研究者同士で批判や議論を繰り返すことで、研究をよくしていこう、という土壌があるのです。
今回は、そのうちのひとつとして、グエンの哲学にかなり神話的でありながらも、そこに「遊び」の要素を加えることで、よりよい理論へと導こうとしている、マイケル・リッジによる研究を紹介いたします。今回の記事はグエンの理論を知っていることが前提となってしまうので、まずはこちらの記事をご覧ください。
グエンの理論に遊び心を加える
リッジは、「グエンのアプローチが根本的に正しいと考えているため、彼の理論を反論したり、細部の欠点を指摘したりするつもりはない」と前置きしながらも、そこには重要な要素が抜けていると主張します。ずばりそれは「遊び心(playfulness)」です。
リッジの議論は以下のように組み立てられています。まず、リッジはグエンの理論に見られる3つの緊張関係を整理し、次にリッジが定式化した遊び心の概念を導入し、この概念がグエンの理論における緊張を遊び心概念によってどのように緩和されるかを説明します。
グエン論における三つの緊張

リッジは、自らが提示するグエン論における3つの緊張は、グエンが提示した「努力のプレイ」が持つ、深い没入、狭い集中、目標指向といった性質に、共通して由来していると言います。
無関心性の問題
まず、最初の緊張は、努力のプレイと、その美的鑑賞との間にあるものです。グエン自身もこの点に気づいており、それに対して説明を行っています。その緊張とはどのようなものなのでしょうか。
この緊張を説明するためには、まず美的鑑賞についてのかなり伝統的な見解を前提としなければなりません。ごく簡単に説明すると、無関心性のテーゼとは、美的鑑賞や美的判断を下す際には、「実践的関心」と呼ばれるような、実生活の利害関心(interest)がかかわってはいけない、というようなものです。美的鑑賞には、この「無関心性」という態度が必要だということをカントという大変有名な哲学者が提示しており、それ以来、この無関心性というものが美学において非常に重要視されてきました。
したがって、努力のプレイと美的鑑賞との間にある緊張とは、無関心的な態度と実践的な「関心のある」態度との間で生じるようなものです。グエンはこれに対して、ベンス・ナナイという哲学者の美的経験についての見解を採用することで問題を回避しようとしています。
ナナイの美的経験に対する見解とは、ざっくり言うと、美的経験を形作るものとは、ある特徴を持った「注意の仕方」であるというものです。ナナイが言うには、美的経験においては、私たちの注意は対象に対して集中していますが、性質に対して分散しているのであり、これこそが美的経験を特徴づけるものだというのです。例えば、ある風景の美的鑑賞を想定してみてください。あなたの注意は風景に集中していますが、その風景が持つたくさんの性質に対しては分散しており、多くの性質を同時に捉えているのです(木の形や、草花の並び方など)。

これに対して、ゲームプレイにおいては、わたしたちは勝利するために、注意にいわば実践的フィルターをかけ、勝利に役立つものに注意を向けます。これによって美的経験に不可欠な種類の注意とは相容れないように見えてきてしまうのです。このようにして、努力のプレイと行為者性に対する美的鑑賞との間に緊張が生じることとなります。
グエンは、この緊張を緩和するために視点をシフトするという方法を提案しています。どういうことかというと、私たちは、ゲーム中で何かしらの美的経験をしたあとで、それを創造的に回想することができます。これにより、行為者性を美的に鑑賞することが可能というわけです。
しかし、リッジは、これは緊張の理想的な解決ではないと指摘します。リッジ曰く、実際の経験と、その美的鑑賞との間に過度の距離が生じてしまうというのです。例えば、もしあるチェスプレイヤーの記憶が不確かなものであったら、試合中で効果的な手を見つけたときの感覚を正確に思い出せないかもしれず、さらには、たとえ記憶が信頼できる場合だとしても、ゲーム中で実行力が発揮されている、まさにその瞬間にその実行力を捉えている経験に対して、あとになってその実行力を回想する経験は、鮮やかさが失われてしまう傾向があるように思われるのです。
価値捕捉問題

第二の緊張は、特定の「ゲーミフィケーション」における価値構造と、現実世界における豊かな価値構造との間に生じるものです。これはグエンが「価値捕捉の問題」と呼ぶものです(この問題に対しても前の記事で触れています)。
ゲーミフィケーションとは、実生活における実践的な状況にゲーム的形式を導入し、その強い動機づけの力を利用して、人々が本来十分な動機づけがない場合でも、その活動に従事するように促すという仕組みです。その導入は有用に働くことも多いのですが、現実世界における価値は豊かで微妙なものであるはずなのに対し、ゲームの力によって明確な目標を提供することによって、ゲーム的な単純な価値体系が、現実世界のより豊かで微妙な価値体系と置き換わってしまう可能性があることをグエンは懸念しているのです。
自律性の問題
第三の緊張関係は、努力のプレイ(およびゲームプレイ全般)と自律性(autonomy)の間の緊張です。グエン自身は、ゲームプレイが自律性を高める可能性があると主張しています。ゲームのルールは制限であり、人の行為の自由を束縛するものであるという考えに対して、むしろ、チェスのルールがなければ、チェックメイトが不可能であるように、ゲームはある行為を形作るものであると反論しています。さらはに、様々な種類のゲームをプレイすることで、私たちは多様な形態の行為者性を身に着け、現実の生活でそれらを柔軟に切り替える能力を養うことができ、それによって自律性を高めることにつながると言うのです。
また、努力のプレイが自律性を高めると主張する中で、グエンは上に挙げたミゲル・シカールを批判しています。シカールは、真の自由はルールの制限の外にある「構造化されていないプレイ」においてのみ見つかるという強い主張をしています。それに対しグエンは、上述したような、ゲームのルールが、特定の行為を可能にする点に焦点を当て、シカールに対して反論しています。
しかし、リッジは、シカールの意見にも保存すべき点があると指摘しています。リッジは、日常生活においてもゲームのことばかり考えてしまうようになったプレイヤーの例を挙げ、自律性の貧困化がありうるというようなことを述べています。これに対し、「遊び心」役に立つのではないかというのです。
遊びのスタンス

リッジはグエンは自身の見解を補足し、以下の3つの「スタンス」を提示していることに触れます。
2.鑑賞者のスタンス:ゲームやその一部を観察している状態。
3.デザインのスタンス:ゲームのデザイン自体に注意を向けるスタンス——そのルール、目標、グラフィック、要素、それらの一貫性、どのような遊びを可能にするかなど。
リッジはここに、4つ目の姿勢を追加しようとします。
この、遊び心のスタンスは、プレイのスタンスを重複するものではありません。プレイのスタンスは「ゲームをプレイすること」に関わるものであり、ゲームをプレイしていても必ずしも遊び心を持っているとは限らないし、その逆も然りです。リッジは、遊び心に含まれるような「遊び」を以下のように定義します。
活動に台本があるというのは、エージェントの行動が既存の台本によってある程度固定されていることです。リッジは、活動全体を通じて行動を固定するルールに従っておこなう行為や、組み立てラインで部品を組み合わせるための単純なルールに従う作業者、本能によって活動が固定されている動物、などは「脚本化」されていることを指摘しています。
そうなると、すべてのゲームプレイは脚本化されているようにも思えますが、リッジは、遊びは「段階的」な概念であり、たとえルールに従っているように見えても、行為がルールによって完全に固定されておらず、そのルールを辞退してプレイをやめることができる限りで、遊びとみなすことができると示唆しています。さらにリッジは、この遊び概念を「楽しさ(fun)」と結び付けます。

遊びによる緊張の解消
リッジは、遊び心のスタンスは、緊張を解消するだけでなく、グエンの理論を豊かにすると主張します。なぜなら、遊びと楽しさはそれ自体で価値があり、私たちがゲームをプレイする主な理由の一つだからです。
リッジは、チェスを例として焦点を当て、遊び心のスタンスがどのように緊張を解消するかを説明します。
まず、グエンは、努力のプレイに没頭する際、私たちの実践的な関心は、私たちの行為者性への知覚を実践的に関連する方向に偏らせる傾向があることを指摘していました。リッジはこの際に、私たちは事前に、どの特徴が実践的に関連するかを正確に知らない点を指摘しています。例えば、チェスの駒の「臭い」のような特徴は安全に無視することができますが、そうしたフィルタリングによって、経験が美的にならないわけではないでしょう。もしプレイヤーが完全に一つの特性に集中しているなら、その経験は美的ではないと言えそうですが、逆に、経験の対象のすべての特性に集中する必要もないと考えられます。むしろ、すべての特性に注意を向けることは人間にとっては不可能であるともいえるでしょう。
しかしながら、美的経験が経験に対して、いかなる実践的フィルターも課さないことを要求するなら、焦点の定まり具合が異なるということだけでは、努力のプレイと美的経験の緊張を解消できません。しかし、リッジはここで興味深い可能性が浮上すると言います。リッジが言うには、私たちは、実践的関心のために、真に無関心な視点を採用するかもしれないと言うのです。

リッジは例として、『ウォーリーをさがせ!』のイラストを無関心な視点で眺め、目が偶然ウォーリーに止まったら、ぼーっとしながらページをめくっているような最中でもそれが目立つ、というかなりありそうなケースを取り上げます。これと同様に、経験豊富なチェスプレイヤーは、打開策を探すために、目の前の局面に対してまず無関心な視点で眺める、ということがあると指摘するのです。
チェスプレイヤーにとって、ひとつのアイデアに固執して失敗してしまう、ということは珍しいものではないでしょう。このような事態を避けるためには、視点を「計算モード」から「創造的モード」へと切り替えることが必要であると述べます。そのために、「遊び心」がそのような事態への「完璧な対抗手段」として働くと言うのです。遊び心は、私たちに、より広範で多様な視点を与えることで、実験と新しいアイデアを促進する機能があるのです。
また、リッジは、単に盤面を眺める際でなく、チェスをプレイするとき特有の遊び心の発揮ポイントがあると言います。ある程度熟練したチェスプレイヤーは、プレイしているとき、目の前の局面から一連の可能な手へと視点を移します。それから、それらの可能な手それぞれに対して無関心な態度をとることで、その手が開く攻撃のライン、脅威となる駒、その手が残してしまうウィークポイント、その手が相手に提供してしまう新たな可能性など、手の特徴を、散漫なしかたで遊び心を持って捉えます。これは非常に知的な過程でありながら、それでも散漫な注意なのです。このような注意の形態によって、可能な手への美的な楽しみ方を引き出すのです。そして、遊び心がその達成を助ける限り、それはグエンによる行為者性の美学を強化するのだと、リッジは主張しています。

このようにして、リッジはさらに第二、第三の緊張の解消についても説明しますが、紙幅の都合でそれらについては省かせていただきます。遊び心とゲームプレイをポジティブな仕方で結び付けようとする研究はよくありますが、リッジの論は、それを明確にグエンの理論と結び付けている点、また、遊びや遊び心を「脚本化されていない活動」として特徴づけている点が独自性であると言えるでしょう。個人的には、チェスにおける探索を「無関心なもの」とするのは、ちょっと難しいようにも思えますが(少なくとも、カント的な無関心性が達成されるというのなら、もう少し深い論証が必要な気がします)、可能な手を吟味するときの態度が、遊び的なスタンスであるというのは、かなり魅力的な視点のように思えます。
参考文献
- Ridge, Michael. 2021. “Fun and (striving) games: playfulness and agential fluidity.” Journal of the Philosophy of Sport 48 (3), 403-413.
美学者とは
美学者の役割
- 【美的判断】なぜある人が「美しい」と感じる対象を、別の人は「そうでもない」と思うのか
- 【芸術作品の価値】作品が私たちの感性に与える影響を、どう評価し、言葉で説明できるか
- 【日常の美】ファッションやインテリアなど身近なところに潜む「美しさ」をどのように考えるか
こうした問いに取り組むのが美学者の役割です。近年では、ゲームの体験やデザイン、スポーツや身体表現、さらにはSNSなど、従来は「美学」とはあまり結びつかなかった分野にまでその探究範囲が広がっています。哲学や芸術学と深く関係しながら、現代社会のあらゆる「感性の問題」に光を当てるのが、美学者と呼ばれる人々なのです。

【PROFILE】
北海道帯広市出身。早稲田大学文学研究科博士後期課程在籍。専門は、ゲーム研究、美学。主な論文に、「個人的なものとしてのゲームのプレイ: 卓越的プレイ、プレイスタイル、自己実現としての遊び」『REPLAYING JAPAN 6』、「ゲームにおける自由について──行為の創造者としてのプレイヤー──」『早稲田大学大学院 文学研究科紀要 第68輯』。ゲームとファッションとタコライスが好き。