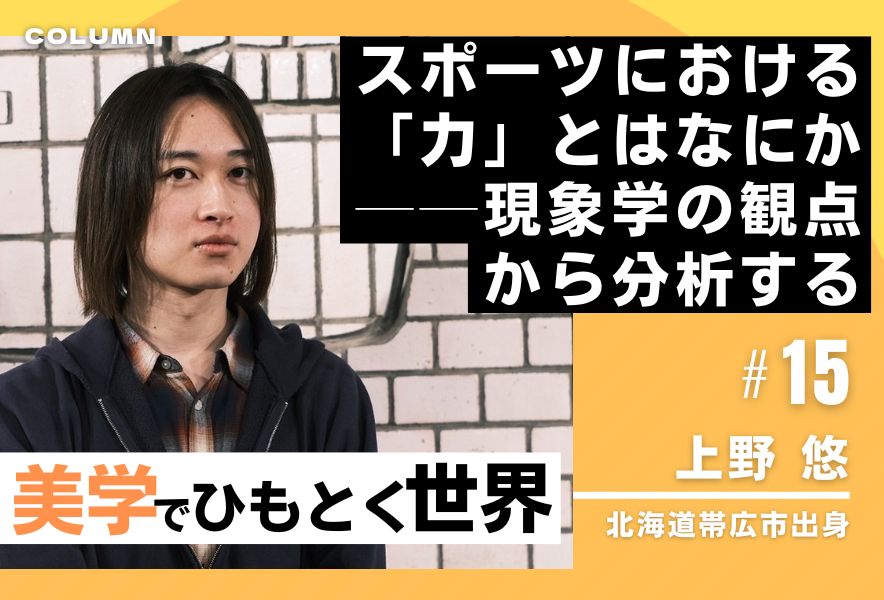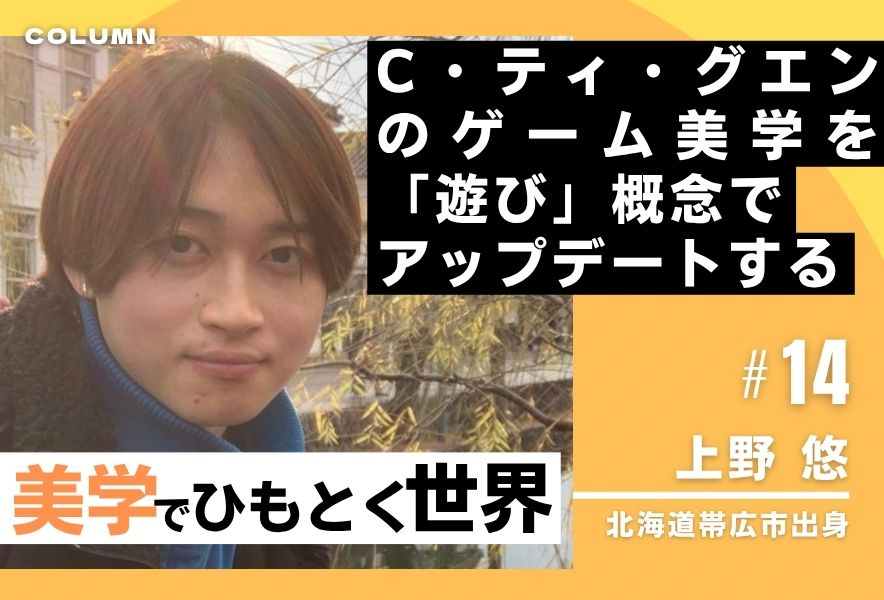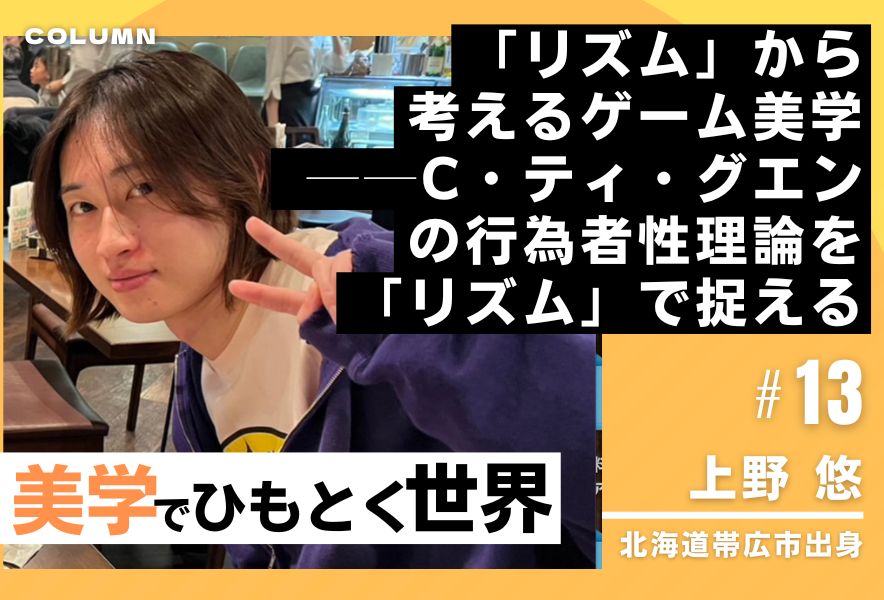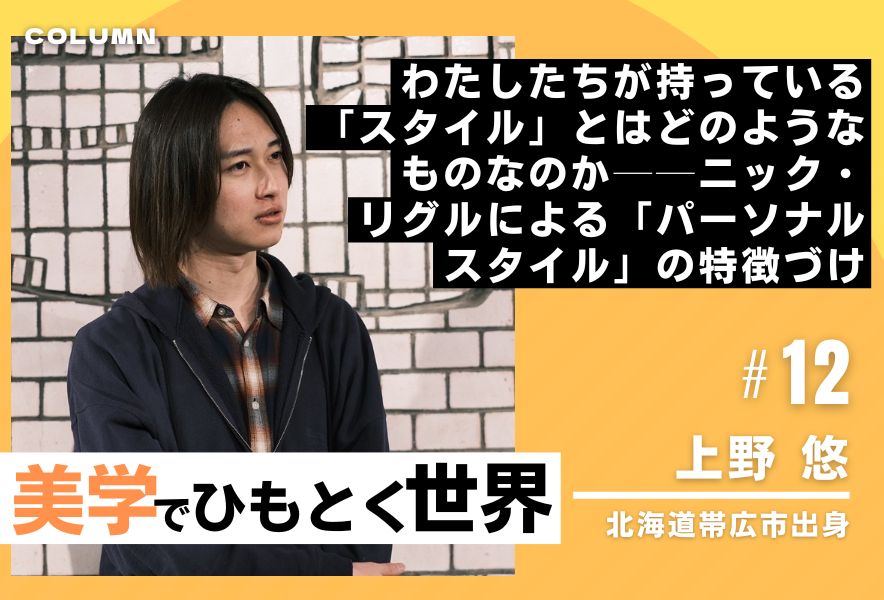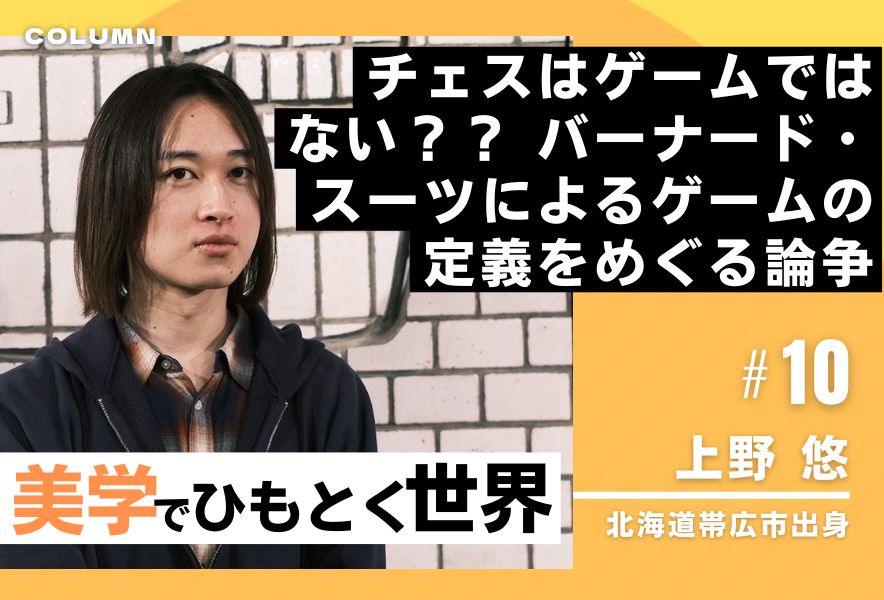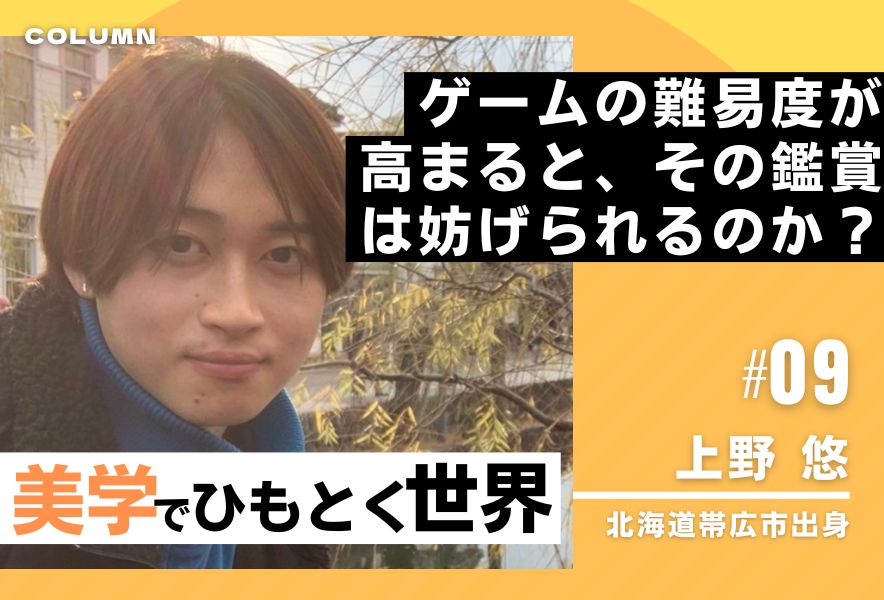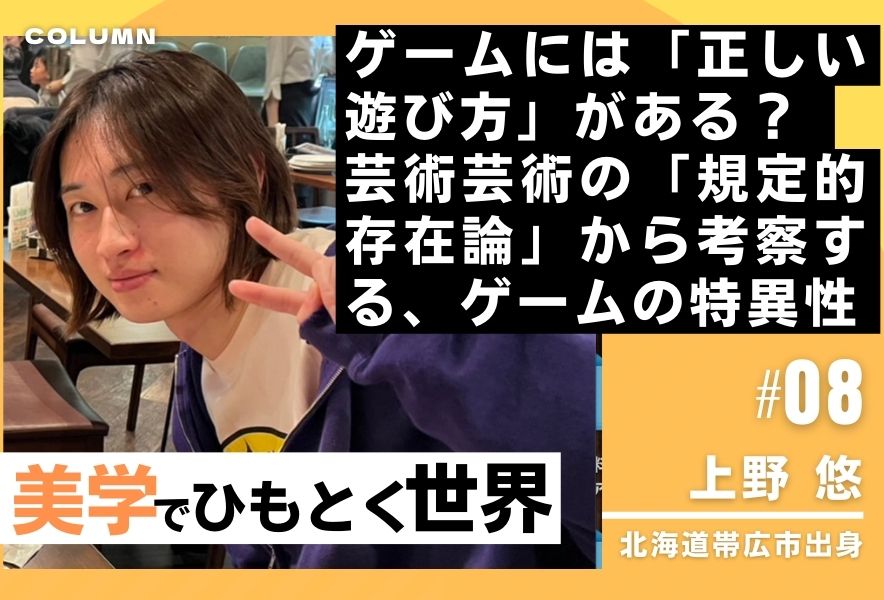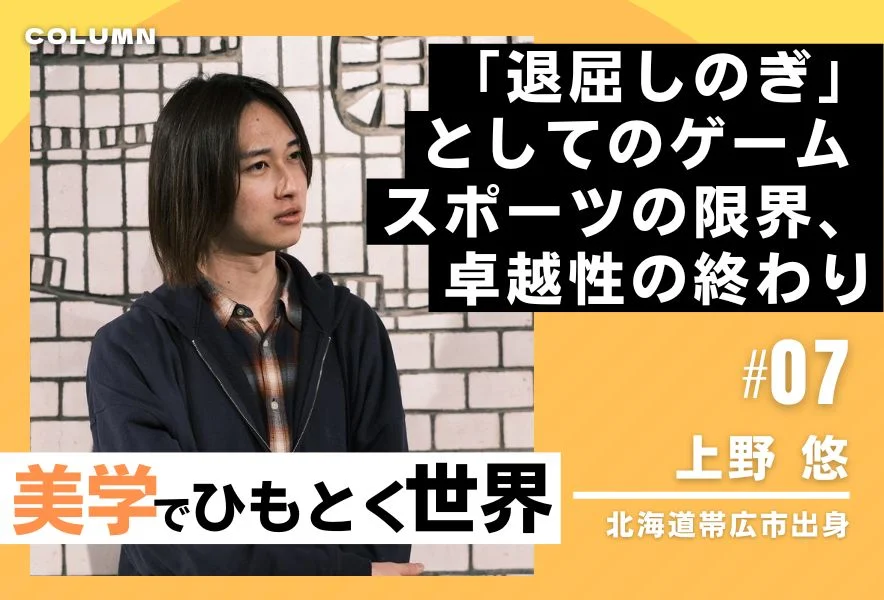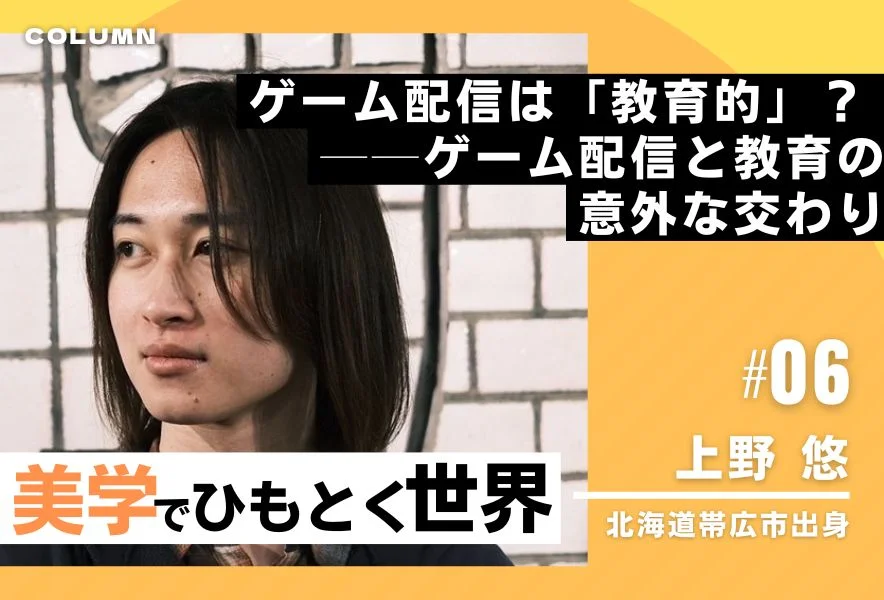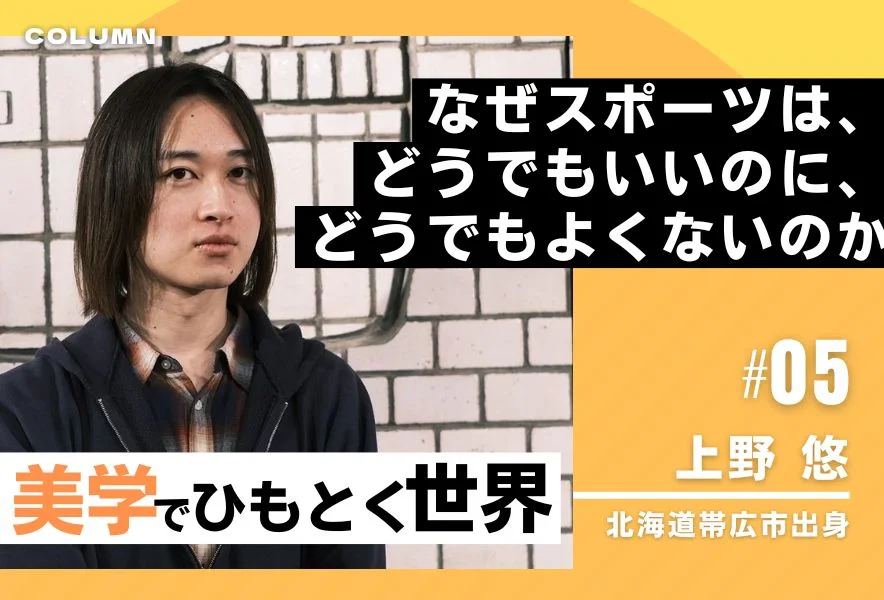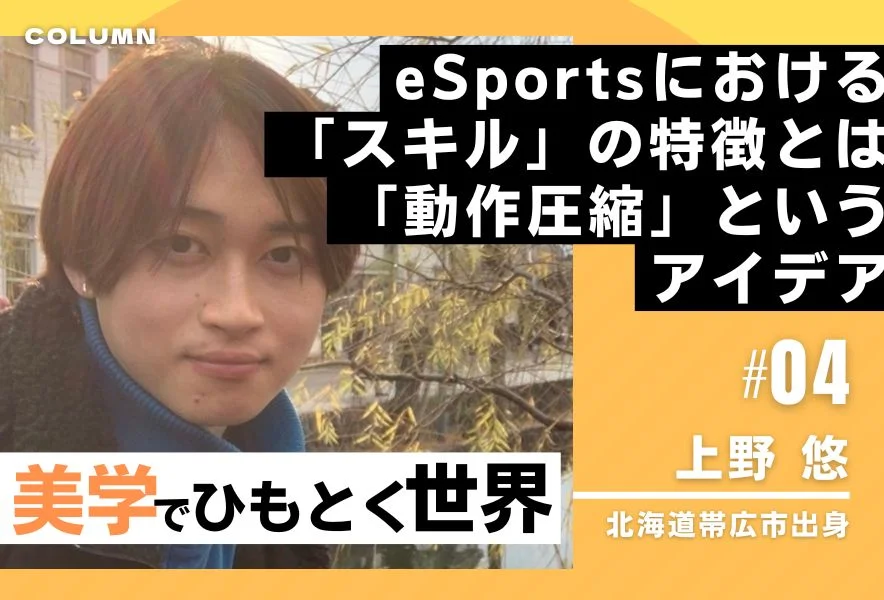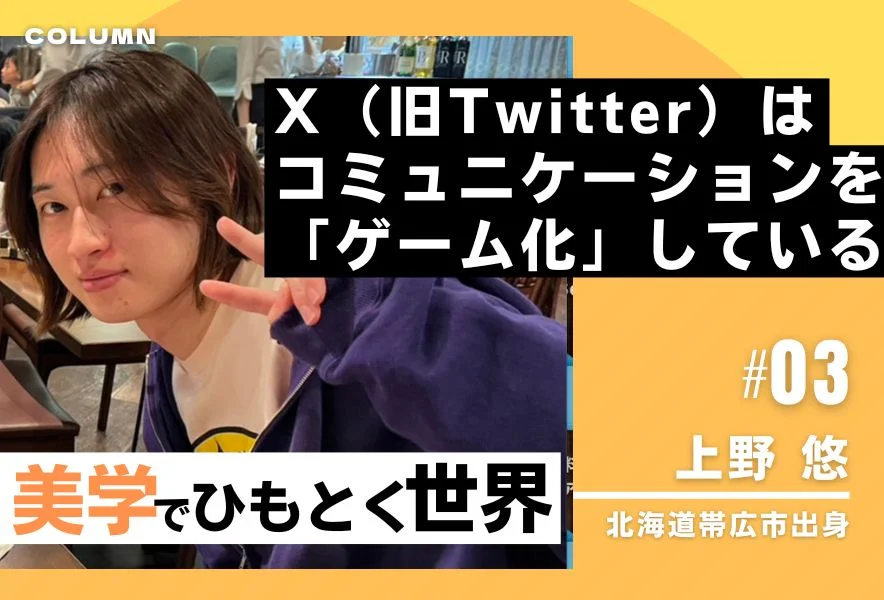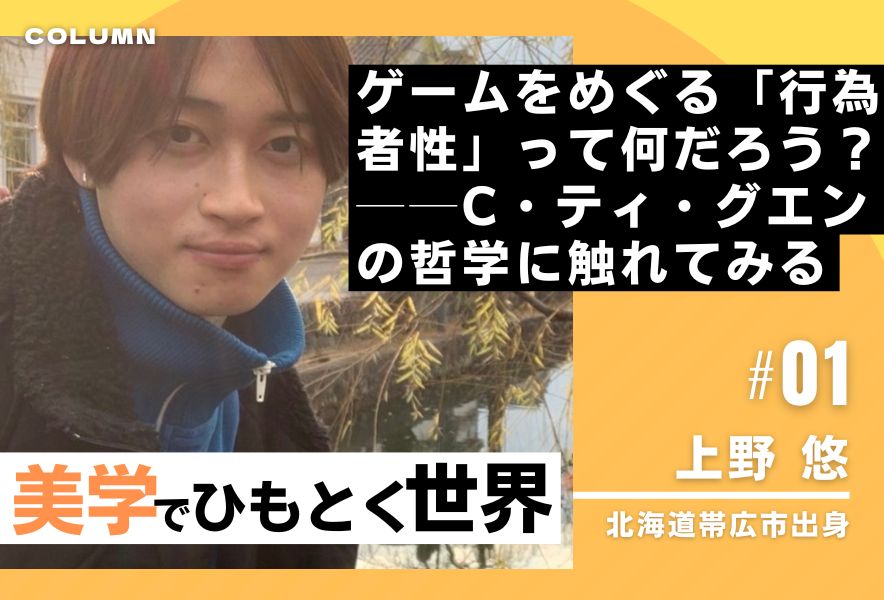【連載】美学者 上野悠の「美学でひもとく世界」
スポーツにおける力

スポーツにおける筋力トレーニングの重要性は近年ますます高くなりつつあります。ウエイトリフティングや格闘技などといった、筋力が明確に試合の勝敗を左右するような競技だけではなく、ほとんどすべてのスポーツで筋力は重要な要素となっています。筋力が必要ないスポーツなど存在しないと言ってもいいかもしれません。
しかし、スポーツにおいて重要な「力」は筋力だけではありません。持久力や精神力といった「力」も非常に強いファクターとして機能しています。また、他の選手や、環境から受ける「力」も存在します。それには、物理的なものもあればそうでないものも含まれるでしょう、例えば、「重圧」や「抵抗」などです。我々はスポーツをするとき、様々な意味での「力」を感じながらプレイしているのです。

では、私たちがスポーツにおいて感じている「力」について、正確な理解を得ようとするとき、どんなものに頼ればいいのでしょうか。まず考えられるのは、物理的・自然科学的な指標です。自然科学においては、力(F)は質量(m)と加速度(a)の積であり、「F = m × a」という式で表されます。
このように自然科学的な力の理解やそれに基づいた知識の体系は、もちろん有用ではあるのですが、しかしながら、それだけでは取りこぼしてしまうような「力」についての理解の仕方があるかもしれません。ドイツのスポーツ社会学者であり、フランクフルト・アム・マイン大学の教授であるロベルト・ググツァは、そうした考えから、「現象学」という哲学的手法を用いて、スポーツにおける力(strength)について分析しようとしています。
「新しい現象学」のスポーツへの応用

ググツァによると、現象学は、人々の日常生活において現れる現象の一般的な構造を記述することにあります。ググツァはこの現象学を用いることで、スポーツにおける力現象の一般的な構造を明らかにし、スポーツにおける力の現象の多様性を示すと言うのです。
現象学と言えば、有名どころは、フッサールやハイデガー、メルロ=ポンティなどが挙げられますが、そのなかでもググツァの論が依拠するのは、ヘルマン・シュミッツというドイツの哲学者が提示した「新しい現象学」と呼ばれるものです。新しい現象学とはどのようなものなのでしょうか。
シュミッツはある人にとっての主観的事実を重視し、現象を「ある人にとってのある時点での現象とは、その人が本気で否定することができない事実であるような状況(Sachverhalt)である」と定義します。シュミッツは、フッサールのように現象の本質を決定することではなく、「その人にとって何が真実であると考えるべきか」という問いに関心を持っているのです。そうしたモチベーションのもとで、シュミッツの新しい現象学は、研究者が何を現象として考慮すべきかを決定するために、ある方法論的アプローチを用います。
シュミッツの方法論
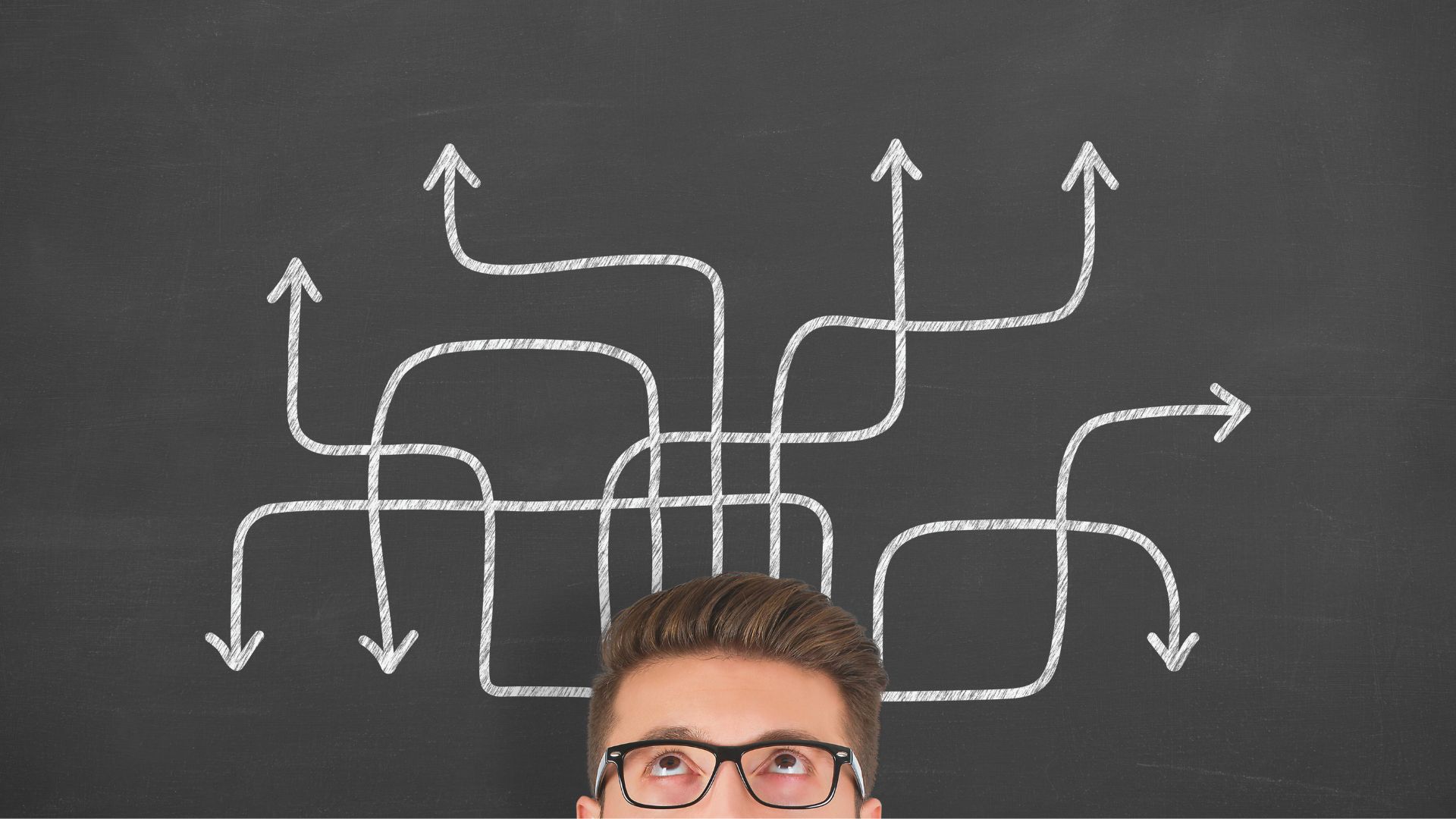
シュミッツは自身の方法を「現象学的修正」と呼びます。現象学的修正とは、意図的に構築されるようなものではない、人々によって実際に感じられる形で起こっていることに接近することを目的としている方法論なのです。シュミッツはこのために、以下のような三段階のメソッドを提案しています。
1. 記述的段階
記述的段階では、日常言語を用いて現象の領域を記述することが目的です。ここでは、個人的な経験、議論、テキストの読解、テレビの報道などに基づいて、その現象の領域に含まれると考えられるような様々な現象を収集します。その後、この現象の領域に属性を付与し、これにより他の現象の領域と区別できるようにします。今回のケースでは、日常の生活において「力」という言葉で説明できる、共通の特徴を持つ現象を探すことが最初のステップとなります。
2. 分析段階
分析段階では、現象において繰り返し出現する特徴を特定し、用語で固定する必要があります。この分析段階の目的とは、問題となっている現象の持つ、一般的な構造的特徴に呼び名を与えて識別するためのカテゴリー体系を構築することです。各カテゴリーは、組み合わさってより複雑な現象を生み出すよう基礎的な現象です。シュミッツはこれを、様々な単語を作るためのアルファベットのようなものだと述べています。今回は、力の現象学的アルファベットを発案することになります。
3. 結合段階
結合段階では、さまざまなカテゴリーを結びつけて、個々の現象を再構成的に記述できるようにします。第二段階で開発された「アルファベット」は、いわば「単語」として組み合わされ、具体的な現象を可能な限り正確に記述するために使用されることになります。今回は、「力」の「現実的定義」と、スポーツにおける力現象の現象学的記述に用いられる力の現象学的アルファベットを提示します。
力の経験

ググツァはシュミッツに倣い、まずは日常的な「力」の経験を記述しようとします。ググツァは以下のように列挙します。
それが身体的に過酷なものであれ(物体を持ち上げたり押したり、上り坂を歩いたり、マラソンを走ったり)、精神的に過酷なものであれ(難しいテキストを読んだり、問題を解決したり)、努力を要するもの。
例えば、顔に風を受けて前進するために体を支える必要がある自然現象といった抵抗。また、議論で自分の意見を押し通さなければならないときに、相手がそれに反対する場合なども、それは抵抗の力として経験され、克服すべき現象として捉えられる。
人、本、風景、曲など、何であれ、自分を魅了し、心を奪うようなもの。
自分何らかの影響を及ぼすような感情、気分、雰囲気。また、強い感情を与える異様な映画や動物といったものも力を持つ。
望む・望まないにかかわらず、文字通りまたは比喩的に特定の方向へと突き動かすようなもの。
例えば、朝ベッドから出られない時、何もしようと思えない時、弱い自分がまたジョギングに行くのを妨げるときといった、「生命を駆動させる力」が明らかに減退したり完全に緩んだりしたときに現れるようなもの。
このようにして、ググツァは「力の現象」としてみなせるような人生経験のリストをつくりました。では、これらのそれぞれ大きく異なる「力現象」が持つ、一般的な構造的特徴とはなんでしょうか。

力の定義
ググツァは上のリストをもとに、力を以下のように現象学的に定義します。
まず、ググツァは力現象の基本的な特徴とは、それが効果として経験される点にあると考えます。日常の経験として、力の現象は、身体的に感じられる効果として現れるのです。
また、ググツァは、風の吹き付け、映画の触覚、サッカー試合の熱狂、閃きの到来、上り坂を歩く努力など、といった諸現象を、それらは身体的に押しつけられるように感じられる侵入的な作用として経験されるのだと考えます。
さらにググツァは、力のソース(the source of strength)と力の場所(the place of strength)という区分を導入します。力のソースとは力を感じさせる何かのことであり、力の場所とは、力現象が経験される場所、つまり私たちの身体です。ググツァによると、力のソースと力の場所は同じコインの表裏の関係にあり、これらは、シュミッツが「一方的な移入」(einseitige Einleibung)と説明する関係にあります。この同化は、力のソースが力の場所に対して支配的な役割を果たすという意味で一方的なのです。

ちょっとむずかしいですが(私も理解があまり正確ではないかもしれません)、例えば、針に刺されて痛みを感じるとき、痛みは私たちにそれに対処しなければならないという強迫観念を生み出させます。こうした効果が「一方的な移入」と言われるものです。
力のソースは、それによって人々が自発的に何らかの方向性へと動機づけられるように、知覚可能な形で人々に影響を与えるものです。もしそうなら、力は感じられる身体への侵入的効果として現れます。したがって「力とは一方的な移入を通じた侵入的効果」なのです。
力のカテゴリー体系
ググツァは続いて、力のカテゴリー体系(またはアルファベット)を次の 10 のカテゴリーに分けます。
①引くpulling
②押すpushing
③求心力centripetal
④遠心力centrifugal
⑤持ち上げるlifting
⑥下げるlowering
⑦強いstrong
⑧弱いweak
⑨重いheavy
⑩軽いlight
ググツァはまず、力の現象の基本的なカテゴリー対は、引きと押しであると言います。さらにそこから、力が「一方的な移入による侵入的な効果」として現れる場合、その身体的に感じられる方向と強度に応じて、分析的な区分によりさらに体系化できると述べます。

まず、身体的に感じられる方向に関して、力の現象は、内向きの作用として求心力、外向きの作用として遠心力として現れたり、上昇または下降の作用として現れたりします。求心力とは、主に身体に作用する圧迫的な力であり、文字通りまたは比喩的に跳ね返る抵抗、受ける打撃、襲われる感情などです。遠心力は、主に身体的に感じられる引きの力であり、何かや誰かへの渇望、魅力的な本が及ぼす引き、何かをしたいという強い衝動、魅力的な人物、魅力的な物体などが含まれます。
内向的・外向的に作用する力は、いわば身体的に水平に感じられる力ですが、上昇または下降する力は、身体的に垂直に感じられる力です。持ち上げる力とは、例えば、空中に跳び上がるような自発的な喜びや、眺めるだけで心が高揚する景観の崇高さであり、下降させる力は、文字通りにも比喩的にも重いリュックや、存在的な不安、または大きな社会的責任など、下方向に引き下げるような力です。
さらには、身体的に感じられる「強度」の観点から、力の経験は強さと弱さ、重さと軽さという現象学的特徴も持ちます。力のソースにかかわらず、力は主観的な事実であり、その効果は常に強さと弱さのグラデーションの中にあります。最大の力は、意識を失うショックであり、一方、非常に優しく触れるもの——視線や物理的な触覚——は、極めて弱い経験として描写できます。
一方で、重量や負荷のようなものの一方的な移入によって生じる力の経験は「重い」ものとして表現されます。このような知覚可能な「重みのある」抵抗を克服することは、「気楽さ」または「解放感」のように感じられることがあります。例えば、マラソンで「ゾーンに入った」状態にある場合、レースの終盤で脚が重く感じられても、ゴールに向かって「飛んでいる」ように感じられるでしょう。これは「軽さ」の経験となります。
身体的な力

こうして力の現象のカテゴリー化を行ったググツァは、第三段階、結合段階に移ります。まず、ググツァはスポーツにおいて最も頻繁に言及されているであろう、「身体的な力」について分析します。
ググツァによると、スポーツの根本的な力現象は「生命力」(vital driving force)です。生命力は、あらゆるスポーツ活動の基礎となるような力であり、その力のソースは自身の身体です。身体は、生理的な状態やプロセスが一方的な移入を通じて身体的な強さの経験をもたらす、強さのソースであり、生命力とは、自身の身体から発されて、身体に感じさせる力なのです。
生命力は十分な睡眠や休息、またはウォームアップ運動によって促進され、逆に疲労や病気などによって抑制されます。主観的には、生命力はスポーツにおいて運動への衝動として体験されます。こうした衝動は、引きの、遠心的な効果を持つ力の経験となります。
ググツァは、こうした生命力が運動において果たす根本的な重要性は、否定的な側面からも明らかであると述べ、その一例として「自己の弱まり」と呼ばれる概念を取り上げます。自己の弱まりを感じる人は、生命の推進力がほぼ完全に欠如しているため、運動を困難に感じたり、全く行えなかったりします。この身体的な力は、スポーツ活動が始まる前に、影響を受けた主体を圧倒してしまうのです。これは例えば、「バッテリーが切れた」などといったように表現される経験だと考えるとわかりやすいかもしれません。自己の弱まりの影響を受けた者は、生命力が徐々に衰えるような経験を、抑圧的で、求心的で、重く、強い経験として体験し、最終的に「バッテリーが空になった」状態ではそこから逃れることができなくなります。そうした際、自身の身体を力のソースとしてその力が最大に高まると、「力の場所としての身体」を完全に消滅させ、その結果として、疲労による失神などが引き起こされるのです。

他者の身体的力
ググツァは他者が及ぼす身体的な力は、力のソースが自身の身体の場合とは違った経験を与えると述べています。
特に、興味深いのは、シュミッツを参照しながら、「動作の示唆」(Bewegungssuggestion)と呼ぶものです。これは、他者の身体から発せられるものであり、飛ぶボールの運動や、こちらを捉えるために伸びる拳は、それらに影響を受ける人々が特定の行動を取るように促す点で、身体的に強力な現象であると言えます。例えば、サッカー選手は、ボールの飛んでくる方向に応じてピッチ上のボールを受け取れる位置へ走り、ボクサーは向かってくる拳を避けるために横に一歩踏み出します。
ググツァは、このような場合における力のソースは、物体そのもの(ボールや拳)ではなく、それに伴う動作の示唆であると言います。というのも、物体そのものではなく、動作の示唆による侵入的な効果(典型的には引き寄せる遠心力)が、私たちを特定の行動へと誘うからです。
心理的な力

しかしながら、ググツァは、スポーツの力に関する新現象学的分析の真の価値は、こうした身体的力を超えた力現象を特定し、現象学的に適切な方法で記述可能にする点にあると言います。これには、心理的力や社会的力のほか、ググツァが半-もの(half-things)と呼ぶものの力現象が含まれますが、今回は、このうち、心理的な力について触れたいと思います。
試合中、アスリートは、心理状態や心理プロセスにより、身体的に侵入的な力を経験します。これは、知覚、思考、記憶、アイデア、意志力、予期、直感などによって引き起こされる身体的な経験を指します。スポーツ科学、特にスポーツ心理学は、このような精神状態やプロセスを、認知的プロセスに影響を与える「心理的要因」や、個人の性格特性や傾向などとして位置付けていますが、スポーツ現象学ではこうしたものを「力」として扱うのです。
ググツァが挙げる、スポーツの行動と相互作用の中心にある例は「集中力」です。 集中力は、運動の成功的な実行のための基本的な前提条件であり、初心者であろうと熟練したプレイヤーであろうと、集中力が欠如していると、習慣化された運動であっても実行に失敗する可能性があります。
ググツァによると、新しい現象学的な視点からは、集中は求心的に圧迫され、知覚的に緊張した注意として感じられる身体的な経験であると言えます。例えば、ペナルティキックを蹴るために集中している場合、集中は身体的に感じられる収縮的な、経験とであり、諸感覚を統合するものです。もちろん、運動の実行に意図的に集中することもできますが、それでも集中は「身体的に感じられる経験」であり、そのことは、個人的要因(自信の欠如)、身体的状態(疲労)、または環境条件(騒音)の干渉により、集中が不可能になることがよくある、という事実によっても示されているのです。

またそのほかにも、過去の失敗の記憶などは、求心的で抑圧的な重さの効果をもたらすのに対し、開始直前の落ち着かせる自己暗示、遠心的で高揚的で、軽さの効果をもたらす可能性があると言います。
ググツァによると、このような心理的過程を「力現象」として理解することは、なぜそれらが効果的であるのか、意味を持つようになるのかを理解するのに役立つのです。記憶、自己言及、訴求、意志、または意図といった、心理的な力のソースによる、身体への侵入的効果が欠如していると、その物理的実現はより困難になると考えられるのです。
そのほかにもググツァは、半-もの、すなわち雰囲気的なものの持つ力や、社会的なものの持つ力についても分析します。こうしたものも主観的な意味での「力」の現象として認めることで、スポーツにおけるそれらの効果や意味を確認することができるのです。
美的行為の記述として

今回紹介したスポーツにおける「力」の現象ですが、私自身がこの論文に着目したのは、この論が、ゲーム研究者で美学者の松永伸司による「美的行為」という概念の存在にあります。松永は、ゲームのプレイ(彼はこれをゲーム行為として定式化しています)を「美的行為」として特徴づけようという提案をしているのですが、その美的行為とは以下のようなものです。
美的行為は、それをおこなうのに趣味に類比的なある種の特殊なセンスを必要とするものであり、それゆえ誰もがあたりまえのようにできる行為ではない。また、その行為をおこなう仕方が一般化できるようなものでもない(たとえば、特定の手順を概念的に把握すればできるようになるといったものではない)。しかし、それでいて、行為する際のポイントを指摘したり、その行為の内実を不十分なかたちではあれ言語化したりすることで、そのやり方を他人に伝えることができる──このような行為である。(松永 2018, 183)
私の考えは、この美的行為の個々のケース(野球における美的行為、将棋における美的行為)の経験を記述する際に、ググツァの提示した現象学的方法や、力の現象の分析やカテゴリーづけが役に立つのではないか、というものです。というのも、ゲームにおける行為や経験の記述というのは、例えば絵画や映画の観賞の記述と比べて蓄積が少なく、言語化することが相対的に難しい状況にあるからです。そのなかで、今回の記事で見た「力の現象」という概念は、何らかの手掛かりになってくれるような気がします。
参考文献
- Gugutzer, Robert. 2024. “Strength as phenomenon: a pure phenomenology of sport.” Journal of the Philosophy of Sport 51(3). DOI: 10.1080/00948705.2024.2370461.
松永伸司. 2018. ビデオゲームの美学. 慶應義塾大学出版会.
美学者とは
美学者の役割
- 【美的判断】なぜある人が「美しい」と感じる対象を、別の人は「そうでもない」と思うのか
- 【芸術作品の価値】作品が私たちの感性に与える影響を、どう評価し、言葉で説明できるか
- 【日常の美】ファッションやインテリアなど身近なところに潜む「美しさ」をどのように考えるか
こうした問いに取り組むのが美学者の役割です。近年では、ゲームの体験やデザイン、スポーツや身体表現、さらにはSNSなど、従来は「美学」とはあまり結びつかなかった分野にまでその探究範囲が広がっています。哲学や芸術学と深く関係しながら、現代社会のあらゆる「感性の問題」に光を当てるのが、美学者と呼ばれる人々なのです。

【PROFILE】
北海道帯広市出身。早稲田大学文学研究科博士後期課程在籍。専門は、ゲーム研究、美学。主な論文に、「個人的なものとしてのゲームのプレイ: 卓越的プレイ、プレイスタイル、自己実現としての遊び」『REPLAYING JAPAN 6』、「ゲームにおける自由について──行為の創造者としてのプレイヤー──」『早稲田大学大学院 文学研究科紀要 第68輯』。ゲームとファッションとタコライスが好き。