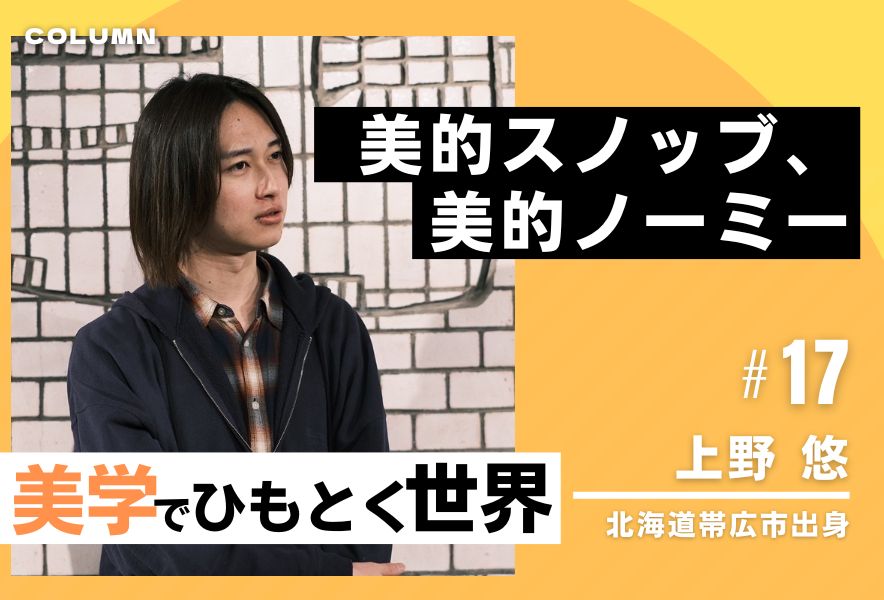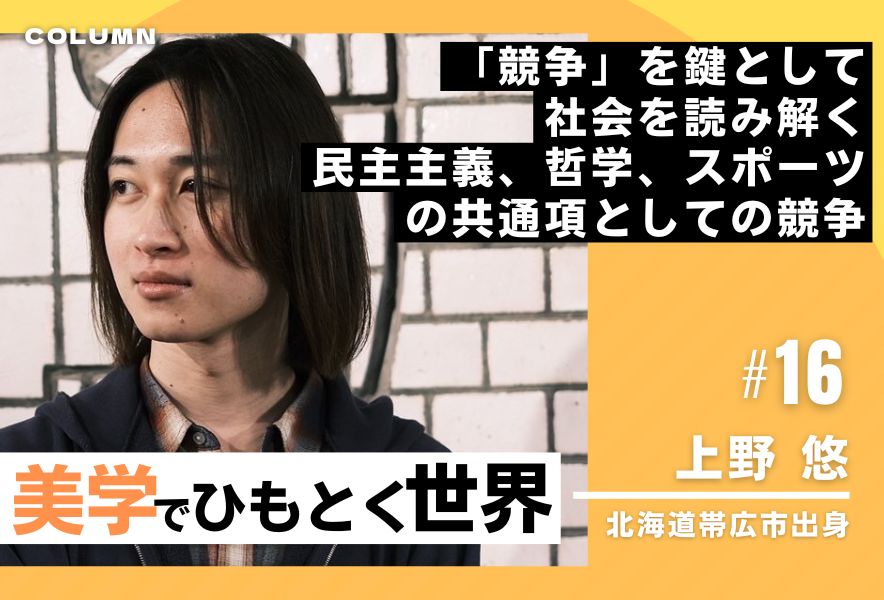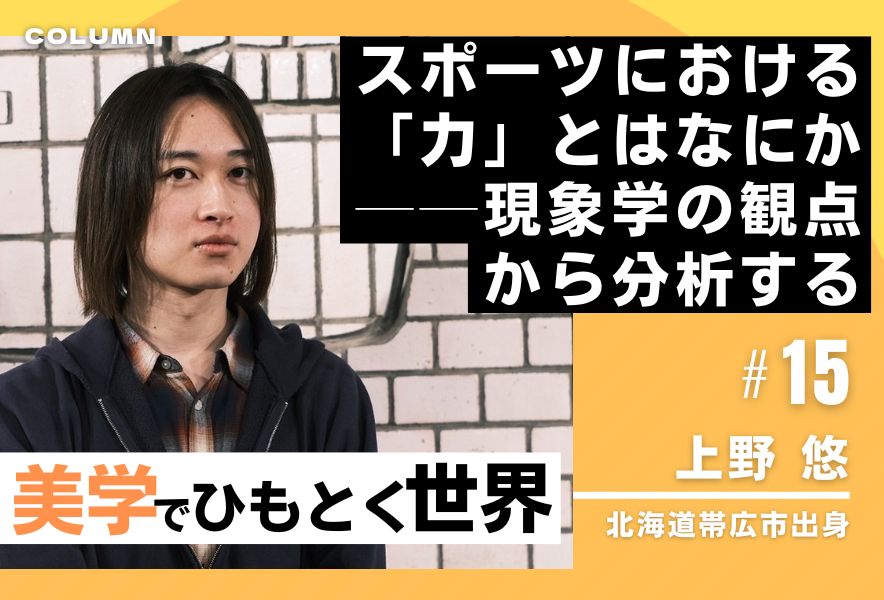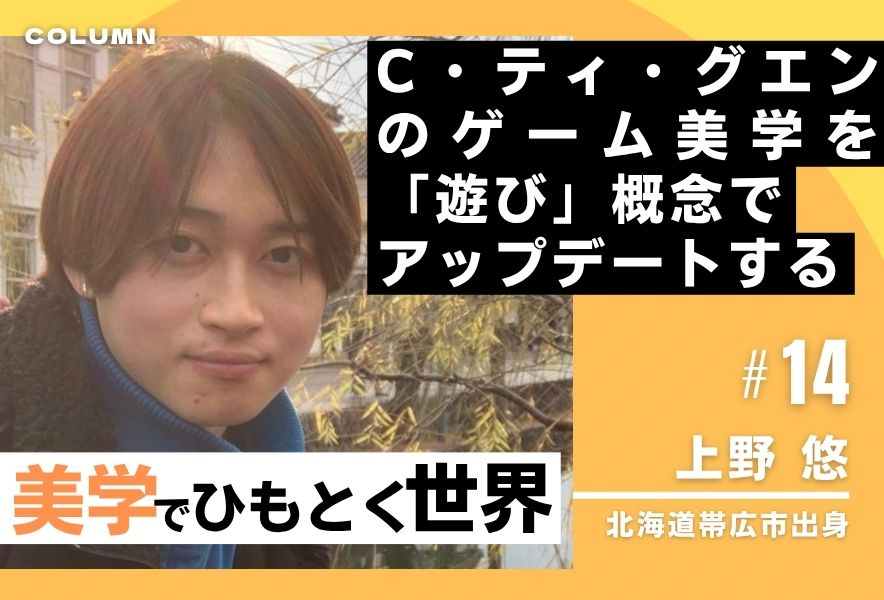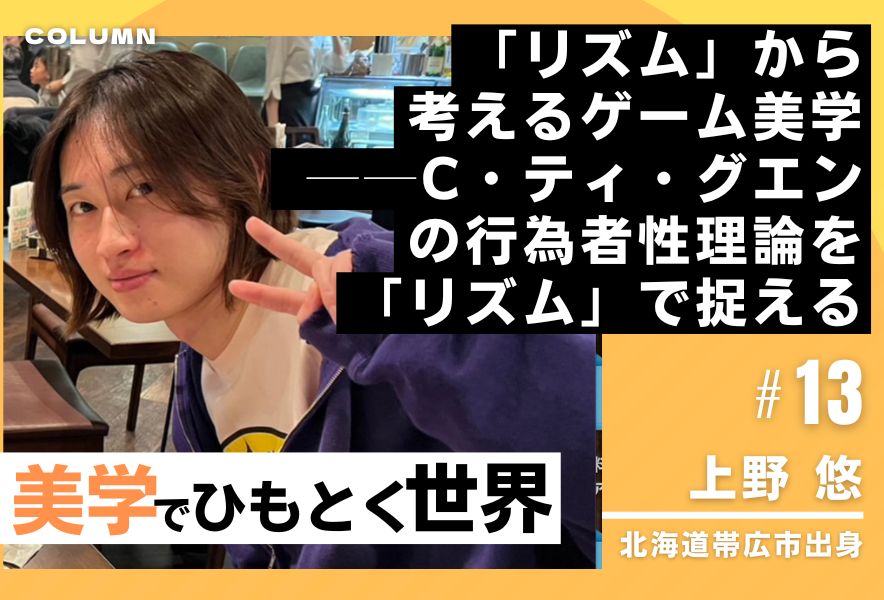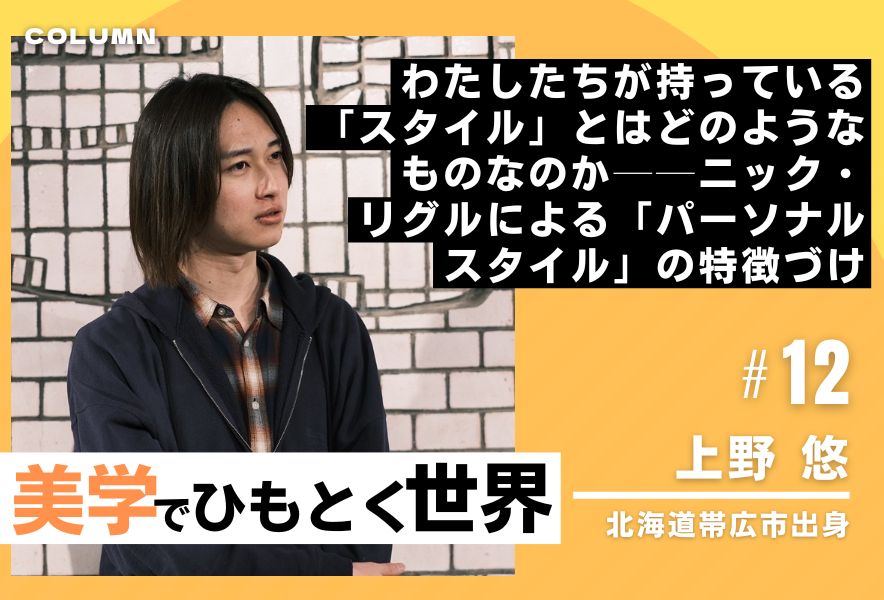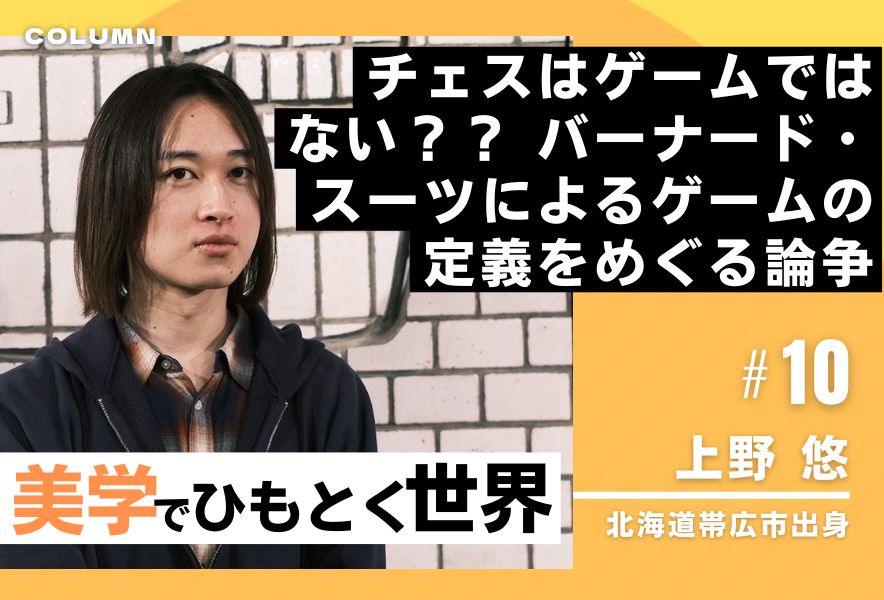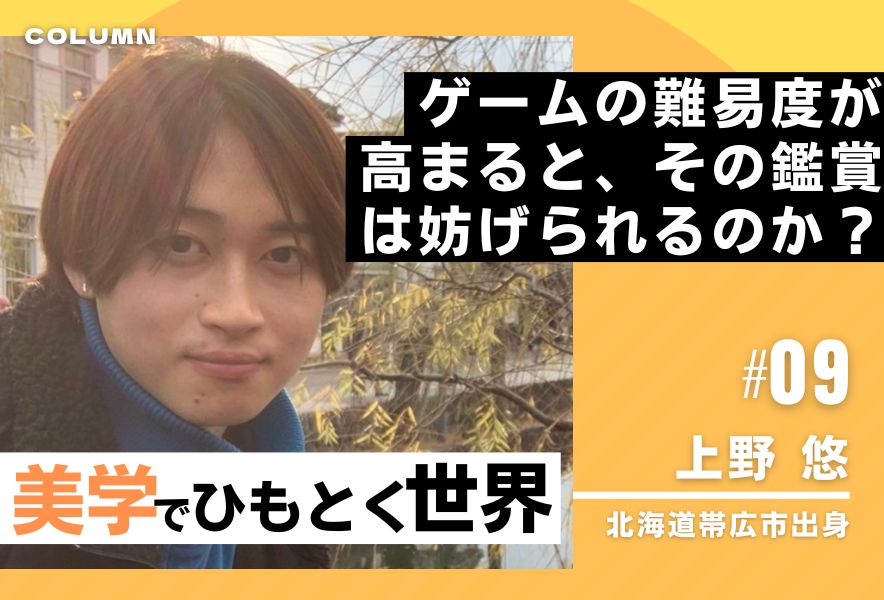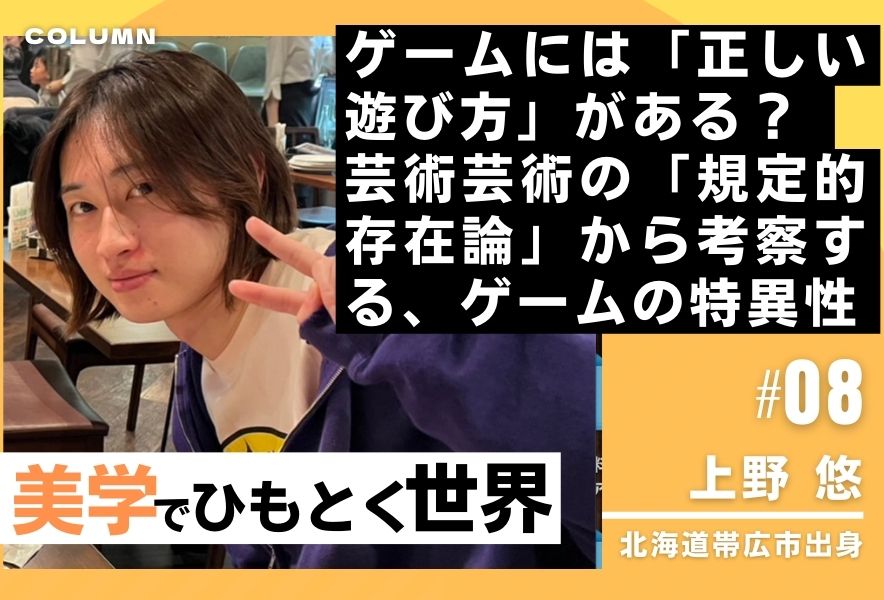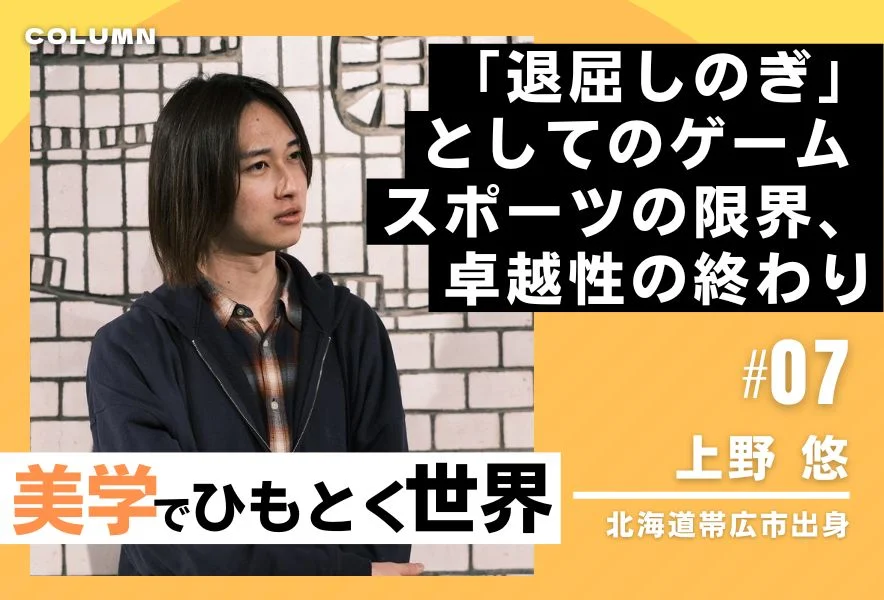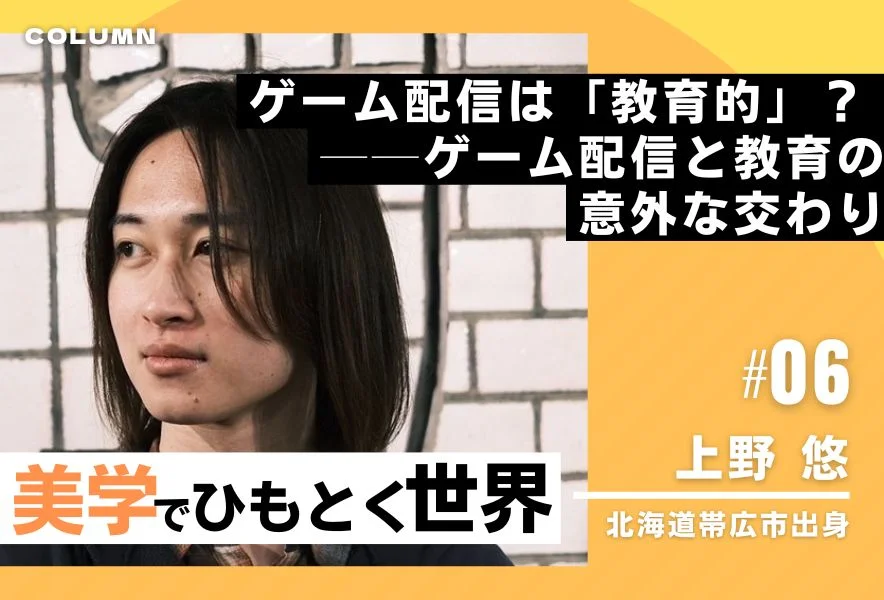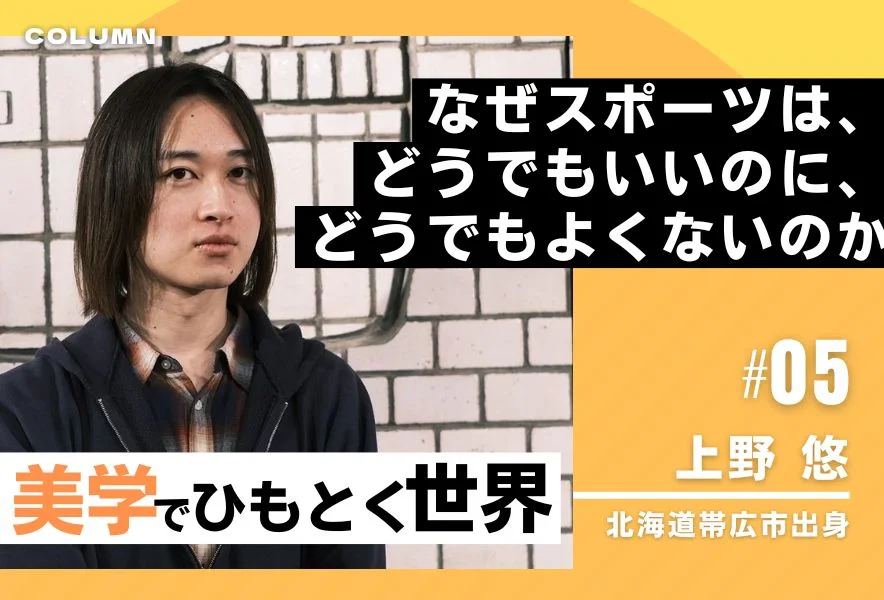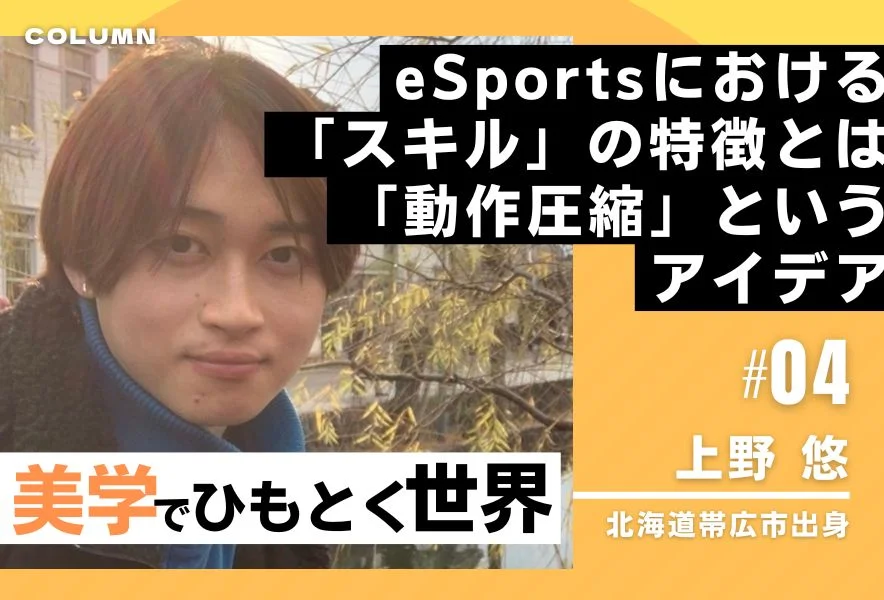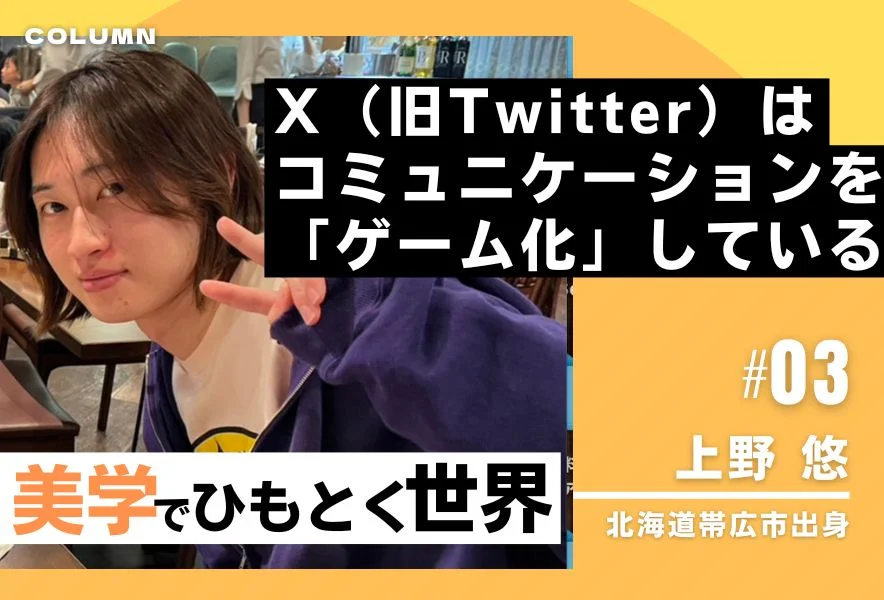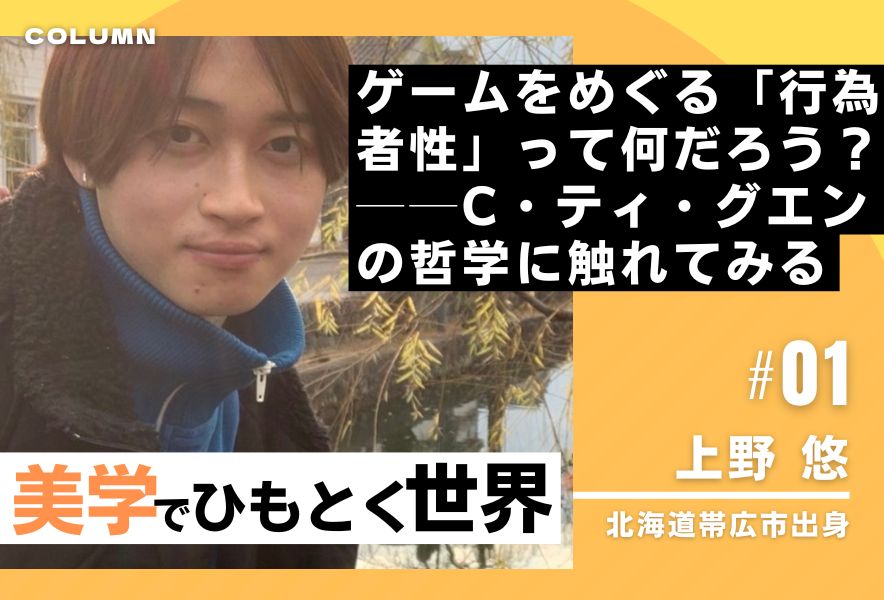【連載】美学者 上野悠の「美学でひもとく世界」
美的スノッブ

みなさんの身の回りにこんな人たちはいませんか。ブランドものを身につけ自分の社会的地位をアピールする人、洗練された趣味のよさを持つがゆえにそうでない人を見下す人──。
こうした人たちは、「美的スノッブ」としてカテゴライズされる人たちなのです。近年、美学の領域では、こうしたスノッブのわるさが、わたしたちの美的実践をいかに脅かすかについて考えようとする動きが出てきています。
ステファニー・パトリッジ(Patridge 2023)は、こうした美的スノッブについての議論を整理整頓し、スノッブを4つの種類に分類しています。
社会伝染型スノッブ
ひとつ目が、社会伝染型スノッブ(social contagion snobbery)です。このタイプのスノッブはマシュー・キアラン(2010)によって明らかにされています。
キアランのいうスノッブ=社会伝染型スノッブは、ある美的対象を、美的に妥当な理由からではなく、社会的威信のために──他者を感心させるために──好きになろうとするような人です。

例として、キアランは「illyのコーヒーを好む人」の例を挙げています。ここで想定されているような人は、「自分を特定のタイプの人間として区別される」ために、「illyというブランド」と関連づけられるような人になりたいと望んでいるのです。ここで、主張されているのは、もちろん、illyコーヒーを好む人全般がそうであるということではなく、みんなからの感心を得るため、という理由で、ただただ好きであるというわけではないブランドを好んでいる人は美的スノッブである、ということです。
さて、こうした社会伝染的なスノッブたちは、そうした判断を下すに至るような、ある傾向性を持っています。彼らは、美的なよさを社会的地位の高さと混同してしまうという、誤った指向性を持っているのです。こうした誤った傾向は、彼らの美的指向性を体系的に歪めてしまいます。その結果、スノッブは、特定の美学的な「落とし穴」にはまりやすくなってしまうのです。
例えば、このタイプのスノッブは、美的評価において臆病で偏狭な傾向があります。そして彼らは特に、あるものの美的価値と社会的評価が乖離するような状況に陥ると、作り話をしたり、過度な一般化に走ったり、偏った注意の向け方をしたり、あるいは、誤ったジャンル分けをしてしまったりなどといった、美的に誤った行動をしてしまうようになるのです。

社会的地位と美的価値は一般的に言って乖離したものであるのですが、社会伝染型スノッブの判断は社会的地位を追随してしまうのです。ごくまれなケースでは、地位と美的よさが一致することもありますが、その場合、スノッブの美的判断はただ偶然的に正しいだけなのです。社会的威信は美的妥当性のないものであるため、スノッブの美的判断は正当化されず、そうしたスノッブの美的判断は正しい知識としてカウントされないのです。
態度型スノッブ
ステファニー・パトリッジ(2018)は、上記のキアランの分析では捉えきれない「スノビズム」のより現代的な概念を指摘しています。
このスノッブは、自分より下の趣味を持つと思われる人を見下すような人です。パトリッジは、自己と他者に対して有害な「態度」を取るこの種のスノッブを、態度型スノッブ(attitudinal snobbery)と呼びました。

態度型スノッブは、「局所的な判断を支える基準に基づいて、個人の全体的な地位や価値について包括的な判断を下し」てしまいます。つまり、この場合はある人の美的判断の能力(=趣味)だけを見て、その人の人格や地位、人としての価値についての決定を下してしまうわけです。
しかし、このような態度型スノッブははしばしば実際によい趣味を持っていることがあることを指摘しています。社会的伝染型スノッブが、一般的な人々から自らを分離するためにあれこれの作品を好むのに対し、態度型スノッブは、あれこれの作品を評価する能力(それが正しかろうが間違っていようが)ゆえに一般的人々から分離していると考えるのです。
すると、一見すると、社会的伝染型と態度型のスノッブの大きな違いは、前者が美的判断を妨げるのに対し、後者はそうしない点にあると考えられます。しかしパトリッジは、態度型スノッブも美的判断を損なう可能性があると言います。

典型的な態度型スノッブは、社会的地位の指標となるような、美的なスキルや達成に基づいて人を判断します。例えば「私はクラシック音楽の判断が結構イケている」ではなく、「クラシック音楽について何も知らない人々より私は優れた人間だ」や「彼女は音楽の趣味が良いから、そうじゃない人より優れた人間だ」などといった風に考えるのです。
ここでパトリッジは、アリストテレスが提示した「徳ある人は、正しいことを正しい理由で行うだけでなく、そのことに対して正しい感情を抱くべきだ」というテーゼに目を向けます。キアランの社会的伝染型スノッブは、理由が正しいもの(徳に適合的なもの)ではないため、「理由の条件」に反します。一方で、態度型スノッブは、自分の鑑賞能力に対して間違った感情を抱いたり、間違った態度を示したりするため、「感情の条件」に反すると考えられるのです。
文脈型スノッブ
パトリッジ(2018)はさらに、美的な判断を損なうスノッブの第三の形態として、文脈型スノッブ(contextual snobbery)を提唱しています。いわく、文脈型スノッブは、社会的文脈を読み解く失敗として現れるのだと言います。

文脈型スノッブの典型的な形態は、通常の文脈では洗練されているとされるような美的なスキルを、何らかの意味で「社会的地位が低い」とされている社会的文脈において行使することです。これだけだとちょっとわかりづらいですが、パトリッジはわかりやすい例として、バーベキューのときに、ふだんはビールのソムリエをしている人が、バドワイザーを勧められた状況を挙げます。もしこのソムリエが「このビールはひどい」という美的理由からバドワイザーを拒否した場合、パトリッジはこれがスノビズムであると言うのです。ソムリエのビールの美的特徴に関する判断は、ある意味では正確であっても、その拒否はスノビズムである可能性があるのです。
パトリッジは、単に「高級な」美的判断能力を行使する行為自体が、文脈によってはスノッブ的行為になる場合があると指摘しています。というのも、社会的文脈は美的判断に影響を与えると思われ、

あるいは
という2パターンのいずれかのような推論が妥当であるように考えられるからです。いずれにせよ、パトリッジは、ビールを拒否するという行為とそれに対応する美的判断「バドワイザーは悪いビールだ」は、どちらもスノッブであると言うのです。
真の階級主義型スノッブ
一方で、ゾーイ・A・ジョンソン・キング(2023)は、これまでの見下しの説明は「階級主義によって歪められた美的評価」という「スノッブの典型例」を見逃してしまっていると主張しています。キングの言うスノッブとはキアランのスノッブに近いものですが、階級主義型スノッブは、ある美的対象について、それらを低い階級と関連づけることにより、その対象を実際よりも劣ったものと判断してしまうのです。したがって、そうしたスノッブたちの美的判断は誤っているのであり、彼らの美的判断は階級的差別に「感染」しているために誤ってしまうのです。

キングは、キアランの「スノッブ」とキングの「スノッブ」は、同じように美学的判断を誤る可能性が高いタイプの人々であるものの、キアランの方のスノッブは(キングの巻ゲルものと違い)美的推論を全く行っていないのだと言います。キアランのスノッブは、美的対象をその美的性質のためにではなく、それが当のスノッブの地位を向上させる可能性のために価値づけています。つまり、社会的伝染型スノッブのくだしている判断の根拠は、美的推論ではなく、社会的地位に関するの推論なのです。
一方で、キングは、パトリッジのスノッブ——態度型スノッブと文脈型スノッブ——については、美的推論に従っているが、それらが取り組んでいる美学的推論はまったくもって「完全なもの」である可能性があると指摘しています。というのも、それらの誤りは、彼らが取る態度(態度型スノッブ)にあるか、または美的判断を適切な文脈外で表現すること(文脈型スノッブ)にあるからです。よって、キングは、上記3つの例では、「評価の対象についての正当な評価を下すことにこだわっているが、実際には正当な評価を下せていない」というスノッブの重要な特徴をすくいだせていないと言うのです。

美的ノーミー
さて、ここまでスノッブについて説明してきました。「こういう人いる!」と思われた人もいらっしゃるのではないでしょうか。そうでない人も、美的スノッブの問題点や、なにがわるいのかについて理解していただけたかと思います。
一方で、ある意味美的スノッブの逆ともいえる人々についての研究もなされています。ティン・チョウ・ラウ(2024)は、そうした人々たちを「美的ノーミー(aesthetic normie)」と名付け、分析の対象としています。美的ノーミーとは、ざっくり言えば、人気のある美的対象に関与する人のことです。ラウは、例えば、マーベル映画、テイラー・スウィフトの歌、TikTok のダンス、倉庫の壁に映し出されたゴッホの絵画のデジタル投影などといった例を挙げ、これら人気のある美的アイテムに固執する人について考えてみるように促し、私たちの美的生活の倫理的側面について考察したいのならば、ノーミーにもっと注目すべきであると主張しています。

ただし、ラウは、ノーミーは真の美的理由に基づいて美的選択を行うこともありうることに注意を促します。美的理由は、ノーミーの意思決定においても重要な役割を果たしており、ノーミーたちはより人気のない美的アイテムではなく、人気の美的アイテムを選ぶ他の動機を持っているだけなのです。
美的ノーミーの二つの動機
ラウはノーミーを人気の美的アイテムへと向かわせる主要な動機が 2 つ存在するとしています。1つめの動機は、「社会性への欲求(drive towards sociality)」です。この動機によって行動するノーミーを、ラウは「社会的ノーミー(social normies)」と呼んでいます。2つめの動機は、「挑戦の回避(avoidance of challenge)」です。この動機によって行動するノーマリーを、ラウは 「挑戦回避型ノーミー(challenge-averse normies)」と呼びます。このうちラウは主に1つめの社会的ノーミーに焦点を当てて分析していきます。

社会性への欲求とは、「コミュニティの中で協力し、共有し、互いに依存し合う欲求」のことです。この欲求にのっとり、わたしたちは、社会的な存在として、互いに協力し、何かを共有しようとしますが、もちろん、これには、美的対象を一緒に体験し、その体験について互いに話し合うことも含まれるのです(友達と一緒に映画を見に行ってそれについて語り合ったりしますよね)。そして、こうした共有によって、私たちは互いの美的な努力の成果を享受することができるのです。
私たちは時間や資源に限りがあるため、どの美的対象を探求するか(例:どの映画を見に行くか、もうすぐ会期が終わる現代美術の展示を見に行くかどうか)を判断する際に、他の人の判断(例:あの映画はよい映画なので見に行くべき、あの展示はつまらないので見に行かなくてよい)を判断材料として利用することがしばしばあります。こうした「美的分業」に私たちは依存しているのだとラウは指摘します。つまり、社会性によって私たちの美的生活は支えられているわけです。

しかし、ラウは、社会性への欲求は、しばしば美的範囲、さらには美的深みを制限する可能性があるのだと指摘します。というのも、第一に、社会性への欲求によって、美的選択において社会的な規範に従う人は、意識的に不人気の美的対象を避けてしまう可能性があり、第二に、社会的規範に従う人は、美的アイテムの人気をその品質や価値についての有力な判断材料として捉えることがあるからです。さらにいえば、そうした人々は、時に意識的にこのようなことを行うことがあります。
しかしながら、 美的経験の幅を広げることは、そうしなければ得られなかった、より大きな、または、幅広い美的価値へのアクセスを可能にすると考えられます。ノーミーであることは、私たちの美的範囲を制限するため、未知の価値の高い美的経験や美的価値へのアクセス機会を奪うことで、よい美的生活の妨げになってしまう可能性があるのです。また、そうした傾向は、一部のアーティストに人気が偏ることによって、その他のアーティストの露出の機会が少なくなり、すでに人気のある美的アイテムの人気がより高まる、という循環に陥ると、ラウは指摘しています。
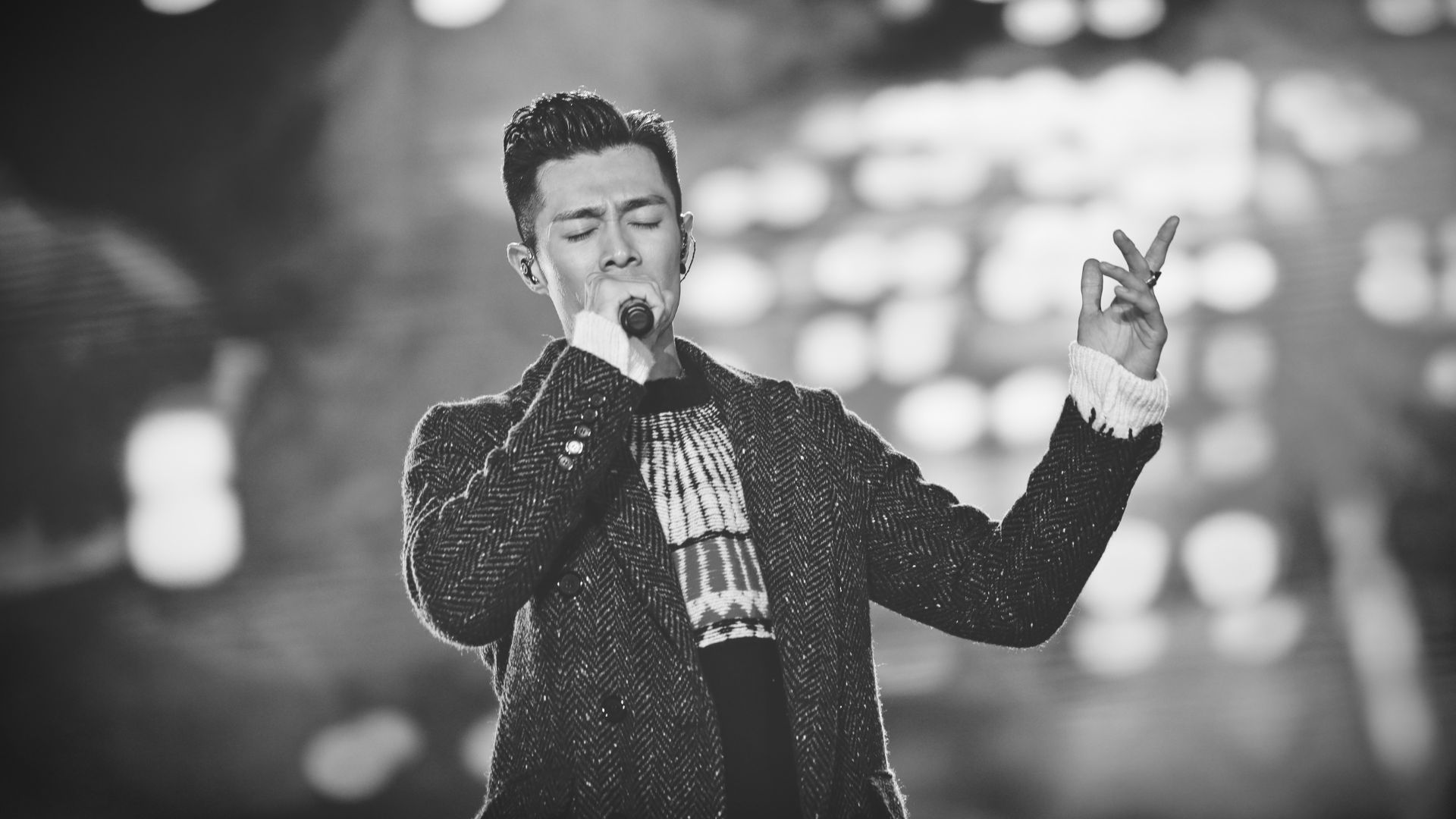
社会的つながりの再方向付け
こうした問題について、ラウは、社会性への欲求の再方向付けを行うことによって、解決することが可能であると主張します。
私たちは、人気のあるものとそうでない美的対象の両方に関わり、それらに対する深い評価と理解を育むこと──美的開放性(aesthetic openness)を持つこと──により、私たちは美的性格(それぞれの持つ美的な好みの個性)を育みます。こうしたそれぞれの好みがないような世界、つまり私たち全員の趣味嗜好や考え方が同じで、あらゆる場面であらゆる物事においてつながっている世界はかなり恐怖ですが、私たち全員が決してつながらないような世界もまた恐怖です。私たちは、適度に個性を持ち、適度につながることが必要なのです。
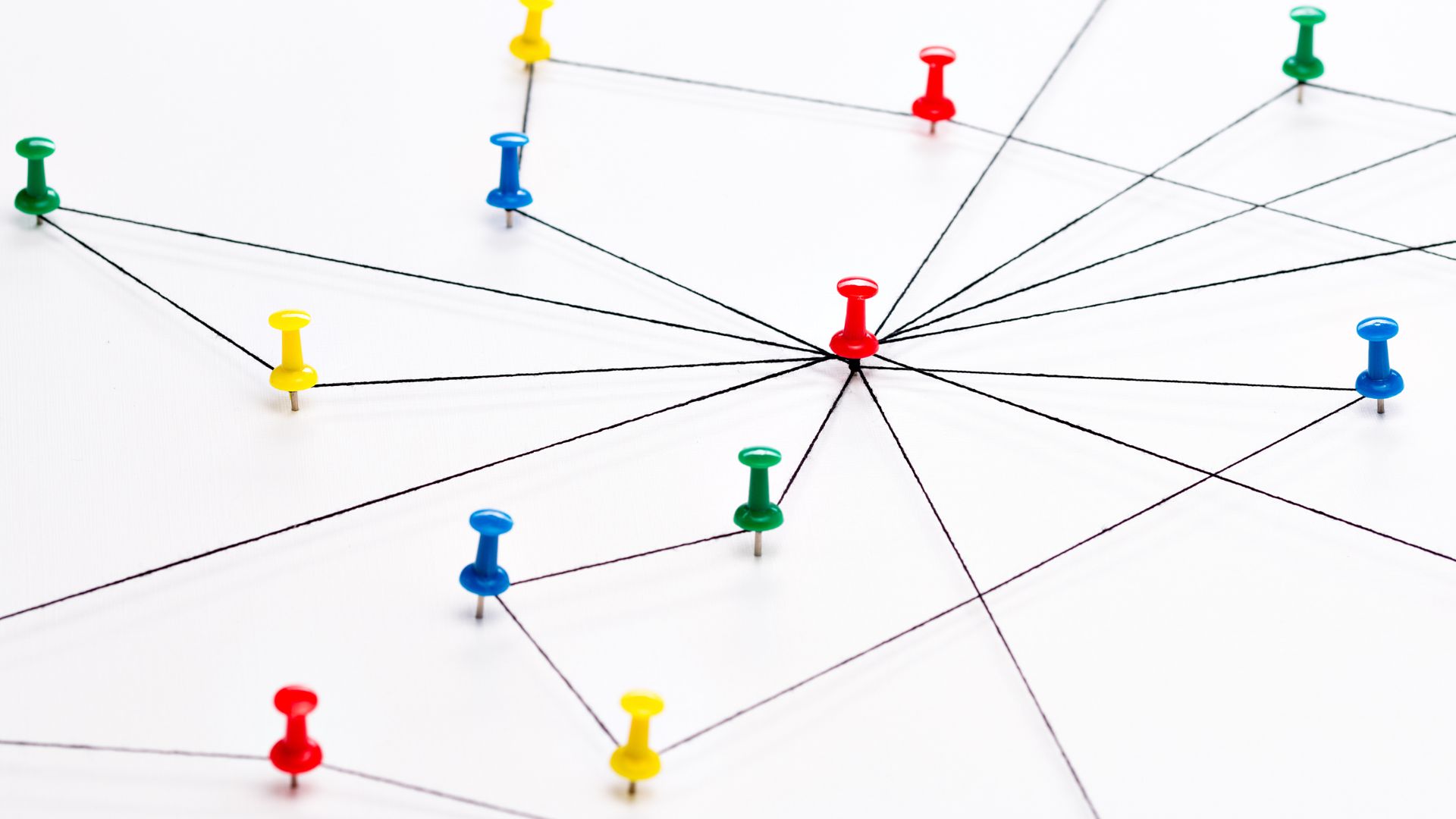
美的開放性を持つことは、私たちの社会的つながりをより豊かなものにしてくれるということをラウは強調しています。ラウは、『必殺!恐竜神父(原題:The VelociPastor)』というへんてこりんな映画を好む友人の例を引き合いに出し、そこに見られる友人の美的開放性は、彼の素晴らしさを示しており、ラウ自身も新しい美的アイテムを試したり、自分を真剣に考えすぎないようにしたりするきっかけになっている、と述べています
美的な個性や美的開放性は、美的コミュニティの土台となり、そうしたコミュニティは、より深い人間関係を育み、美的分業の恩恵を受けることを可能にします。ラウは、こうした考えを、ニック・リグルから参照しています。リグル(2022)は、美的開放性が単に美学的に価値あるものであるというだけでなく、それは、そうでなければ交流する理由がなかった人々とつながるのを助けるという意味で、社会的に価値あるものであるのだと指摘しています。美的開放性を持つことで、私たちは他者とよりよくつながることができ、社会性への欲求をそのように再方向付けすることにより、美的コミュニティの創造を通じて、社会性の価値ある形を生成するのです。
美的スノッブと美的ノーミーとの付き合い方

今回は美的スノッブと美的ノーミーという二種類のよくない美的なありかたについて、ステファニー・パトリッジ(Patridge 2023)やティン・チョウ・ラウ(Lau 2024)の論文を使って説明してきました。美的アイテムの選択を通して社会的優越性を示したり、他者を見下したりすること(美的スノッブ)や、人気のある美的アイテムにばかりとびつくこと(美的ノーミー)が、みんなの美的生活にとってよくない傾向性を形作ってしまうと言うのは確かにうなずける話のように思えます。
しかしながら、スノッブ的態度やノーミー的態度をとる人が身の回りにいると言う方もいれば、自分こそがそうなのではないか、と思ってしまう人もいらっしゃるのではないでしょうか。私がまさにそうです。私の話で言うとおそらく、音楽やファッションについてはスノッブなところがありますし、映画に関してはかなりノーミーです(マーベル映画を友達と毎作観に行きますし、アカデミー賞をとった作品はそれだけで観に行こうと思います)。自分がそうであるからというわけだけではないですが、自分の中のスノッブ的側面やノーミー的側面を一切合切なくそうとすることはかなり難しいのではないかと思えます。

これについて、美学者の松永伸司さんが興味深いことを言っています。松永さんは、「美的ノーミーに共感するか、美的エリートに共感するか」という問いに対して、「美的エリートに共感する面もあるし、美的ノーミーに共感する面もある。加えて、美的スノッブに(しぶしぶながら)共感せざるを得ない面もある。自分の中にそれぞれのキャラクターがいる。それぞれをどう飼い慣らすかという態度でいたい」と答えています。
「飼い慣らす」という表現は、スノッブに親和的な自己やノーミーに親和的な自己の上に、それらをコントロールしようとする、より高次の自己──いわば、二階の自己─の存在を示唆しているように思えます。これを仮に「統制的自己」と呼びましょう。ここで問題になるのは、統制的自己はどのようにして、自分の中のスノッブやノーミーやエリートをコントロールすればいいのか、ということです。それがどのような方法であるのかについては後で少し触れたいと思いますが、重要なのは、スノッブやノーミーを完全になくそうと努めるよりは、それらをいかにコントロールするかに考え方をシフトした方がいいのではないか、ということです。

また、ちなみにですが、松永さんはラウのものとは少し違った「ノーミー」観を持っているように思えます。というのも、松永さんは美的ノーミーについて、「明らかにチープなものであれ明白に思い出補正によるものであれ、どうしようもないパーソナルな選択傾向があること(そしてそれに愛着を覚えること)は、美的ノーミーと親和性がある」と述べており、ノーミーの美的選択が、その対象が人気かどうかというよりは、個人的な愛着によって着色されているものとして捉えていると思われるからです。
このことについては、私は次のように考えました。私たちが生まれてから間もない子供のころ、身の回りにあるのは、ほとんどがポピュラーだったりチープだったりする美的アイテムです。小学生低学年の頃から、フランシス・ベーコンの絵画を愛好したり、『ユリシーズ』を愛読書としたりするような子どもはいないわけです(よっぽど意識の高い家庭に育ったらそうではないかもしれませんが)。ですから、そうしたアイテムに個人的な経験と重ねたり、個人的な思い入れを抱いたりして、それによって美的ノーミー的な傾向性が形成されるというのは、自然なことのように思えます。
ですがもちろん、私たちは成長するにつれて、様々な美的アイテムに触れていくことになります。ラウの論を引き合いに出すならば、その過程において、私たちは挑戦的な姿勢をもって、美的にオープンな態度をとるべき、という話なのかもしれません。
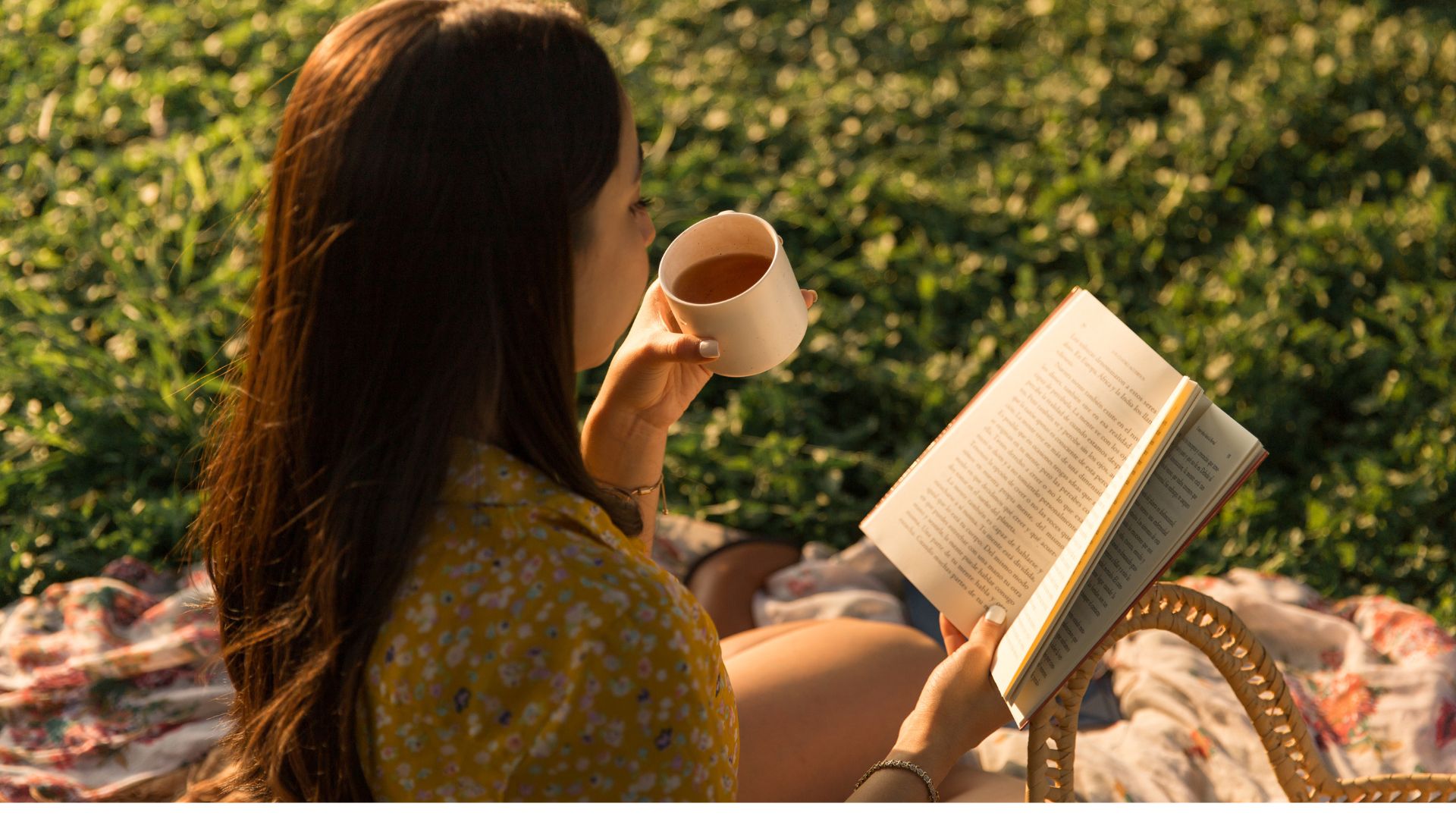
さて、統制的自己がスノッブやノーミーを飼い慣らす方法についてですが、私は、パトリッジの文脈型スノッブに着目します。パトリッジは「文脈型スノッブは、社会的文脈を読み解く失敗として現れる」と述べていましたが、裏を返せば、美的態度や美的判断にはそれにふさわしい文脈があるということです。バーベキューパーティーではバドワイザー(これは明らかにノーミー的アイテムの代表的なものであると思われます)をほめるべきだし、仲の良い友達といく大衆映画はわかりきったプロットにハラハラしながら楽しく鑑賞するべきなのです。
スノッブ的自己やノーミー的自己やエリート的自己を飼い慣らす、統制的自己が正しく機能するためには、それに使われるための文脈に対する感性的な判断力を養うことが必要なのではないでしょうか。そして、そのような文脈に合わせて美的態度をとることは、社会的観点に基づく合理的判断であるかもしれませんが、私としては美的判断でもあるのではないかと思います。文脈を読み取り、その文脈にふさわしい態度を選択するのは感性的な判断であるように思われるからです。そうであるならば、スノッブ的自己やノーミー的自己やエリート的自己を飼い慣らす、統制的自己が正しく機能するためには、それに使われるための感性的な判断力を養うことが必要なのです。
参考文献
- Lau, Ting Cho. 2024. “Aesthetic Normies and Aesthetic Communities.” Journal of Aesthetics and Art Criticism 82, 407–417. DOI: https://doi.org/10.1093/jaac/kpae014
- Patridge, Stephanie. 2023. “Aesthetic Snobbery.” Philosophy Compass, e12940. DOI: https://doi.org/10.1111/phc3.12940
- Riggle, Nick. 2022. “Aesthetic Lives: Individuality, Freedom, and Community.” In Aesthetic Life and Why it Matters, edited by Nick Riggle, Dominic Lopes and Nanay Bence, 32–60. Oxford University Press.
美学者とは
美学者の役割
- 【美的判断】なぜある人が「美しい」と感じる対象を、別の人は「そうでもない」と思うのか
- 【芸術作品の価値】作品が私たちの感性に与える影響を、どう評価し、言葉で説明できるか
- 【日常の美】ファッションやインテリアなど身近なところに潜む「美しさ」をどのように考えるか
こうした問いに取り組むのが美学者の役割です。近年では、ゲームの体験やデザイン、スポーツや身体表現、さらにはSNSなど、従来は「美学」とはあまり結びつかなかった分野にまでその探究範囲が広がっています。哲学や芸術学と深く関係しながら、現代社会のあらゆる「感性の問題」に光を当てるのが、美学者と呼ばれる人々なのです。

【PROFILE】
北海道帯広市出身。早稲田大学文学研究科博士後期課程在籍。専門は、ゲーム研究、美学。主な論文に、「個人的なものとしてのゲームのプレイ: 卓越的プレイ、プレイスタイル、自己実現としての遊び」『REPLAYING JAPAN 6』、「ゲームにおける自由について──行為の創造者としてのプレイヤー──」『早稲田大学大学院 文学研究科紀要 第68輯』。ゲームとファッションとタコライスが好き。