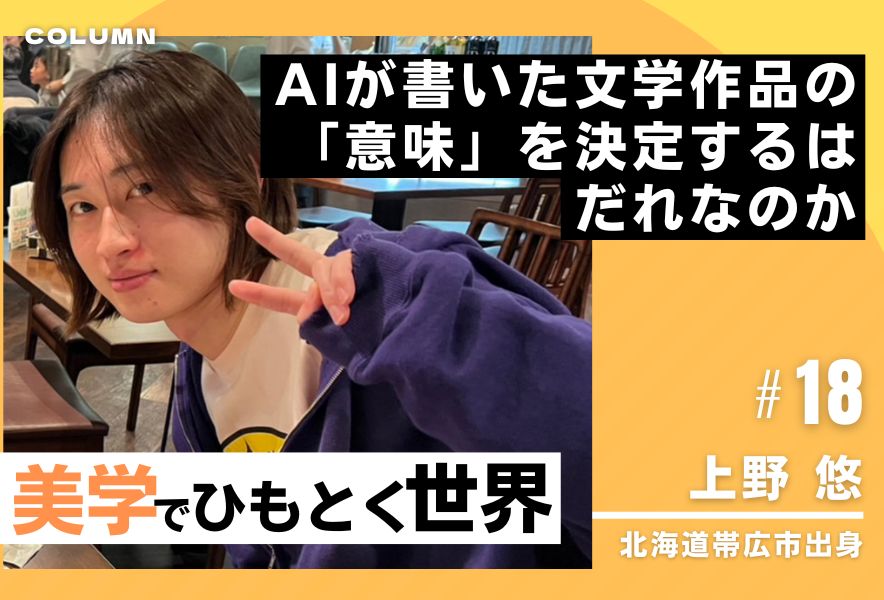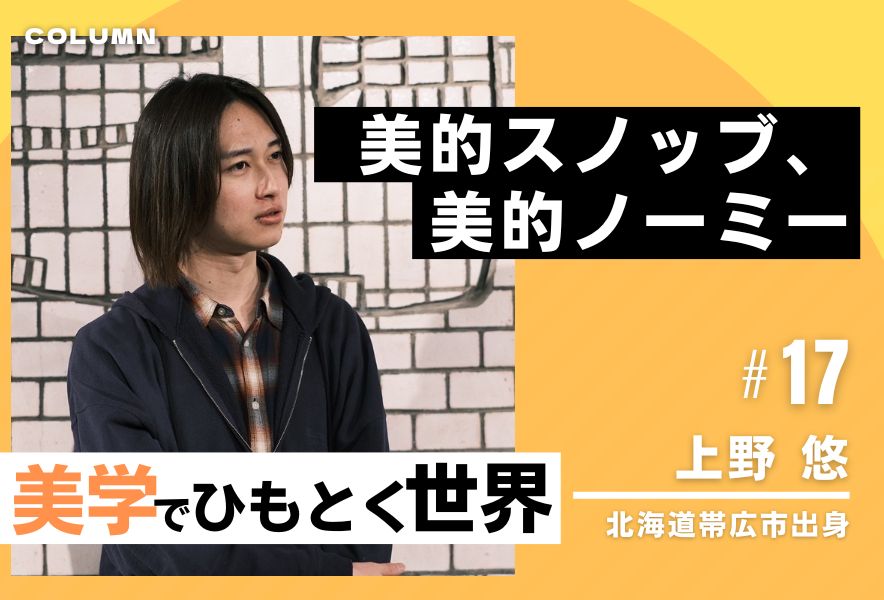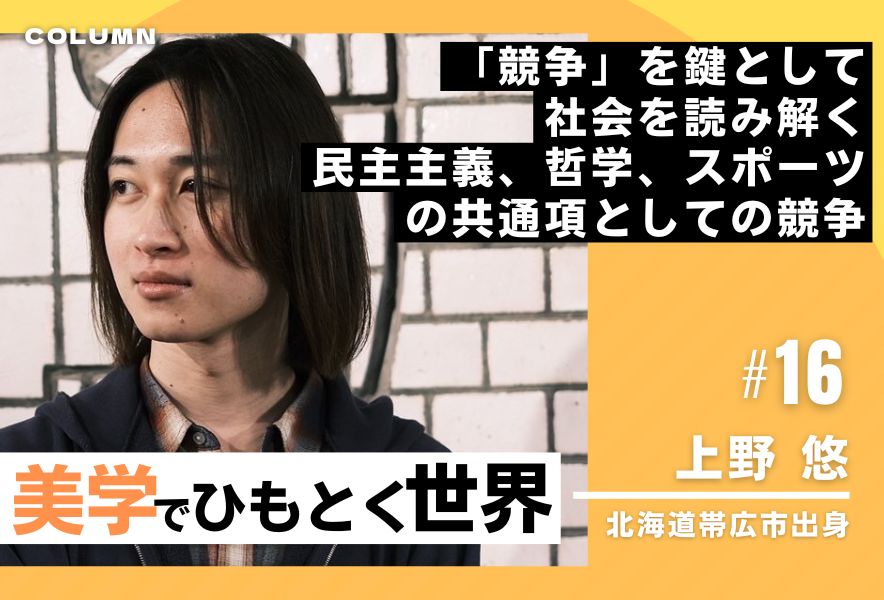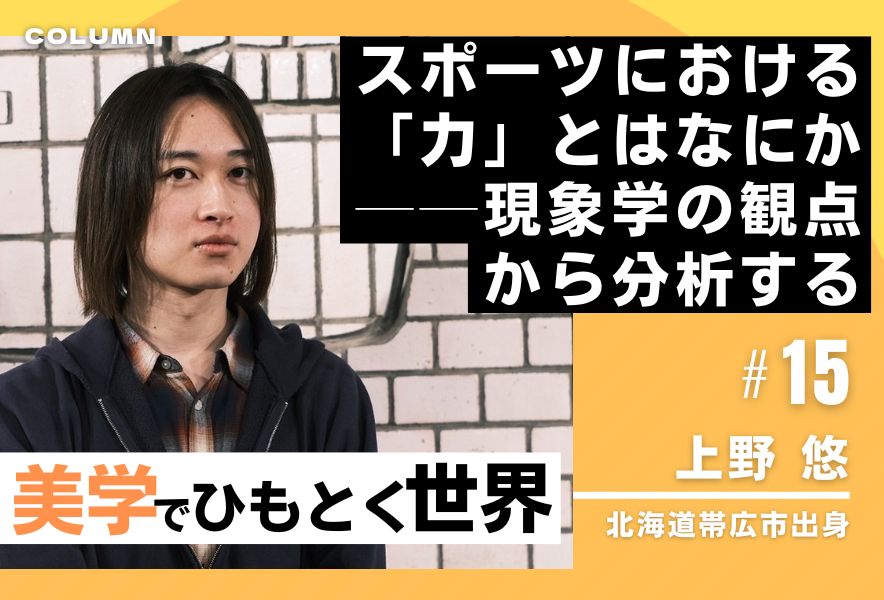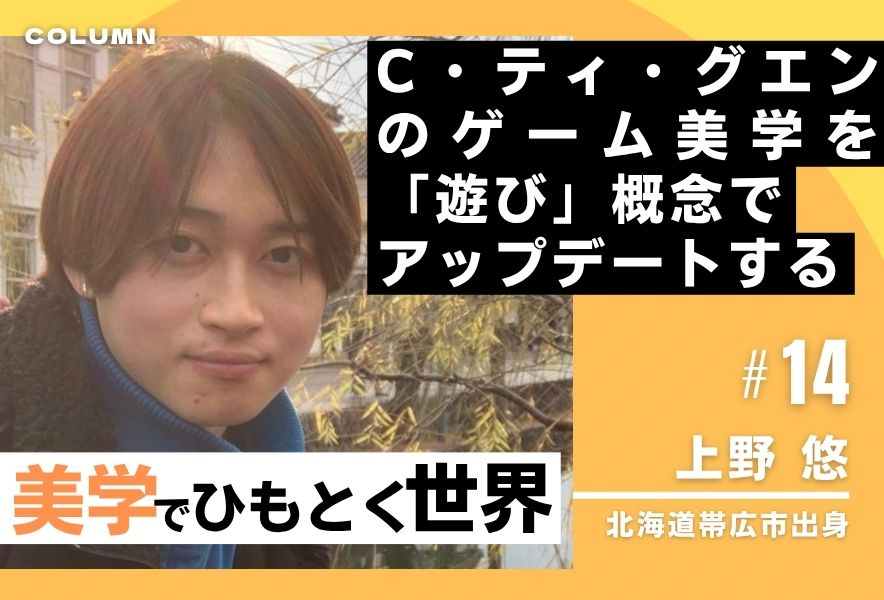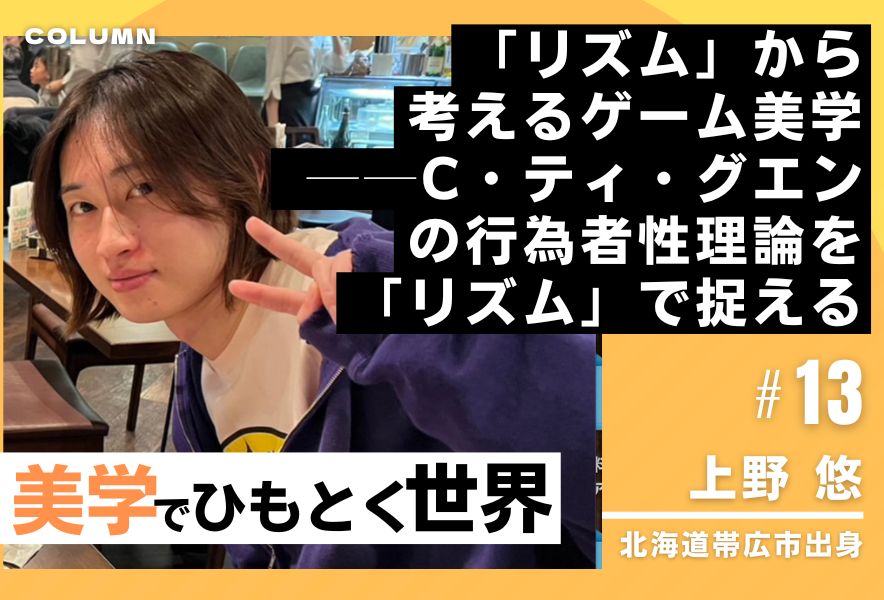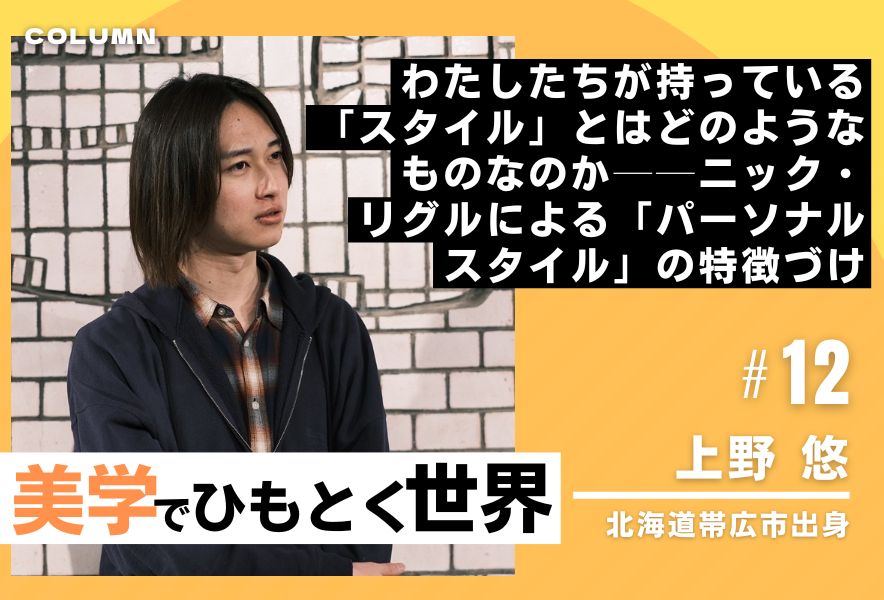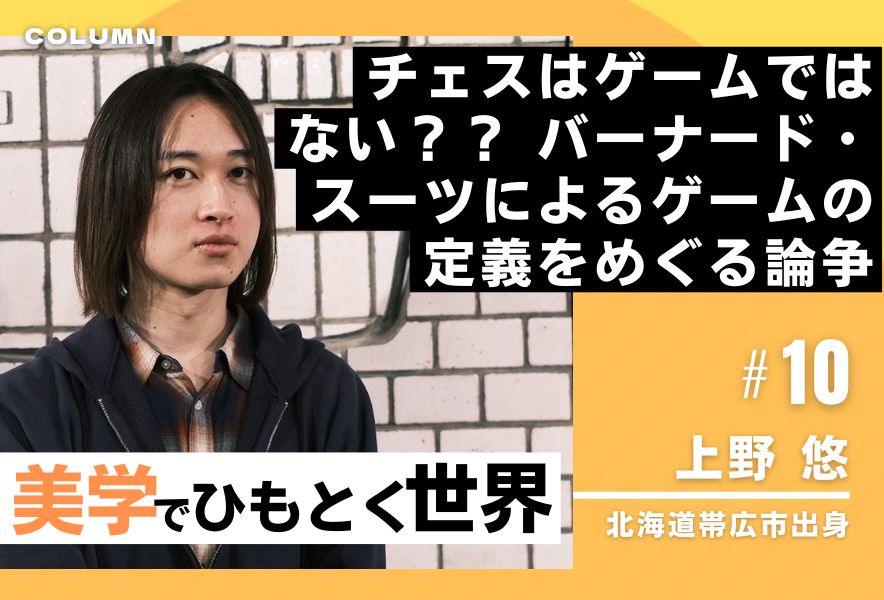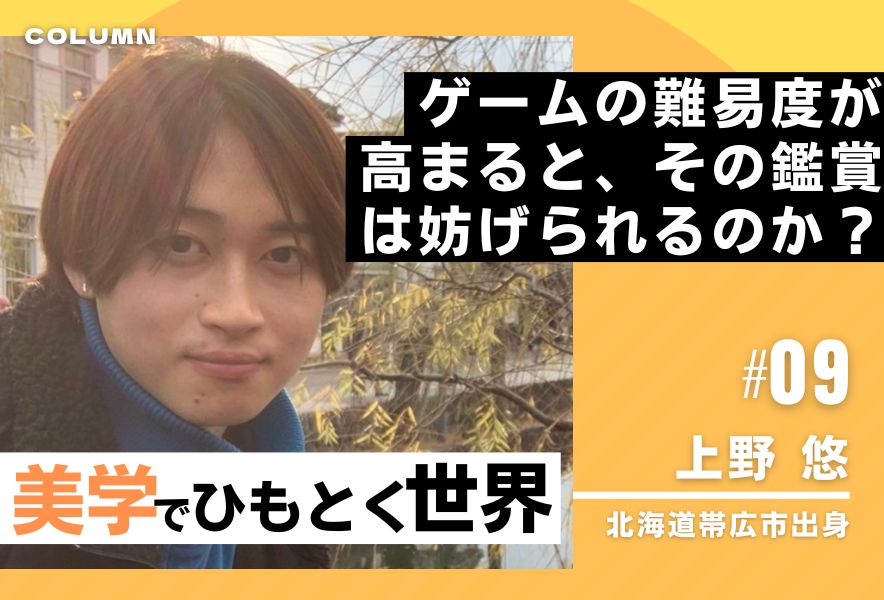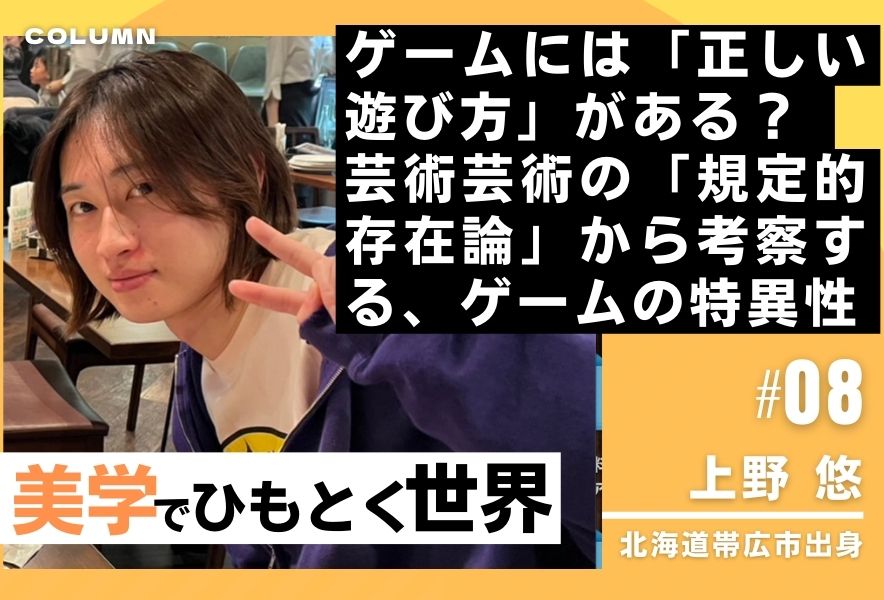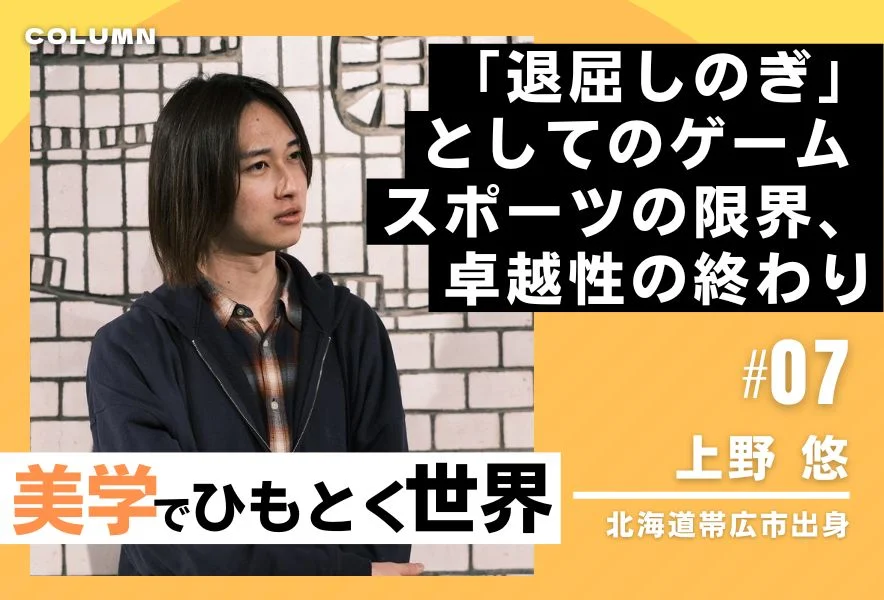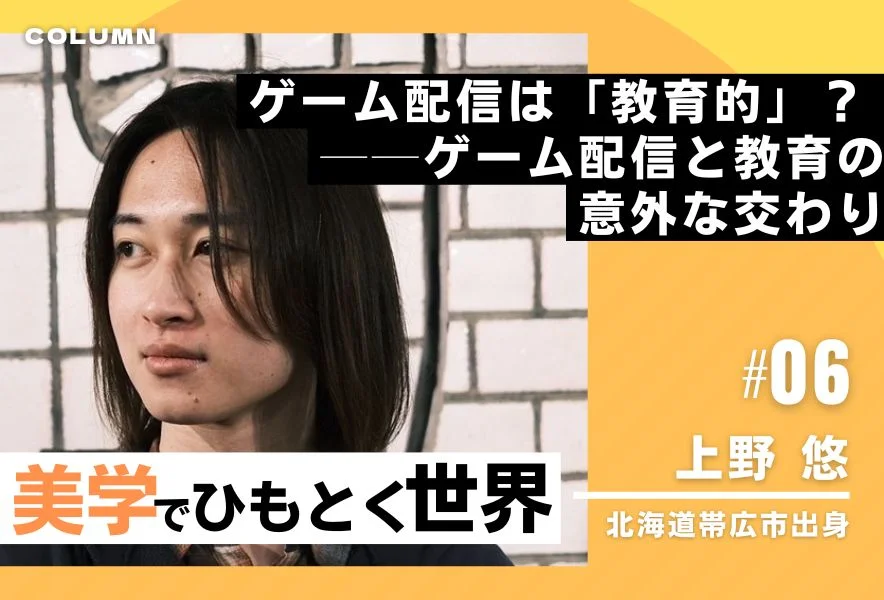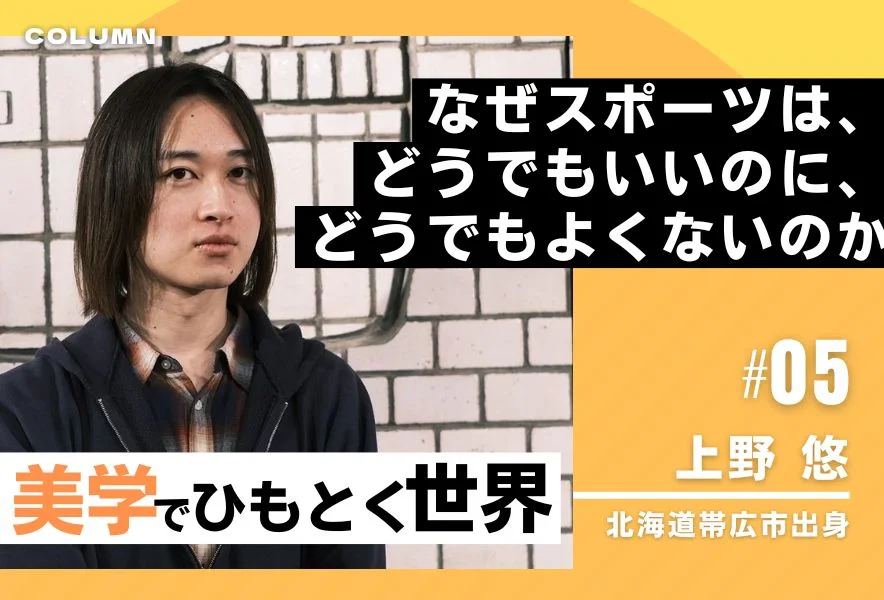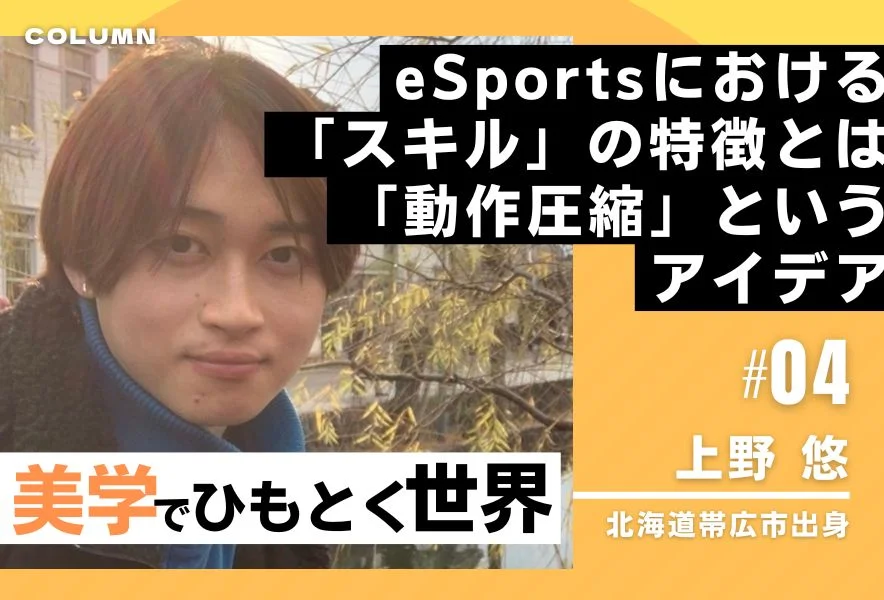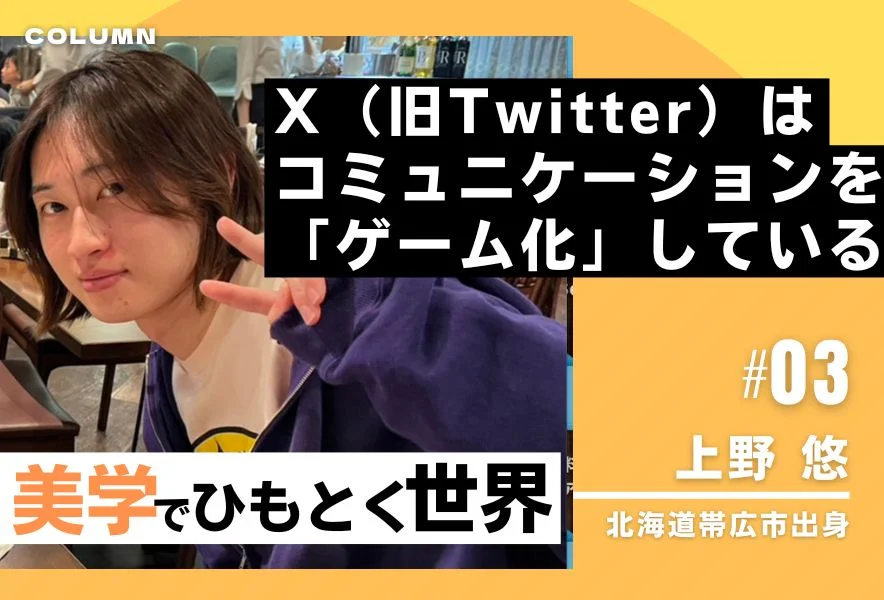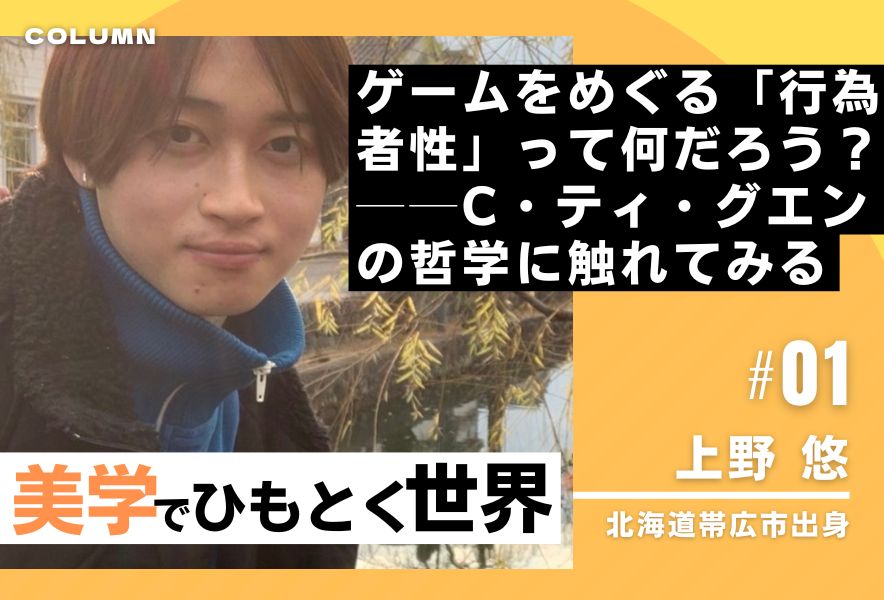【連載】美学者 上野悠の「美学でひもとく世界」
AIが書いた小説

昨今の生成AIの台頭は、私たちの生活に大きな変化をもたらしています。特に、AIがイラストや小説、音楽といった芸術作品を制作してしまうことは、驚きや、新鮮さを持って受け入れられると同時に、AIが制作した作品に違和感を示す人や、そういった流れがもたらしうる変化は歓迎できないものなのではないかと警戒している人も少なからず見受けられます。
AI作品の登場は、美学にとっても無関係なものではありません。芸術や美的なものをとりまく環境の変化を素早く反映する傾向のある美学の分野では、AIが生成する芸術作品に関係する議論もさっそくなされているのです。
今回は、そうしたもののうちのひとつとして、AIが書いた文学作品の「文学的意味」はどのように決定されるのかについての分析を行った研究を紹介します。
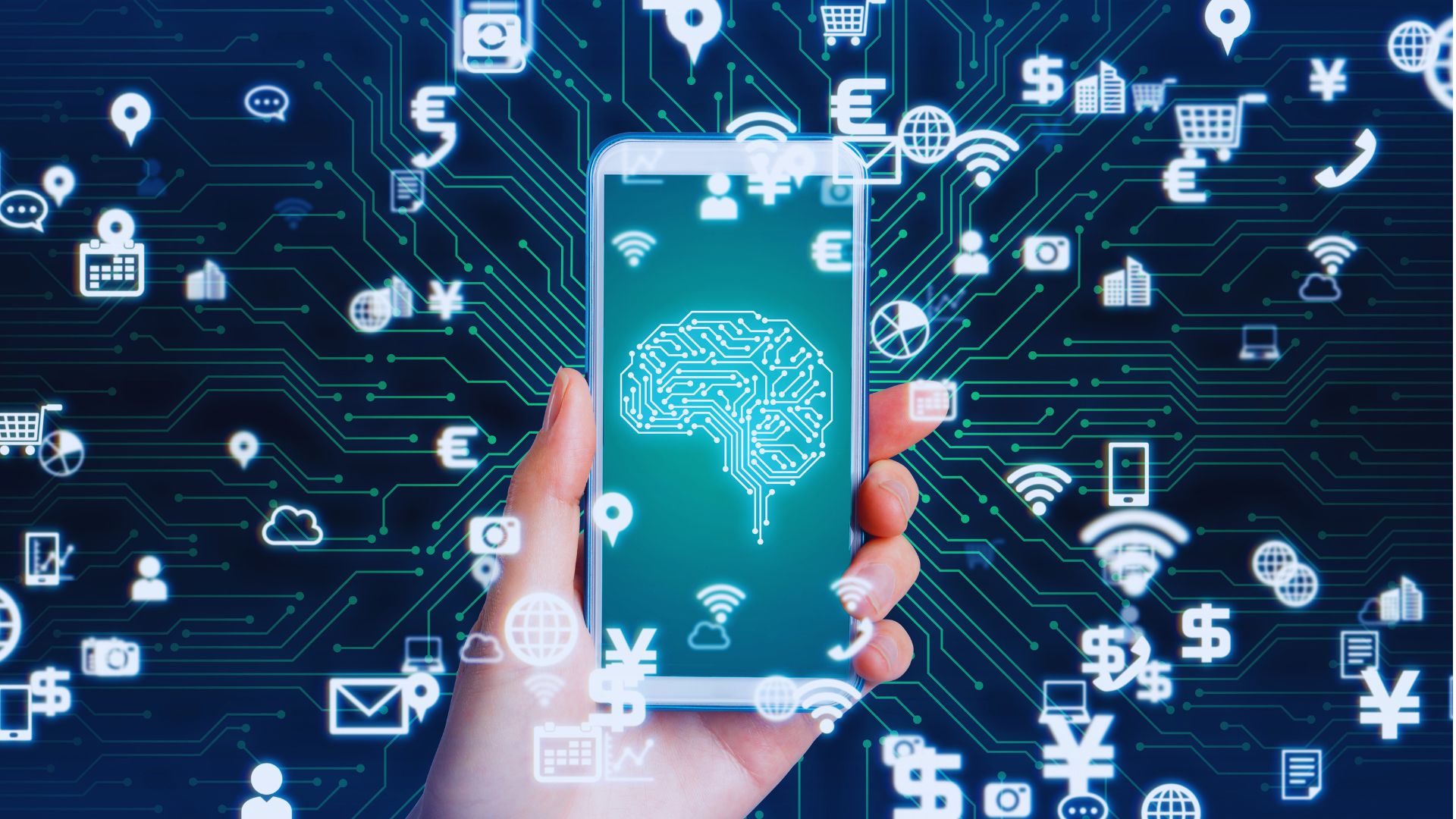
クイーンズ大学で、主にAIの哲学や、芸術の哲学を対象にした研究をしているPh.D候補生のソフィー・ヴラドはAI 生成の文学作品に「意味」があると考える場合、その意味を決定する主体を特定するためにどのような立場がよりよいのかについて、6つの立場を挙げ、比較しながら検討しています。
ヴラドが挙げるのは、
控えめな現実意図主義(Modest Actual Intentionalism)の1つ目のバージョンと2つ目のバージョン
慣習主義(Conventionalism)
実際の作者についての仮説的意図主義(Actual Author Hypothetical Intentionalism)
そして仮定作者についての仮説的意図主義(Postulated Author Hypothetical Intentionalism)
といった6つの立場です。
ヴラドは、AI 生成テキストのケースにおいて意味を付与する方法を判断する上で、慣習説と仮説的作者についての仮説的意図主義のみが有望な可能性を示しているとし、さらに後者が両者のうちより強い立場であると論じています。

ヴラドは、それに伴って
人工的テキスト(artificial text)
伝統的テキスト(traditional text)
の三区分を提示し、人工的テキストの一部は固定された意味を持つと主張します。その次に、テキストの意味が固定される仕組みに関する 6 つの主要な見解を概観し、そのうち、慣習主義(conventionalism)と仮定作者による仮説的意図主義(PAHI)の 2 つの見解のみが、この問題の解決に可能性を示し、最終的に慣習主義に反対し、PAHI を支持する理由を説明します。
では、順を追ってみていきましょう。
LLM(大規模言語モデル)
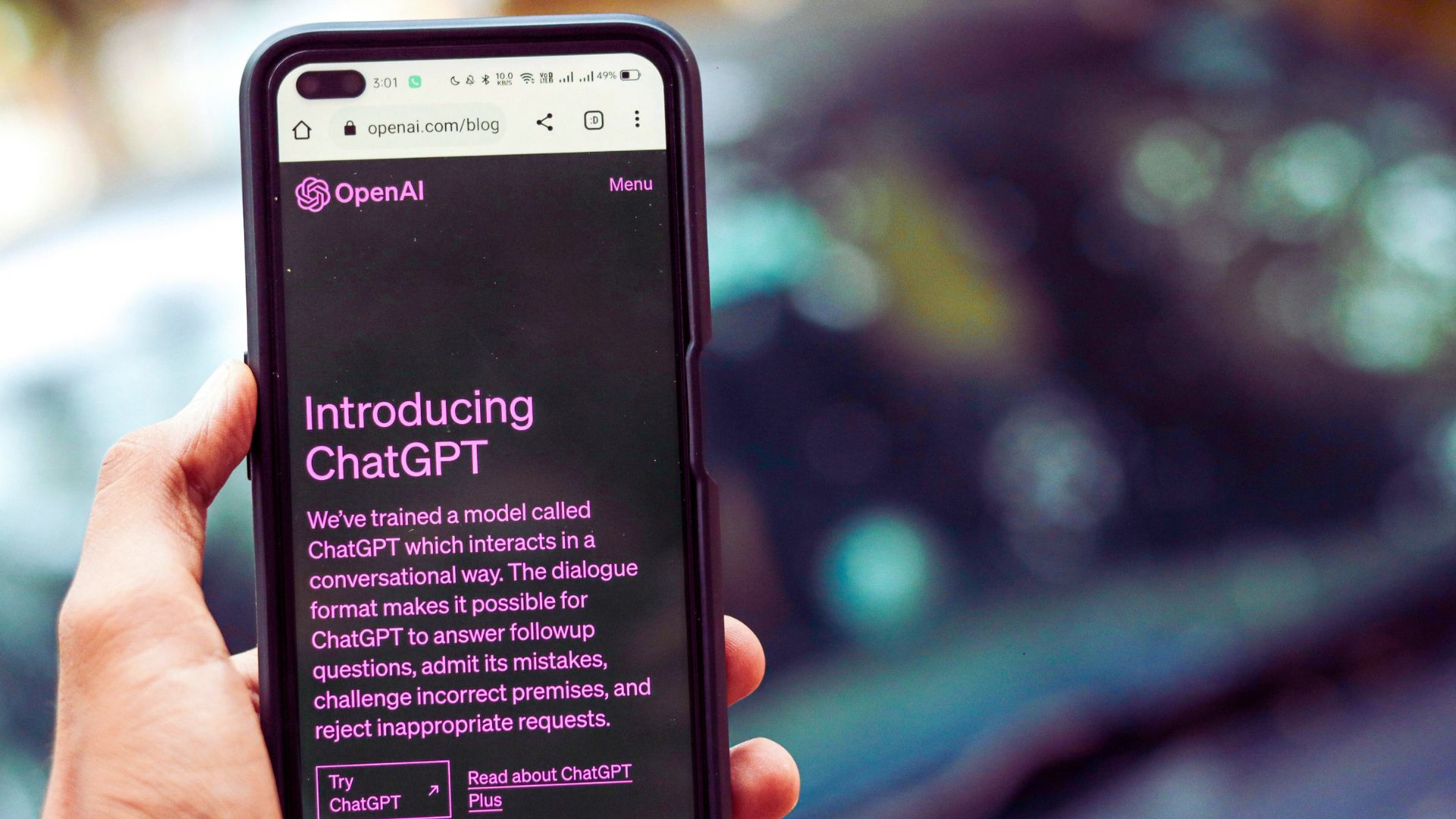
昨今話題になっている「LLM」とは、ユーザーが入力するプロンプトに基づいてテキスト出力を生成する生成型AIの一種です。LLMは、インターネットから収集したテキストのデータセット、書籍からのテキストなど、大規模なデータセットを学習材料にして訓練されます。
詳細な仕組みの説明は省きますが、LLMは、例えば「エドガー・アラン・ポーのスタイルで、騎士がドラゴンを倒す物語を書いてください」というプロンプトでも上手く機能します。これは、このモデルがポーの語彙や文法だけでなく、騎士がドラゴンを倒すファンタジー物語の定番要素なども認識できるからです。
しかしながら、 LLMは主にパターン認識によって機能するため、生成するテキストに対して意図的な態度を持っているわけではないのです。したがって、テキストに意図的に込められた意味の創造者としての「著者」という地位を適切に付与することはできないと考えられるのです。
ヴラドは、この段階で、2 つの可能性が考えられると述べます。最初の選択肢は、このような出力を「テキスト」として認めず、作者も文学的意味も持たないと否定することです。2 つ目の選択肢は、出力をテキストとして認めるものの、固定された文学的意味を持たないと否定することです。ヴラドは、そうした想定される意見に対し、反論を展開し、 AI 生成作品がテキストであり、そのようなテキストには固定された意味があるという立場を支持しようとします。

錯覚的テキスト、人工的テキスト、伝統的テキスト
AI 生成作品に意味を帰属させる問題の解決策の一つは、そのような作品が「文学的テキスト」である可能性を否定することです。しかし、ヴラドは、文学研究者の間で批評の対象として──あるいは、伝統的な文学の理解に挑戦するものとして──取り上げられてきたようなAI生成作品の例を挙げ、こうした立場は採用すべきでないと主張します。そういうわけで、AI作品が「文学的テキスト」であることが認められうるような立場が必要となってくるのです。
しかし、テキストには意図的な要素が含まれていなければならない、とするような立場の人たちを説得するためには、テキストは意図的な主体によって生み出されたものでなければなりません。ヴラドは、そうしたオーソドックスな文学的テキストの例として、シェイクスピアの『リア王』を例に挙げますが、次のような、場合を想定するよう促します。
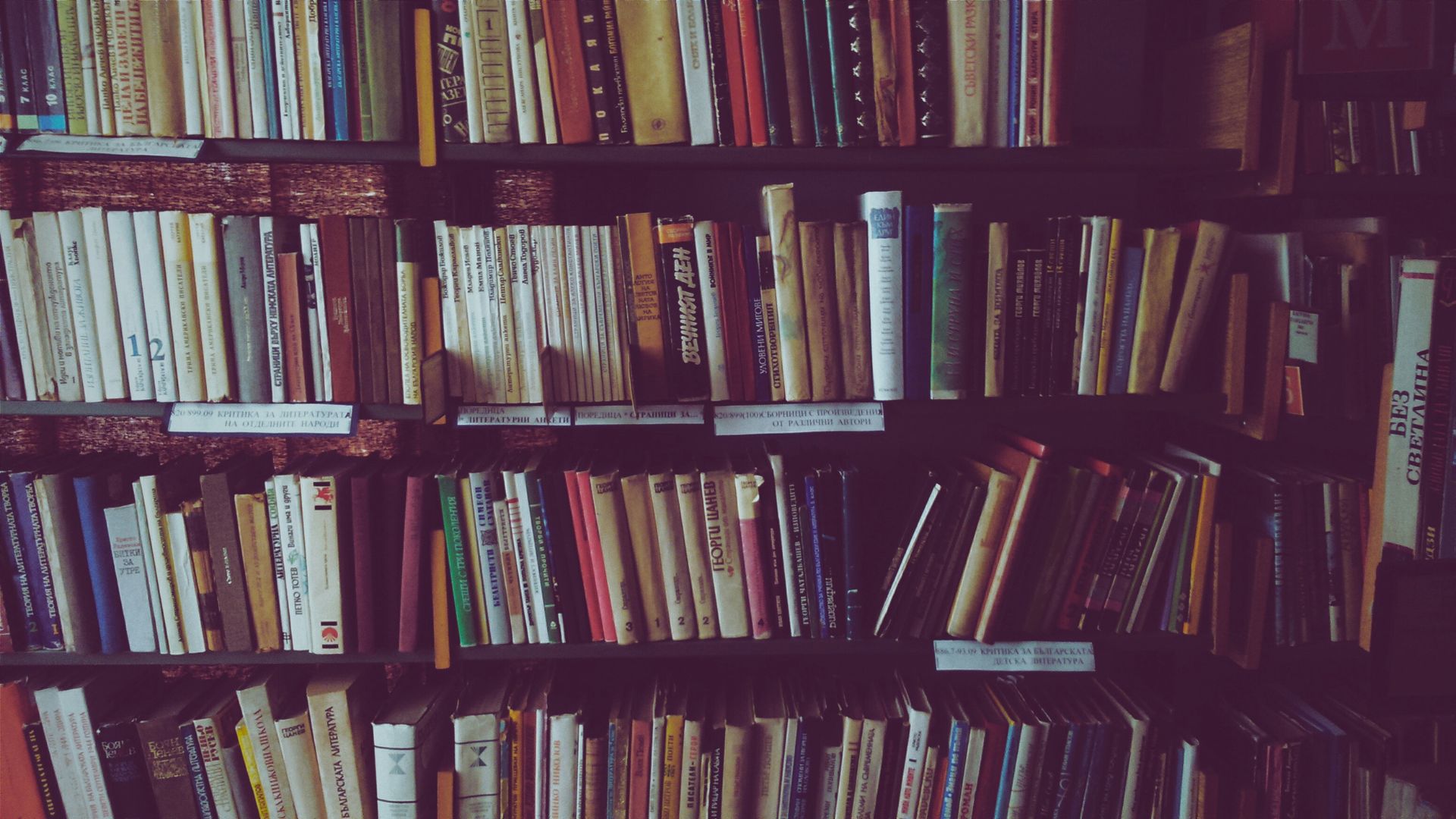
もし、風によってランダムに配置された岩の群れがシェイクスピアの詩の一節を形作ったとしても、それは文学的テキストではありません。しかし、アーティストがその岩の群れの写真を撮影し、例えば、『シェイクスピアの岩』とラベルを付け、アート界に提示した場合、それが観客や批評家によって受け止められれば、その作品はテキストとしての地位を持つ可能性があるのです。
こうした例を挙げ、ヴラドは次のように整理します。まず、『リア王』は「伝統的テキスト」となります。それは意図的な主体——つまり作者——が作品を創造しようと決めた結果なのです。一方で、岩の群れは「錯覚的テキスト」です。つまり、テキストのような「見かけ」を持つものの、テキストそのものではありません。すると、『シェイクスピアの岩』はそれらの間にある、中間的な位置を占めているように見えます。
『シェイクスピアの岩』は、意図的な主体によって作成されたものではありませんが、その文学作品としての地位は意図的な主体に依存しているのです。ヴラドは、AI 生成作品もこれと同じであると言います。それらもまた、意図的な主体によって作成されたとは言えませんが、その作成はキュレーターの主体性に依存しているのです。この意味でヴラドは、『シェイクスピアの岩』のような作品を「人工的テキスト」——作者を持たないテキスト——として定めます。

「文学的意味」と人工的テキスト
ヴラドは、『シェイクスピエアの岩』のような、一部の人工的テキストに、固定された意味があるかどうかを考察しようとしますが、その前に、まず「文学的意味」を他の「意味」から区別します。
「文学的意味」は、文学作品というものがその部分の総和を超える意味を持つという点で、「語義的意味」と区別されます。これをヴラドは、ジョージ・オーウェルの『動物農場』という小説を例に挙げて説明します。この小説の「文字通り」の読み方は、農場の動物についての物語なのですが、この作品を文学的に読むならば、これは明らかに政治的闘争についての寓話的な作品であるがわかります。前者のような「意味」が語義的意味であり、後者のような「意味」を文学的意味としてそこから区別するのです。

さて、こうした文学的意味については、ヴラド(が依拠するStein Haugom Olsen)の整理によると、テキストの意味はテキストに内在すると主張する自律性理論(autonomy theories)、テキストの意味は記号とシステムの間にある関係を解釈することを通じて決定されると主張する記号論的理論(semiotic theories)、テキストの意味は、テキストの作者の意図によって付与されると主張する意図主義的理論(intentionalist theories)といった三種類の理論に大まかに分けられるとしています。
しかし、文学的意味に関して、ロラン・バルトをはじめとした、テキストには固定された意味がないと主張する派閥も存在します。こうした主張は、過激に解釈するならば、読者ごとに異なる意味が存在するということになります。つまり、テキストは意味を一切持たず、読者による解釈のみが存在するのです。
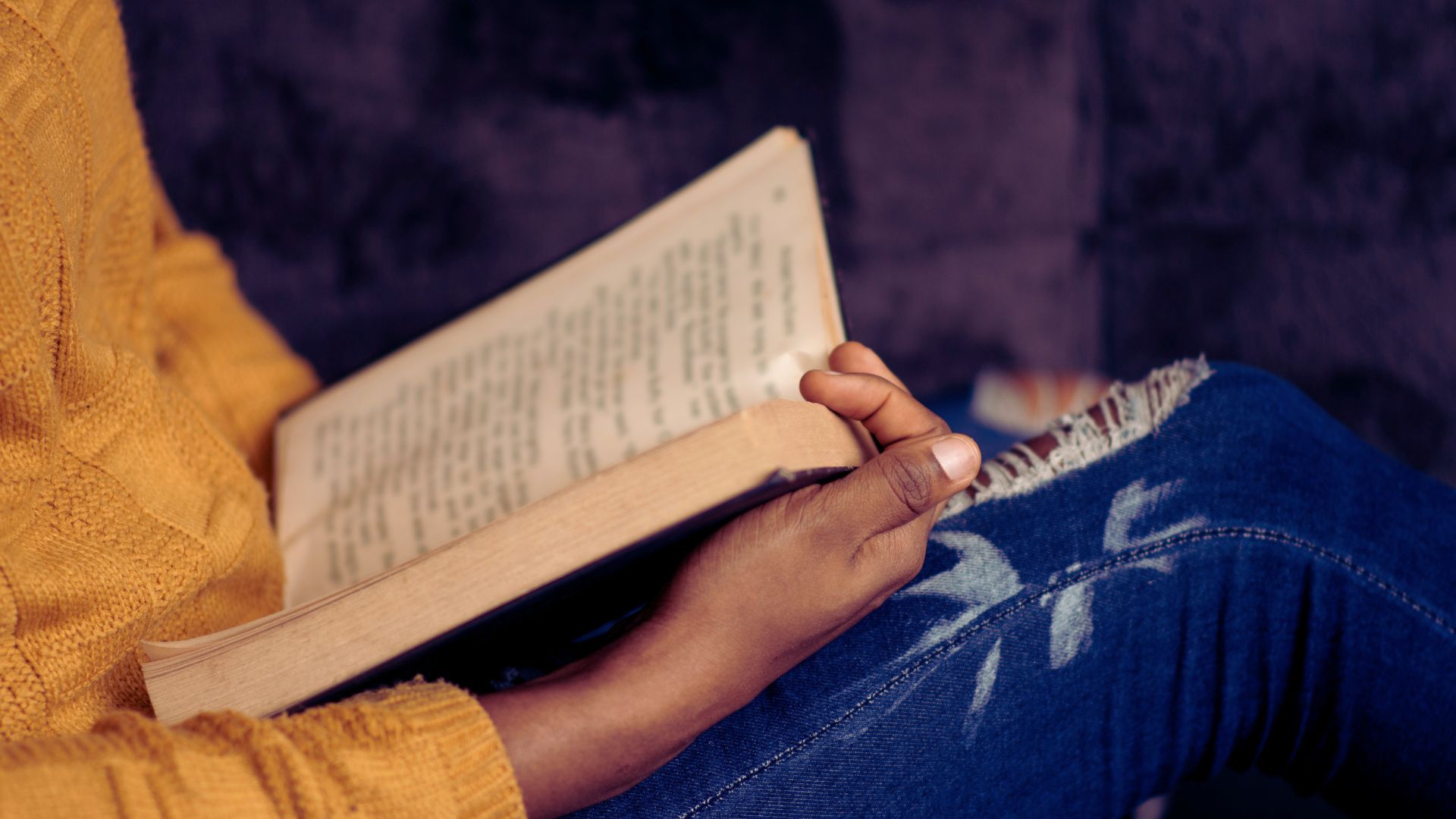
ヴラドは、こうした過激な主張には問題があると述べます。それは、テキストの意味について誤る可能性を認めないという点です。ヴラドは、あるテキストについてのある解釈は、そのほかの解釈よりも正しい場合があると指摘し、例として『動物農場』を 2016 年の米国大統領選挙の寓話と解釈することは誤りであると考えられることを挙げます。なぜなら、『動物農場』の執筆と出版は2016年よりはるかに前であるからです。解釈のみが存在するのだとしたら、このこともほかの解釈と同じように正しいものとなってしまうのです。
そうではなく、ある種の人工的テキストが固定された意味を持つと仮定するならば、その意味を固定する主体は誰なのか、あるいは何であるのかという謎が浮上するのです。
文学的意味の帰属に関する6つの見解

ここから、ヴラドは、文学的テキストの意味が固定される仕組みに関する6つの主要な理論を挙げ、それらを検討します。それが、極端な現実意図主義(EAI)、 2つのバージョンの控えめな現実意図主義(MAI1 と MAI2)、慣習主義、実際の作者についての仮説的意図主義(AAHI)、および仮定作者についての仮説的意図主義(PAHI)の6つです。ヴラドは、それぞれを簡潔に説明した上で、EAI、MAI1、MAI2、AAHIを解決策として排除します。
まず、EAIとは、言語的慣習に関わらず、テキストの意味を固定するのは作者の意図であるという立場です。ヴラドの例を流用するならば、これは、著者が「リンゴは赤い」という文を「バナナは黄色い」という意味で意図した場合、その文脈では後者が前者の意味であるとすべきことを意味します。

これに対し、控えめな現実意図主義は、EAIの持つこの奇妙な特徴を、作者の意図と言語的慣習が一致する場合、意味を決定するのは著者の意図であると主張することで対処しようとしている立場です。MAI1 の支持者は、著者の意図が言語的慣習と異なる場合、テキストの該当部分は意味を成さないとしますが、これとは異なるMAI2 の支持者は、このような場合、意味は言語の慣習によって決定されるか、または、該当部分の意味は曖昧なままとなる、とするという違いがあります。これにより、MAI2 は、あるテキストが特に曖昧である場合には、慣習主義にくだる可能性がでてきます。
慣習主義は、テキストの意味を決定するのは言語の慣習であるとする立場です。ただし、それには文脈も考慮すべきだと主張する人もいます。慣習主義者は、テキストが曖昧である場合の対処法に関する意見については分かれていますが、いずれにせよ、作者の意図に委ねることはしないという立場です。
仮説的意図主義には 次のような2 つの形態があります。AAHI (実際の作者についての仮説的意図主義)は、ある作品の意味は、その作品についての情報に通じた鑑賞者が、実際の作者の意図について形成する最善の仮説によって決定されると主張します。一方で、PAHI(仮定作者についての仮説的意図主義)は、作品の「実際の」作者ではなく、「言語を完全に習得している」などといった特徴を持つ「理想的な」作者であるという点においてAAHIと異なります。AAHI はしばしば現実意図主義の一形態にくだってしまう一方で、PAHI は慣習主義にくだる危険性があります。
AI生成作品の場合

AI 生成作品の場合、作者に意味を委ねることは、意味を成さなくなってしまうとヴラドは指摘します。なぜなら、AI生成のような人工的テキストは「作者を持たないテキスト」だからです。この事実により、EAI、MAI1、MAI2、AAHI は、AI 生成テキストの謎を解決する意味帰属理論の候補から除外されます。なぜなら、これらすべての理論は、少なくとも一部のケースにおいて、意味が固定されるために作者の存在を必要としてしまうからです。
まず、EAI と AAHI の場合、意味を求める対象となる作者が存在しません。つづいて、MAI1 では、AI 生成テキストは意味のないものと見なされる必要があります(作者の意図がないので)。MAI2 においては、AI作品の持つテキストの意味は言語的慣習によって固定されることになります。つまり、AI作品の場合、MAI2は常に慣習主義に帰着することになるのです。
こうしてヴラドは、テキストの意味を付与する6つの競合する理論のうち4つを排除しましたが、慣習主義とPAHI は依然として残っていることになります。ここからヴラドは、慣習主義がパズルを解決する可能性があるにもかかわらず、それを拒否し、代わりにPAHIを採用すべきだと論じます。
人工的テキストの意味の固定

一見すると、観衆主義は AI 生成テキストの意味を帰属させるというパズルを適切に解決できるように思えます。言語的慣習だけが意味を固定するのだと主張することで、作者の不在という問題を回避するからです。
しかし、ヴラドは「メタテキスト的なレベルで発見される意味を説明できない点で問題が生じる」と指摘します。このことを説明するために、ヴラドは、スティーブン・マルチェによるDeath of an Authorという作品の例を挙げます。
スティーブン・マルチェのDeath of an Authorは、ChatGPT のようなAIモデルを、ほとんどすべてにおいて使用して書かれた探偵小説です。物語は、著名な小説家の殺害事件を調査する文学批評家を中心に進んでいきますが、LLMの企業やAIが絡んだ複雑な陰謀に巻き込まれ、批評家自身も殺人容疑者となってしまうというものです。この作品は、表面上は探偵小説ですが、より深いレベルでは、人間と AI の関係、特に文学の領域におけるその関係を探求しており、その意味では、この短編小説自体が自己言及性を持っており、作品の制作プロセスそのものが、比喩的に表現されているのです。Death of an Authorは、テキストの個々の部分を通じても解釈可能ですが、それによって、作品自体が意味に組み込まれているというメタテキスト的なポイントは失われてしまうのです。

ヴラドは、これまで、AI生成テキストの意味付与に関する2つの主要な問題を指摘してきました。最初の問題は、テキストが意味を獲得するために作者の存在を前提とするような、ほとんどの意図主義に関するするもので、AI の場合、意味を委ねるべき作者が存在しないという問題です。2 つ目の問題は、従来の意味帰属理論がメタテキスト的なレベルでの意味を説明できない点にあります。ヴラドは、PAHIがこれらの問題を効果的に解決する方法を示すと言います。
まず、作者性の問題です。PAHI にのっとると、テキストの意味を決定するのは実際の作者ではなく、「理想的な作者」がテキストに付与する意味に関する、鑑賞者の最も適切な仮説が意味を決定します。理想的な作者の存在を仮定する場合、鑑賞者が情報に基づいた仮説によって意味を決定するため、作者の不在という問題は、まず完全に回避されます。
次にヴラドは、理想的な作者の存在を仮定することで、従来の解釈論では説明できないメタテキスト的な意味を説明できると言います。PAHI における仮定された作者は、言語の習熟を含んだ、メタテキスト的な書き方の方法論を持っていることになります。したがって、PAHI はテキストの意味を個々の要素の総和として理解するのではなく、テキストを全体として捉えることで、メタテキスト的なレベルで意味を解き明かすことができるのです。

慣習主義とPAHIは、両者とも最初の問題(作者の不在)に対処できますが、PAHI のみが第二の問題(作者不在のテキストがメタテキスト的なレベルで固定された意味を持つこと)に対処できるのです。ヴラドは、この点から、PAHIはAI生成テキストの意味の固定化を説明できると認めるべきであると述べているのです。
参考文献
- Vlaad, Sofie. 2025. “Texts without authors: ascribing literary meaning in the case of AI.” In Journal of Aesthetics and Art Criticism 83 (1):4-11.
美学者とは
美学者の役割
- 【美的判断】なぜある人が「美しい」と感じる対象を、別の人は「そうでもない」と思うのか
- 【芸術作品の価値】作品が私たちの感性に与える影響を、どう評価し、言葉で説明できるか
- 【日常の美】ファッションやインテリアなど身近なところに潜む「美しさ」をどのように考えるか
こうした問いに取り組むのが美学者の役割です。近年では、ゲームの体験やデザイン、スポーツや身体表現、さらにはSNSなど、従来は「美学」とはあまり結びつかなかった分野にまでその探究範囲が広がっています。哲学や芸術学と深く関係しながら、現代社会のあらゆる「感性の問題」に光を当てるのが、美学者と呼ばれる人々なのです。

【PROFILE】
北海道帯広市出身。早稲田大学文学研究科博士後期課程在籍。専門は、ゲーム研究、美学。主な論文に、「個人的なものとしてのゲームのプレイ: 卓越的プレイ、プレイスタイル、自己実現としての遊び」『REPLAYING JAPAN 6』、「ゲームにおける自由について──行為の創造者としてのプレイヤー──」『早稲田大学大学院 文学研究科紀要 第68輯』。ゲームとファッションとタコライスが好き。