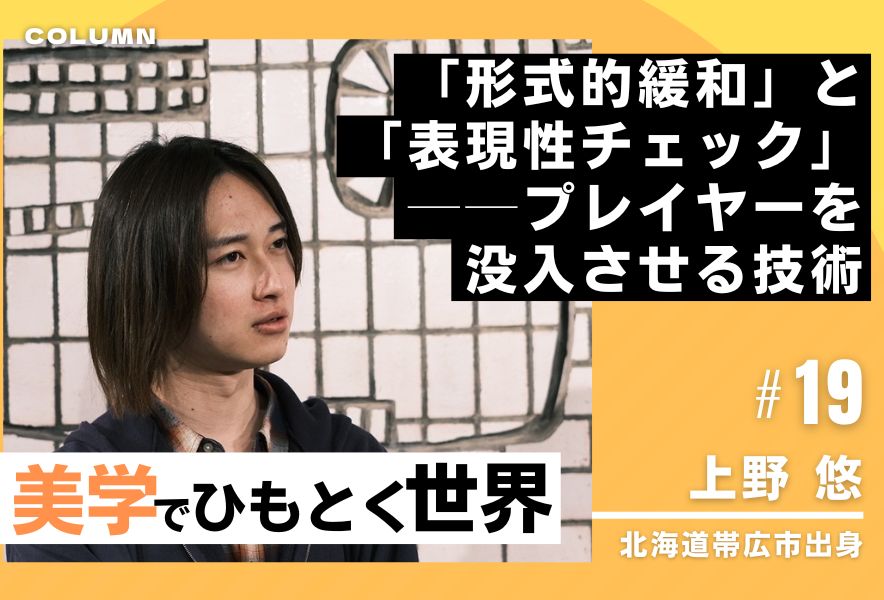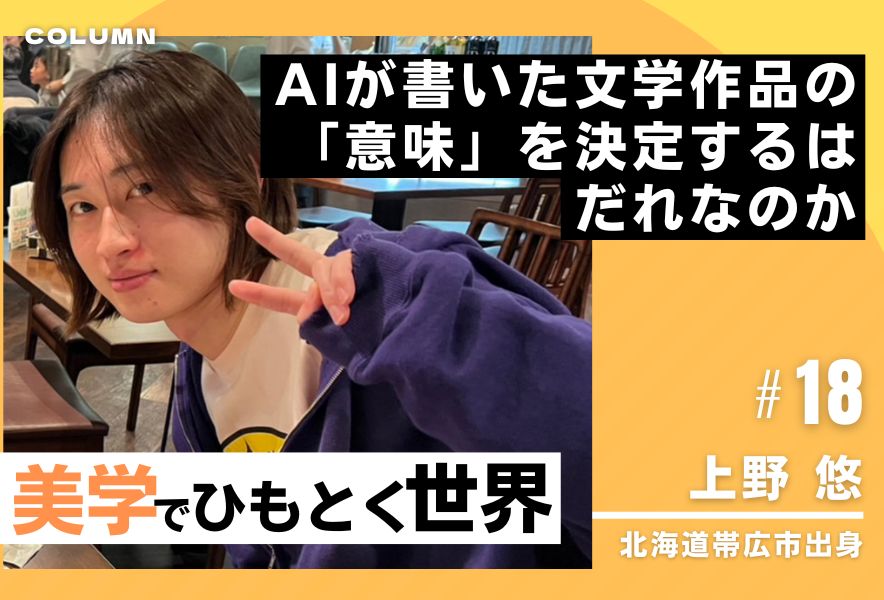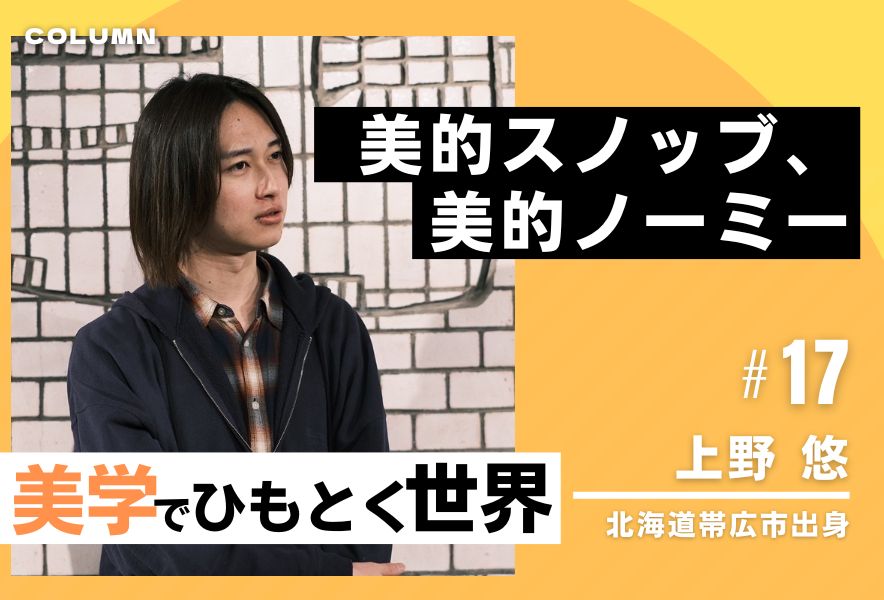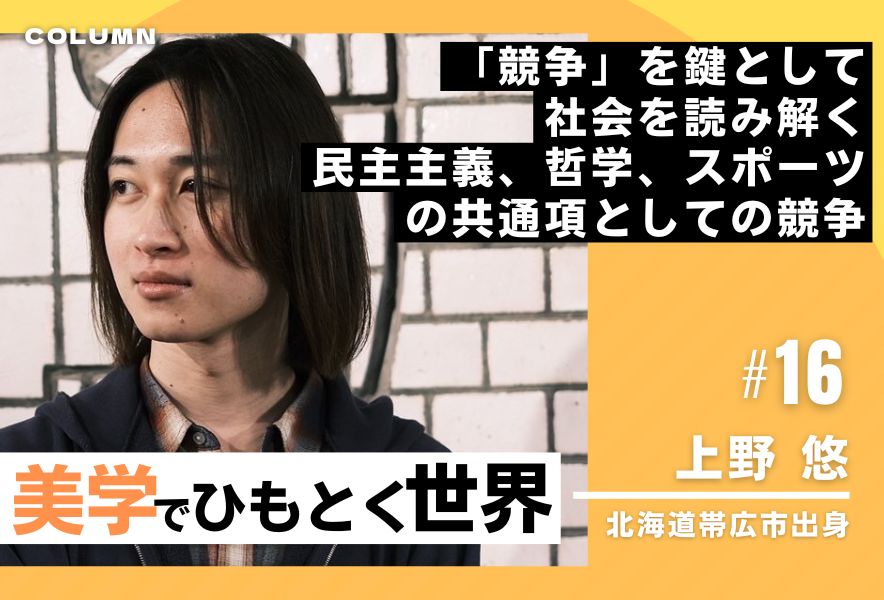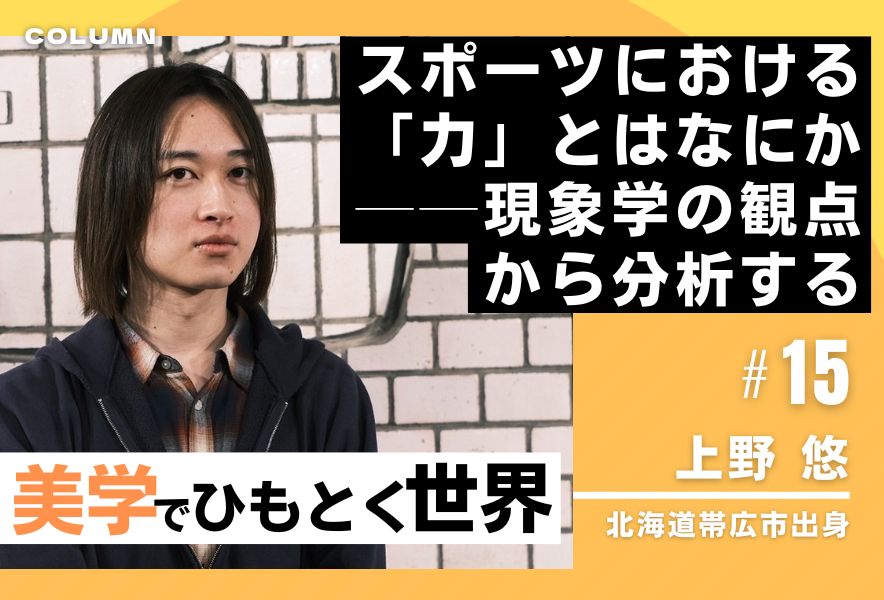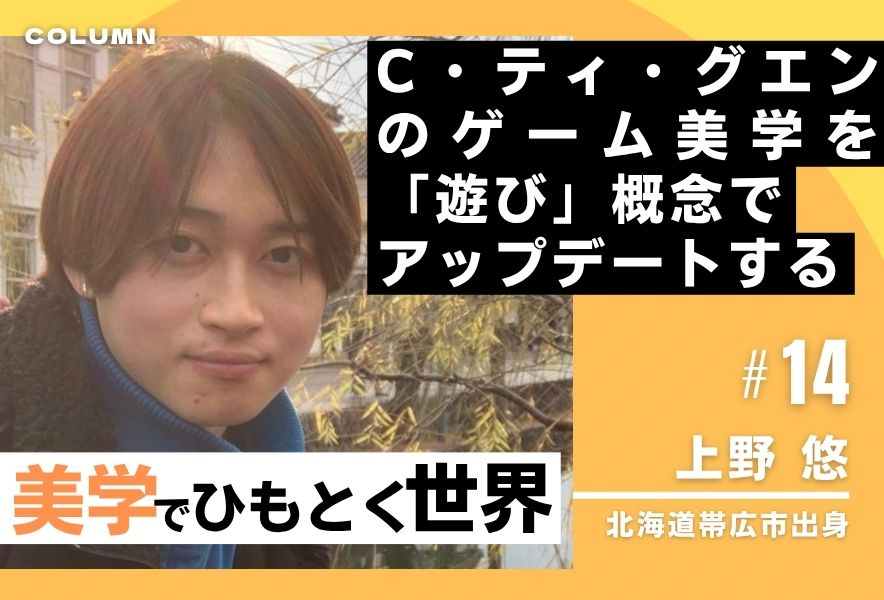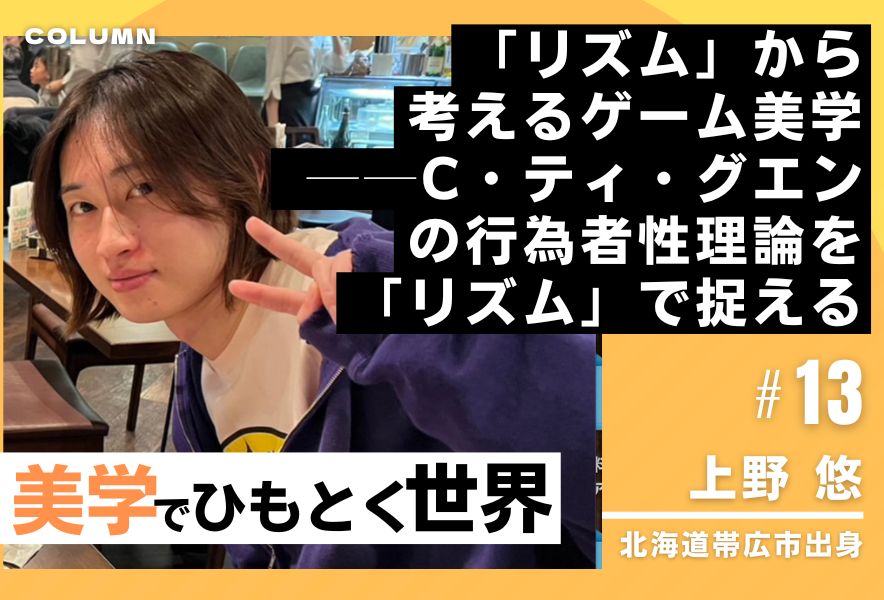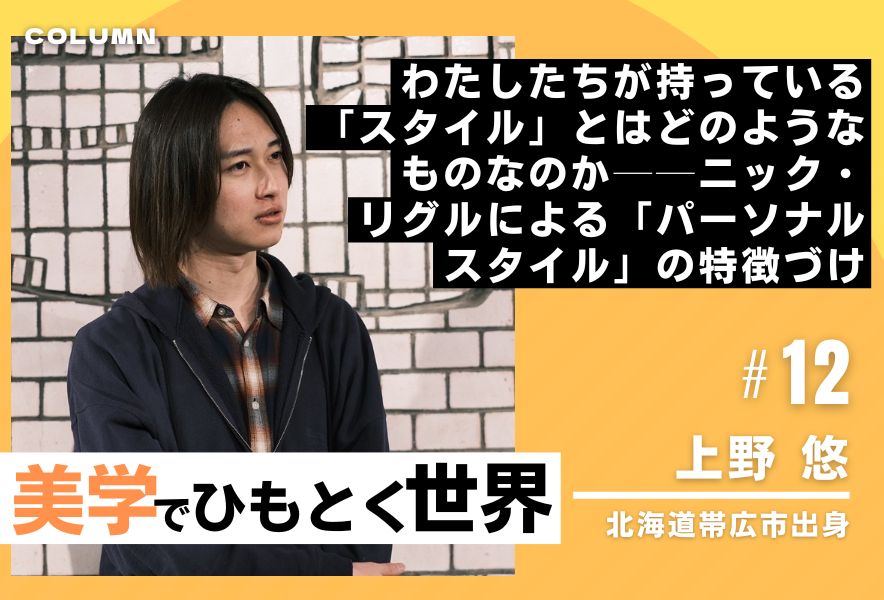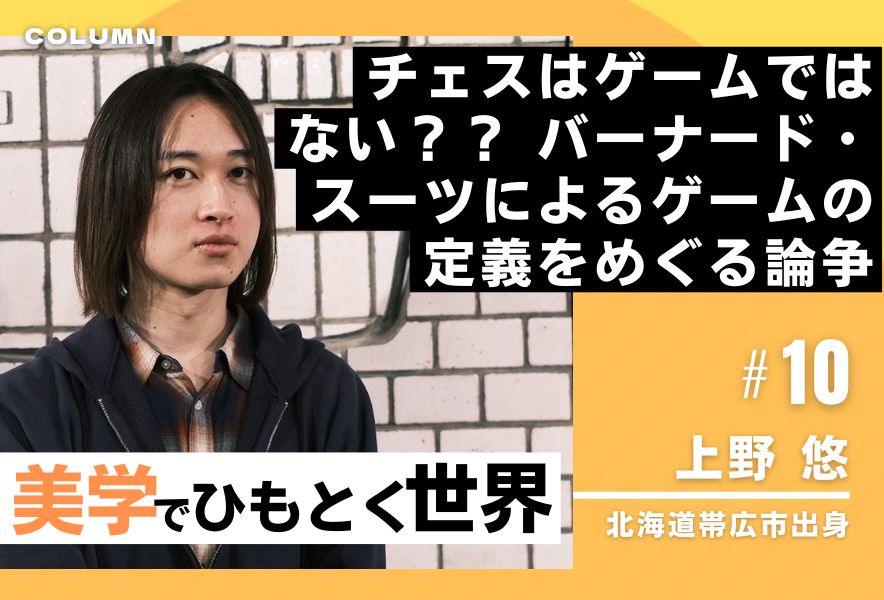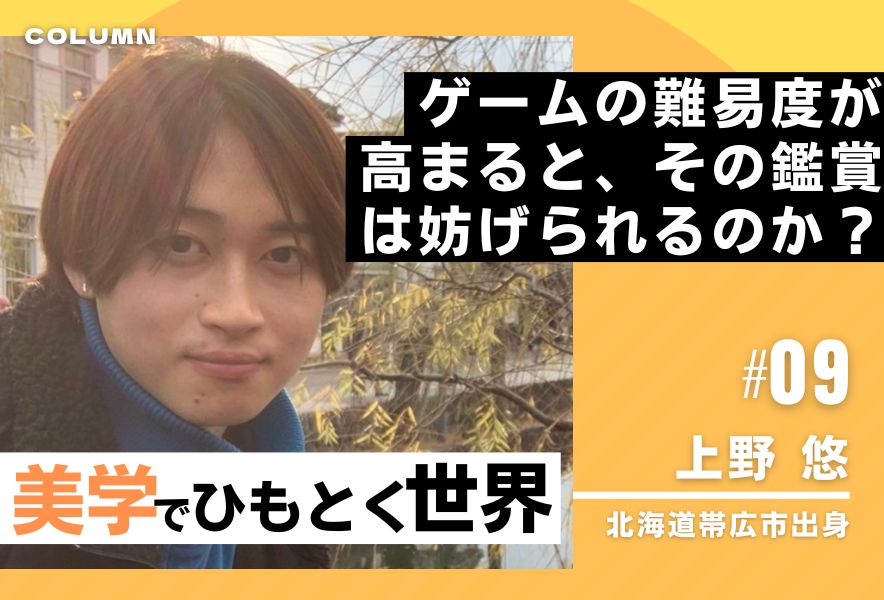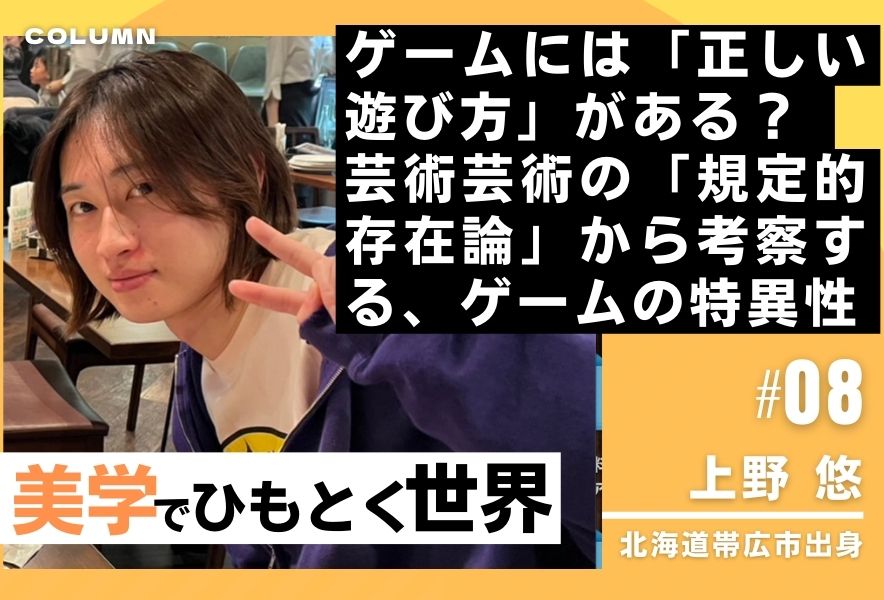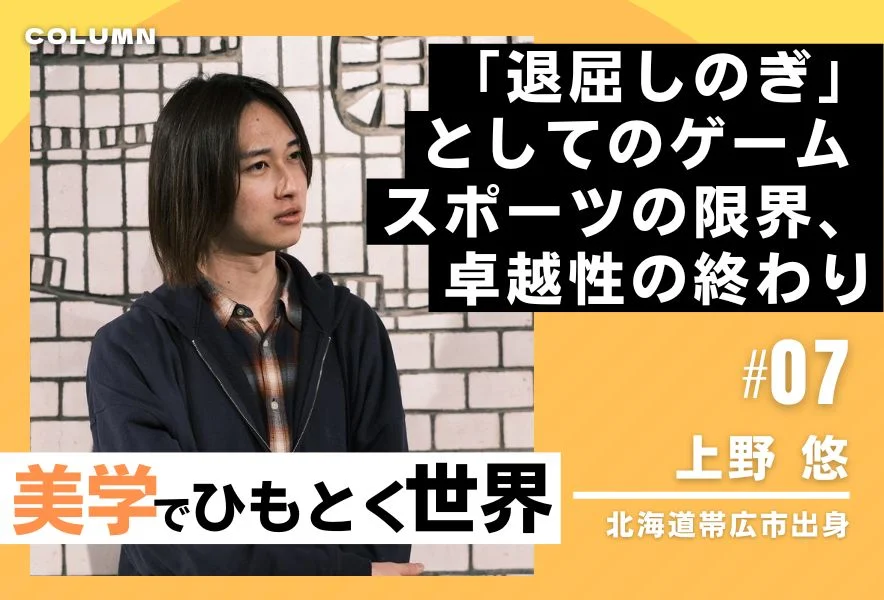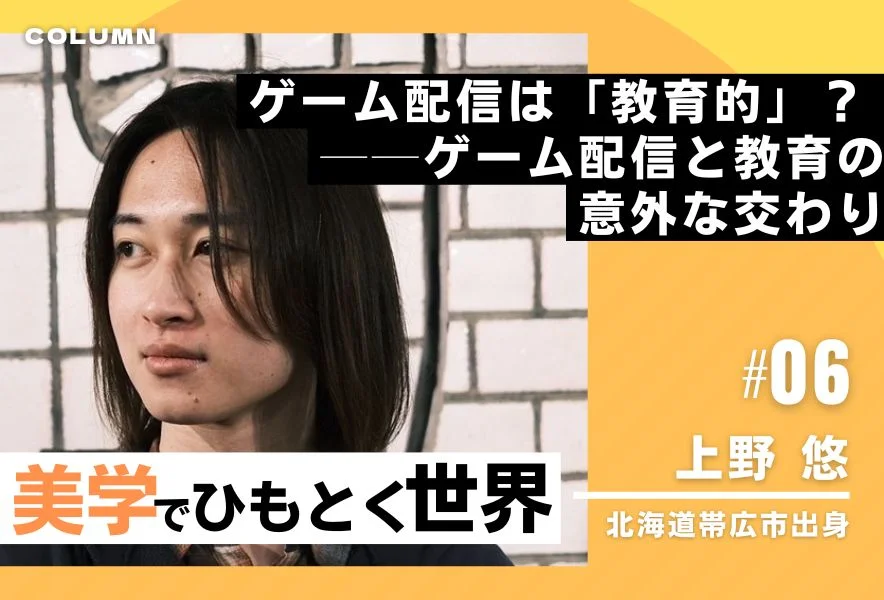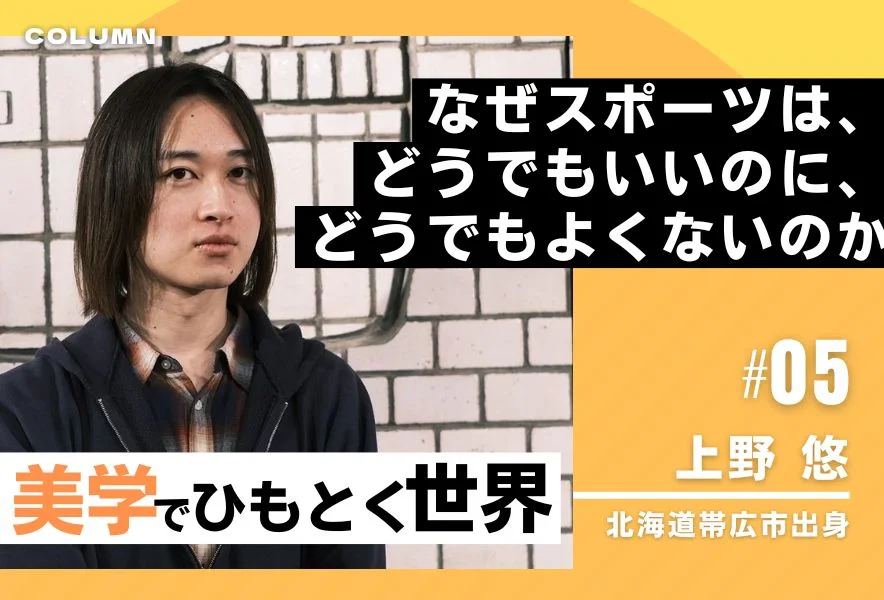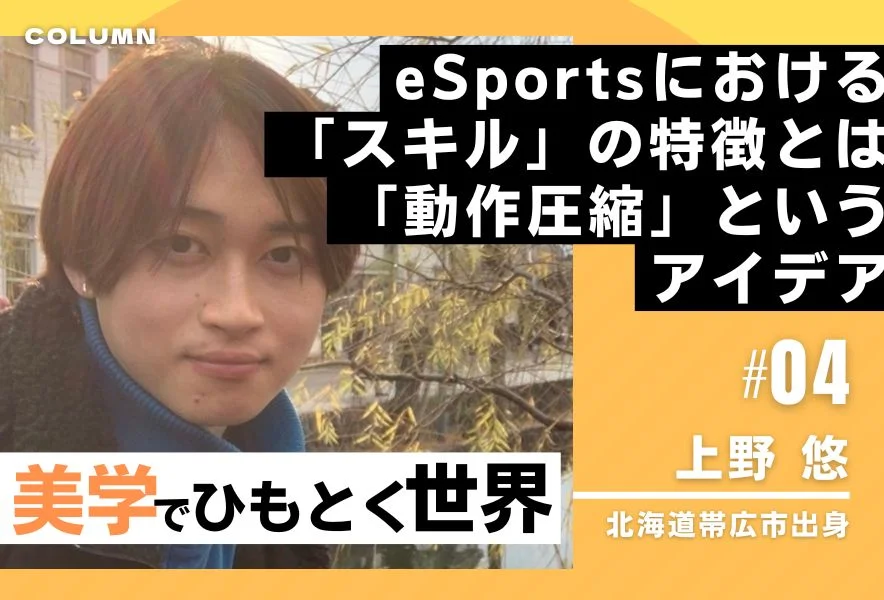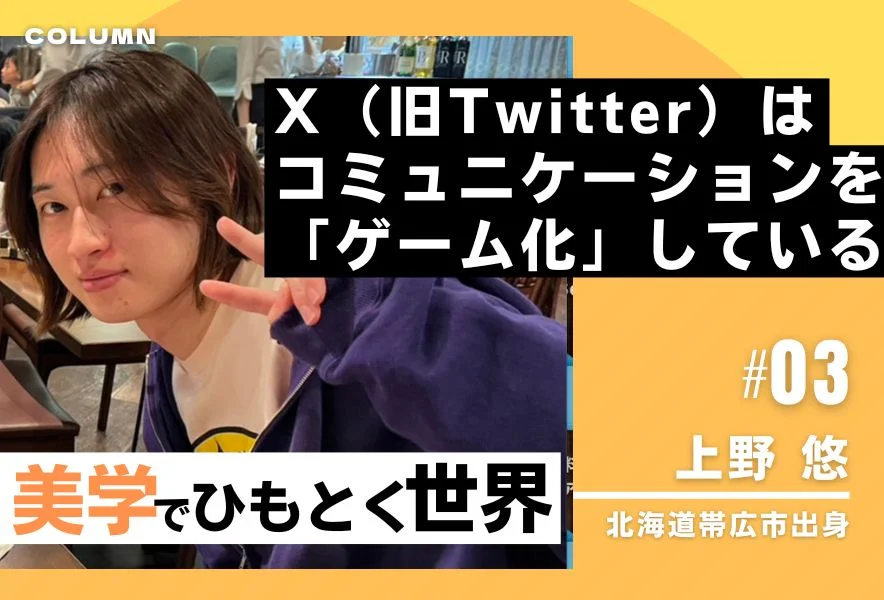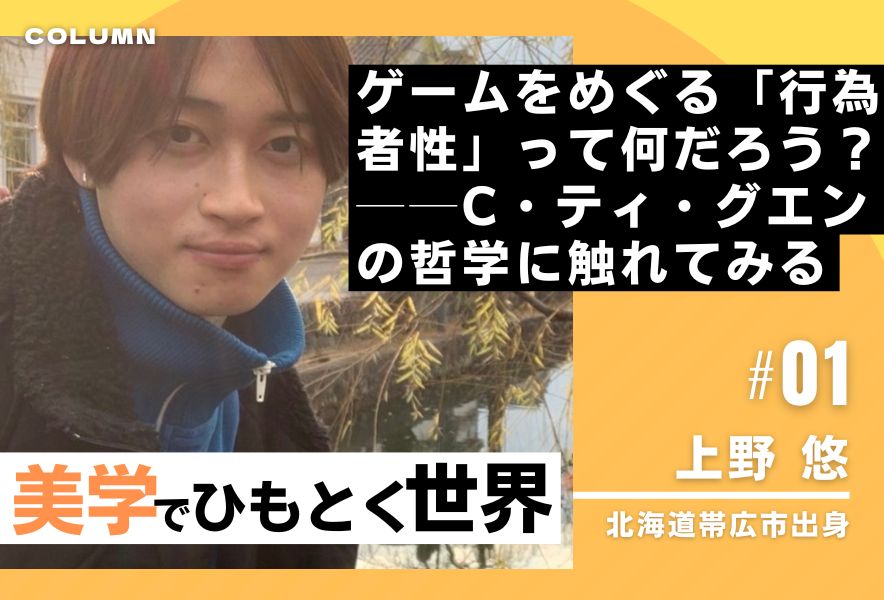【連載】美学者 上野悠の「美学でひもとく世界」
ゲームにおけるフィクションとそのおかしさ

みなさんは「ビデオゲーム」と聞いて、どのような作品を思い浮かべるでしょうか。おそらく多くの人が思い浮かべるのが、『ドラクエ』や『FF』などといったRPG作品、または、『スーパーマリオ』シリーズや、『GTA』シリーズのようなアクションゲームでしょう。『ドラクエ』のようなRPGと、『マリオ』のような横スクロールアクションには、ゲームシステム(=ゲームメカニクス)として考えると、かなり大きな開きがあるように思えます。
一方で、両者には共通点もあります。それは、「フィクション」の側面を持っていること──わかりやすく言うと、「物語」をその内容として含んでいること──です。考えてみると、かなり多くのビデオゲーム作品には物語が含まれていることに気づかされるのではないでしょうか。
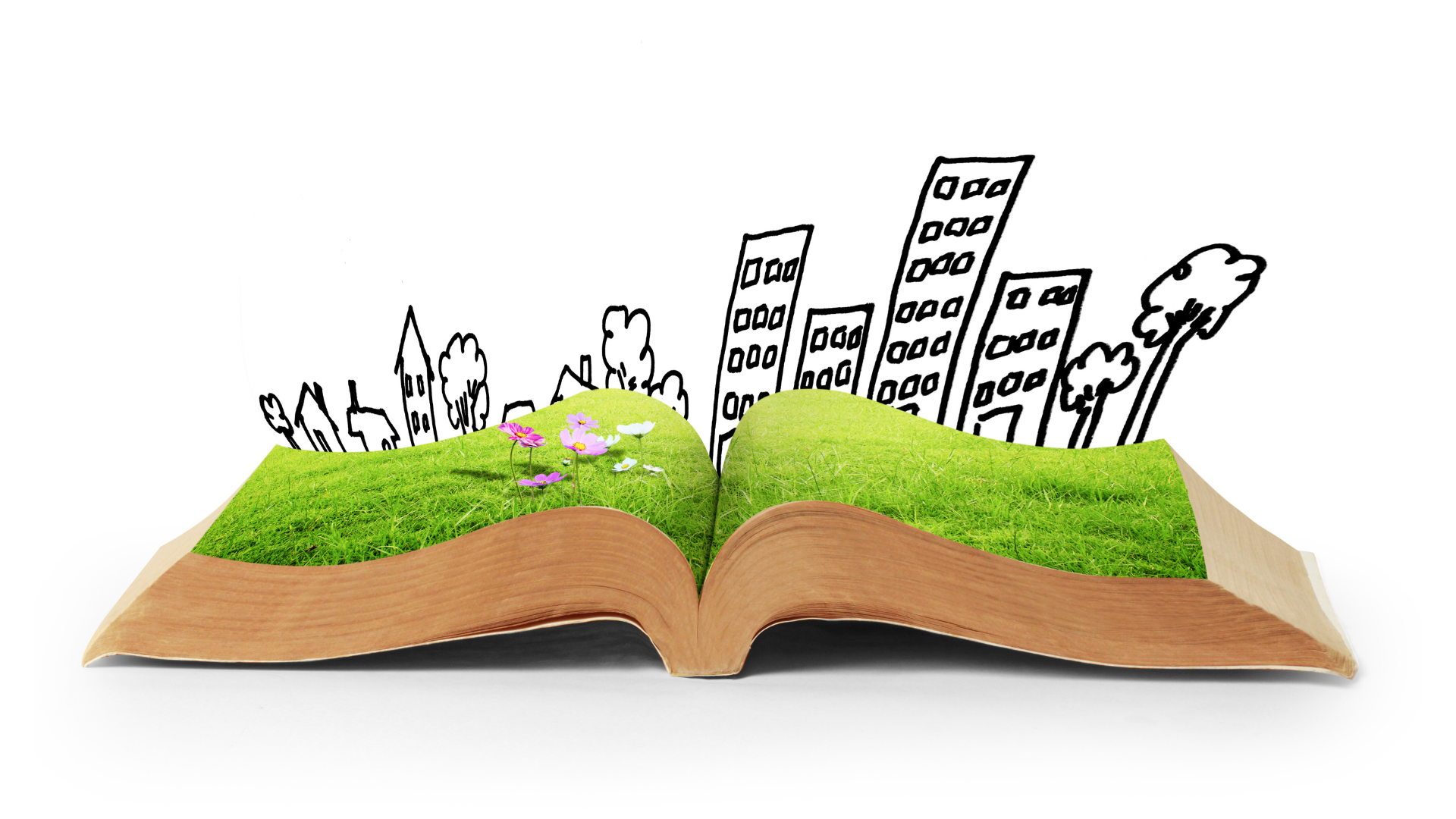
しかしながら、ビデオゲーム作品を物語作品としてとらえると、おかしなことがたくさん出てきます。例えば、「チュートリアル」の存在です。多くのビデオゲーム作品は、プレイヤーにゲームメカニクスを学習させるために、ゲームプレイにチュートリアルを導入します。しかし、こうしたチュートリアルは、物語のどこに位置付けられているのでしょうか。作品によっては(特に最近の作品には)、チュートリアルを物語の中に、かなりうまく溶け込ますことができているようなものも見受けられますが、やはり、ゲームを物語として見た場合、チュートリアルの存在はかなり不自然なものとなってしまいます。
では、プレイヤーは、チュートリアルを、物語を不自然なものにするものとして厭うのかというとそうではなく、物語が進められていく最中であっても、チュートリアルを自然なものとして受け入れているように思えます。いったいなぜなのでしょうか。
なぜプレイヤーはゲームの物語の不自然な点を受け入れられるのか

ノッティンガム大学のアシスタント・プロフェッサーであるカール・エガートンはこうした疑問を解決するものとして「形式的緩和(formal reliefs)」と「表現性チェック(representation checks)」という二つの概念を提示しています。それでは、これらの概念がどういうものなのか、これらの概念によって何がどのように説明されるのか、見ていくことにしましょう。
ゲームにおけるフィクションの重要性
まず、エガートンは、ゲーム作品におけるフィクションの重要性を指摘します。エガートンは、ビデオゲーム作品の『Bio Shock』(Irrational Games 2007)と、ボードゲーム作品の『Agricola』(Uwe Rosenberg 2007)を比較し、前者が作品全体に対して、比較的物語が果たす役割が大きいのに対し、後者が、それほどではないということを示しています。前者は、プレイヤーの作品に対する最低限の関与(minimal engagement)に、物語シークエンスが必要不可欠であるのに対し、後者においては、ゲーム内のタスクを完了するためには、ルールに対する最低限の理解だけで十分であることから、そうではないのです。
しかし、それでもなお、両ケースにおいて、作品に対する物語的な見方が強く推奨されており、妥当な形で規定的なものだとされているのだと、エガートンは指摘します。ただ単純に点数を積み重ねていくだけでは、ゲームを十分に楽しめなくなるだけでなく、適切な形で作品に関与するということに失敗してしまうという重大な問題が生じてしまうのです。
もちろん、ゲームの中には、「オセロ」や『テトリス』など、フィクションをほとんど含まないようなものもたくさんあります。それについてエガートンは、それらはこの論文の対象ではないと適切に議論の範囲を限定しています。
この論文においては、美的関与のためにフィクションへの関与を必要とするゲームが存在することを示すだけで十分であり、それらのゲームに議論の焦点を当てているのです。以下特に断りがない場合は、ビデオゲームやゲームという語は、物語を含むものを指すと思ってください。
物語における「虚構的緩和」と「現実性チェック」

エガートンは、私たちのフィクションへの美的関与がどのように変化するかを理解するための有用なものとして、Margrethe Bruun Vaage(2013)が提示した二つの概念を参照します。
Vaageは、物語作品の作者が、鑑賞者が美的関与を失敗する可能性があるような箇所において、鑑賞者の関与を継続させるために様々な技術を用いていることを指摘しています。
例えば、連続ドラマ『ブレイキング・バッド』を観る際、主人公であるウォルター・ホワイトというキャラクターに感情移入します。ホワイトは、有害な薬物の製造・販売者であり、さらには自らの利益のために殺人まで犯すようになるような、現実にいれば許しがたいはずのキャラクターです。
こうした人物が現実にいた場合、共感するのは困難ですが、物語の虚構性を強調するような様々な技術が、キャラクターから距離を置く必要を感じることなく、深く関与し続けることを可能にするのです。

例としては、BGMをうまく使うことや、スタイリッシュな撮影技法、または物語の奇妙な要素に鑑賞者の注意を向ける手法、といったものが挙げられています。このような場合において、Vaageが「虚構的緩和(fictional reliefs)」と呼ぶ、創作者が物語の虚構性に注意を向けることで観客の関与の仕方を変えるような現象が生じるのです。
この虚構的緩和には対となる概念としてVaageは「現実性チェック(reality checks)」というものを提示しています。Vaageは、例えば、物語の社会的な影響を考察させるために、フィクション作品は、その物語を現実の出来事の連鎖のように扱うよう促す技術を用いることがあると指摘しています。
再び『ブレイキング・バッド』を例に挙げ、薬物をつくる資金のためにある人物が残酷に殺されたり、ウォルターがある人物を、都合がいいからと黙って見殺しにしたりするような場面では、私たちはその状況を現実のものとして直面するように促されると言います。
このとき、われわれ鑑賞者は、もはや「静かな男が凶悪犯罪の首謀者になる」というファンタジーに安全に没頭することはできず、一時的にウォルトを現実の人物として非難するように意図されているのです。このように、制作者がフィクションをノンフィクションに近づけて観客の関与を促す場合、私たちは「現実性チェック」を受けているのです。
ゲームへの適用
物語要素が存在するゲームにも、当然この二つの概念セットが適用可能です。例えば、虚構的緩和は、ビデオゲームのさまざまな特徴を説明してくれます。例えば、血をオフにできる機能や、暴力的なシーンがカートゥーン調であること、サウンドトラックやナレーションといった要素によって、フィクションであることが強調されているのです。
ゲームにおける現実性チェックについては、エガートンは『BioShock』の例を挙げています。ゲーム内のキャラクター、「リトルシスターズ」は不気味な存在としてオーバーに表現されていますが、プレイヤーが彼女たちを殺すか救うかの選択を迫られたときに(前者を選択するとボーナスが得られます)その選択が提示されると、小さな女の子が画面の中心に映し出され、恐怖に震える顔が印象的にプレイヤーに対して提示されるのです。

ここで、プレイヤーは明確に選択にプレッシャーを感じさせられるように設計されているとエガートンは指摘しています。このとき、プレイヤーは一時的にゲームの虚構的な要素から引き離され、それまでのゲームプレイの過程ですんなりと受け入れられていた暴力性に対して、不快感を覚えるようになるのです。エガートンは、こうしたテクニックはボードゲームにおいても同様にみられることを例を挙げて述べています。
ゲームの不整合な描写
さて、一方で私たちは、ゲームを虚構として楽しみ、物語作品として関与するだけではありません。私たちプレイヤーは、ゲームのルールにも関与します。
例えば、よくできたゲームメカニクスは、作品への関与を維持するために、現実的な態度へと我々を移行するのではなく、形式主義的で非表現的な態度へとわれわれをいざなうことで、一時的にその虚構的態度を停止させているのかもしれないのです。

エガートンはまず、『Agricola』の例に戻ります(彼は、ビデオゲームよりもボードゲームの方が親しみがあるのかもしれません)。 『Agricola』のルールセットには、「動物」トークンの獲得と保持に、「柵を建設して牧場を作成し、動物の種類に対応する専用の牧場がないと、その動物を獲得できない」という特定の要件があります。そして、収穫のたびにそれら動物は繁殖し、その数が増加します。
ここには、他のゲーム同様、ルールとフィクションの内容の間には支えあうような関係が存在しています。つまり、ゲーム内の特定のトークンの収集にポイントが与えられることで、その農場を経営するプレイヤーのフィクション上の地位が強化され、反対に、他のプレイヤーが家族を養うのに苦闘する、という状況が強められるのです。
一方で、『Agricola』では、ルールセットのある2 つの要素がフィクションとルールの緊張関係を浮き彫りにしてもいるのです。
1つ目は、各プレイヤーはシステム外に「ペット」として 1 匹の動物を保持できること、2つ目は、プレイヤーが保有する動物の数に関わらず、収穫ごとに各種類の動物は 1 匹ずつしか増加しないこと、です。
もし、先ほどのような、ルールとフィクションが結びついたような態度でプレイヤーがゲームに臨むなら、動物の 1 匹をペットとして家に置くという提案はおかしいわけです。というのも、動物は専用の牧場がないと飼育できない、というルールだったはずだからです。また、動物たち(例えば、羊)が 2匹でも8匹でも、毎年追加で獲得する羊は 1匹だけというのも、現実的に考えたらおかしいことになります。
もし、このゲームに固定された虚構的関与のレベルがあるのだとすれば、エガートンは、以下の2つの選択肢がありうるとしています。
(2) このようなゲームは、奇妙な点に影響されることなく美的関与ができるような、一貫性と分かりやすさのレベルを超えようとしていない(つまり、目指すレベルは固定されているが低い)。
エガートンは、どちらの結論も正しいとは思えないといいます。
最初の可能性に対しては、『Agricola』はボードゲームとして高く評価されており、さらにはこれらのルール(特に動物の繁殖に関するルール)はゲームにとって重要であるというのがその理由として挙げられています。
さらには、エガートン曰く、この選択肢を支持するためには、シミュレーションがすべてのゲームの理想であるという結論になってしまいますが、このことは、ボードゲームがビデオゲームに本質的に劣るという不都合な結果を招いてしまうからです(私〔上野〕としては、ただちにそういうことにはならないように思えますが…。シミュレーションとしての整合性は、それがボードゲームであるかビデオゲームであるかという事柄とは別個のものとして存在しているように思われます)。
第二の可能性を排除するためには、二つ の選択肢を検討する必要があるとエガートンは指摘しています。その選択肢とは、
⑵このゲームが、ほかの部分から孤立した、不一致や理解不能な要素を含むような世界を描写しようとしているのかもしれない
というものです。
しかし、ゲームにおいてこうした一貫性が魅力的であることは明確であり、囲いの計画と建設に対しての注意深い判断、収穫が近づくにつれ他のプロジェクトを犠牲にして畑を耕す必要性が高まる緊張感、といったものは、ゲームを引き込む要素の一部となっており、もし『Agricola』がこのような一貫性のある物語から著しい距離を保っていたり、突然物語から恣意的に逸脱したりしていたら、ゲームとして自ら設定した目標(=意図)を達成できなかったように思われるのです。
以上のことから、どちらの結論も妥当でないため、エガートンは前提を拒否すべきであると述べます。このようなケースでは、固定された美的関与のレベルは存在しない、つまり、関与は動的なものなのです。しかし、ここで観察されるような没入度の変動は、虚構的緩和や現実性チェックを通じても適切に説明できないことがわかります。
まず、『Agricola』の例は、明らかに現実性チェックではありません。現実的な性質を参照することは、状況を解釈することをさらに困難にしてしまいます。
また、もしこれが虚構的緩和の場合、プレイヤーの、虚構に向けられるような態度が強化される必要がありますが、私たちが『Agricola』の不整合な状況を受け入れる際の困難は、現実との整合性だけでなく、フィクション内部の整合性にも起因しています。『Agricola』のフィクション内では、動物が逃げないように柵が必要であることは理にかなっていますし、動物の数が増えるほどその増加速度が速くなるということも理にかなっているのです。
形式的緩和と表現チェック
形式的緩和

エガートンは、ゲームのこうした側面を説明するために、フィクションの緩和に類比させた、「形式的緩和」という概念を導入すべきだと主張しています。
形式的緩和とは、ゲームの形式的またはルール中心の要素が優先され、それに応じてゲームの表現への関与を一時停止または弱めることが許されるような事態を指します。つまり、クリエイターがプレイヤーの美的関与に影響を与えるために、意図的にゲームのルールに意図的に注目させるようなテクニックのことです。
エガートンは、この特徴がボードゲーム形式に特有ではないことを示すため、ビデオゲームの例を挙げます。この例がまさに「チュートリアル」です。
初めてプレイするプレイヤーが、ゲームの「本編」で求められることになる複雑なタスクをこなすことができるように、多くのゲームは、可能な行為の範囲や種類など、ゲームメカニクスの一般的な理解を得るためのチュートリアルを提供します。
一部のゲームはゲームの物語に干渉しないような形でチュートリアルを提供しますが、チュートリアルをゲーム本編に組み込むケースも珍しくありません。こうした場合、ゲームプレイの開始部分を形成する単一のセグメントとして、または、ゲーム全体に分散した小さなセグメントの集まりとして実装されます。
チュートリアルにおいては、非プレイヤーキャラクターがプレイヤーキャラクターに、特定のコマンドを入力するよう指示するといった、「第四の壁」を破るような事態が頻繁に発生します。
また、明示的に指示されなくても、プレイヤーはコマンドをテストするために任意の 行動を求められる場合があります。これらの要素を物語の中に直接組み込むと、物語の滑らかさは損なわれてしまうのですが、私たちはそのような逸脱をゲームを楽しむためのものとして受け入れているのです。
ただし、これはチュートリアルが決して美的な欠点にならないという意味ではなく、チュートリアルはより効果的に実施される場合もあります。
ですが、チュートリアルの成功は、物語との整合性だけで決まるわけではありません。むしろ、物語にうまく統合されていても、プレイヤーがやることを理解するのが非常に困難になってしまっている、などといった理由で、悪いチュートリアルであることもあるのです。
また、エガートンは別の例として、「ミニゲーム」を挙げています。ミニゲームは時に、ゲーム本編で世界崩壊の危機であるにもかかわらず、キャラクター(やプレイヤー)はいつもと変わらない態度でこれを行うことがあります。こうしたゲーム内の機能は、ゲームのフィクション要素からの認識可能な逸脱として、形式的な緩和を提供し、ゲームの「挑戦」要素への集中を許容するのです。
ルールとフィクションの内容の間の緊張関係という一般的な展望は、以前から議論されてきたものであり、エガートンはそれらと比べて今回の論文の前進を示しています。
エガートンは特に、イェスパー・ユール(2005)に対して、ユールは、ポイントスコアや複数の「ライフ」といった例を挙げ、いわゆる「不整合なゲーム世界」について議論していますが、この扱いは問題点を解決していないと指摘しています。
第一に、ユールが依拠する「不整合」の概念が過度に強すぎるからであるとエガートンは主張します。というのもそれによって、私たちがゲームをプレイするときに、矛盾したものを想像するよう求められているかのような誤解を招いてしまうからです。
それに対し、エガートンは、ゲームには真の矛盾はほとんど存在せず、通常は起こっていることを何らかの解釈で説明することができると述べています。
第二に、ユールによる矛盾の解決方法は「ルールがフィクションに優先する」というものですが、これに関してエガートンは、これは今回扱ったような問題が美的関与にどのように影響するかを理解する助けにはならないという指摘をしています。エガートンは、形式的緩和と表現性チェックという概念によって、これらの問題をクリアできると考えているようです。
表現性チェック

エガートンは、上記のように、虚構的緩和との類比によって考察することで、ルールとフィクションの関係の複雑さをより明確に認識できることを示してきました。彼曰く、この関与の側面は動的かつ限定的なものです。ルールへの注目は一時的なものであり、ルールがその要求を課さなくなった時点で、豊かに表現されたフィクションの内容に対する関与に戻ることができるのです。
エガートンは、虚構的緩和に形式的緩和の類比があるなら、現実性チェックの類比も存在すべきだと述べます。ゲームが私たちに、ゲーム中の何らかのものを表現的に扱うことから遠ざけることができるなら、逆に表現的に扱うように導くこともできるだろうと彼は主張しています。
エガートンは再び、『Agricola』の例に戻ります。『Agricola』におけるプレイヤーの目標はポイントの蓄積かもしれませんが、プレイヤーがゲーム内で演じるキャラクターの目標は、自給自足の農耕世界で生き残り、可能な限り繁栄することです。そのキャラクターにとって、家族を養えないことは、豚を飼育できないことよりも大きな失敗となります。エガートンは、もし、プレイヤーがこの選択肢を選んだ場合、その勝利はプレイヤーによって「成功のためなら手段を選ばない冷酷な所業」として捉えられるだろうと述べています。
また、エガートンは、プレイヤーとしてでは なく、キャラクターとして決断を下すよう促される例として、『Dead of Winter』(Jon Gilmour and Isaac Vega 2014)というボードゲームを挙げています。このゲームでは、それぞれのプレイヤーキャラクターが異なる性格を持つ者として描かれており、プレイヤーはキャラクターの性格に合った行動を取ることを期待されるのです。
ゲームの製作者は、バックストーリーやトークンの記号的デザイン、または装飾的な要素を使用することによって、フィクションの内容に則すような類の行動を弱く促すこともあれば、キャラクターの描写に合った行動を奨励するルールを提供することで強く促すこともできるのです。
そして、そのような行動が奨励されるような事態、つまり、クリエイターがゲームの虚構的要素にプレイヤーの注意を引き、プレイヤーの関与に影響を与えるように内容を表現するようなテクニックを、エガートンは「表現性チェック」と呼びます。
エガートンは、 表現性チェックはビデオゲームではより明確な形で現れると指摘しています。というのも、ビデオゲームの正確なメカニクスは、 多くの場合プレイヤーには不透明であるからです。
例えば、サッカーゲームでゴールを狙ってシ ュートするコマンドを入力する際、結果に関する複雑な法則は、ざっくりとした予測以上のものはプレイヤーに開示されません。そのような状況下で結果が特に予測困難な意思決定を促される場合、これは「表現性チェック」として機能します。つまり、プレイヤーはゲーム上の戦略ではなく、キャラクターの目標に基づいて行動するよう促されるのです。
虚構と現実の逆転

記事内でも少しふれたように、ゲームにおけるフィクションの研究については、多くの蓄積があり、往々にしてゲームのフィクションの奇妙な点が取り上げられ、その解決を試みる形で議論が進められます。
特に、イェスパー・ユールはそうした点を「不整合なもの」として捉えたのですが、エガートンはそこから一歩進んで、その不整合さを、制作者によってその都度されるプレイヤーの注意の焦点の操作として概念化しました。
今回エガートンは、「虚構的緩和」と「現実性チェック」という概念(これら自体は映画研究の文脈のものです)の類比によって、概念を提示したわけですが、興味深いのは、
元の概念が、虚構に注意を向けさせることによって、現実に則した場合に生じる多少の無理を鑑賞者に受け入れさせるというものだったのですが、ゲームでは、逆に、形式に向けさせることによって、物語に則した際に生じる無理を受け入れさせるものとなっているのです。
このことが何を示しうるのかは、私にはまだ思いつかないですが、ゲームの物語とそれ以外の物語の相違点を考えていくうえで、重要な示唆となるかもしれません。
参考文献
- Egerton, Karl. 2022. “Player Engagement with Games: Formal Reliefs and Representation Checks.” Journal of Aesthetics and Art Criticism 80 (1):95-104.
Juul, Jesper. 2005. Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds. MIT Press.
Vaage, Margrethe Bruun. 2013. “Fictional Reliefs and Reality Checks.” Screen 54: 218–37.
美学者とは
美学者の役割
- 【美的判断】なぜある人が「美しい」と感じる対象を、別の人は「そうでもない」と思うのか
- 【芸術作品の価値】作品が私たちの感性に与える影響を、どう評価し、言葉で説明できるか
- 【日常の美】ファッションやインテリアなど身近なところに潜む「美しさ」をどのように考えるか
こうした問いに取り組むのが美学者の役割です。近年では、ゲームの体験やデザイン、スポーツや身体表現、さらにはSNSなど、従来は「美学」とはあまり結びつかなかった分野にまでその探究範囲が広がっています。哲学や芸術学と深く関係しながら、現代社会のあらゆる「感性の問題」に光を当てるのが、美学者と呼ばれる人々なのです。

【PROFILE】
北海道帯広市出身。早稲田大学文学研究科博士後期課程在籍。専門は、ゲーム研究、美学。主な論文に、「個人的なものとしてのゲームのプレイ: 卓越的プレイ、プレイスタイル、自己実現としての遊び」『REPLAYING JAPAN 6』、「ゲームにおける自由について──行為の創造者としてのプレイヤー──」『早稲田大学大学院 文学研究科紀要 第68輯』。ゲームとファッションとタコライスが好き。