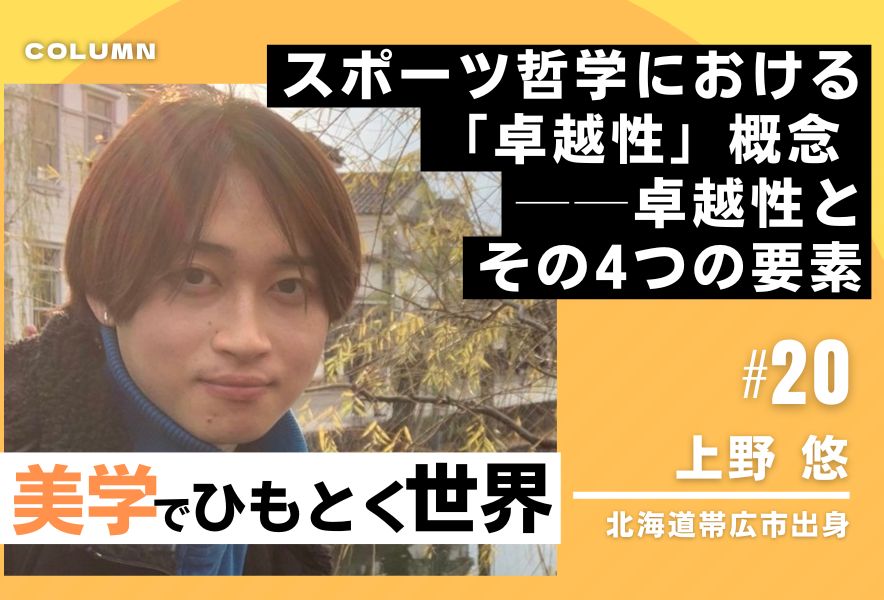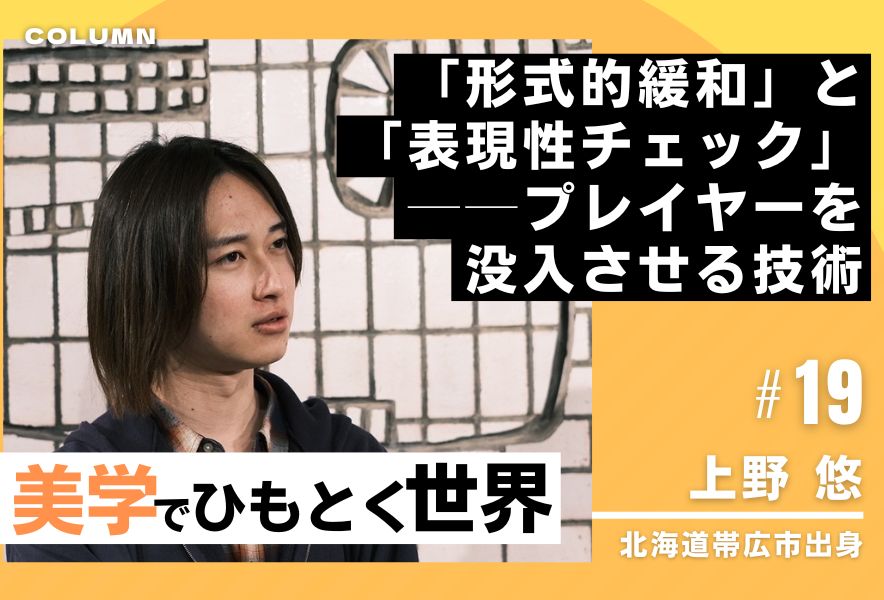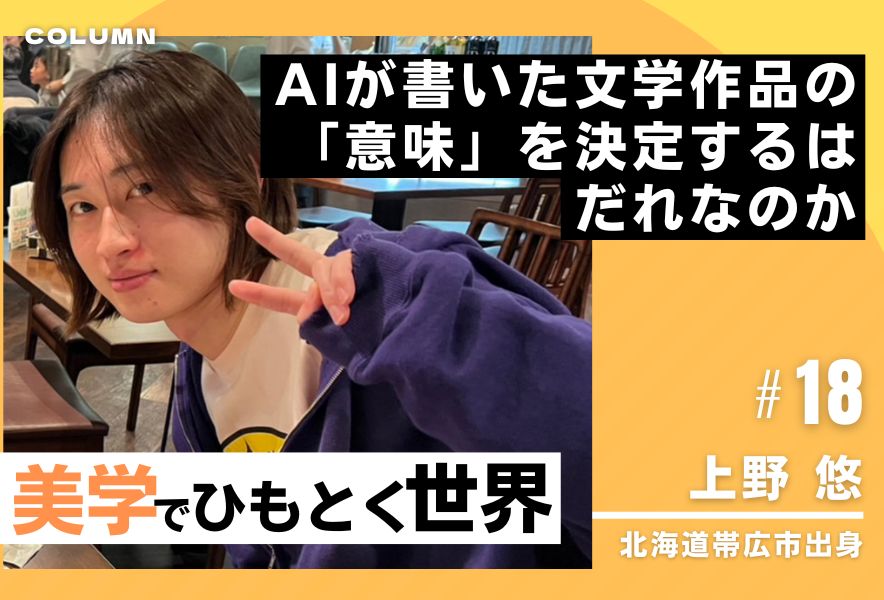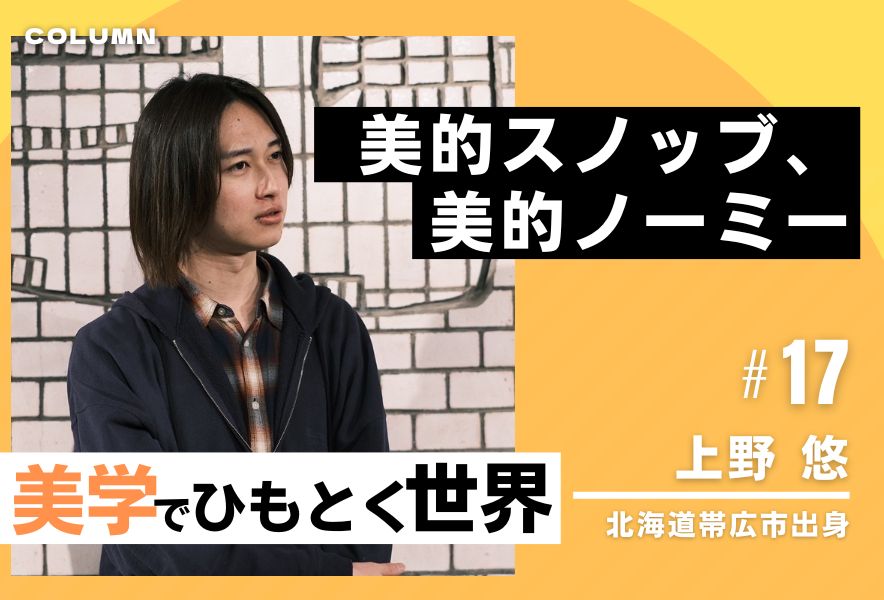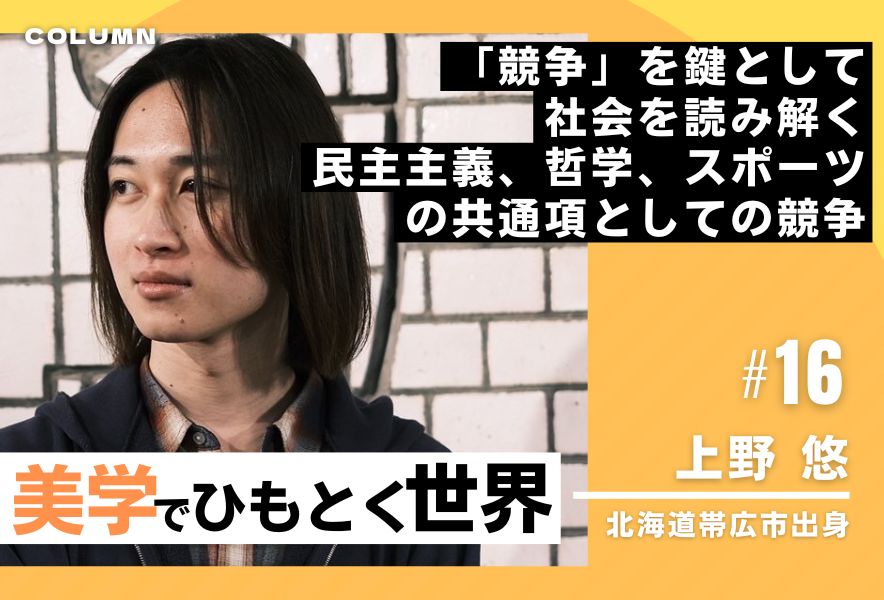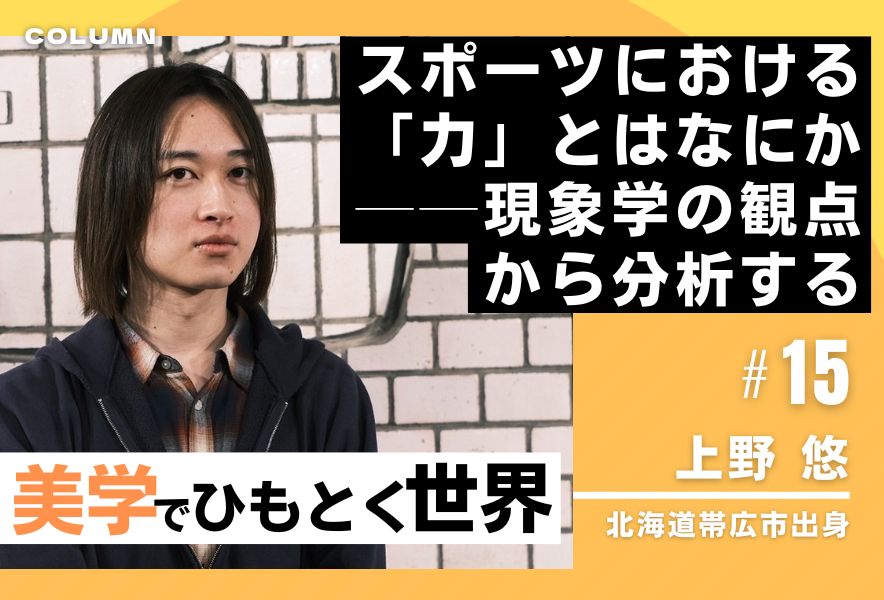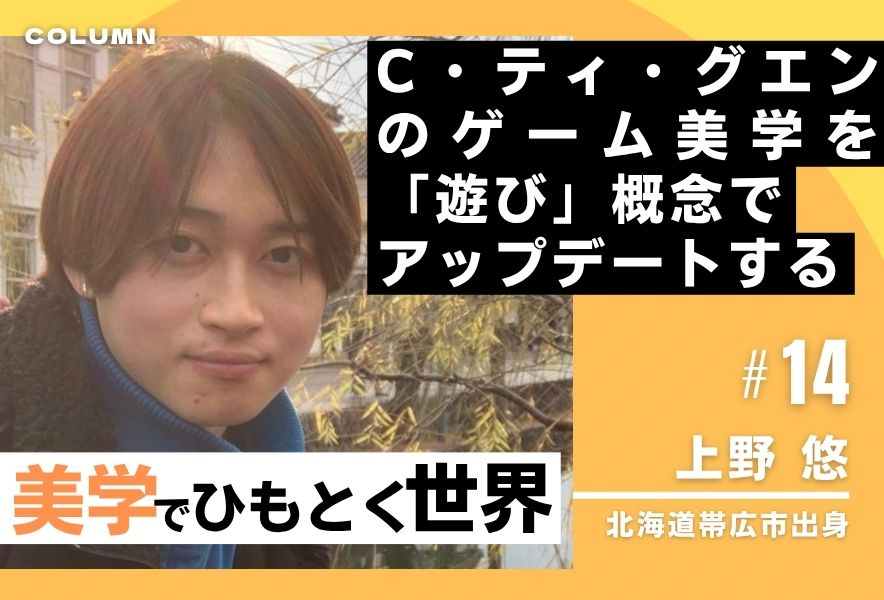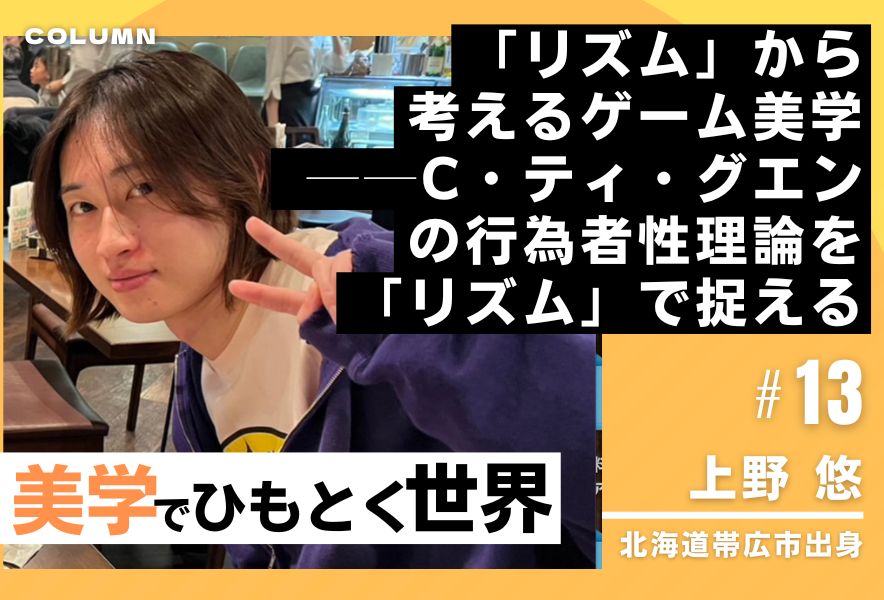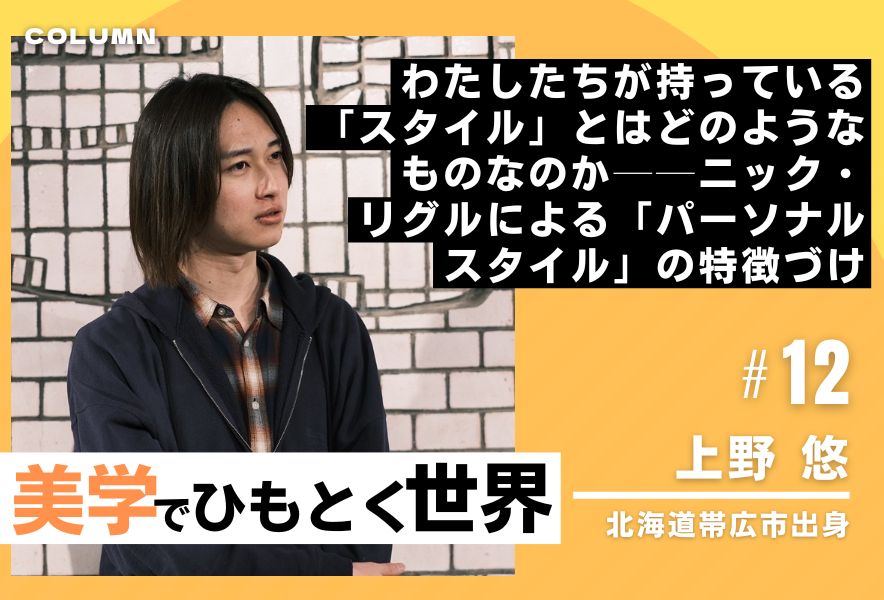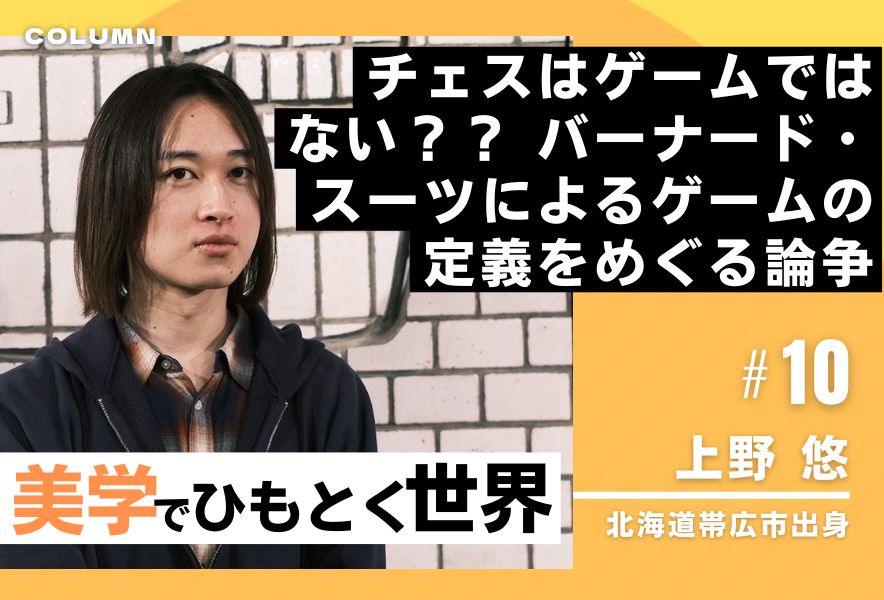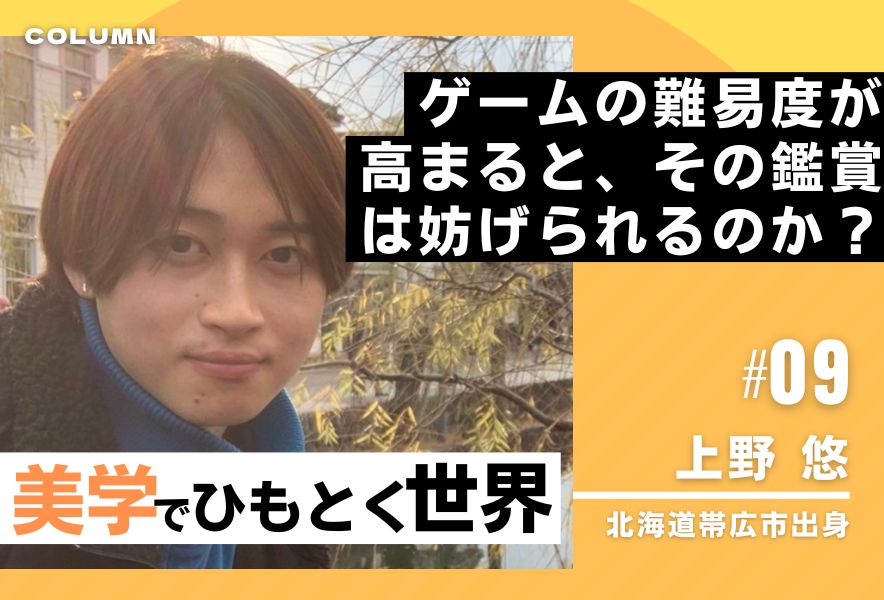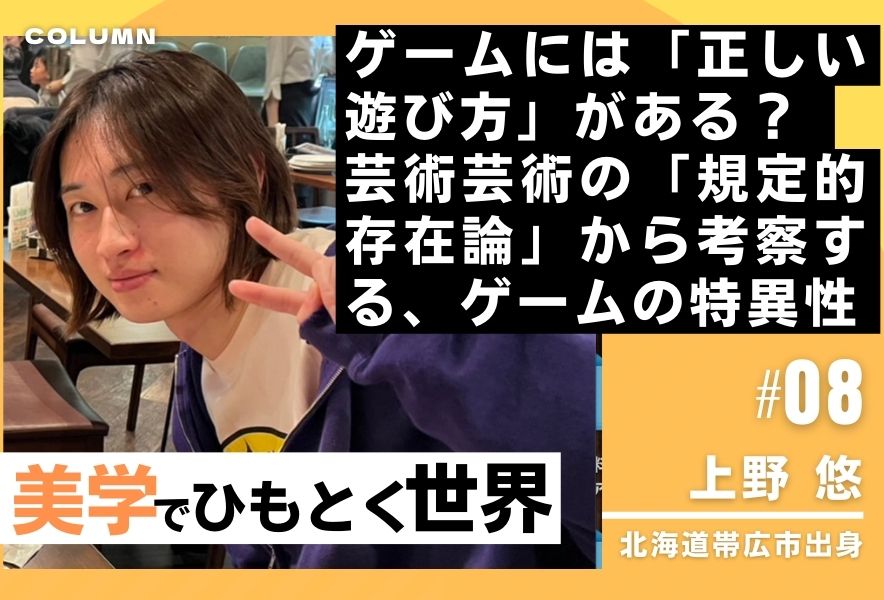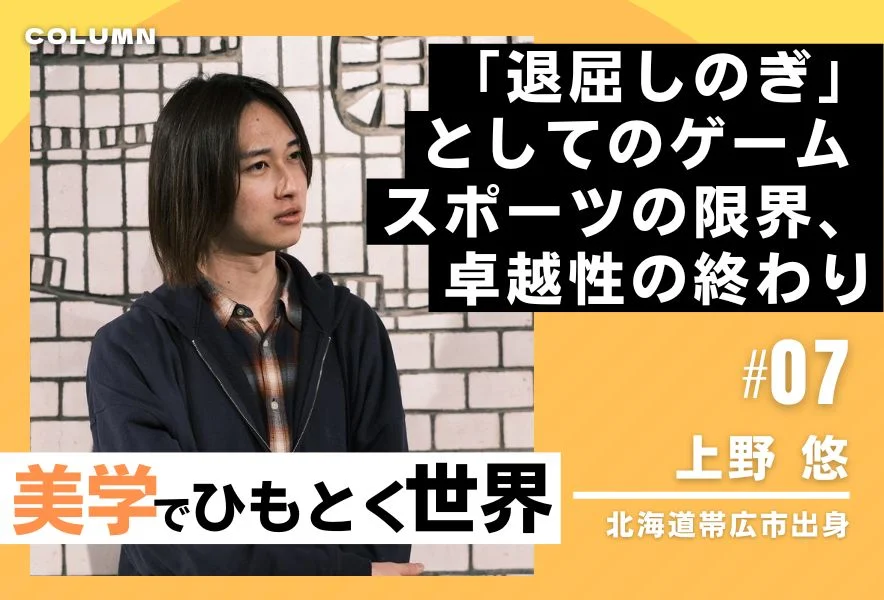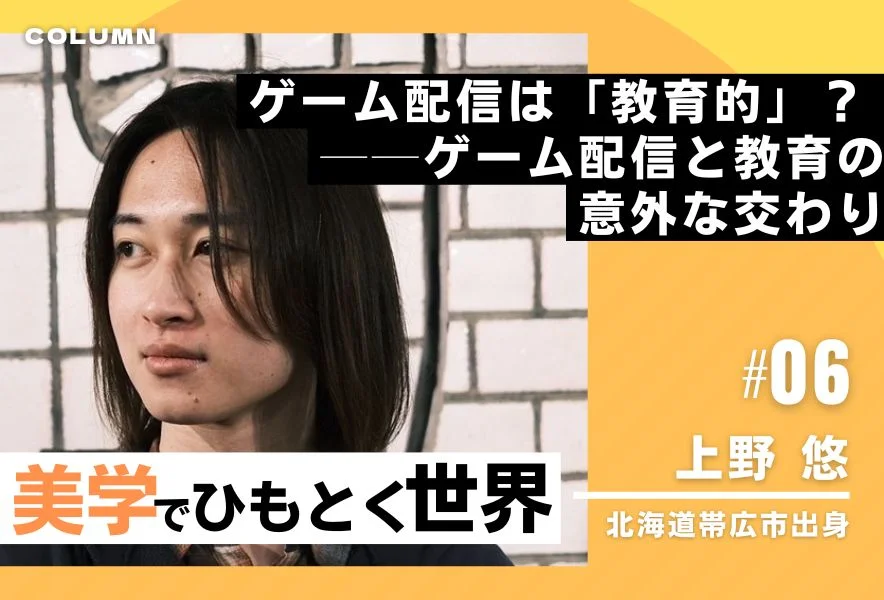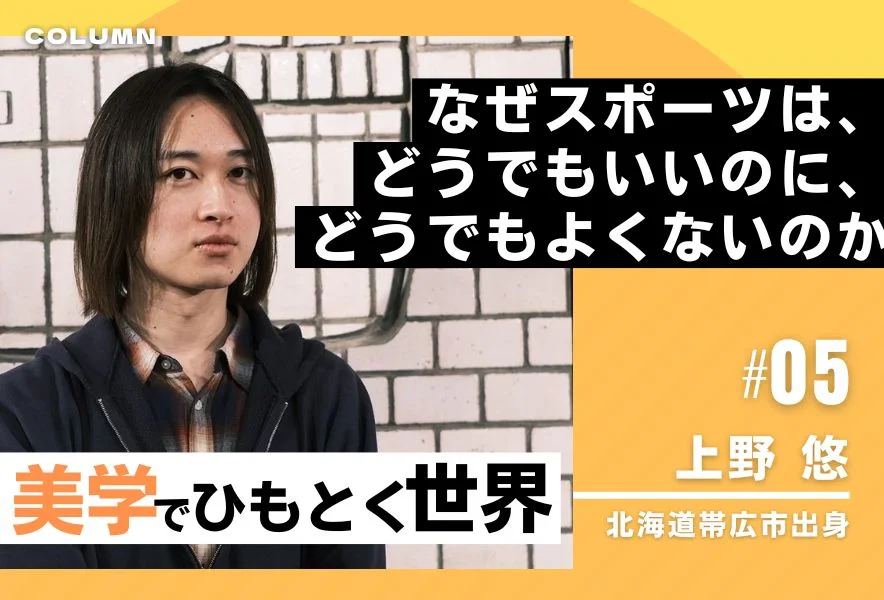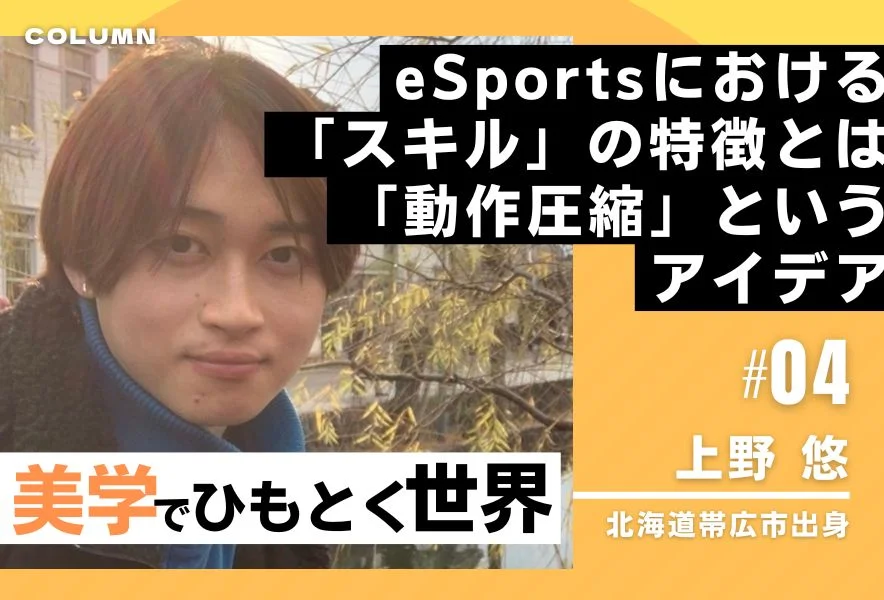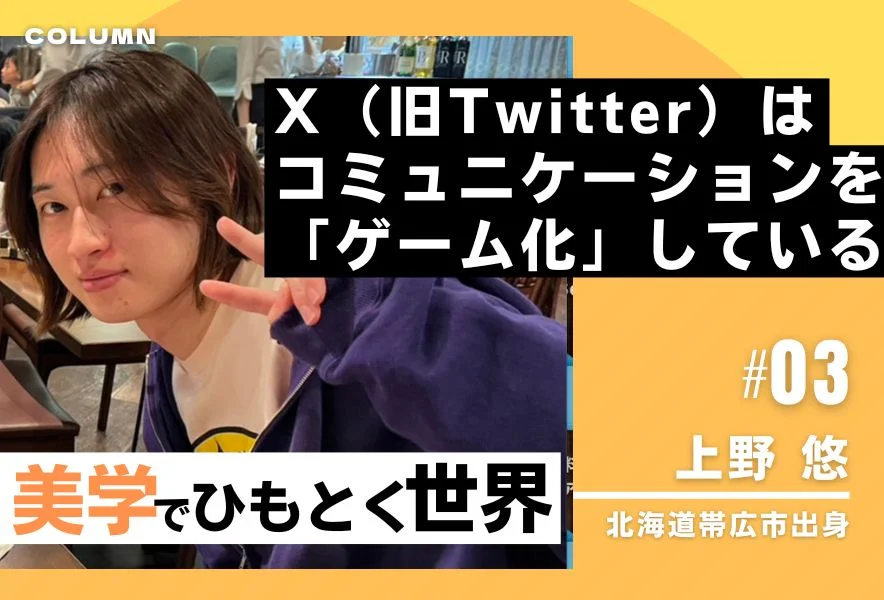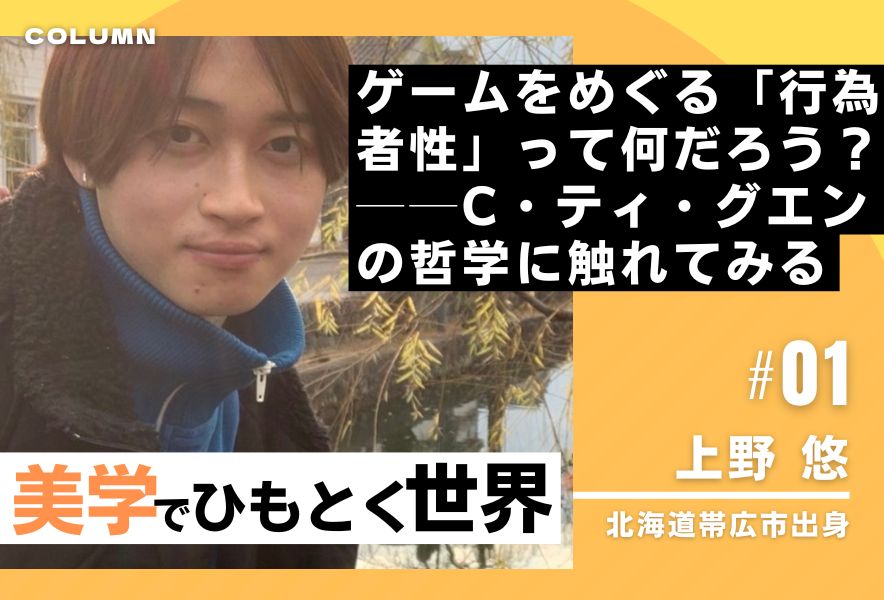【連載】美学者 上野悠の「美学でひもとく世界」
スポーツ哲学における「卓越性」という概念
本連載でも何回か取りあげてきましたが、哲学にはそのサブジャンルの一つとして、スポーツを対象にするその名も「スポーツ哲学」という分野があります。

スポーツが哲学の対象となることに、あまりピンとこない方も多いかもしれませんが、スポーツの哲学には「スポーツの本質(nature)とはなにか」という直球の問いかけや「スポーツの重要な価値とは何か」という伝統的な議論から、最近では、「ドーピング」の問題や、「ジェンダー」の問題についての議論も白熱しているなど、その取り扱いの範囲は多岐にわたります。
そのなかで、近年のスポーツ哲学──特にスポーツ倫理についての議論において──根幹となっているのが「卓越性(excellence)」という概念です。卓越性概念は1999年に発表されたJ・S・ラッセルによる“Are Rules All the Umpire Has to Work With?”という論文に端を発し、今ではスポーツ哲学における最重要概念と言っても過言ではないようです。
しかしながら、卓越性という概念はその重要さのわりに、その「中身」についてはあまり精査されてきていなかったと問題提起をした研究者がいます。スウォンジー大学のジョン・ウィリアム・ディバインは上記のことを指摘し、卓越性には、「卓越性のクラスタ」、「卓越性の量」、「卓越性の明確さ」、「卓越性のバランス」という4つの要素からより詳細に見ることができると主張しています。今回は、ディバインの論文を取り上げ、卓越性という概念について紹介しつつ、ディバインによる分析の射程を見ていきたいと思います。
卓越性とはなにか
スポーツの価値とは、第一に、人間の優れた技能や能力が試され、培われ、発揮される場を提供することにあると言えます。これは運に左右されるような活動とは対照的です。くじで当たるために特別なスキルはいりませんが、スポーツで勝つためにはそのようなスキルが必要とされます。これは、スポーツに運の要素がないと言っているわけではなく、ボールの跳ね返り方や風の吹き方など競といった運に左右される出来事は、発揮された技能の結果に重要な役割を果たす可能性がありますが、スポーツを構成しているルールが参加者の行為者性を制限することにより、勝利は特定のスキルや能力の行使によってのみ達成されることになります。

例えば、ボクシングでは、銃や剣などの武器を使った技能は禁止され、パンチの技能によって勝敗が決されるように、参加者の行為者性が制限されています。このことと同様に、スポーツが卓越性に基づく活動であり、特定のスポーツがそのスポーツにおける卓越性を促進しているのであれば、そのスポーツの中で、当該の卓越性の発揮を損なうような形での慣習の変更は禁止されなければならないという規範性が存在してしかるべきであるということになるのです。しかし、あるスポーツにおいて、卓越性の発揮が損なわれるとはどういうことなのでしょうか。
スポーツ哲学における現在かなり有力な規範理論的立場である「広い内在主義(broad internalism)」(「解釈主義(interpretivism)」とも呼ばれる)の支持者たちは、スポーツの意義と目的を、独特のタイプの卓越性を発揮する場を提供することに置いています。そのうちの一人であるロバート・L・サイモンは、スポーツ競技は「卓越性の相互探求」として捉えられるとき、道徳的に正当化可能になる(morally justifiable)のだと主張しています。この考え方によれば、スポーツは、競技者がそれぞれが持つ卓越性を最もよく引き出すような、適切に要求の厳しい挑戦を相互に提供することで、卓越性を追求する互いの努力を促進するような協力的な活動であるとき、最もよい状態となるのです。

しかし、ディバインは、「広い内在主義」の代表者といえるサイモンやラッセルにおいては、卓越性が促進されたり阻害されたりするとはどういうことなのかについては、ほとんど指針が示されていないと指摘しています。彼らによる論は、卓越性がスポーツの中心的価値であること、そしてスポーツにおける規範、ルール、実践の設計においては、卓越性を守るための措置を講じるべきであることを立証しようとしているのであり、どのようにすればこれを達成できるのかという議論は、依然として一般性の高いレベルにとどまってしまっているのです。
しかし、卓越性がスポーツ哲学において広範に扱われている以上は、卓越性をスポーツの価値の中に入れる者は誰であってもその輪郭に関心を持つべきであると、ディバインは主張しているのです。そこで、ディバインは、スポーツの卓越性には4つの要素があり、それら要素から、さらに、卓越性が促進されたり、損なわれたりするような4つの方法が考えられることを示します。また、ディバインは、自らの論が、スポーツに限定されているものの、音楽の演奏やアカデミックな評価など、卓越性に基づくような、他の規範領域における倫理的推論を照らし出す可能性も残していると述べてもいます。
卓越性のクラスタ

この世に、あらゆるスポーツにおける卓越性を試験するようなスポーツは存在せず、各スポーツは、特定の卓越性のセットのみをテストするように設計されています。例えば、槍投げはキャッチする能力ではなく投げる能力を、ボクシングはキック能力ではなくパンチ能力を、マラソンは水泳能力ではなく走力をテストするように設計されているのです。
さらに、各スポーツは、複数の種類の卓越性をテストしています。例えば、マラソンでは、(とりわけ)持久力、メンタルタフネス、戦略的センスなどが一緒にテストされます。このように、あるスポーツがテストするために設計されているような卓越性のセットを、そのスポーツの「卓越性のクラスタ」と呼びます。もちろん、卓越性のクラスタには大小があり、多面的なスポーツ(テニス、ラグビー、トライアスロンなど)においては、そのクラスタに含まれる卓越性の数がより多くなる可能性が高いといえるでしょう。

卓越性のクラスタは、ルール変更によって拡大したり縮小したりする可能性があります。例えば、ラグビーからスクラムが削除された場合、効果的なスクラムの組み方にまつわる卓越性セットが、ラグビーから失われることになります。同様に、トライアスロンに含まれている3種目のうちの1種目が削除された場合、トライアスロンの卓越性クラスタは縮小します。逆に、サッカーのなかにラグビーのような「スクラム」が含まれるようになると、サッカーの卓越性クラスタは拡大することになります。
ディバインはさらに、卓越性クラスタには、「許可下の(permitted)」クラスタと「活動的(active)」クラスタという2つの異なる概念の区別を導入することができると述べています。許可下のクラスタは、ルールのもとでその行使が許可されている卓越性によって構成されているのに対し、活動的クラスタは、スポーツの競技結果を決定づけるような卓越性によって構成されるものです。つまり、活動的クラスタは、そのスポーツで成功した参加者のパフォーマンスに典型的に見られるような卓越性で構成される卓越性クラスタであり、多くの場合、許可下のクラスタに包含されることになります。許可下のクラスタに含まれている卓越性は、ルール上認められた卓越性ですが、必ずしも、当該スポーツにおいて常に発揮されている卓越性であるわけではないのです。

また、卓越性のクラスタは縮小したり、拡大したりすることがありますが、スポーツを構成するルールの変更によって、それらがなされることもあれば、スポーツ内における「流行」によって変化することあります。そのようなことは、しばしば、熟練したプレイヤーによる卓越したプレイによって起こります。つまり、あるプレイヤーの開発したテクニックが広く受け入れられたり、それによって以前まで顕著だった技術が廃れたりするのです。
卓越性の量
あるスポーツにおける「卓越性の量(Quantum of Excellence)」は、そのスポーツで実現されている、あるいは実現可能な卓越性の合計(the amount of excellence)に関係するものです。卓越性の観点からは、スポーツにおける卓越性の量を減少させるような規範、ポリシー、慣習は、全面的に反対されます。つまり、卓越性の量は多ければ多い方がよいということになるのですが、その卓越性は当のスポーツが持つ卓越性のクラスタから引き出されているものでなければなりません。

ディバインは、あるスポーツが「アマチュアスポーツからプロスポーツへ移行」することを考えてみるように促します。このような変化によって、選手は、スポーツで試されるさまざまなスキルを身につけ、そのスポーツが要求する身体的な達成に、よりきめ細かく対応できるように身体を発達させるため、より多くの時間、よりよい資源、よりよいコーチングを得ることができるようになります。その結果、熟練者レベルでのプレイの平均レベルは一般的に向上し、そのスポーツの卓越性が以前よりも「多く」参加者の間で実現されるようになります。つまり、卓越性の量が増えるので、こうした移行は歓迎されるべきものであるわけです。
このように、スポーツにおいて達成されるプレイのレベルに影響を与えるものはすべて、その卓越性の量に変化を与える可能性がある。ディバインは例として、走り高跳びの「フォスベリー・フロップ」やテニスの「オーバーアーム・サーブ」といった、生体力学的に優れたテクニックが発見され、そのスポーツで広く採用されるようになれば、ルールに変更がないにもかかわらず、そのスポーツの卓越性の量が増加することになることを指摘しています。
卓越性の明瞭さ

ディバインは、卓越性は、ただ単に発揮されるだけでなく、それが発揮されているように見えるべきであることを指摘します。卓越性の明瞭さ(clarity of excellence)とは、スポーツの卓越性の知覚可能性であり、また、卓越性を他の成績決定要因から切り離すことができる度合いです。卓越性の明瞭さは、あるスポーツのクラスタにおいて特徴的な卓越性を見分けることができるかどうか、また、その卓越性がどの程度パフォーマンスに寄与しているかを正確に見分けることができるかどうかの両方に関するものです。このような明瞭さは、体操やフィギュアスケートのように、競技結果が審判員による採点に基づいて決定される「審判スポーツ」にとっては特に重要なものとなります。
卓越性を明瞭にすることは、優れたパフォーマンスを正確に評価するためにも、信頼できるルールの適用を保証するためにも重要となります。例えば、熟練したアーチェリープレイヤーが発揮する重要なスキルの一つは、競技中の熱気においても完全に静止する能力です。ほんのわずかな動き(心臓の鼓動による震えでさえも)が、射撃の精度を損なう可能性があるので、競技者は競技中に心拍数を下げるための心理的テクニックを開発し、心拍と心拍の間に矢を放つことができるようにしているそうです。しかし、心拍を下げる効果を持つβ遮断薬は、心拍をほとんどコントロールできない射手に対して、上記のような心理的テクニックをマスターするのと同等の生理的鎮静効果を与えることができてしまいます。その結果、β遮断薬はアーチェリーの核となる技術を見極めにくくしてしまうという点でよくないものなのです。

また、明瞭さの議論は、多くの場合、私たちがあるパフォーマンスを評価する際には、その選手が発揮した卓越性の種類と程度に非常に敏感でなければならないという関心に基づいていています。特に審判スポーツにおいては、審判員が卓越性の発揮を知覚できることが極めて重要になります。しかし、専門家や審判員だけでなく、選手自身にとっても、卓越性を認識できることが重要となるのです。というのも、スポーツ選手は、自分のパフォーマンスが、自分が発揮した卓越性をどの程度反映しているのかを見極めることができなければ、熟達した感覚をほとんど味わうことができなくなってしまうからです。明瞭さは、観客のいないところで行われる審判のいない試合でも生じる懸念なのです。
卓越性のバランス

スポーツのクラスタ内の卓越性は、特定の階層的な関係を示すことがあります。あるスポーツのクラスタ内に含まれているそれぞれの卓越性は、どれも、ある程度は競争結果の適切な決定要因となりますが、クラスタ内のいくつかの卓越性は、他のものよりも重要であるべきなのです。私たちは、ある特定の卓越性がテストされることだけを気にするのではなく、それがそのスポーツで成功した人たちのパフォーマンスにある程度寄与していることも気にしています。サッカーのリオネル・メッシや、テニスのセリーナ・ウィリアムズなどは、そのスポーツの「卓越性の模範」となるような選手たちです。
卓越性のバランスに関する懸念が生じるのは、そのスポーツで成功している人たちによるプレイ方法の変化によって、そのスポーツのクラスタの中で、特定の卓越性が他の卓越性よりも相対的に重要視されるようになったときであるとディバインは指摘しています。ある卓越性は、卓越性の模範となる競技者のパフォーマンスにおいて、他の卓越性よりも大きな貢献をするべきなのです。パフォーマンスに大きく貢献するべき卓越性が周縁的な役割に追いやられ、その結果、脇役であるべき別の卓越性が重要性を増した場合、卓越性のバランスが崩れ、修正が必要になる可能性が高いと言えるでしょう。

例えば、サッカー選手にとって、スローインは周縁的ではあるがある程度パフォーマンスに関連性のある卓越性です。スローインはプレイを再開するための手段として使われますが、成功してもボールを保持するチャンスが増えるだけで、ゴールに直結することはほとんどありません。しかし、もし選手がスローインのスキルを向上させたり、ボールがより簡単に宙を舞うように設計し直されたりして、スローインが非常に重要な攻撃機会となれば、サッカーの卓越性のバランスは変化し、スローインが試合結果において新たな優位性を獲得することが予測されます。その場合、ボールを投げる距離を制限するためにスローインを規制する必要があるかもしれないのです。
実際に、90年代か2000年代初期にかけてのウィンブルドンはその好例となるとディバインは言います。この時期の男子テニスの選手権大会は、強力なサーバーたちが席巻していました。この時期では、強力なサーブが大きすぎるアドバンテージとなるため、戦略重視な選手はあまり勝てなくなってしまっていたのです。テニスは戦略的なセンスや戦術的な洞察力を尊ぶスポーツでしたが、ビッグサーバーの時代には、そのようなスキルの重要性は薄れていってしまっていました。そうした傾向に歯止めをかけるため、ウィンブルドンでは、主に、コートの構成と硬さが変更され、より高く安定したバウンドを促し、その結果、長いラリーが可能になるという変更がなされたのです。そして、こうした変更は、望ましい卓越性のバランスを取り戻すようになされたものなのです。

卓越性のバランスは、競技において卓越性クラスタを構成する各々の卓越性が互いに望ましい関係にあるかどうかに関係し、最も重要とみなされる卓越性の発揮が、卓越性の模範となるような人々によるプレイのあり方において大きな意味を持つのです。卓越性のバランスという概念は、特定のかたちの均衡が存在し、そこから逸脱するものは卓越性のバランスに反することを示唆しています。しかしながら、卓越性のバランスとは、唯一のプレイ様式だけを規定するものではなく、一定の範囲を認めるものであり、いわば、プレイにおける望ましい「パラメーター」の形を規定するものです。実際、テニスの例が示しているよう、卓越性のバランスは、複数のプレイスタイル(例えば、ベースライナーとサーブ&ボレーヤー)が共存するように設計されていることもあるのです。
卓越性とプレイスタイル

ここまでディバインは、卓越性に4つの要素があり、それぞれに適応した、卓越性の促進のされ方や損なわれ方が考えられることを示してきました。ディバインの議論は、卓越性を原理として、それぞれのスポーツのルールや望ましいあり方、実際のあり方が流動的なものであり、その移行がどのようになされていくかを明確にしてくれている点で、非常に有用な研究なのではないかと思います。
今回の議論はディバインも示唆しているとおり、スポーツ以外にもある種の「スキル」が重視される実践において広く適用できるものなのではないかと思います。例えば、ディバインが例に挙げていたのは伝統的なスポーツでしたが、eSportsにもほとんど同じように適用できる論だと思います。

また、ディバインの論は、総じて、個々のプレイヤーのプレイやプレイスタイルなどが、かなりの程度で意識されています。手前みそになってしまいますが、私自身も「プレイスタイル」について論じた論文で今回のディバインの論を引用しています。
そこではしている議論を少しここでも引きましょう。プレイスタイルは時に、プレイヤー間での議論の対象となることがあります。要するに、どんなプレイスタイルが尊重されるべきで、どんなプレイスタイルが排除されるべきなのか、というような議論です。そうした議論をするときに、今回ディバインが提示した4つの要素を用いると議論をよりよく進められるかもしれません。例えば、FPSという対戦ゲームのジャンルがありますが、そこではしばしば、用いられるデバイスの差異に基づく論争(いわゆる、「キーマウVS PAD論争」など)が勃発します。そうしたときに、今回で言うと例えば「卓越性の明瞭さ」といったスコープを持ち出すことで、何が問題となっているのか、また、どのように議論を進めるべきなのか、ということが格段にわかりやすくなるのではないかと思います。
このように、今回のディバインの論のような研究は、スポーツ哲学内だけでなく、スポーツ実践(もしかしたらそれを越えた領域においても)における諸議論にとっても有用なものとなるのです。

美学者とは
美学者の役割
- 【美的判断】なぜある人が「美しい」と感じる対象を、別の人は「そうでもない」と思うのか
- 【芸術作品の価値】作品が私たちの感性に与える影響を、どう評価し、言葉で説明できるか
- 【日常の美】ファッションやインテリアなど身近なところに潜む「美しさ」をどのように考えるか
こうした問いに取り組むのが美学者の役割です。近年では、ゲームの体験やデザイン、スポーツや身体表現、さらにはSNSなど、従来は「美学」とはあまり結びつかなかった分野にまでその探究範囲が広がっています。哲学や芸術学と深く関係しながら、現代社会のあらゆる「感性の問題」に光を当てるのが、美学者と呼ばれる人々なのです。

【PROFILE】
北海道帯広市出身。早稲田大学文学研究科博士後期課程在籍。専門は、ゲーム研究、美学。主な論文に、「個人的なものとしてのゲームのプレイ: 卓越的プレイ、プレイスタイル、自己実現としての遊び」『REPLAYING JAPAN 6』、「ゲームにおける自由について──行為の創造者としてのプレイヤー──」『早稲田大学大学院 文学研究科紀要 第68輯』。ゲームとファッションとタコライスが好き。