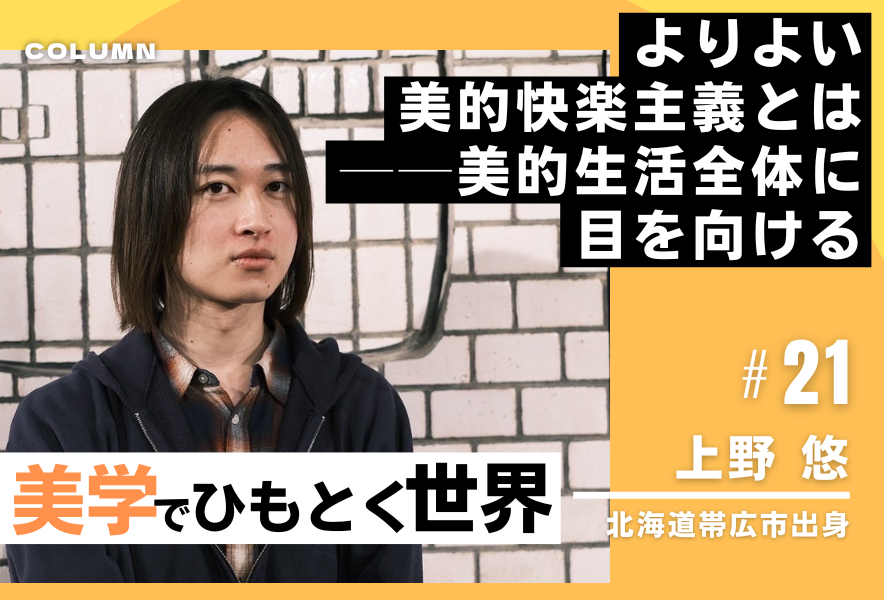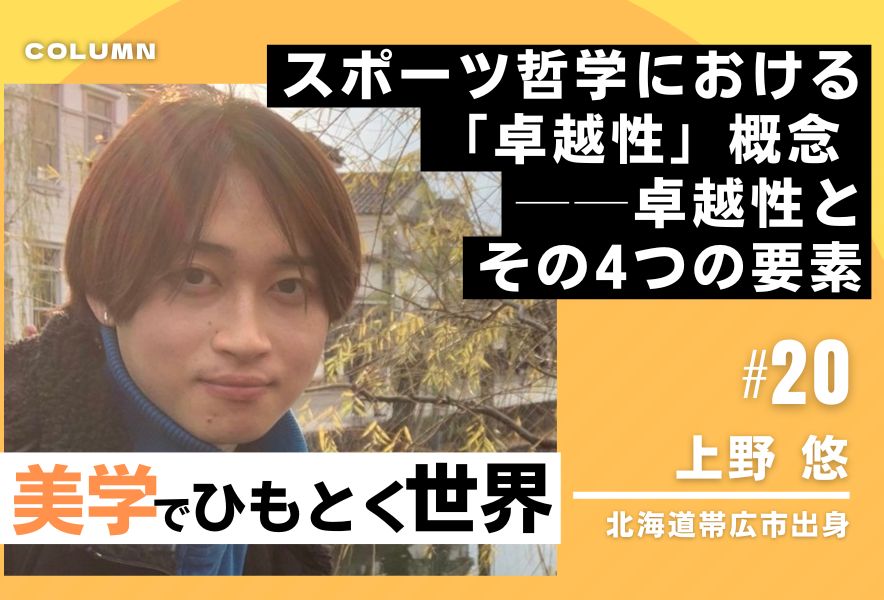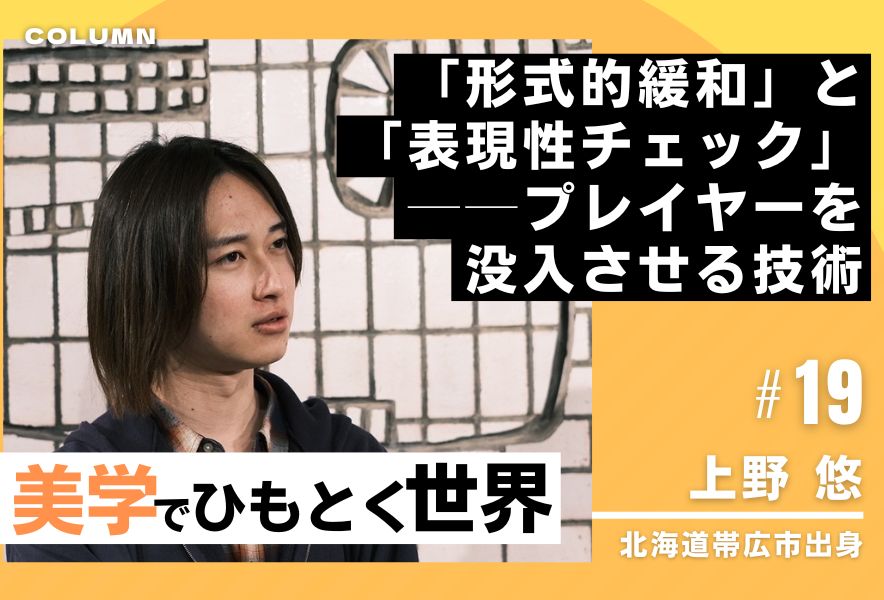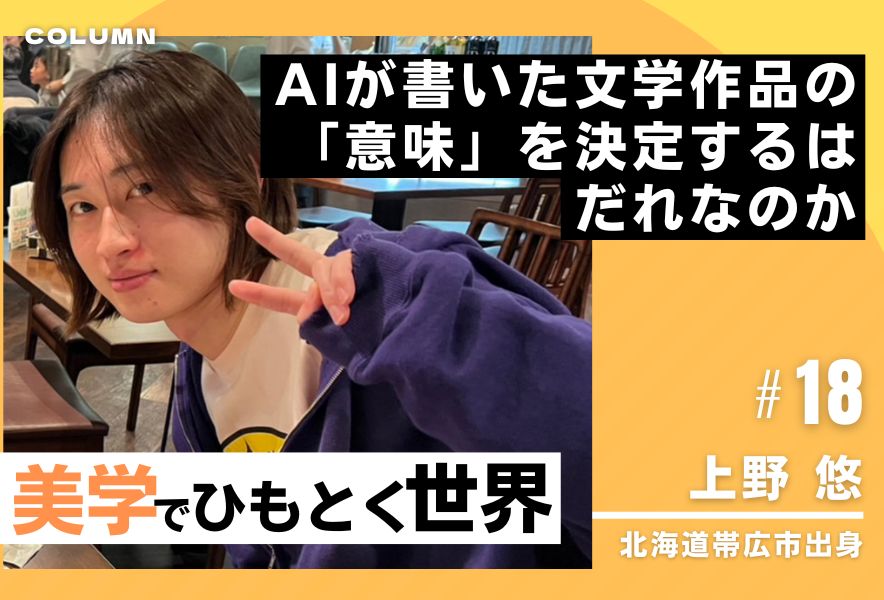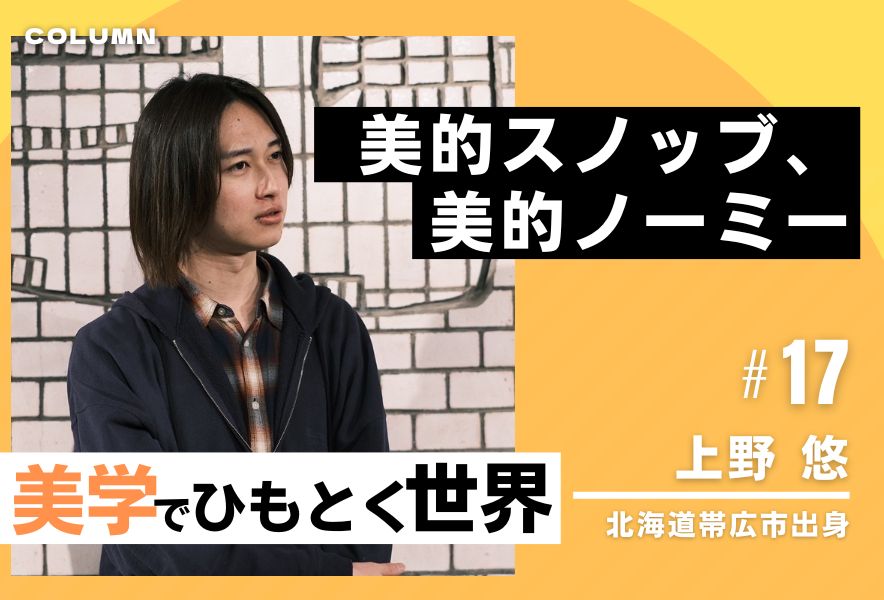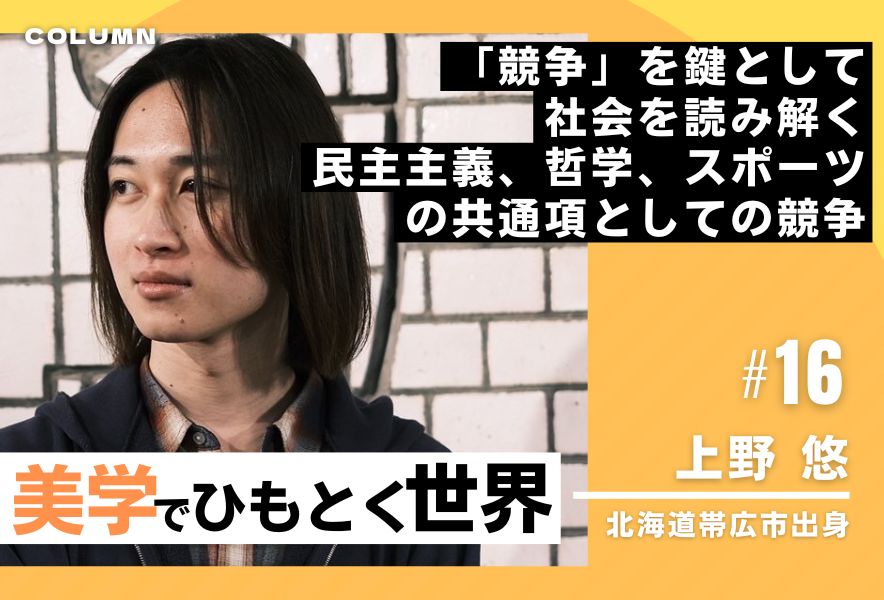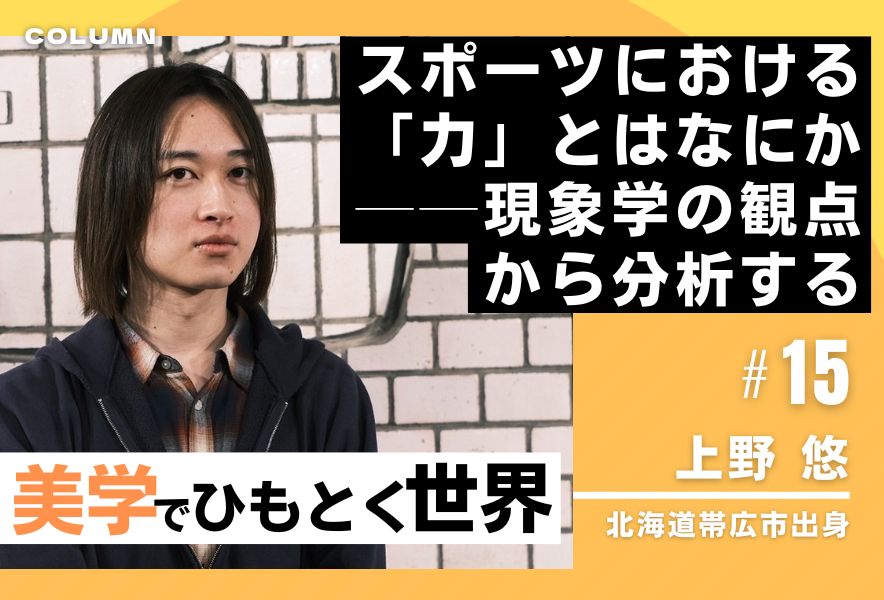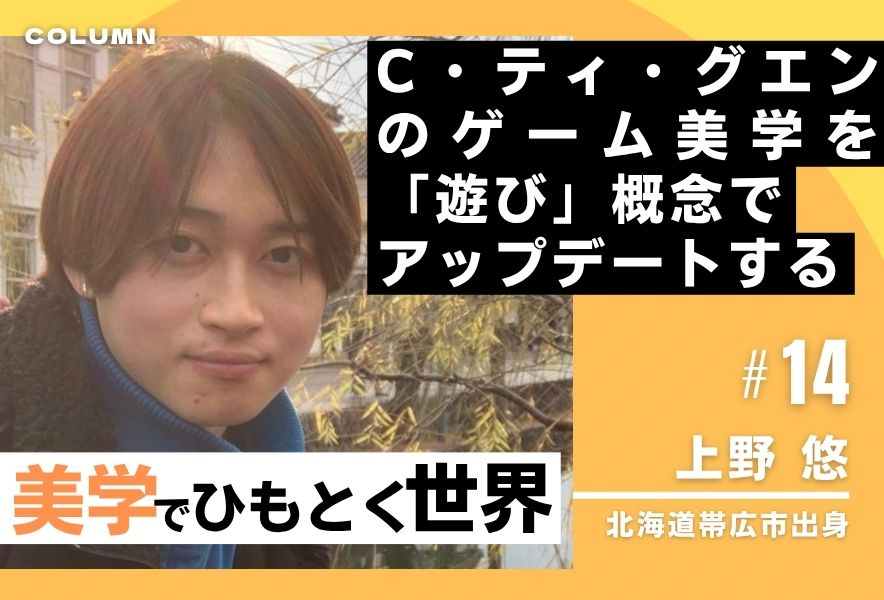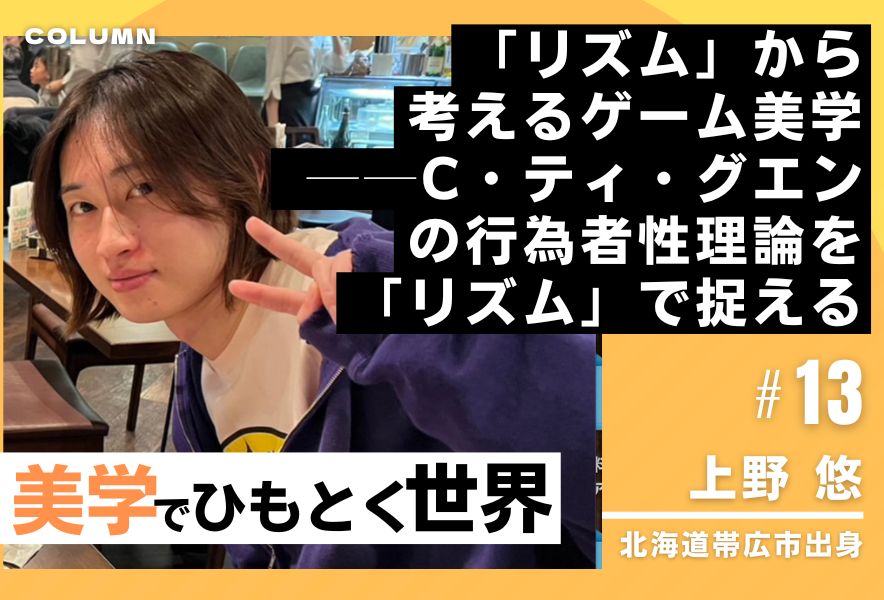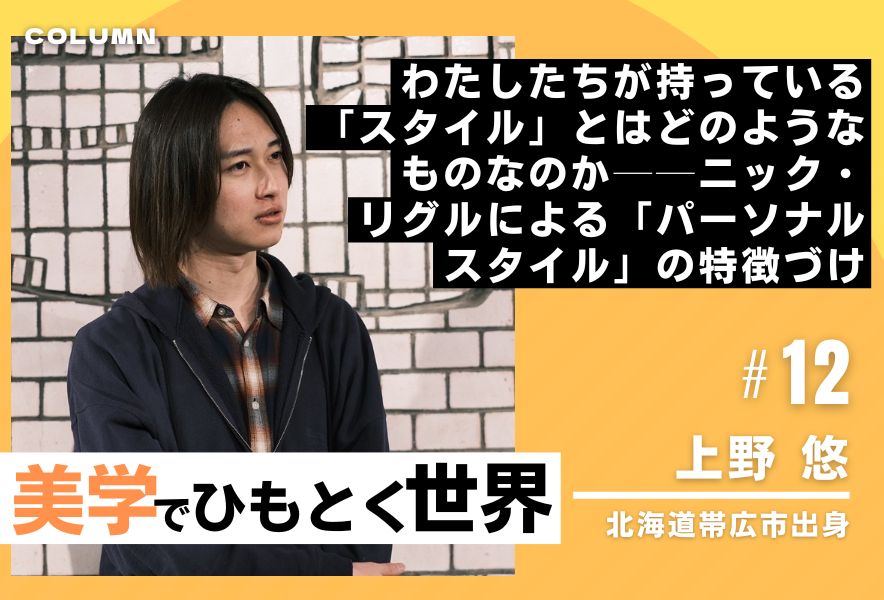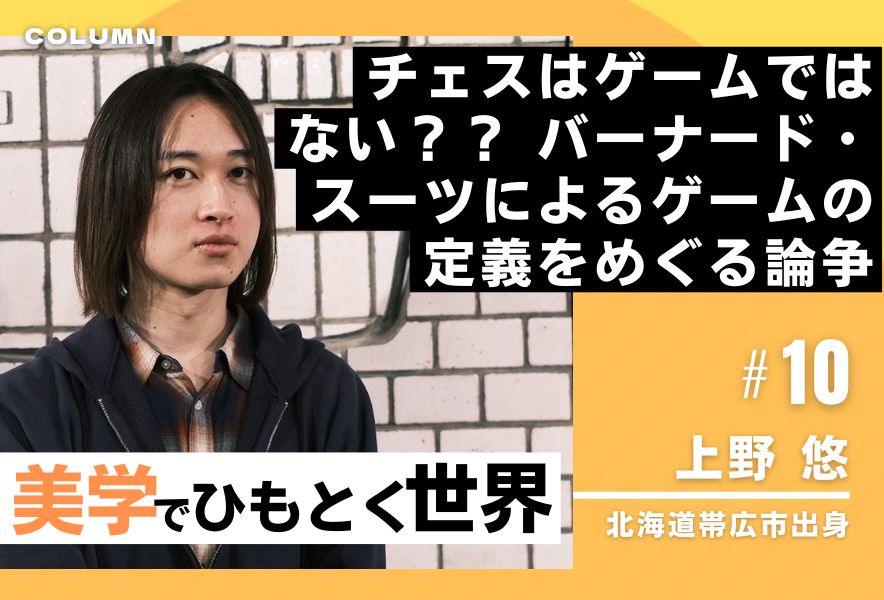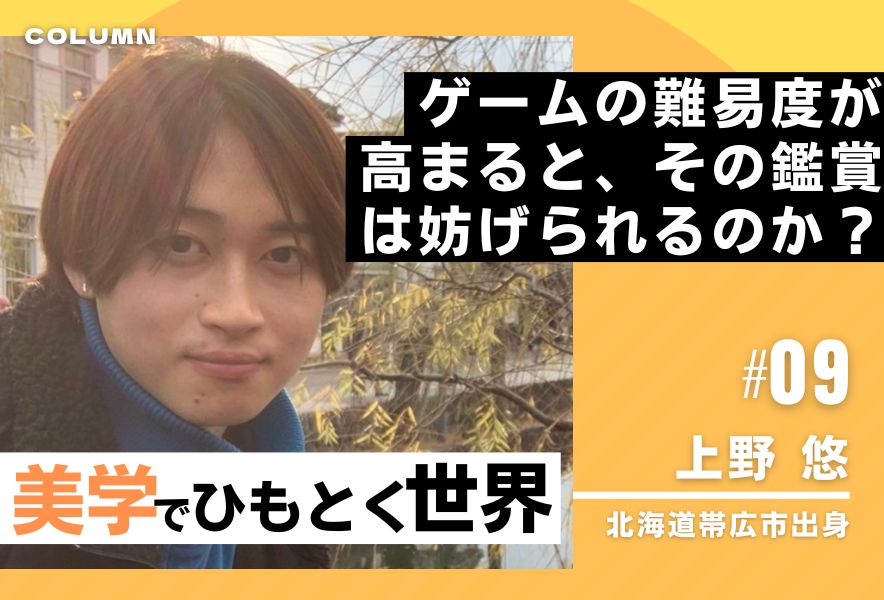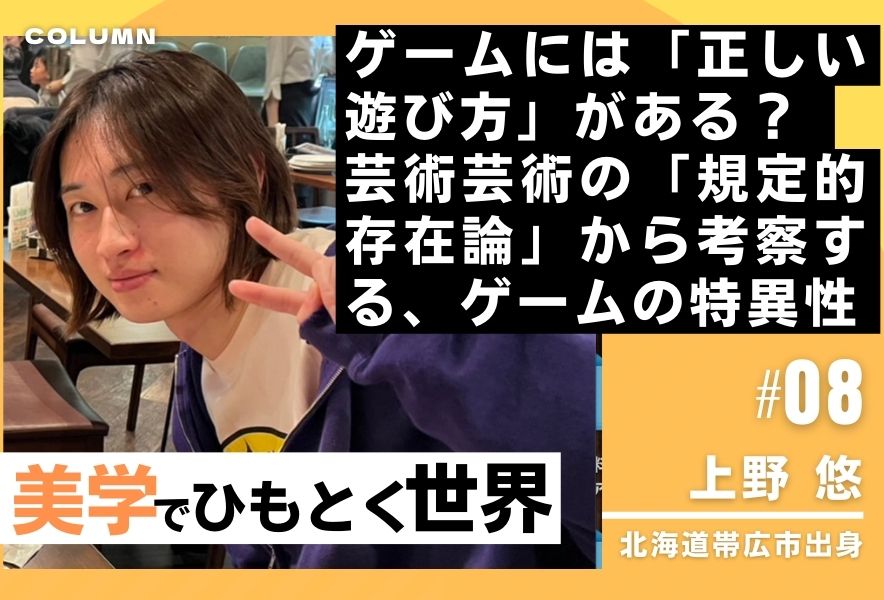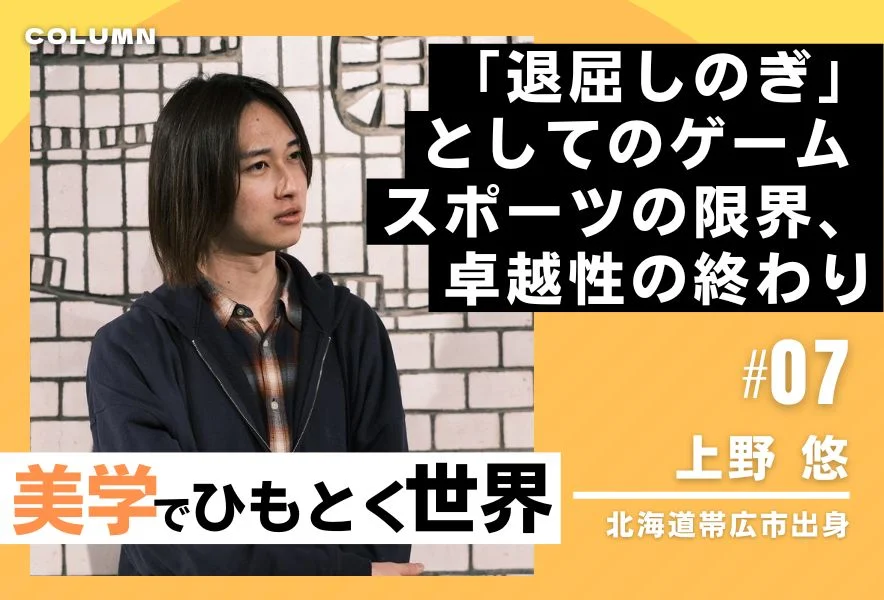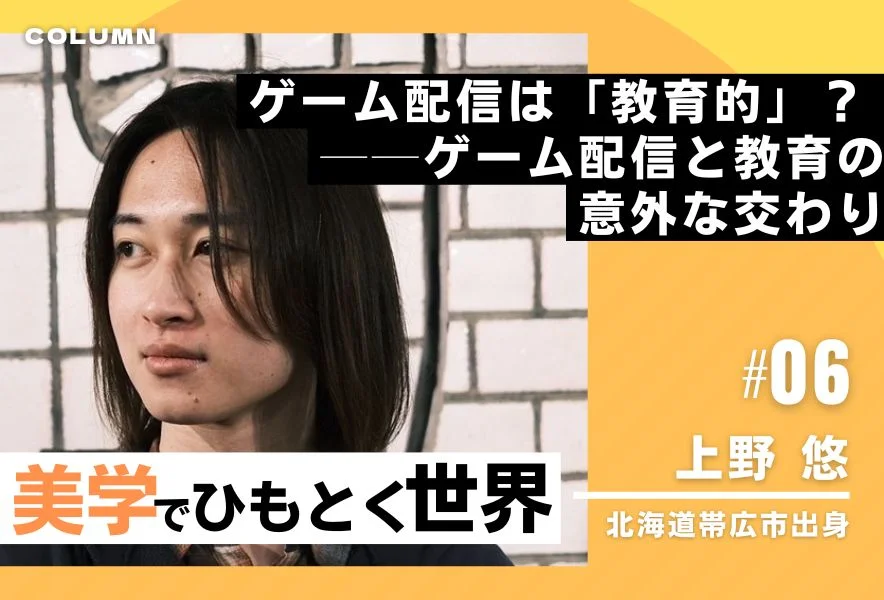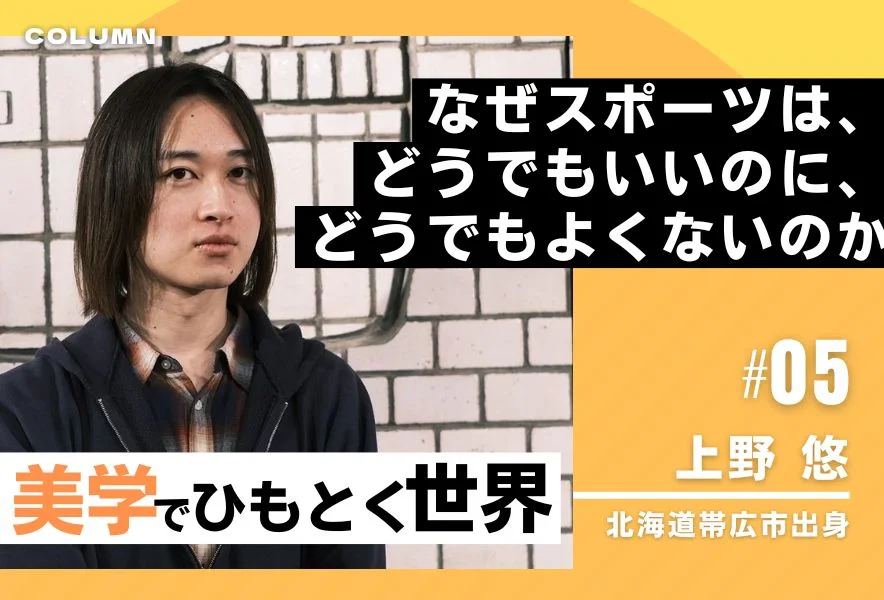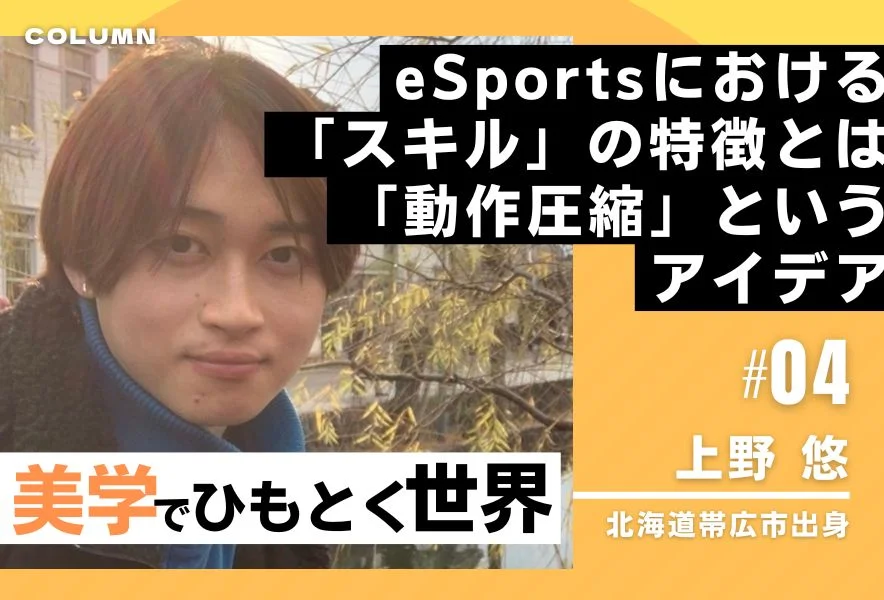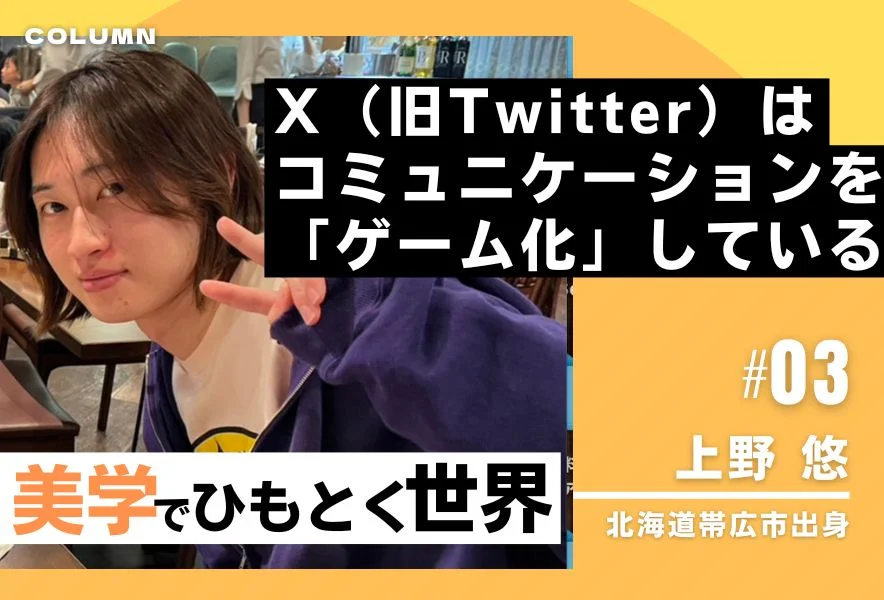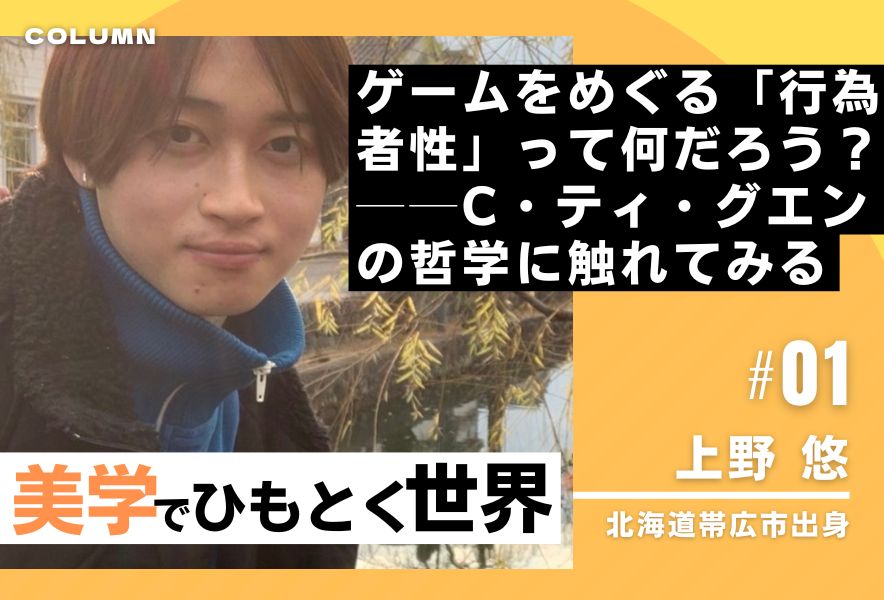【連載】美学者 上野悠の「美学でひもとく世界」
美的価値

モネの『睡蓮』のような芸術作品や、雄大な自然の景色、味わい深いコーヒーなど、われわれは、身の回りにあるさまざまなものを見たり、聴いたり、味わったりして、その美しさや、優美さ、キレのよさなどといった諸性質を感じ取りながら、それらを楽しみます。
このとき、そうした性質(=美的性質)を感じさせてくれるようなものには、なんらかの価値があるように思われます。こうした、美的なものに宿る価値を「美的価値」と言います。
美的価値をめぐる議論は、ここ数年ほどで大きな盛り上がりを見せています。というのも、これまで美的価値の理論としてデフォルトのものであった「美的快楽主義」という立場に対して、様々な批判やその代替案の提示がおこなわれているからです。
美的快楽主義
まず、美的快楽主義(以下「快楽主義」)とはどのような立場なのでしょうか。快楽主義のテーゼはかなりシンプルで、大雑把に言うと、芸術作品を代表とする美的アイテムの持つ美的価値は、それがもたらしてくれる経験の好ましさに由来している、というものです。この快楽主義は長年美学におけるデフォルトの立場(=一番強い立場)だったのですが、近年これに対しさまざまな反論や議論が巻き起こっているのです。
そうした議論のうちの一つとして、マシュー・ストロールとC・ティ・グエンは、ジェームズ・シェリーによる快楽主義への有名な批判に対して、むしろ、快楽主義の改訂および擁護を試みています。前提として、彼らは美的価値について、それぞれの多元主義的立場をとっていることを表明していますが、快楽主義の擁護を通して、快楽主義へのより良い理解に到達したり、そうして得られる洞察が彼らの多元主義へ貢献したりすることを望んでいるようです。
「過大評価」の問題

さて、ジェームズ・シェリーはどのようにして、快楽主義へ批判を突きつけているのでしょうか。
快楽主義の最もシンプルなバージョンは、「芸術作品の価値は、それが与える美的快楽にある」とする考えです。ここから、合理的な推論として、「われわれは、対面した芸術作品から、できるだけ多くの快楽を引き出すべきである」ということが導き出されます。快楽主義からはこのことが順当な帰結として引き出されるのです。
シェリーはこの点に目を向けて反論を組み立てます。もし上記のようであるならば、ある作品の「正しい解釈」が、その作品がもたらす美的快楽の量を減らしてしまうような場合、われわれはその正しい解釈を採用せずに、ひたすら美的快楽を増やしてくれるような解釈を──たとえそれが誤った解釈だったとしても──受け入れるべきであるということになってしまうのです。
このような考え方には明らかに問題があります。芸術作品を鑑賞する者は、その作品を正しく理解するべきであるという規範がかなり強い度合いで存在しているように思われるからです。このことは、芸術作品にはそれぞれたった一つの正しい解釈が存在している、ということを含意しているわけではありません。そうではなく、三島由紀夫の『金閣寺』をラブコメとして読むのは──たとえそのことによって美的快楽が最大化されるとしても──正しくない鑑賞である、というようなことです。
シェリーはこうした考えに基づいて、芸術作品の「過大評価」の可能性──作品を高く評価しすぎることは可能であり、それは避けるべきことである──を快楽主義は示すことができない、ゆえに間違っているのだ、と主張しているのです。
生活全体へ目を向ける

ストロールとグエンは、シェリーのこうした批判に対して、美的快楽主義を改定する形で擁護しようとします。彼らの取る戦略とは、ひとことでいうと、「美的生活へのズームアウト」です。彼らは、シェリー(とシェリーが批判対象としているジェラルド・レヴィンソン)のように、「特定の作品との特定の出会い」の場面を問題にするのではなく、もっと長い目で見た、「美的生活の全体」を問題にして考えようとしています。
二人によるシェリーへの再反論を見てみましょう。彼らは、シェリーが「過大評価」という傘の下で、以下のような二つの異なる現象を誤解していると言います。
- 過剰な楽しみ(over- enjoyment)
…作品を過剰に楽しむことによって、その作品を過大評価する - 誤判断(misjudgement)
…作品の持つ快楽を与える能力を誤って評価することによって、作品を過大評価する。
彼らは、快楽を得ることと、快楽を与える能力について判断を下すこととは別のことであることを指摘し、それらが離れてしまうケースを示します。
まず、ある作品を、それに対する事前の期待が高かったがゆえに、それがほんとうは期待外れだったとしても、そうした自分の気持ちを誤魔化して作品を高く評価してしまう、というケースが挙げられています。二人によると、これは、作品によって与えられた快楽を誤って判断してしまっているという点で、誤判断に分類される過大評価です。
次に、経験した快楽を正確に認識できていても、対象の快楽を与える能力を誤判断してしまうというケースです。ストロールは、あるアルバムを聴いてその作品から多大な快楽を得て、それを高く評価しましたが、何度も聴いてしまったことによって、作品の「底が抜けて」しまい、むしろその作品に嫌気がさしてしまった、という例を挙げています。それは、彼がこのアルバムに快楽を感じすぎていたということではなく、彼の最初の評価が、このアルバムが喜びを与える長期的な能力については誤って判断してしまっていたということなのです。
3つ目に挙げられているのが、快楽の相対的価値を見誤ってしまうケースです。我々は、ある作品からできる限りの快楽を得ていたとしても、その快楽を最高の快楽であると誤認してしまうことがあるのです。グエンは、(若い頃に)マクドナルドのフィレオフィッシュを最高の快楽を与えてくれる料理であると誤認してしまっていた、というケースを挙げています。

そして、こうした例から引き出される重要な点として、この種の過大評価は、美的生活において現実的な障害として作用することがあるが述べられています。というのも、もしある人が、何らかの対象から、可能な限り最高の快楽を得たと考えれば、それ以上の美的な探求をしなくなるかもしれないからです。
さて、一方には「過剰な楽しみ」があり、これは作品に対して適切以上の喜びを感じることです。もう一方には「誤判断」があり、これは作品が私たちに与えてくれた、あるいはさらなる関与によって私たちに与えてくれる可能性がある、快楽の量を誤って評価すること、でした。ストロールとグエンは、シェリーの反論はこれらのうち、あくまで、過剰な楽しみに関するものであり、誤判断の可能性は認めていないことを指摘します。
それに対し、ストロールとグエンは、この誤判断に訴えることで、快楽主義者が過大評価をしないようにする正当な理由が生まれることを主張しています。過大評価が、私たちの美的探求の妨げになったり、誤った推奨につながったりすることで、私たちは可能な限り最大の快楽を逃してしまうことになるのです。このことを二人は「もし、マクドナルドのフィレオフィッシュ以上の快楽はないと考えるならば、他の食べ物を求める欲求はなくなる」のだと表現しています。
二人は、快楽主義の可能性に対するシェリーの過小評価は、真空地帯で孤立した芸術鑑賞の特定のエピソードの分析に囚われているせいであると指摘しています。そうではなく、「ズームアウト」して、そのようなエピソードを事後的に振り返ったり、同じ作品に関わり続けたりするような、美的生活全体を考えることで、快楽的な過大評価の可能性が見えてくるのです。今この瞬間の過大評価は、たとえそれがその瞬間においては十分な快楽を提供するとしても、より大きな、未来の快楽を阻むものとして作用してしまうのです。
快楽主義の正当化へ向けて

では、ストロールとグエンは、そこからどのように美的快楽主義をよりよいものに変えていくのでしょうか。
彼らはまず、ディヴィッド・ヒュームの論を参照し、洗練された識別能力がよりよい快楽を可能にするのだという考え方を取り出します。こうした考え方の魅力と妥当性を示すために、彼らは再びマクドナルドの例を出します(マクドナルドが好きな人ごめんなさい)。
この世の多くの人は最初、マクドナルドの味が大好きです。しかし、その後、彼らはマクドナルドの欠点がわかるようになり、一方で、例えば、きちんと丁寧に時間をかけて調理された自家製の煮込み料理に価値を見出すようになります。じっくり煮込んだ自家製煮込み料理を一度も食べたことがない人は、マクドナルドがこれ以上ないほど美味しいものであると思い続けるかもしれませんが、自家製煮込み料理の味わいがわかるようになった人で、マクドナルドの料理が最上級の美的価値を持つと思うようになる人はほとんどいないと考えられます。
彼らによると、快楽主義者は、こうした進歩を、より洗練された快楽を新たに知ったという観点から説明することができるのです。識別能力と知覚の発達が、煮込み料理の優れた快楽を経験することを可能にし、それとトレードオフのようにして、マクドナルドの欠点に気づかせるようになるのです。このように、快楽主義の正当性を主張するためには、過大評価を発見し、それをなくしていくことが、よりよい快楽への長期的なアクセスを可能にする感覚的・認知的発達の過程と合致していることを示せればよいのです。
「目利き」とウォルトンのカテゴリー論

というわけで、ストロールとグエンは、快楽主義が、芸術作品との特定の出会いの場面において、得られる快楽を減らしてしまうことになるような、センスの洗練を正当化するための方法を2つ提示しようとします。
一つ目が、ケンダル・ウォルトンのカテゴリー相対的な芸術理論に訴えるものです。ウォルトンのカテゴリー相対理論とは、作品の持つ美的性質は、(目や耳などで)直接知覚できる以上のものにも依存しているとする論です。では何に依存するのかというと、その作品が位置付けられる「カテゴリー」なわけです。この場合のカテゴリーとは、「絵画」や「映画」、あるいはもっと絞って、「モダニズム絵画」や、「アメリカン・ニューシネマ」のようなものが例として挙げられるような抽象的存在物です。
つまり、作品の持つ美的性質は、作品が属するカテゴリーにとって、作品から知覚される諸特徴のどれが標準的であるか、反標準的であるか、あるいは可変的であるかに左右されるのです。あるカテゴリーにとって標準的な特徴とは、作品をそのカテゴリーに含める資格を与える傾向にあるものであり、逆に標準的でない特徴とは、作品をそのカテゴリーに含める資格を失わせる傾向があるもののことを指します。絵画が平らであることは標準的であり、絵画がチーズでできていることは反標準的なわけです(これはストロールとグエンが出している例です)。このどちらにも属さないものが可変的ということになります。そして、作品制作におけるだいたいの操作はこの可変的特徴の中で行われます。
さて、こうしたカテゴリー相対的な理論は、作品に対する鑑識眼を持った人=目利きが、よいよい美的快楽にアクセスできるとされていることを説明してくれます。つまり、目利きとはそのカテゴリーに知悉した人であり、そのカテゴリーにおける標準的・半標準的・可変的特徴を見分けることができるのです。

しかし、こうした見分けは、時に美的快楽の現象を招きます。このことを二人はプーアル茶の例を出して説明します。プーアル茶は熟成によって独特の美的性質を獲得しますが、プーアル茶に親しみのない人はこれを嫌い、むしろ若くてフレッシュな方を好む傾向にあると考えられます。しかし、目利きはむしろフレッシュなプーアル茶を平凡なものとして、熟成されたものを非常によいものとしてみなし、前者の快楽をいくぶんか失う一方で、後者の味わいを楽しむことができるのです。このようにして二人は、カテゴリーの学習と美的能力をむすびつけ、その過程が、より大きな先の楽しみのために、手前にある楽しみを失うことをもたらすことを説明します。
細部にこだわる美的関与のプロセス
二つ目のアプローチは、著者の一人であるグエンの提示した美的鑑賞のゲーム的性質に訴えるものです。
グエンによれば、私たちはしばしば芸術作品について、正しい判断を得ることを目指します。そのために、私たちは作品の細部までじっくりと観察し、自分の解釈が合っていることを確認しようとするのです。しかし、グエンは、こうした過程において、私たちは正しい判断を得ることだけを気にしているわけではないことを指摘しています。というのも、芸術作品について正しい判断を下す最も簡単な方法は、専門家に委ねることですが、私たちは必ずしもそうしようとせず、作品の細部の観察にそくして、自分自身で判断を下そうとするのです。
グエンはこうした現象を、ゲームの構造と類比的に捉えようとします。ゲームでは、わたしたちは目標(例えば、マラソンにおけるゴールテープ)に向かって奮闘しますが、その奮闘は目標そのものと言うより、それによってもたらされる手段に基づく活動にこそ価値を見出しているのです。

つまり、芸術鑑賞において私たちは、作品の正しい理解を得るという目標そのものではなく、それに至るまでのプロセスの方を求めて、そうしているのだ、というわけです。私たちが直接的な快楽を減らしてまで正しい理解を得ようとするのは、そうすることで得られる解釈のプロセスにより大きな快楽を見出しているためなのだ、というのが、彼らの2つ目のアプローチです。
改良された快楽主義
ストロールとグエンは、ある作品との出会いにおける快楽の損失は、他の作品との出会いにおける快楽のより大きな見積りを認識することによって、それを上回ることができると主張してきました。彼らは、「わずかに改善された美的快楽主義」とは、単にその事実を認めるだけであると述べています。

さらに二人は、そこから一歩踏み込みます。というのは、逆算的に、作品との出会いの価値とは、その作品に触発される様々な関与──見ること、探すこと、解釈すること、思索すること──によって顕在化(cash out)されるものであるということです。つまり、作品の価値とはそれにまつわる様々な行為を触発することにあるのです。しかし、より重要なものとして、彼らは、特定の作品との実際の出会いを超えた、別の種類の価値ある美的活動を想定していることです。そのうちの一側面として、彼らは、美的生活の価値の一部は社会的なものであり、それは芸術について語り、議論し、ランク付けし、批評し、それについて書くといった活動のうちにあるということを示唆しています。
彼らにとって、美的快楽とは、作品との単一の出会いだけでなく、美的生活全体を通じて蓄積されていくものなのです。さらには、成長の過程そのものが快楽となることもあることも指摘されています。
ストロールとグエンは、最終的に彼らの提示する快楽主義を「関与的快楽主義(engagement hedonism)」として次のように定式化します。
- 美的価値は、美的快楽から成る、あるいは美的快楽から派生する。
- 美的快楽は、美的生活のさまざまな活動を通して見出すことができる。作品との出会いにおいても、美的生活のより大きな社会的・教育的活動においても。
- 自己開発(self-development)のさまざまな側面の価値は、美的快楽の生涯にわたる増大という観点から顕在化されうる。
美的エリート志向
以上のように、彼らは、美的生活において快楽を追求する最善の方法は、あらゆる場面で快楽を最大化しようとすることではなく、むしろ長期的な自己開発プロジェクトに取り組むことであると主張します。私自身の考えとしては、こうした考えにはおおむね同意します。彼らの説明は、私たちが「通」になろうとして努力することをうまく説明してくれていると思います。

しかしながら、こうした考えは従来の美的快楽主義とは違った意味で、エリート主義的であるとも言えそうです。前に紹介した、美的ノーミーのような存在は、自己開発プロジェクトに取り組めていない者(意志の弱い人)として処理されそうな気がします。そのことを良しとするのか、どの程度エリート主義的な側面を認めるのかは気になるところです。
また、彼ら自身も認めていますが、彼らの論は、洗練度の高いものと低いものを比べたときに、後者を好むような人には効力が低くなります。より洗練度が高いものの方がよりよい快楽を与えるはずだ!という前提に関しては、私たちの直観に訴える形で処理しています(これも彼ら自身認めています)。実際、今回の論に対し少なからず反感を覚えたような人にとってはこの点がひっかかるのではないでしょうか(そんなことを言われても自分はマックが好きだ、みんながみんなマックより凝った料理の方がいいというわけじゃなくない?などなど)。また、趣味の悪いものをあえて評価するような実践とも相性が悪いかもしれません(俺はあえてマックをほめるんだぜ!という人)。おそらくはこうした人々や実践は最初から説明の範囲の外にあるのだと思われますが、こうした例をとっかかりにして、今回の論に対する反論やオルタナティブについて考えてみるのもいいかもしれません。
参考文献
- Strohl, Matthew, and C. Thi Nguyen. 2024. “Building a Better Aesthetic Hedonism.” Philosophical Topics 52 (1): 7–24.
Nguyen, C. Thi. 2020a. Games: Agency as Art. Oxford: Oxford University Press.
—-. 2020b. “Autonomy and Aesthetic Engagement.” Mind 129 (516): 1127-56.
—-. 2023. “Art as a Shelter from Science.” Aristotelian Society Supplementary 97 (1): 172-201.
Shelley, James. 2010. “Against Value Empiricism in Aesthetics”, Australasian Journal of Philosophy 88 (4): 707-720.
—-. 2011. “Hume and the Value of the Beautiful.” British Journal of Aesthetics 51 (2): 213-222.
—-.2019. “The Default Theory of Aesthetic Value”, British Journal of Aesthetics 59 (1): 1-12.
Walton, Kendall L. 1970. “Categories of Art.” Philosophical Review 79 (3) :334-367.
美学者とは
美学者の役割
- 【美的判断】なぜある人が「美しい」と感じる対象を、別の人は「そうでもない」と思うのか
- 【芸術作品の価値】作品が私たちの感性に与える影響を、どう評価し、言葉で説明できるか
- 【日常の美】ファッションやインテリアなど身近なところに潜む「美しさ」をどのように考えるか
こうした問いに取り組むのが美学者の役割です。近年では、ゲームの体験やデザイン、スポーツや身体表現、さらにはSNSなど、従来は「美学」とはあまり結びつかなかった分野にまでその探究範囲が広がっています。哲学や芸術学と深く関係しながら、現代社会のあらゆる「感性の問題」に光を当てるのが、美学者と呼ばれる人々なのです。

【PROFILE】
北海道帯広市出身。早稲田大学文学研究科博士後期課程在籍。専門は、ゲーム研究、美学。主な論文に、「個人的なものとしてのゲームのプレイ: 卓越的プレイ、プレイスタイル、自己実現としての遊び」『REPLAYING JAPAN 6』、「ゲームにおける自由について──行為の創造者としてのプレイヤー──」『早稲田大学大学院 文学研究科紀要 第68輯』。ゲームとファッションとタコライスが好き。