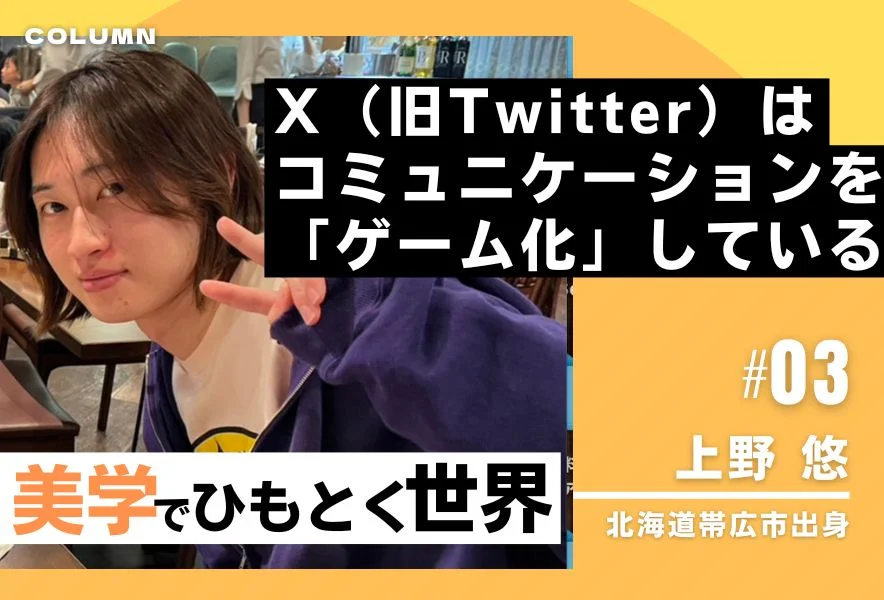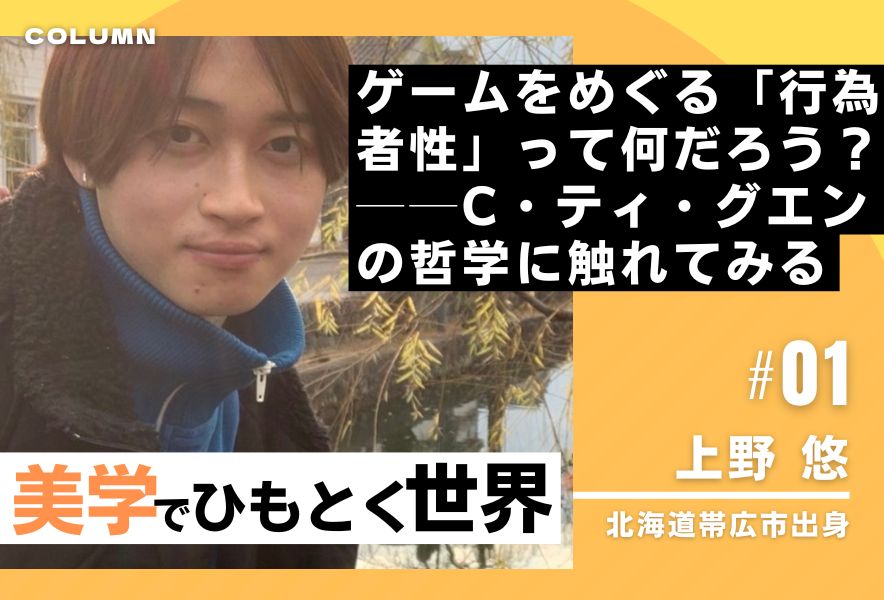【連載】美学者 上野悠の「美学でひもとく世界」
みんなだいすきツイッター

みなさんはツイッター、やってますか? なんていう聞き方がばかばかしくなるほどに、今やツイッターは、コミュニケーションツールとして、多くの人が当たり前のように使っているサービスとなっています。特に日本では利用率が全人口の半数に届きそうなくらいに普及しており、世界でも屈指のツイッター好きの国と言えます。
(※ツイッターは2023年に「X」と名を変えてしまいましたが、今回紹介する論文は2021年に発表されたものであり、「Twitter」の呼称が使われているため、本記事でも「ツイッター」と呼ぶことにします。)
ツイッターと言えば、情報を収集・発信するのに便利だったり、様々なツイートや動画コンテンツを見ることのできる「娯楽」としてのツールとしても好まれていたりして、どちらかと言えば「好き」な人が多いSNSなのではないでしょうか。さらに、ツイッター上では日々、独特のミームやノリが生まれては拡散されていっており、単なるコミュニケーションツールにとどまらない、文化の形成・維持の場としての側面も強まりつつあると言えるでしょう。
しかしながら、みんなだいすきツイッターには、そうしたよい面だけがあるわけではありません。
ツイッターはコミュニケーションを「ゲーム化」してしまう?

第一回でも紹介したユタ大学の哲学研究者、C・ティ・グエンは、ツイッターについて批判的な見解を述べています。彼が言うには、ツイッターはコミュニケーションを「ゲーム化」しており、それによって、人々がコミュニケーションを行う際の、本来多様なはずである価値観を画一化・単純化してしまう恐れがあるというのです。
ツイッターに愛着を持っている皆さんの中には、こうした論に反感を持つ人も少なくないかもしれません。そうした人はぜひ、その「反感」を胸に秘めたまま、これから紹介するグエンの論と対峙することで、自分なりの考えをより明確/明晰にする一助となれば、と思います。
コミュニケーションの「ゲーム化」とは?
では、ツイッターによってコミュニケーションが「ゲーム化」されてしまうとは、どのような事態を指しているのでしょうか。グエンはツイッターのもつ「数値化」の機能に着目します。みなさんご存じのように、ツイッターには「いいね」「リツイート」「フォロワー数」を表示する機能があり、それらの具体的な数値は、ユーザーがツイートを通して行うコミュニケーションに「点数をつける」ことになります。こうした機能は、数字がどんどん上がっていくのを見ることで、ツイッターに「中毒性」をもたらします。
さらにもう一つ、「点数をつける」以外に、いいね・リツイート数とフォロワー数は、それぞれ短期的/長期的な視点での「ランキング」を提供することになります。これによって、普通の会話とは異なり、どのツイート/ユーザーが最も人気を獲得しているか、ということを正確に把握し、比較することができるようになります。
背景にある「ゲーミフィケーション」への警鐘
グエンはツイッターのゲーム化について論じることで、同時に、安易な「ゲーミフィケーション」へ警鐘を鳴らそうとしています。ゲーミフィケーションとは、ざっくりいうと、ゲームでないものをゲームのような仕組みを取り入れることで、ジェイン・マクゴナガルという人がその代表的な支持者です。
ゲーミフィケーションの支持者たちは、ゲーミフィケーションは「モチベーションを高める技術」であると主張します。ゲーミフィケーションがモチベーションを高めるとは、どういうことでしょうか。そもそもゲームとは、「何らかの明確な目標を人為的に設けること」で成り立ちます。
例えば、サッカーは、「ゴールにボールを入れること」を目標として設定し、手を使うことを禁止することで「手段を制限する」ことによって、ゲームとして成立しています。ゲーミフィケーションは、そのようなゲームの仕組みの「一部」を利用し、コミュニケーションなどの現実の(ゲームでない)活動を、単純で明確な目標を「再設定」することによって、行為に対する報酬などといった形で「成功や進歩」も単純化・明確化します。ゲームがゲームであるうちは、こうした「目標と手段の明確化」は大きな魅力となります。
このようにゲーミフィケーションされる以前の「自然な」コミュニケーションには、「情報の伝達や説得」「友情」「真実の追求」といった複雑で多岐にわたる目的の分布がありました。しかし、ゲーミフィケーションされたツイッターでは、私たちは、「より高い、いいね・リツイート・フォロワー数の追求」という、あらかじめ用意された動機づけにシフトされるように誘われているのです。こうして、ゲーミフィケーションは、価値観を均質化してしまう恐れがあるとグエンは指摘しています。
ツイッターはコミュニケーションをどのように変えるのか
 しかし、こうした見方には以下のような反論も考えられます。いいね・リツイート・フォロワー数などを用いた、ツイッターの「採点」メカニズムが、ちゃんと様々な価値観をすくえるように機能しているのではないか、という反論です。実際、ツイッターのユーザーたちは、それぞれ異なった価値観を持っているはずです。それぞれのユーザーはそれぞれの価値観で、いいね・リツイートを押したり、他のユーザーをフォローしたりします。では、そうした個々人の賛同を集約する機能を持った、いいね・リツイート・フォロワー数は、多様な価値観に対して、全体的に成功したと言える有効な尺度となりうるのではないでしょうか。
しかし、こうした見方には以下のような反論も考えられます。いいね・リツイート・フォロワー数などを用いた、ツイッターの「採点」メカニズムが、ちゃんと様々な価値観をすくえるように機能しているのではないか、という反論です。実際、ツイッターのユーザーたちは、それぞれ異なった価値観を持っているはずです。それぞれのユーザーはそれぞれの価値観で、いいね・リツイートを押したり、他のユーザーをフォローしたりします。では、そうした個々人の賛同を集約する機能を持った、いいね・リツイート・フォロワー数は、多様な価値観に対して、全体的に成功したと言える有効な尺度となりうるのではないでしょうか。
グエンはこうした想定反論に対して、3つの点を並べて、再反論をしようとします。第一に「いいね・リツイートを押すのは瞬時の反応である」という点です。いいねやリツイートは、大抵の場合、ユーザーの“第一印象”で肯定的な反応である場合に行われます。それにより、いいねの数でコミュニケーションを評価することによって、私たちはユーザーが「すぐに」楽しめるようなコンテンツに偏ってしまい、熟考を促すようなツイートは成功しないようになってしまうのです。
第二に、「いいねやリツイートは、行為的な反応を示したユーザーの〈数〉を際立たせる一方で、反応の〈質〉を強調しない」という点です。いいねやリツイートは、するか/しないかという至極単純な二値によって測定されます。それにより、「少数だけど深く届くようなメッセージ」よりも、「届き方は浅いけど、多くの人にアピールするメッセージ」の方が評価される傾向となってしまうのです。
第三に、たとえ上記二つの問題をクリアしていてもなお、「ユーザーの関心を一枚岩の統計に集約してしまう」という問題が残ってしまうことが指摘されます。ユーザーが自らの関心を適切に反映しているようなツイートをしっかりといいね・RTできていたとしても発生する問題です。これは、音楽を例にとるとわかりやすいでしょう。音楽にはロックやポップス、クラシックなどいろんなジャンルがありますよね。それぞれのジャンルは価値基準が違うので、各々の価値観のもとで、その良し悪しが判断されるはずです。しかし、もし全アーティストが、だれが一番人気を得れるかの「人気取りゲーム」に屈してしまった場合、すべてのアーティストは最も人気のあるジャンル(ポップスでもロックでもいいですが)だけに集中してしまうようになるはずです。これと同じことが、ツイッターのメカニズムは志向してしまっていると、グエンは述べているのです。
「ゲーム化」する社会とどのように向き合えばいいのか

ここまで、ツイッターのような「ゲーミフィケーション」の仕組みが、及ぼしうる悪影響について説明してきました。しかし、ツイッターのようにゲーミフィケーションの仕組みが導入されたものは、現在の世の中にはたくさんあります。これらとうまく向き合うにはどうすればいいのでしょうか。
「価値に依存しない」ユーザー
グエンは、ツイッターに対するユーザーの態度には以下のような3つの者が考えられると言います。それが、「①ゲームプレイング・ユーザー」、「②被価値捕捉ユーザー」、「③価値独立ユーザー」の3つです。手身近に説明しましょう。
まず、「ゲームプレイング・ユーザー」は、ツイッターを“ほんとうに”「いいね・RT・フォロワー」獲得のゲームとしてプレイするようなプレイヤーです。ゲームの結果や過程が現実に影響を及ぼさないように(例えば、友達と『人狼』をしていて、だまされたとしてもそのことを道徳的に責めるような人はいないでしょう)、ツイッターが徹頭徹尾ゲームだとしたら、こうした人は無害になります。しかしながら、当たり前のように、ツイッターはゲームではないので、ゲームだと思ってる人がする、インプレッション稼ぎをするための嘘を交えたツイートを、そうではないと思っている人が真に受けてしまう、ということが起こってしまいます。
次に、「被価値捕捉ユーザー」です。これは、ツイッター上の「スコア」を内面化し、長期的なコミュニケーション目標に変えるようなユーザーを指します。本来、私たちの持っている多種多様な価値観は、豊かで繊細で、表現することが難しいものですが、現代社会において、私たちはよく、自分の価値観を単純化、典型的には「数値化」したものを提示するような仕組みの下に置かれます。例えば、大学におけるGPAや、ヘルスケアアプリが提示する歩数などの数値がそれにあたります。歩数の多さと健康や、GPAと学びの質は必ずしも一致しないものですが、私たちは次第にそれらの数値を最大化することに夢中になってしまいます。グエンは、こうした事態を「価値捕捉」と呼び、価値に捕捉されたユーザーを、「被価値捕捉ユーザー」と呼びます。それらユーザーは本来の目的を見失ってしまう傾向にあるのです。
そこでグエンは、第三の可能性を示唆します。それが「価値独立ユーザー」です。価値独立ユーザーは、ツイッターのスコアのような数値を、単なる報告として扱い、さらなる目的を追求するために利用することができるようなユーザーです。数値を、目標ではなく、単に有用なデータとして扱うのです。価値にとらわれたユーザーはスコアに振り回されてしまいますが、価値に依存しないユーザーはスコアを「管理」することができるようなユーザーです。
ほんとうは、すべてを「質的な」尺度のもとで行為できればいいのかもしれませんが、現在の社会ではそうはいきません。私たちは、普通に生きていれば、さまざまな「数値化」に直面しなければなりません。そこで必要なのは、「数値を最大化することを目標にする」というゲーム化の誘惑に抗って、その先にある目標を見失わずに、徹頭徹尾、数値化を単なる道具とみなすことのできるような態度である、という帰結をグエンは「ゲーム哲学」の視点から提供しているのです。
(参考文献)
Nguyen, C. Thi. 2021. “How Twitter gamifies communication.” In Applied Epistemology, ed. Jennifer Lackey, 410-436. New York: Oxford University Press.
美学者とは
美学者の役割
- 【美的判断】なぜある人が「美しい」と感じる対象を、別の人は「そうでもない」と思うのか
- 【芸術作品の価値】作品が私たちの感性に与える影響を、どう評価し、言葉で説明できるか
- 【日常の美】ファッションやインテリアなど身近なところに潜む「美しさ」をどのように考えるか
こうした問いに取り組むのが美学者の役割です。近年では、ゲームの体験やデザイン、スポーツや身体表現、さらにはSNSなど、従来は「美学」とはあまり結びつかなかった分野にまでその探究範囲が広がっています。哲学や芸術学と深く関係しながら、現代社会のあらゆる「感性の問題」に光を当てるのが、美学者と呼ばれる人々なのです。

【PROFILE】
北海道帯広市出身。早稲田大学文学研究科博士後期課程在籍。専門は、ゲーム研究、美学。主な論文に、「個人的なものとしてのゲームのプレイ: 卓越的プレイ、プレイスタイル、自己実現としての遊び」『REPLAYING JAPAN 6』、「ゲームにおける自由について──行為の創造者としてのプレイヤー──」『早稲田大学大学院 文学研究科紀要 第68輯』。ゲームとファッションとタコライスが好き。