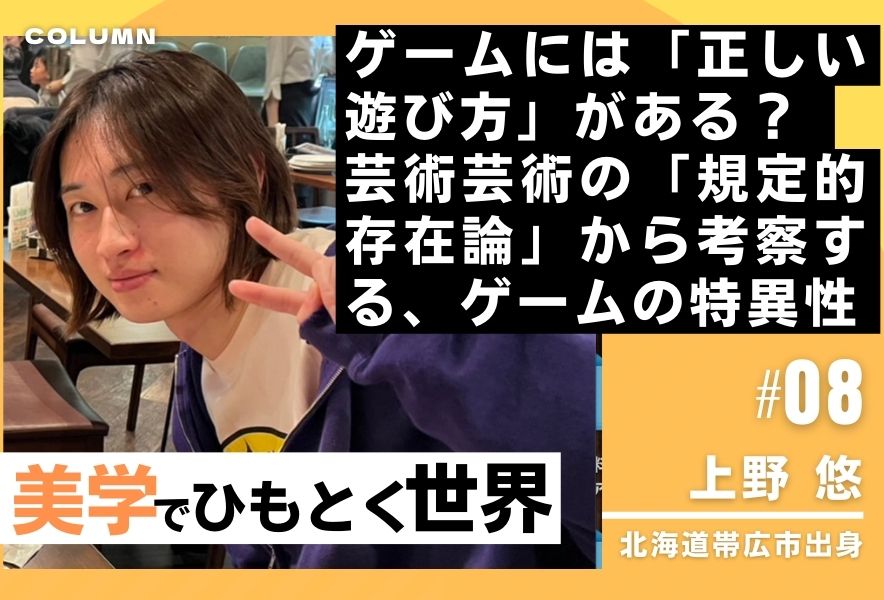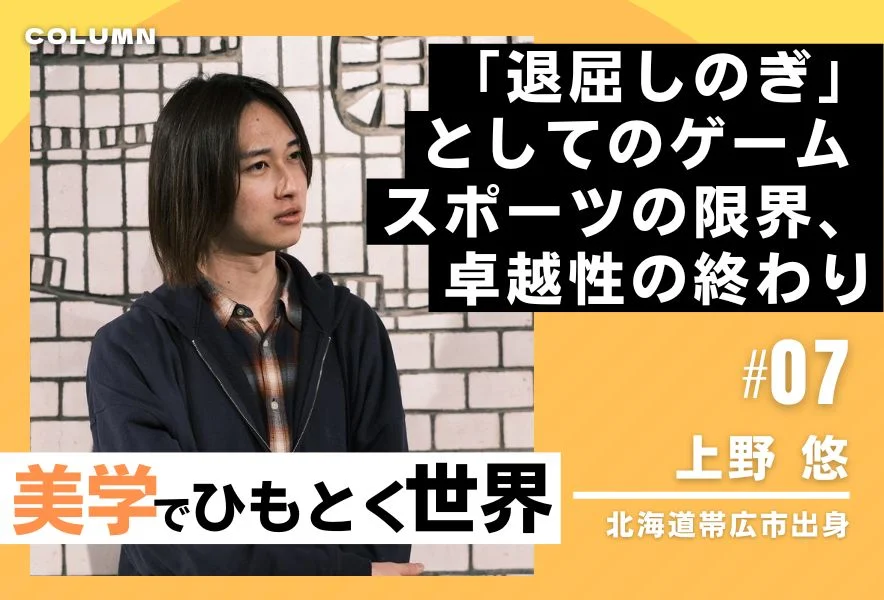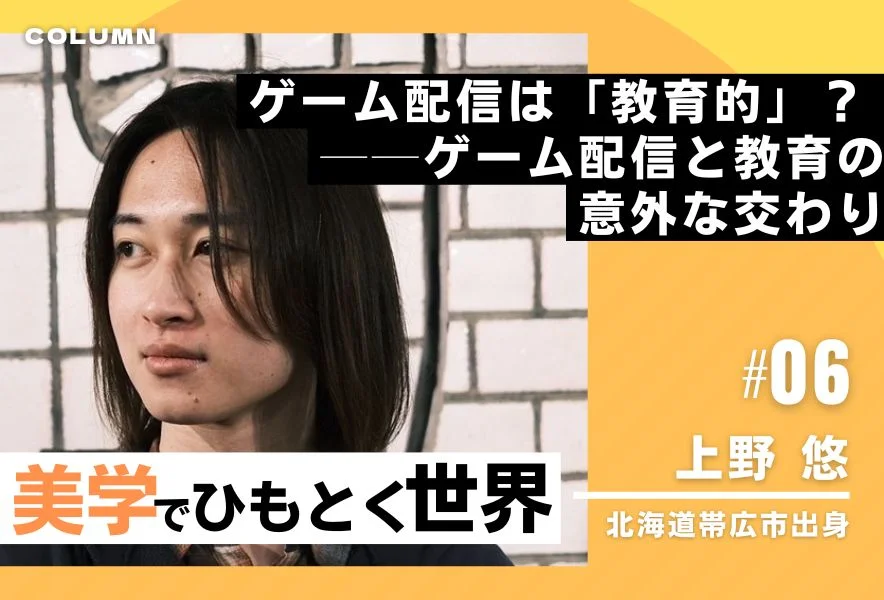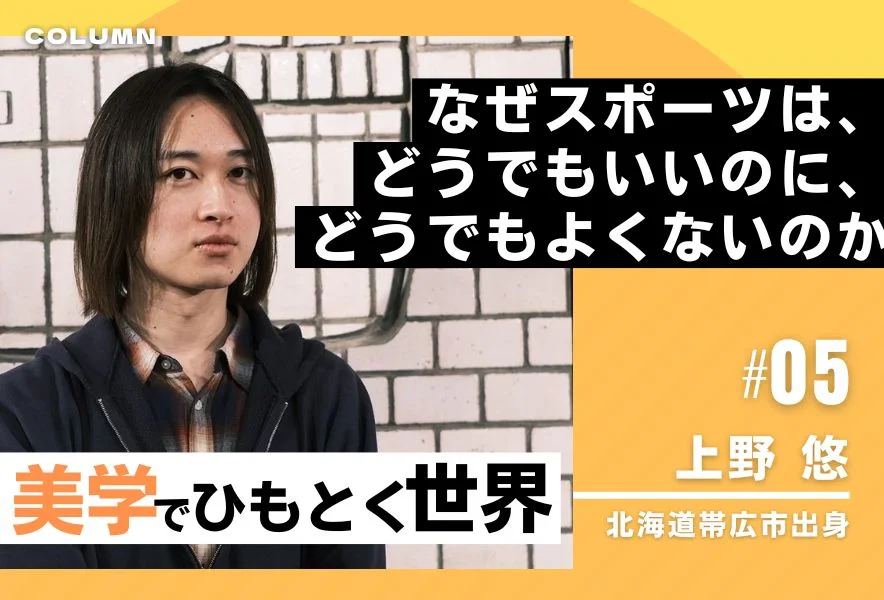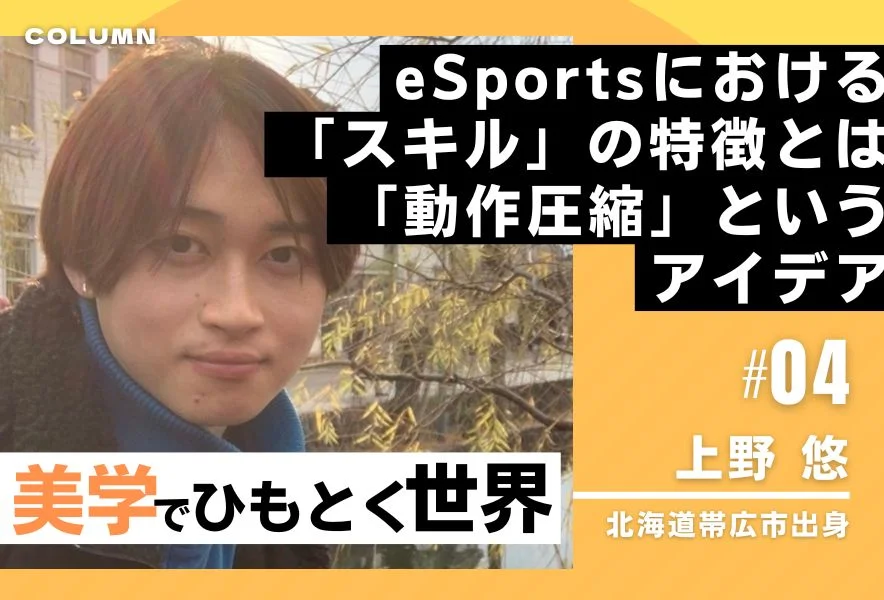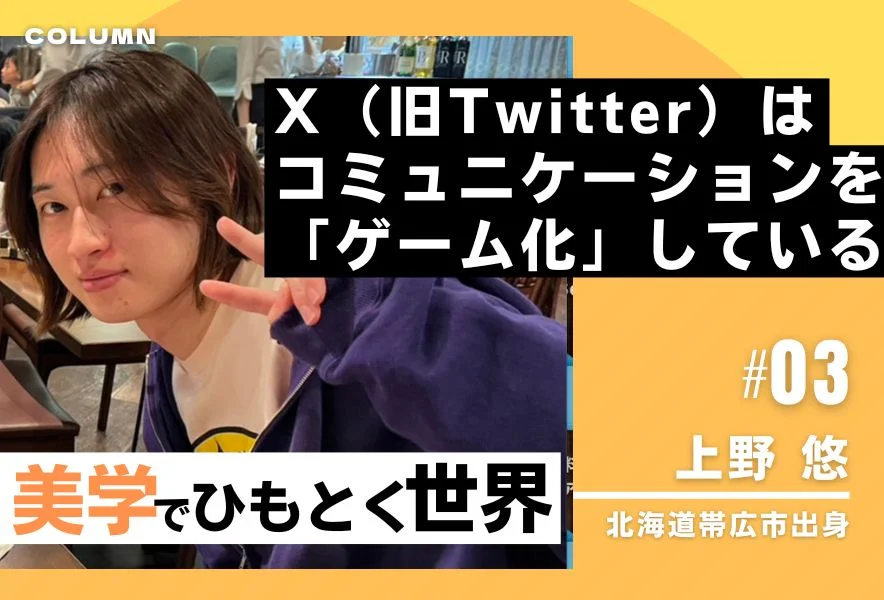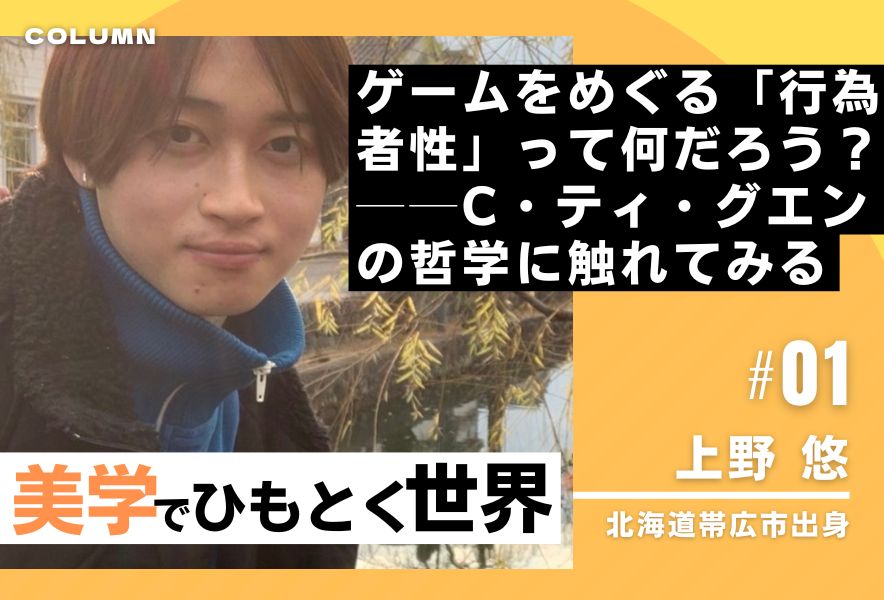【連載】美学者 上野悠の「美学でひもとく世界」
ゲームの「正しい」遊び方?

映画や小説は、一度でも通しで鑑賞すれば、その映画について語ることができますよね。それらに限らず、絵画や彫刻なども、一度でもその作品を鑑賞すれば、その出来のよしあしについてある程度評価することができます。しかし、「ゲーム」については、そうはいかない場合があるかもしれないのです。
C・ティ・グエンはこの点について、興味深い議論を提供してくれています。グエンは、“The Right Way to Play a Game.”という論文で、一部のゲーム作品との「適切な出会い方」は伝統的な芸術作品のそれとは異なるということを論じています。
ゲームは「自由に」遊ばれるべきという考え方
グエンがゲームとの適切な出会い方、つまりは、ゲームの「正しい遊び方」があると主張するのには、ゲーム研究における、ある文脈があります。それは、「ゲームは自由に遊ばれるものであり、“正しい遊び方”のような規定が存在するべきでない」というような考え方です。グエンは、こうした考え方の代表として、オッリ・タピオ・レイノと、ミゲル・シカールという人を取り上げます。まずは、レイノの主張から見ていきましょう。
レイノによる批判──「ゲームの正しい遊び方」は「意図の誤謬」である
レイノは、これまでのゲーム研究者たちが、「ゲームを研究するには、デザイナーの意図に沿った精神でゲームをプレイしなければならない」という暗黙の了解を前提としてきたことを批判します。レイノはこれを、「意図の誤謬(the intentional fallacy)」という、美学分野で有名な問題の一種であると指摘します。
意図の誤謬とは、ウィムザットとビアズリーという人たちが共著で提出した論文が元になっていますが、現在では、作品の正しい解釈や意味を決定したり、鑑賞者の作品に対する正しい反応を定めたりするために、「作者の意図」を考慮に入れるべきではない、ということを示すために用いられることが多い用語です。例えば、私たちは、作者が「悲しさを引き起こしたい」と考えて描いた絵に対して、悲しさ以外の様々な反応を見せたり、様々な解釈をしたりことができ、そういったことは自由に為されるべきです。
レイノは、これをゲームの「ルール」にも適用しようとします。レイノは、「作者の意図」という考えに由来した、プレイヤーのプレイの仕方についての規定を前提とするような考え方は、意図的誤謬の一種であり、無視すべきものである、と主張しています。レイノは、小説の読者が文章を自由に解釈できるのと同じように、ゲームは自由にプレイされるべきである、と言うのです。

グエンによる反論──美学における「規定的存在論」という概念をもとに
グエンは、レイノの意見に対し、分析美学における「規定的存在論」と呼ばれるようになったものを見てみましょう。規定的存在論とは、小説、絵画、映画、楽曲や演奏などを含んだ、「作品」全般について、そうした作品たちは、それらとどのように関わるかについての規定によって部分的に構成されている、ということを示すものです。例を挙げると、絵画をみるとき、わたしたちはふつう、それを正面から見て楽しむべきであり、裏側から見たり、舌で味わったりするべきではありません。また、小説を読むときは、文字を並べてある順に読むべきであり、逆から読むべきではありません。
このように、作品にはそれらとの「適切な出会い方」があり、そうした規定をなくした、ただ物理的な存在としての物体とは別の身分を持つものなのです。また、こうした規定は、作品のどういった側面に着目すべきなのか(絵画で言えば、「見た目」など)という、「注意の焦点」を明らかにしてくれます。
そして、重要なのは、このような、規定的存在論を保持することは、「意図の誤謬」を主張することと両立させることができるということです。規定存在論は、どういう方法が、作品との適切な関わりの最小限のものとしてみなされるのか、を作者が設定できると述べるだけであって、作品の正しい意味や解釈を、作者が決定することができるという考えとは、まったく別の問題なのです。つまり、規定論的実存論に則っても、作者が作品に設定できるのは作品の「内容」のみであって、その「意味」ではないと主張することが可能なのです。
シカールによる批判──「ゲームの正しい遊び方」は「遊びの自由」を妨げる
グエンは、レイノの意見に対し、「規定的存在論」という概念を持ち出すことで、ゲームを規則に従ってプレイすることが「意図の誤謬」に当てはまると心配する必要はないということを示しました。しかし、もう一人の「正しい遊び方」の批判者、シカールはより強い主張をしています。
シカールは、遊びとは本質的に自由なものであり、既存の文脈を乗っ取ることで成り立つという意味で、「流用的」なものであると述べています。遊びには、実用的なものを通常の文脈から取り出し、その使い道をいつもとは別のものに変えてしまうような力があるのです。しかし、強固な規定を持つようなゲームは、こうした流用を拒むため、真の遊びを妨げることになってしまいます。シカールはそれに対し、そうしたゲームのルールや目標の規定を無視することが許されると主張しているだけでなく、むしろ無視して別のものにしてしまうような行為を称賛しているのです。

グエンの理解によると、シカールの主張は 2 つのステップに分かれます。シカールはまず、「遊び」こそを第一のものとし、ゲームは遊びのために作られる道具のようなものにすぎないと述べ、次に、遊びとは、本質的に、構造化されていないというものであると主張しているのです。シカールは、遊びとはカーニバル的で流用的、攪乱的であり、まじめくさった文脈を乗っ取って、バカバカしいものに変えてしまうようなものこそが遊びであると考えているのです。したがって、デザインされたゲームと遊びの間には緊張関係が見受けられるようになります。
シカールによると、遊びを意図した目的のために利用し、制御し、導くようなゲームデザインは遊びの本質的な性質に反しているのです。その代わり、ゲームの制作者は、遊びを誘発するような文脈や舞台装置のようなものを提供するだけでよいと考えています。シカールの称賛するゲームデザインとは、まさにMinecraft (Mojang 2011)のようなものです。
グエンによる反論──「美的コミュニケーション」としてのゲーム
これに対し、グエン、シカールの言うような「自由な遊び」の重要性を否定するつもりはないと前置きしながら、自由な遊び「だけ」がゲームの唯一の正当な目的であるという主張に異議を唱えようとします。
グエンが示す、もう一つの役割とは「コミュニケーション」です。ゲイリー・アイゼミンガーという美学者による美的コミュニケーションについての論を参照し、ゲームを美的コミュニケーションとして捉えようとします。美的コミュニケーションとは、ある人が意図的に、その状況を経験することそれ自体に価値があるものだと誰かが感じることを目的とし、またそのように感じさせる効果を期待しながら、ある状況を作り出すことを言います。これには、必ずしも表象的ないしは概念的な内容を持つ必要はなく、例としてグエンは、「寿司を握ること」を挙げています。
グエンは、多くのゲームは「美的コミュニケーション」を目的としながら、特定の価値ある経験を生み出し、制作物を通じてそれを他者に伝えようとしているのだと主張しています。ゲームとは、多くの場合、行動やスキル、意思決定、行為といった「活動」に関する、美的に価値のある経験を伝えようとするものなのです。また、このような、「美的コミュニケーション」という考え方は、ゲーム作品の示す規定に、われわれプレイヤーが従おうとする理由を理解する手助けともなります。というのも、「なぜ私たちは、特定のルールに従いながら、指定された目標を達成するという遊び(=ゲーム)をしたいと思うのか」という問いに対し、そうすることで、制作者が伝えようとする美的ななにかを経験するため、という風に答えることができるのです。
グエンは自由な遊びの重要性を否定しているわけではないと強調しながらも、ただ、自由な遊びとコミュニケーションの間にはトレードオフの関係があると述べています。というのも、ゲーム以外のほとんどのコミュニケーション(例えば「言語」など)にも同様に、共有された規定が備わっており、コミュニケーションを成立させるためには、共通基盤を安定させるために、一連の規範や規定を共有する必要があります。こうした共有された規定や規範を拒絶すればするほど、より自由に遊ぶことができますが、同時にコミュニケーションの送受信は難しくなってしまい、反対に、確立されたコミュニケーションを望むほど、共有された規範に縛られる必要があるのです。

「最低限の邂逅遭遇」と「深い邂逅遭遇」
グエンは、規定的存在論をさらに掘り下げ、そこから導かれる「2 つの要件」を提示します。それは、「最低限の邂逅遭遇」と「より深いもしくは充実した邂逅遭遇」というものです。
最低限の遭遇に関して言うと、例えば、絵画と最低限の適切な遭遇をするには、その絵画の表面を視覚的に捉える必要がある、というようなことです。小説を最小限に遭遇するには、順番に文字を追って読む必要があります。対して、深い遭遇とは、作品とのより深い、あるいはより充実した遭遇をするにはどうすればよいか、というものです。例えば、20世紀絵画においては、より深い鑑賞とは、筆のタッチの細部をより注意深く観察したり、アーティストの声明を読んだり、美術史を学ぶことであるというように言われています。
では、ゲームにはどのような規定が考えられるのでしょうか。グエンは、ゲームにおける遊びの規定に関して、興味深い示唆を述べています。少なくとも最低限で考えると、私たちはルールに従って、指定された目標を目指してプレイすることになりますが、それだけではないとグエンは考えるのです。グエンは、ゲームは創発的かつ戦略的なものであるため、ゲームに適切に遭遇するためには、必要なプレイ回数やスキルレベルに関する規定も存在するのだと指摘しています。
グエンは、一部のゲームでは、ゲームと適切に遭遇するために、複数回のプレイと中程度のスキルが必要とされ、また、一部のゲームでは、より深い遭遇には非常に多くのプレイと高度なスキルの習得が必要であると主張します。この見解のもとで考えると、ゲームの特徴が見えてきます。例えば、映画は 1 回観ただけでも、それに対する評価を下しても差し支えないかもしれませんが、特定の種類のゲームについては、1 回プレイしただけでそのよしあしを判断することは──第1章だけを読んだだけで本を批評するのと同じように──不適切であると考えられるのです。グエンは、この考えを例証するために、パーティーゲーム、重厚な戦略的ゲーム、コミュニティ進化ゲームという、3つの異なるゲームジャンルを想定します。
ゲームにおける適切な出会い──パーティーゲーム、ストラテジーゲーム、コミュニティ進化ゲーム
グエンはまず、パーティーゲームに関して述べます。彼によると、パーティーゲームとは、長期的なスキルの向上が重要でない、あるいは積極的に妨げられるような慣習とみなされます。例えば、ジェスチャーゲームで絶対に勝つために、動画を見て研究したり、こっそりと練習していたりすることはナンセンスに感じられますよね。実際にパーティーゲームとみなされるゲームでは、勝者が選ばれるシステムは明らかに恣意的になるように作られていることをグエンは指摘しています。このようなゲームでは、勝利を求めて「真剣に」プレイしたことしかないような人は、むしろ、そのゲームについての、何らかの判断を下すべきではないように思われるのです。
こうしたパーティーゲームとは別に、グエンが「ヘビィなストラテジーゲーム」と呼ぶ、複雑な創発性を持ったストラテジーゲームにおいては、繰り返しプレイすることが、ゲームとの最低限の遭遇の、必要条件になるのだとしています。チェスや囲碁といった、戦略的ゲームには、複数回プレイすることで初めて見えてくるような仕組みがあります。そうした仕組みは、新しく始めたプレイヤーにとっては明白に見えてはいませんが、実際にはそのゲームにとって中心的なものなのです。
それゆえ、プレイヤーは、ヘヴィなストラテジーゲームの作品を十分に体験するためには、それらの中心的な特徴を明らかにするのに、十分なスキルを身につける必要性が生まれるのです。囲碁の熟練者と初心者では囲碁に対する、いわゆる「理解度」が明らかに異なっているのです。
そして、ゲームには複数人でプレイすることによって初めて、「最低限の遭遇」が果たされるようなゲームがあります。いわゆる「マルチプレイヤーゲーム」です。
しかし、グエンは、そうしたマルチプレイヤーゲームよりも、さらに深く社会的要素が組み込まれたゲームというものがあると述べています。それが、彼が「コミュニティ進化ゲーム」と呼ぶカテゴリーです。このジャンルの主な例としては、『マジック:ザ・ギャザリング』(Wizards of the Coast 1993)のような、いわゆるトレーディングカードゲーム(TCG)の多くが挙げられるでしょう。
グエンによると、こうしたゲームの熱心なプレイヤーは、いわゆる「メタ」または「メタゲーム」と呼ばれるものに深く関与するようになります。プレイヤーたちは、ゲームで勝つために、コミュニティに参加し、そこでどんな戦略やデッキが現在強いとされているのか、流行しているのかを把握する必要があるのです。コミュニティの中で形成される「戦略空間」は、現在強力とされているデッキにプレイヤーが対応し、その対応にまた別のプレイヤーが対応する、というような形でどんどん進化していくのです。
これによって、作品と適切に遭遇するためには、複数回のプレイが必要であるだけでなく、プレイヤーコミュニティへの参加が必要となってきます。グエンは、この種のゲームでは、オンラインフォーラムなどのリソースからゲーム外の情報を活用し、対応することが、ゲームによって「存在論的に」規定されているのであり、よって、ゲームと適切に遭遇するための必要条件であると主張しているのです。
グエンのこうした見解が正しいとするならば、コミュニティ進化ゲームは存在論的に他の種類の作品とは非常に異なるということになります。映画などの場合は、一人で見ただけでも正当な美的判断を下すことができますが、コミュニティ進化ゲームの場合は、コミュニティに組み込まれ、そのコミュニティにおいて進化していく「メタゲーム」に参加しなければ、そのゲームの中心的特徴を十分に経験することはできないのです。

ゲームに正しい遊び方はあるのか?
それでは、グエンは結局、「ゲームには正しい遊び方がある」と考えているのでしょうか。グエンは、答えは複雑であると述べています。
まず、狭義では、その通りである、となります。特定のゲームは作品としてみなされ、それをプレイする正しい方法があり、その方法でプレイすることで、制作者が作品に刻み込もうと意図した、特定の経験を得ることができるのです。その場合、規定に従うことが、オリジナル作品を経験する──つまりは、その作品を「コミュニケーション」の一種として経験する──唯一の方法なのです。
しかながら、グエンはいわゆる「自由な遊び」の可能性も決して否定しません。私たちは、常に制作者の意図通りに作品を享受するのではなく、作品を経験するためのさまざまなやり方を試すことで、新しい作品を生み出す理由がある。例えば、ビデオゲーム作品をできるだけ早くクリアすることを目指す実践である「RTA(リアルタイムアタック)」などはその好例となります。そのようにして、私たちは社会的実践の空間を探求し、新しい規定のパターンを生み出し、どのパターンに焦点を当てるべきかを新たに見出すこともできます。そうして、新たな実践を生み出すことはまた、新たなタイプの作品や新たなコミュニケーションの形態の可能性を生み出すことにつながっていくのです。
参考文献
Leino, Olli Tapio. 2012. Death loop as a feature. Game Studies 12 (2).
—-. 2013. Playability and its absence – a post-ludological critique. DiGRA Conference 2013.
Nguyen, C. Thi. 2019. “The Right Way to Play a Game.” Game Studies 19 (1).
Sicart, Miguel. 2014. Play Matters. Cambridge: MIT Press.
美学者とは
美学者の役割
- 【美的判断】なぜある人が「美しい」と感じる対象を、別の人は「そうでもない」と思うのか
- 【芸術作品の価値】作品が私たちの感性に与える影響を、どう評価し、言葉で説明できるか
- 【日常の美】ファッションやインテリアなど身近なところに潜む「美しさ」をどのように考えるか
こうした問いに取り組むのが美学者の役割です。近年では、ゲームの体験やデザイン、スポーツや身体表現、さらにはSNSなど、従来は「美学」とはあまり結びつかなかった分野にまでその探究範囲が広がっています。哲学や芸術学と深く関係しながら、現代社会のあらゆる「感性の問題」に光を当てるのが、美学者と呼ばれる人々なのです。

【PROFILE】
北海道帯広市出身。早稲田大学文学研究科博士後期課程在籍。専門は、ゲーム研究、美学。主な論文に、「個人的なものとしてのゲームのプレイ: 卓越的プレイ、プレイスタイル、自己実現としての遊び」『REPLAYING JAPAN 6』、「ゲームにおける自由について──行為の創造者としてのプレイヤー──」『早稲田大学大学院 文学研究科紀要 第68輯』。ゲームとファッションとタコライスが好き。