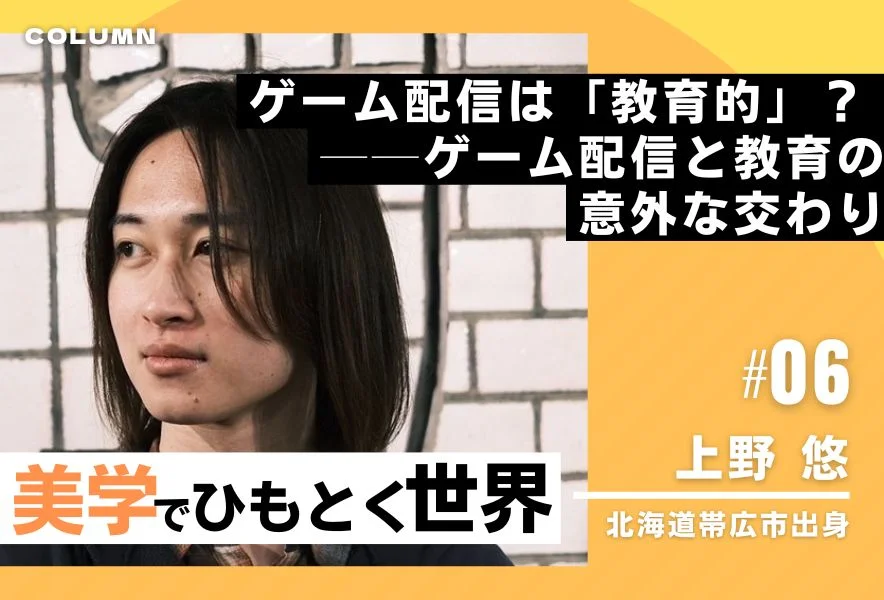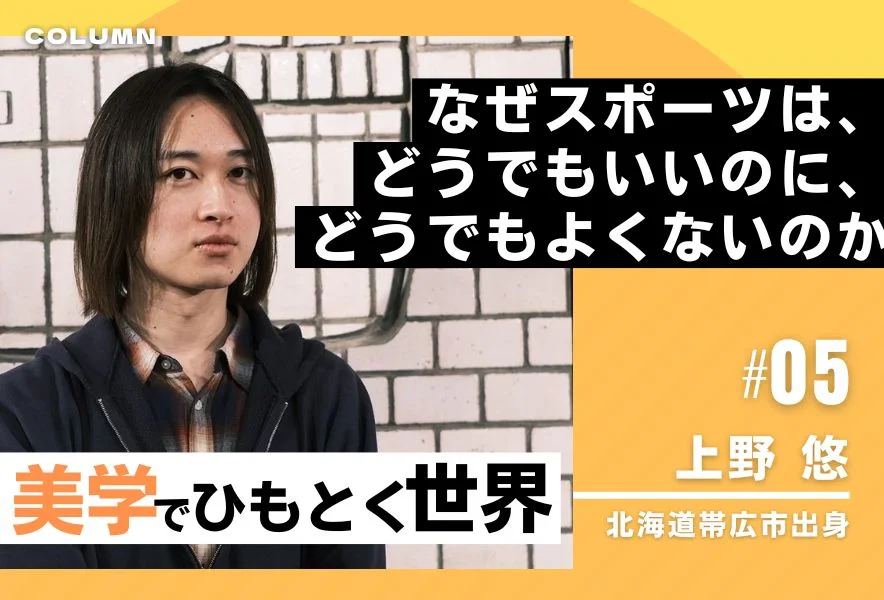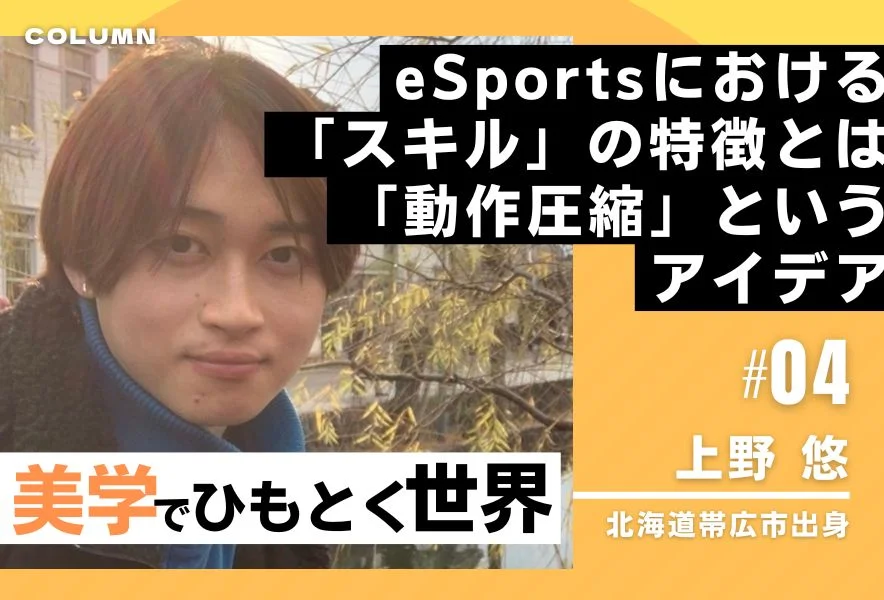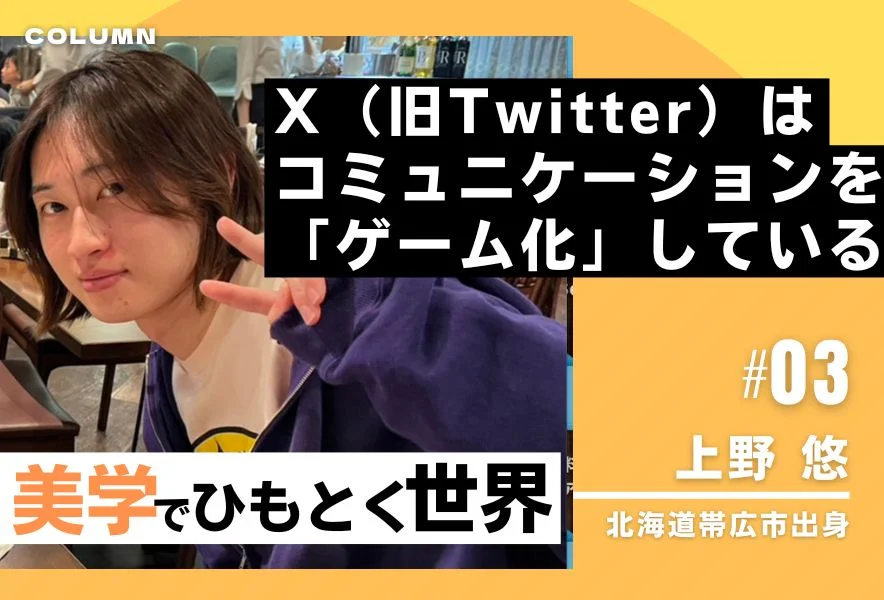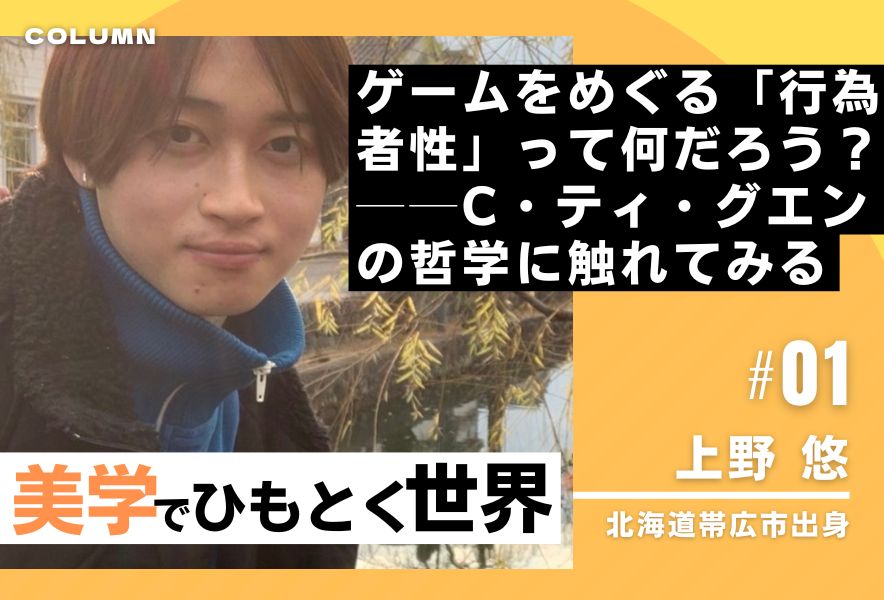【連載】美学者 上野悠の「美学でひもとく世界」
現代の覇権コンテンツ──ゲーム配信

最近、身の回りの友人に暇なときは何やってるのかと聞くと、最も多く返ってくるのが、「YouTubeみてる」という返答です。かくいう自分も、暇なときはもちろん、やらなきゃいけないことがあるときにも、ついYouTubeで自分の好きな動画や配信を眺めてしまう、ということが多々あります。
そんなときに大抵見ているのが、「ゲーム配信」です。ゲームの哲学とか言ってる人間がゲーム配信をよく観ているのは当然のことかもしれませんが、ゲームの哲学とか全然言っていない友人たちのなかにも、ゲーム配信を日常的に観ているという人がかなりいますし、電車で隣に座った人が、結構な頻度でゲーム配信を観ている(覗いているわけではありませんが)ことがあります。少し前だったら、一部のゲーム好きだけが観ているイメージだったのが、ここ数年で非常に増えてきているな、という印象があります。
そんな配信文化の普及とともに、ゲーム実況を含めた「配信」を研究対象にしようという動きも出てきています。配信とeSportsとの関係や、配信における「投げ銭」をはじめとしたマネタイズの構造、などなど、トピックは非常に多岐にわたりますが、今回はその中から、「ゲーム配信」と「芸術教育」に共通点を見出し、双方に役立つような視点を提供しようとしている、ユニークな研究を紹介したいと思います。
ゲーム配信は芸術教育に役立つ?

Ahu YolacとLaura J. Hetrickは、芸術教育者としての視点から、YouTubeやTwitchと9いった、ゲーム配信サービスを、仮想的なコミュニティ内に、ゆるい(informal)学習空間を作り出し、支援する「実践コミュニティ」として、学術的な観点からより詳細に検討する必要があると主張しています。
二人は、教育者としての視点から配信者の行動を観察し、そこに3つの教育上の概念を見出します。そこから、芸術教育者が、配信者たちが意図せず行っているアプローチから学べる点と、配信者が、芸術教育者たちの意図的で目的を持った教育実践から学べる点について提案しています。
YouTubeとTwitch、二つのプラットフォーム
彼らの主張を見ていく前に、前提知識を共有しましょう。ゲーム配信を日ごろから観ているような方々にとっては当たり前の情報となってしまうので、そういった人はぜひ飛ばしてもらって結構です。
Googleが所有する動画配信サービスであるYouTubeは、非常に人気のあるサービスですが、ゲーム配信に関しては、Twitchと比較すると人気が落ちます(日本だとそうでもないですが)。一方で、Twitchで配信したもの録画・編集し、YouTubeに動画としてアップロードするチャンネルも多く見られるなど、YouTubeとTwitchを連携させるような動きが見られます。Twitchが配信サービスである一方で、多くのユーザーはYouTubeを動画投稿プラットフォームとして見られる傾向にあると言えるでしょう。

YouTubeにはTwitchと同様に「ライブチャット機能」があり、配信を通して、コンテンツ制作者と交流することができるほか、YouTubeの動画コンテンツにはコメント欄があり、視聴者はそこにコメントを残すことができます。チャンネル側は、そうしたコメント欄に投稿された視聴者のコメントに対して、動画内で言及したり返信したりすることもできるし、逆に無視することもできます。視聴者たちのコメントは主にチャンネルや特定の動画の内容に向けられたものですが、同じコミュニティのメンバーとして視聴者同士が交流するコミュニティスペースとしても機能することがあります。
一方で、Twitchは、2007年にJustin Kanという人が、自身の日常生活を配信する目的で設立したサービスで、2011年に、Twitchという名称に変更され、ゲーム系のコンテンツに焦点を当てた配信サービスへと拡大していきました。Twitchでは、「雑談」から、「ゲーム」、「Minecraft」や「Valorant」といった特定のゲーム作品、「ASMR」など、各カテゴリーにそれぞれの配信が分類され、興味のあるコンテンツが容易に探すことができるようになっています。当然、Twitchでも、YouTubeと同様に、コンテンツの制作者が主導し、仮想的なコミュニティを形成・維持することができます。
「実践コミュニティ」の形成
この二つのプラットフォームでは、コンテンツ制作者を中心としたコミュニティが形成されますが、ゲーム配信コミュニティの場合、視聴者の多くが視聴しているゲームのプレイヤーでもあるため、何かに対して関心や情熱を共有する人々のグループであり、定期的に交流することで、その何かをより上手にできるようになるような、「実践コミュニティ」としての役割を果たすことが多くなります。そして、こうした実践コミュニティでの交流の結果として、「学習」が生まれるようになるのです。
教育における3つの概念とゲーム配信

こうした実践コミュニティの形成を通して、YolacとHetrickは、ゲーム配信者は、ゲームプレイを視聴者に見せるだけでなく、「マルチメディア学習空間を生み出し、そこで配信者たちは、ゲームの物語、批評的プレイ、ゲーム中に起こるイベント全般について論じ、自らの見解を織り込んだ、かたくるしくない教育を視聴者に提供している」のだと述べています。YolacとHetrickは、ゲーム配信者のような立場で、価値観や規範、物事のやり方、行動や問題解決の方法を示す、いわば「ロールモデル」としての役割を、効果的に果たすことができる可能性を示しているのです。
YolacとHetrickはさらに、教育における3つの重要概念を通して、ゲーム配信の教育的可能性を探ろうとします。それが、「①構成主義(constructivism)」と「②発達の最近接領域(the zone of proximal development)」と「③創発的カリキュラム(emergent curriculum)」です。
ヴィゴツキーの社会構成主義
教育における構成主義には、実はピアジェという心理学者が発端となる「認知構成主義」とヴィゴツキーという心理学者が提唱した「社会構成主義」の二つがあるのですが、YolacとHetrickが扱うのは後者の方です。
ヴィゴツキーの言う、社会構成主義とは、平たく言うと、知識を、社会的な営みによって構成されていくもの、と捉えるものです。それゆえヴィゴツキーは、だれかとの協同による社会的実践によって知識が獲得され、発達が進んでいく過程を重視したのです。YolacとHetrickはヴィゴツキーのいう学習コミュニティに、配信者と視聴者で織りなすコミュニティの構造を当てはめることができるのだと主張しています。
発達の最近接領域
また、ヴィゴツキーは、教育は学習者が「現在到達している水準」ではなく、「到達しつつある水準」に基づいて行われるべきである、と主張し、「発達の最近接領域(ZPD)」と呼ばれるものを提唱しました。学習者には「自分一人でできる水準」、つまり現在到達している水準がありますが、それとは別に、「手助けがあってできるようになる水準」があります。このことをZPDと呼ぶのです。
YolacとHetrickは視聴者であるゲームのプレイヤーが、この現行の水準とZPDの間にあるギャップを埋めるのに、ゲーム配信が役に立つとしています。たくさんの配信者たちは、初心者向け、中級車向け、上級者向けと、いくつかのレベルに分かれたコンテンツを提供します。視聴者は、自分の到達したいレベルに合わせて、能動的に学習していくことができます。

創発的カリキュラム
3つ目の教育理論は、「創発的カリキュラム」の活用です。視聴者が自分にとって重要なものを識別し、関心に基づいて、視聴する配信や動画を選ぶだけでなく、配信者も視聴者の「いいね」、や視聴者数、「コメント」を、今後どのようなコンテンツを制作し配信するかの指標として活用することができます。
こうしてフィードバックが循環する中で、配信者と視聴者は、互いの関心やスキルレベルを認識し、自らが解決したい問題を探求します。ストリーマーはさまざまなレベルの専門知識を駆使してコンテンツを制作し、視聴者は現在の達成を上回るさまざまなレベルで、関心のあるトピックをより深く掘り下げるために利用できるコンテンツを探し求めます。視聴者は、制作者が提供するコンテンツ=カリキュラムを、与えられるのではなく、自らの興味関心に基づいて選択することができるのです。
YolacとHetricは、これら3つの概念が、Twitchや類似のプラットフォームで、配信者たちが意図せず用いているアプローチに当てはまるものであると指摘することで、芸術教育者としての彼らが日々の教育の中で、ゲーム配信者たちと同じ考え方を採用していることを示しているのです。
教育者が配信者から学べるもの

最後に、YolacとHetricは、配信者から教育者が学べるものとして、いくつかの要素を挙げています。一つ目が、「可変的なテンポ」です。
コンテンツ制作者たちは、プラットフォーム上で複数のタイプのコンテンツを提供することで、視聴者がちがった「テンポ」でそれらを視聴することを可能にしています。例えば、視聴者がゲームプレイをリアルタイムで視聴できる配信をしている一方で、配信全体をアップロードしたり、編集した動画を作成したりして、フォロワーが自分のペースでコンテンツに参加したり、何回も視聴できるようにしています。
こうした「時間にとらわれない」アプローチは、教育にも応用できると指摘しています。例えば、教育者が、さまざまなレベルの教材ビデオや録音資料などの視聴覚教材を活用することで、学生は自分のペースでトピックを再確認したり、学習に取り組んだりすることができます。学生は教材を巻き戻したり、停止したり、早送りしたりすることができ、従来の教育でしばしば見られた時間的な制約にとらわれることなく、より能動的に学習に取り組むことができるのです。
また、配信者はコンテンツへの参加を促すような、さまざまなツールを提供します。視聴者はライブチャットに参加し、配信者とリアルタイムでやりとりすることもできますが、動画のコメント欄やSNSなど、配信者が提供する他の手段でも、コンテンツに参加することができます。こうして、複数のコミュニケーション手段を提供することで、コミュニティへの参加方法に多様性を持たせることができるだけでなく、視聴者にさまざまな選択肢を提供することができます。
YolacとHetricは、これを用いて、さまざまなタイプの学生の参加の場を設けることで、学生に選択肢を与えることができ、特定の方法によるコミュニケーションでうまくできなければ、よい成績が得られない、というプレッシャーを感じさせない授業への参加を促すためのツールとなることを示しています。例えば、教育者側はオンラインとオフラインのハイブリットなディスカッション、ホワイトボードやコメント欄など、複数のスペースを提供することで、学生に選択肢を提供することができます。
また、YolacとHetricは、配信者たちのゲーム中のふるまいを、教育者たちも取り入れるように提案しています。例えば、ゲーム配信者は、配信中、それまでのゲームプレイを通じて培った知識やスキルを駆使して、ゲームを進めていきます。このとき配信者たちは意図せず、そのプレイ=デモンストレーションを通じて、同時に自分自身のスキルを向上させながら、視聴者のスキルの向上を支援するガイドにもなっているのです。
YolacとHetricは、こうした過程を教育でも再現するために、例えば、教師は生徒と協力して新しい芸術作品の制作方法や作品のデザイン方法を考案するような授業をしていくことが考えられることや、生徒の実験や失敗に積極的にかかわって、新しい芸術の探求を一緒に進めていくこともできると提案しています。

プロセスへの参加
ほかにも、YolacとHetricは、配信者を通じて学ぶことができる教育の方法や、逆に、芸術教育のテクニックから配信者が学ぶことができることについても思案していますが、彼らのポイントを私なりにまとめると、「プロセスへの参加」という点で両者を結び付けることができるのだと思います。
おそらく、重要なのは「ゲーム」配信であるという点です。ゲームは、それ自体がよく学習過程に例えられるように、課題の提示とそれを解決する方法の探索、というセットが、わかりやすいようにデザインされた形で提示することができます。なので、学習自体にゲームの仕組みを取り入れようとするもの、つまりプレイヤー=学生というモデルはよく見られるのですが、今回の論文がユニークな点は、実際にゲームをプレイする配信者と教育者を重ねている点です。
この類比が通じるのは、YolacとHetricがモデルにしているのが「芸術教育」だからでしょう。芸術教育では、教育者自らが実践する、ということが他の教育よりも有効に働きます。しかしながら、例えば数学の授業で、難問を解く様子を見せるなど、ほかの教育の場でも同様のことはできるかもしれません。
そしてもう一つ重要なのが、視聴者=学生に参加させる、という点です。学習の過程で、学生の積極的な参加を促すべき、という意見自体は珍しいものではないかと思われますが、そのモデルとして、ゲーム配信における視聴者を想定するのはユニークな点だと言えるでしょう。これは私の考えですが、ゲーム配信でチャット欄が盛り上がるのは──家で、友達同士でゲームをするときと同様に──人が何かをやっているのを見るとき、「自分だったらこうするのに」という、ある種のもどかしさが発生するからです。このもどかしさは、「実際にやりたい」という意欲と強く結びつきます。そうした「もどかしさ」を、教育の現場で引き出すには、かなりの工夫が必要かもしれませんが、芸術教育のような場では比較的容易に引き出すことができるかもしれません。
これ以外にも、ゲーム配信をよい教育方法の着想源とする考えには、ある程度の有効性が見られるように思えます。また、人によっては、論文の筆者たちや、私が示唆したもの以外にもより有効な着眼点を見出だせるかもしれません。
参考文献
Yolac, A., & Hetrick, L. J. (2024). “Streamers as Arts Educators: Exploring Their Streaming Approaches as Pedagogical Practices.” Games and Culture, 0(0).
美学者とは
美学者の役割
- 【美的判断】なぜある人が「美しい」と感じる対象を、別の人は「そうでもない」と思うのか
- 【芸術作品の価値】作品が私たちの感性に与える影響を、どう評価し、言葉で説明できるか
- 【日常の美】ファッションやインテリアなど身近なところに潜む「美しさ」をどのように考えるか
こうした問いに取り組むのが美学者の役割です。近年では、ゲームの体験やデザイン、スポーツや身体表現、さらにはSNSなど、従来は「美学」とはあまり結びつかなかった分野にまでその探究範囲が広がっています。哲学や芸術学と深く関係しながら、現代社会のあらゆる「感性の問題」に光を当てるのが、美学者と呼ばれる人々なのです。

【PROFILE】
北海道帯広市出身。早稲田大学文学研究科博士後期課程在籍。専門は、ゲーム研究、美学。主な論文に、「個人的なものとしてのゲームのプレイ: 卓越的プレイ、プレイスタイル、自己実現としての遊び」『REPLAYING JAPAN 6』、「ゲームにおける自由について──行為の創造者としてのプレイヤー──」『早稲田大学大学院 文学研究科紀要 第68輯』。ゲームとファッションとタコライスが好き。